某所で話題になっていたので
大学入試「指定校・付属校推薦入試は即刻廃止を」と大前研一氏
を読んでみた。
 ←入試をどうかすれば夢のように教育改革できるってのも幻想よね
←入試をどうかすれば夢のように教育改革できるってのも幻想よね
冒頭には「迷走する文部科学省主導の「大学入試改革」につきあっていては、日本の大学入試制度は混乱するだけで何も得られない。教育の質を高めるには、どのような入試制度が望ましいのか、経営コンサルタントの大前研一氏が考察する。」とあったので、国全体の施策としてどうすればよいのかの分析が展開されているのかとちょっと期待したけど…
中身は「現在の大学入試制度で、何よりも許しがたいのは私立大学の「指定校推薦入試」や「付属校推薦入試」だ。」で始まっていて…各私立大学がそれぞれ工夫している入試の話? まぁそれはそれでいいとして、
なぜ推薦入試が許せないかというと、推薦が(一般入試よりも)早々と決まってしまって彼らちっとも勉強せんからだという。どきっ。。確かに、うちの次男とか、高三の12月末に学部学科が決まったら、暇なので自動車学校に通ってましたけどね。
しかし「その結果、高校3年間で学んでいるはずの内容を全く理解していないので、大学の理系学部などでは数学の基礎が弱くて授業ができず、補習から始めなければならないという事態になっている。」とあるけど、別にそんなことはなくて、一般入試の人と同じかそれ以上、数学や物理はできるから授業でも別に問題なかったですよ。英語はちょっと…問題あるかも…(小声)
数学がダメで補習から始めなければいけないほどだとすれば、それは推薦が決まってから遊び惚けていたからではなくて(数か月余計に遊んだからってそこまで劣化しない)、もともと基礎学力のない人に推薦合格出しちゃったからでは?
どんな入試をして、どんな人を合格させるかは、大学の命運を握っている非常に重要なことなので、ここは各大学が知恵を絞ってベストを尽くしているはず。いろんな枠を準備して、選考基準をどうすればうまくいくか、考えたあげくのそういう推薦入試をしているということは、まぁ他の枠(たとえば一般入試)を増やしたからってそれよりマシな人材を取れないからやってるのではないでしょうか。
まぁ、とにかく入学者の基礎学力を確保したいってことであれば、全部をシンプルに一般入試枠(ペーパーテスト)にするという方針は理解できるけど、大前氏の主張はそういうことでもないようで、ここからさらにねじれていきます。
「そもそも日本の大学教育は、高校における文系・理系の選択が早いこともあって、オールラウンドに活躍できる人材が育ちにくい。幅広い教養と論理的思考力を身につけるリベラルアーツ教育も極めて貧弱だ。このため、関心分野が偏ったバランスの悪い人間が出てきてしまう。」…じゃ、文系・理系の選択が遅くてリベラルアーツ教育もさかんな付属校ルートなんてバッチリじゃないですか。
入試をいじることで高校以下の教育が変わるかどうか(どう変わるか)もそんなに明らかなつながりがある話ではないと思うけど、大前氏の主張は「日本人が世界で互角に戦えるようになるためには、語学に加えて、セオリー・オブ・シンキングやリーダーシップを身につけることができる教育にゼロベースで転換しなければならない。その契機となるのが真の大学入試改革…」とのことなので、ともかくそういった変化が高校までの教育にもたらされるためにはどういった入試にすればいいのかと。
大前氏の別記事があった:
大学入試は卒試・書類・面接の3段階選考にすべきである
これによれば、
「卒試」…高校卒業資格センター試験。高校まで12年間の教育内容をきちんと理解したかどうかを検証するもので、英語、国語、地理歴史、数学、理科などの受験科目だけでなく、音楽や美術も含めた全科目で、学習指導要領を司っている文科省が責任を持って全国一斉に行なう。
「書類」…受験生が自分のプロフィール(高卒資格センター試験の結果、内申書、ボランティア活動や社会貢献などのレポート)を志望大学に提出する。大学側はそれを独自の選考基準によってふるい分け、自分たちが受け入れたいプロフィールの学生に受験資格を付与する。
「独自入試」…(ペーパーテストもよいが)面接試験を実施することだ。21世紀は答えを覚えたかどうかではなく、答えのない世界で自分なりの答えを導き出して道なき道を切り拓いていけるかどうかが問われる時代だから、そのポテンシャルを人間性も含めて判断するためには、面接試験が必須なのである。
となっている。たとえばセンターレベルの試験で6割取ることが卒業要件であるってことになると、まぁいいたかないがそれをクリアするために全国の高校生が必死に勉強してくれるわけはなくて大量に卒業できない事態になりそうだ。大前氏もさすがにそれはわかるらしくて、試験クリアできない人には補習をして卒業させると書いているけど、じゃ、結局やっぱり基礎学力の担保はできないよね。
ところで、高校卒業資格センター試験なるものを実施するとなると、もちろん記述とかは無理で全部マークシートにするとしても、受ける人数が現状のセンターよりはずいぶん多くなり、音楽や美術など科目も増え、かつ何度も受けるイメージ、ということは作業量がどれだけ増えるのか…!? ずいぶんな体勢を整えないと無理だと思うけど。
それと、全員にポートフォリオ出させてとなるとそれを読むのだって大変だけど、面接試験必須っていったい、どれだけの量の面接を(それもポテンシャルと人間性を判断できるような)するつもりなのか、そりゃ今回ぽしゃった記述よりずいぶん無理でしょ。と思うと大前氏はこんなことを書いている…
受験生数が多くて先生が足りない私立大学の場合は、自校OBに協力してもらえばよい。
…いやいやいやいや…文科省の共通テスト構想よりさらに無茶いってるよこの人…
いったい寄せ集めで面接して「ポテンシャルと人間性」を判断されちゃう側の身になってみてよ。
こんなでたらめな内容でも、エライ人が書くと週刊誌に載っちゃうんだね。それとも、炎上商法かな…
要するに、「一括で」込み入った入試(記述とか、ポートフォリオとか、面接とか)しようとすると実務上破綻するので、
現状は、各大学が工夫を凝らして、学力重視の一般枠、自己アピール重視のAO枠、高校できちんとやってたこと重視の推薦枠、とか各種取り交ぜてベスト解を探ってるわけでしょ。それ以上のことってないと思うの。
そして、国全体としてはセンター試験みたいな、一律に基礎学力を測るテストを準備している。
何かこれ以上のことができるんですかね? やれるとすれば、それこそ
----- 最後の段落
少子化が進む日本の大学は、これから格差が拡大する。そして、その優劣は入学させた人材の優劣に依存するはずだから、生き残っていくためには優秀な人材の“原石”を入試で見抜く努力を怠ってはならない。各大学はそういう覚悟を持ち、文科省任せではなく、自ら入試改革に取り組むべきなのだ。
-----
ここだけは同意。本気で入試方法を、そして入試問題を磨くべし。
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
大学入試「指定校・付属校推薦入試は即刻廃止を」と大前研一氏
を読んでみた。
冒頭には「迷走する文部科学省主導の「大学入試改革」につきあっていては、日本の大学入試制度は混乱するだけで何も得られない。教育の質を高めるには、どのような入試制度が望ましいのか、経営コンサルタントの大前研一氏が考察する。」とあったので、国全体の施策としてどうすればよいのかの分析が展開されているのかとちょっと期待したけど…
中身は「現在の大学入試制度で、何よりも許しがたいのは私立大学の「指定校推薦入試」や「付属校推薦入試」だ。」で始まっていて…各私立大学がそれぞれ工夫している入試の話? まぁそれはそれでいいとして、
なぜ推薦入試が許せないかというと、推薦が(一般入試よりも)早々と決まってしまって彼らちっとも勉強せんからだという。どきっ。。確かに、うちの次男とか、高三の12月末に学部学科が決まったら、暇なので自動車学校に通ってましたけどね。
しかし「その結果、高校3年間で学んでいるはずの内容を全く理解していないので、大学の理系学部などでは数学の基礎が弱くて授業ができず、補習から始めなければならないという事態になっている。」とあるけど、別にそんなことはなくて、一般入試の人と同じかそれ以上、数学や物理はできるから授業でも別に問題なかったですよ。英語はちょっと…問題あるかも…(小声)
数学がダメで補習から始めなければいけないほどだとすれば、それは推薦が決まってから遊び惚けていたからではなくて(数か月余計に遊んだからってそこまで劣化しない)、もともと基礎学力のない人に推薦合格出しちゃったからでは?
どんな入試をして、どんな人を合格させるかは、大学の命運を握っている非常に重要なことなので、ここは各大学が知恵を絞ってベストを尽くしているはず。いろんな枠を準備して、選考基準をどうすればうまくいくか、考えたあげくのそういう推薦入試をしているということは、まぁ他の枠(たとえば一般入試)を増やしたからってそれよりマシな人材を取れないからやってるのではないでしょうか。
まぁ、とにかく入学者の基礎学力を確保したいってことであれば、全部をシンプルに一般入試枠(ペーパーテスト)にするという方針は理解できるけど、大前氏の主張はそういうことでもないようで、ここからさらにねじれていきます。
「そもそも日本の大学教育は、高校における文系・理系の選択が早いこともあって、オールラウンドに活躍できる人材が育ちにくい。幅広い教養と論理的思考力を身につけるリベラルアーツ教育も極めて貧弱だ。このため、関心分野が偏ったバランスの悪い人間が出てきてしまう。」…じゃ、文系・理系の選択が遅くてリベラルアーツ教育もさかんな付属校ルートなんてバッチリじゃないですか。
入試をいじることで高校以下の教育が変わるかどうか(どう変わるか)もそんなに明らかなつながりがある話ではないと思うけど、大前氏の主張は「日本人が世界で互角に戦えるようになるためには、語学に加えて、セオリー・オブ・シンキングやリーダーシップを身につけることができる教育にゼロベースで転換しなければならない。その契機となるのが真の大学入試改革…」とのことなので、ともかくそういった変化が高校までの教育にもたらされるためにはどういった入試にすればいいのかと。
大前氏の別記事があった:
大学入試は卒試・書類・面接の3段階選考にすべきである
これによれば、
「卒試」…高校卒業資格センター試験。高校まで12年間の教育内容をきちんと理解したかどうかを検証するもので、英語、国語、地理歴史、数学、理科などの受験科目だけでなく、音楽や美術も含めた全科目で、学習指導要領を司っている文科省が責任を持って全国一斉に行なう。
「書類」…受験生が自分のプロフィール(高卒資格センター試験の結果、内申書、ボランティア活動や社会貢献などのレポート)を志望大学に提出する。大学側はそれを独自の選考基準によってふるい分け、自分たちが受け入れたいプロフィールの学生に受験資格を付与する。
「独自入試」…(ペーパーテストもよいが)面接試験を実施することだ。21世紀は答えを覚えたかどうかではなく、答えのない世界で自分なりの答えを導き出して道なき道を切り拓いていけるかどうかが問われる時代だから、そのポテンシャルを人間性も含めて判断するためには、面接試験が必須なのである。
となっている。たとえばセンターレベルの試験で6割取ることが卒業要件であるってことになると、まぁいいたかないがそれをクリアするために全国の高校生が必死に勉強してくれるわけはなくて大量に卒業できない事態になりそうだ。大前氏もさすがにそれはわかるらしくて、試験クリアできない人には補習をして卒業させると書いているけど、じゃ、結局やっぱり基礎学力の担保はできないよね。
ところで、高校卒業資格センター試験なるものを実施するとなると、もちろん記述とかは無理で全部マークシートにするとしても、受ける人数が現状のセンターよりはずいぶん多くなり、音楽や美術など科目も増え、かつ何度も受けるイメージ、ということは作業量がどれだけ増えるのか…!? ずいぶんな体勢を整えないと無理だと思うけど。
それと、全員にポートフォリオ出させてとなるとそれを読むのだって大変だけど、面接試験必須っていったい、どれだけの量の面接を(それもポテンシャルと人間性を判断できるような)するつもりなのか、そりゃ今回ぽしゃった記述よりずいぶん無理でしょ。と思うと大前氏はこんなことを書いている…
受験生数が多くて先生が足りない私立大学の場合は、自校OBに協力してもらえばよい。
…いやいやいやいや…文科省の共通テスト構想よりさらに無茶いってるよこの人…
いったい寄せ集めで面接して「ポテンシャルと人間性」を判断されちゃう側の身になってみてよ。
こんなでたらめな内容でも、エライ人が書くと週刊誌に載っちゃうんだね。それとも、炎上商法かな…
要するに、「一括で」込み入った入試(記述とか、ポートフォリオとか、面接とか)しようとすると実務上破綻するので、
現状は、各大学が工夫を凝らして、学力重視の一般枠、自己アピール重視のAO枠、高校できちんとやってたこと重視の推薦枠、とか各種取り交ぜてベスト解を探ってるわけでしょ。それ以上のことってないと思うの。
そして、国全体としてはセンター試験みたいな、一律に基礎学力を測るテストを準備している。
何かこれ以上のことができるんですかね? やれるとすれば、それこそ
----- 最後の段落
少子化が進む日本の大学は、これから格差が拡大する。そして、その優劣は入学させた人材の優劣に依存するはずだから、生き残っていくためには優秀な人材の“原石”を入試で見抜く努力を怠ってはならない。各大学はそういう覚悟を持ち、文科省任せではなく、自ら入試改革に取り組むべきなのだ。
-----
ここだけは同意。本気で入試方法を、そして入試問題を磨くべし。
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社










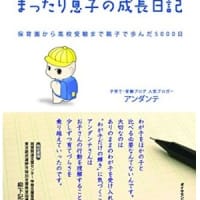











じゃあセンター利用者とか一般入試者は
入学後の成績が推薦よりいいかっていうと、
そうでもないです。
確かに、入学当初の英語の成績は
平均して推薦のほうが悪いとか、
個々の差はなくもないです。
でも、それが4年間続くわけでも、
全教科に共通するわけでもない。
私は、どっちかってーと、
推薦だろうが一般入試だろうが、
ここの大学行きたい!
と思えるような大学目指すしかないよなあ、
と思ってます。
実態とかけ離れていたり、非現実的だったり、
何を根拠にと思う部分もありました。
一部の一般受験至上主義の人たちを増長させており、
正しいことが伝わってないなあと、残念でした。
>数学の基礎が弱くて授業ができず、補習から始めなければならない
そのような付属生、推薦生を、今のところ知りません^^;
数年前に理科大が入試の種類と入学後の成績の関係を
検証した結果を発表しました。
入試、1年終了時、卒業時の成績を比較したところ、
入試の形態や入試の点数と卒業時の成績には、
相関関係がみられず、
大学1年次の成績とは関係性があったようです。
理科大の調査からもわかるように、
入学後興味を持てず勉強の意欲を無くしてしまう
学生がいます。
受験の物理数学は面白く、大学とのギャップが大きいのも一因かと。
あっ、英語に関してはおっしゃる通りです(-_-;;
付属生全員ではないですが...
入試改革もいいですが、大学の教育改革も必要では?
もう少し進級、卒業が厳しくしてもいいような気がしました。
個人差大きいけれどもおしなべてどの枠の子もちょぼちょぼ、と、またそうでなかったら枠のサイズを変更すればいい話なんだから。
付属の子はその大学ラブになって入って、仲間もたくさんいるので楽しくやって、英語ちょっとできなくっても(^^;; なんとかやってるんだと思う。
付属は入ってからのギャップ(学科のやってることが合わない…)になりにくいのも強みですね。情報行き届いてるし一般入試の難易度関係なくじっくり選べるから。
> 入試改革もいいですが、大学の教育改革も必要では?
そうねぇ。結局のところ、入試だけでどうこうなるわけじゃない。
まず、指定校推薦で入った方を批判するつもりはありませんのでお断りしておきます。またこれを無くすだけで入試がよくなるわけでもありませんし、教育改革を入試改革に押し付けるのもおかしいと考えています。
しかし指定校推薦は多くの弊害を生んでいることは間違いなく大前氏だけでなく一般入試を受ける受験生のほぼ100%が指定校推薦を敵視していることは事実で廃止含めて見直しは必須ということは断言しておきます。その背景をご存じかもしれませんが紹介します。
◆関西学院の例
https://www.kwansei.ac.jp/kikaku/attached/0000171236.pdf
数年前、立命館が指定校枠を増やしすぎてレベルダウンして評価を大きく落としましたが今は改善しています、一方で同じ状態に陥っているのが関学です。指定校推薦入学者が定員枠を大幅に超えて入るため、一般入試の倍率が急増し、なんと、学部によっては定員の半分以下しか入学できない事態に陥っています。2019年入学者において看板の経済学部において、
一般入試:入学者/定員=0.48
AO入試:入学者/定員=1.55
推薦入試:入学者/定員=1.35
教育学部では
一般入試:入学者/定員=0.35
推薦入試:入学者/定員=4.69
AOや推薦入試入学者が定員をはるかに超えてはいるためあろうことか一般入試入学者が定員をはるかに下回る事態に陥っています。
まあ、これは大学側のマネージメントがズタボロということで必ずしも推薦入試全体が悪いとも言えないですが。しかし、近年よく聞くのは、高校の特進クラスと一般クラスがあって優秀な特進クラスの生徒は推薦枠はもらえず一般クラスの生徒が推薦もらって(当然)受かって特進クラスの人が落ちてしまうという事態があたりまえのように発生しています。高校は少しでも実績をあげるために一般で受かる可能性がある人には推薦を出さないということで戦略としては理解しますが落ちた人はかわいそうです。
https://tokumablog.com/2019/09/27/指定校は苦労する%EF%BC%9F-学力が足りずに入った男の経/
これは指定校推薦で入る人を安心させるために書いた体験談で中身はおいときますが、
偏差値40未満だけど指定校推薦で偏差値55~57くらいの大学に入ったと書いています。指定校推薦ではごく当たり前にみられる偏差値実力差です。こういう人がわんさといるわけですから実力で入った人や偏差値55くらいで落ちた人が指定校で入った人を敵視してしまうのはある意味、仕方ないことです。
入試改革は指定校を無くせば解決するとは思いませんが今の指定校推薦はあまりに不条理であり廃止するか残すとしても改善は必須です。また、あなたのご子息は問題ないようですが実際についていけずに留年する人が多発しているのも事実です。
性質というか傾向に違いがあっても、まぁ何かしらを頑張って入ってきたというような認識? 勝手口から入るための努力というかめんどくささは、不向きな人にはほんとに不向きで、うちの娘とか(たぶん私も)無理なんで、いや勉強だけすりゃなんとかなる表玄関のほうが楽でしょという認識です。個人としては、自分に合った「口」からの入学を目指せばいいという話になりますよね。
一方、大学はいろんな枠から入ってきた学生の後追い調査を通じてよりよい入試を模索していて、結果としては入ってからの成績に差がないという状況になっているようです…というか、そのようにマネジメントするはずで、そうなってないとすればそりゃおっしゃるとおりマネジメントの失敗です。
関東住みなので関西の状況はあまり生で(直接の知人から)入ってこないのですが、そんな歪んだ状況になってしまっているとすれば…それはどういう「大人の事情」があったのでしょうね?