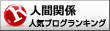礼拝宣教 創世記2章4節b~17節 聖霊降臨(ペンテコステ)
「お帰りなさい」。聖霊降臨おめでとうございます。この日、使徒言行録2章にありますように、聖霊がキリストを信じる群れに降り、神の救いの出来事福音を世界中に伝える教会が誕生いたしました。今日はこのうるわしき喜び出来事を感謝しつつ、礼拝を捧げてまいりたいと思います。
昨日は大阪ブロック女性一日修養会が当教会で開かれ、やすらぎの介護シャローム副社長の俣木聖子さんから貴重な体験に基づくお話を伺いました。その中で、特に心に留まりました言葉は、「神さまから頂いたビジョンを生きることは狭い道を選び取ることであったが、本当にこれでよかった」とおっしゃっていました。人はそれぞれ生かされている存在であり、何らかの使命をそれぞれに与えられているのです。
さて、本日は先程読んで頂いた創世記2章のところから、「人の存在と使命」と題し、御言葉に聞いていきたいと思います。
「人の存在(命)」
先の創世記1章では、神があらゆる被造物、野の草木などをお造になられた後で、動物などの生き物を従わせ治める者として、人をお造りになったという記事を読みましたが。
今日の箇所では、神が人を被造物の初穂としてお造りになったということが強調されています。
2章4節以降に、「主なる神が地と天をつくられたとき、地上にはまだ野の木も、野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。」
火星から探査機によって送られてきた映像など見ますと、草も生えていない荒涼とした赤土の地表に虫一匹も見当たらず、生命が感じられない世界とはこうも殺伐としたものなのか、と思いますが。そんな火星でもかつては水が流れていた運河だったのでは、というような痕跡が見られるということで、その地下には何らかの生き物が存在するかも知れないと、探索が続いているのだそうです。
6節に「水が地下から湧き出て、土の面すべてを潤した」とあります。
地下から泉が湧き出たことによって命が始まってゆくのですね。1章1節には「神の霊が水の面を動いていた」とあります。
神はこの潤された地に、「土のちり(アダマ)で人(アダム)を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられる」ことで、「人は生きる者となった」と、聖書は伝えます。
ここには、私たち人は神によって造られた大地の一部である「土くれ」から造られたことが示されております。人は生まれ、いずれは死に、その体はやがて大地に帰ります。それだけであるのなら何ら草木のような他の被造物と変わりありません。しかし、人は神の命の息が吹き込まれることで、霊を持って生きる者とされた霊的存在である、と聖書は伝えます。それは初めの人のみならず、今も、生きとし生けるすべての人は神の命の息を吹きこまれ生かされている霊的存在であり、そこに人の尊厳があるのです。
さて、8節で、「主なる神は、東の方のエデンに園を設けた」とございます。
このエデンの園が地理的にどこにあったのかは定かではありませんが、エデンには歓喜という意味があり、それは前回のお話になりましたように、神が「見よ、それは極めて良い」とされた見目うるわしい世界がそこに広がっていたことを想起させます。
主なる神は、園に「見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生えさせ」、人はそれを享受しながら生きる喜びを得ていた。それがエデンの園であったということです。今、私たちは流通も発達し、世界中の食べ物を口にすることが出来ますけれども。このエデン、歓喜あふれる世界の恵みを享受して生きる喜びをどこか見失っているような現実の社会であることを、考えさせられるわけです。
ところで、10節には、「エデンから1つの川が流れ、園を潤して、そこで分れて、4つの川になっていた」という記事があります。
先に、地下の湧水が地の面を潤していた、ということに触れましたが。水は命の源であり、それは人が生き、生活していくために不可欠な資源でもあります。旧約聖書の預言者エゼキエルは、幻を見て、水が神殿の敷居の下から湧き上がり、川となって流れゆくそのところはどこでも、群がる生き物すべてが生き返り、果実は絶えることなく実をつけるようすを謳っています。命の川の流れがあるところに、いやしと回復、豊かな食物の宝庫があるのです。
本日は聖霊降臨(ペンテコステ)の記念すべき礼拝を感謝のうちに捧げておりますが。ヨハネ福音書7章37節でイエスさまは、「わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる」と言われました。
これは、イエスさまを信じる人々が受ける聖霊であります。聖霊は生ける命の水であり、川のようにイエスさまを信じる人々からあふれ流れ、働かれるのであります。その豊かな恵みと神の臨在をいただいていることを体験できることは喜びであり、そこに私たちは「キリストにあるエデンの園」を見出すのであります。
「人の使命」
15節にうつりますが。ここで「主なる神は人を連れて来て、エデンの園に住まわせ、人がそこを耕し、守るようにされた」とあります。
先回の1章の創造の記事では、神は人に「動物や生き物を支配し、治めるように命じ、そこに神の「良い」という御声が響き渡ったのでありますが。この2章において神は、「人をそこに住まわせて、地を耕し、守るようにされた。」つまり、その管理を人に委託されたのです。
以前私が住んでいた九州の教会は畑があり、そこにナスやキュウリ、イチジクの木を植えていました。私はもっぱら食べるばかりで、たまに水をやる程度でしたが。それども時々土に触れ実のなってゆく様子を眺めるのは楽しいことでした。何でも土いじりはいやしの効果があるそうで、そういう時人はエデンの園にいた時のことを思い出すのでしょうか。
農園や菜園においてまず何より大事なのは、地を耕して命ある種や苗が育つためのよい土壌を作ることでしょう。そして水をやり日光に気をつけて肥料をやって守ってゆくことはむろん大事ですね。「地を耕し、地を守る。」そのことに心と体を使っていけば、それだけの報いがあるでしょうし、逆にそれを怠たり、その実りを乱獲するなら、その負は人の側に跳ね返ってきます。
福島の原発事故の直後、有機農法に取り組んで来られた農家の主(あるじ)が絶望し自ら命を絶つという痛ましい出来事がありました。長い年月をかけて耕し、手しおにかけてきた土壌が一瞬にして取り返しのつかないような汚染された地となってしまった。その無念というもの如何ばかりであったでしょうか。今も海に地に放射能汚染は繰り返され、それが地下水や井戸を経由し、又海産物や農産物を経由して人体にも及んでいることを危惧いたします。原発事故後、福島フィールドワークに参加した折、放射性物質が大気や水を汚染し、自然界の植物、生物、そして人体を汚染していることのそれが、目には見えないということに言いようのない怖れを強く感じました。
「神は人を住まわせ、人がそこを耕し守るようになれた。」神から管理を委託されたこの大地をどのように耕し、守っていくか。その真価がかつてないほどに問われている今の日本、私たちであります。
「自由と豊かさの中で」
さて、本日の箇所の16節以降を読みます。
主なる神は人に命じて言われた。「園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは、決して食べてはならない。食べると死んでしまう。」
この言葉を読んだ時、ある人たちは、すべての木から取って食べる自由があるなら善悪の知識の木からも取って食べてもいいじゃないか、というかも知れません。
けれども考えてください。エデンの園の所有者は一体誰でしょうか。それは人間ではなく神であります。神が人に生きるためのあらゆる恵みの賜物を与えておられるのです。それはただ神の一方的な恵みによるものです。にも拘わらず、人は自分がまるでそのすべての所有者であるかのようにむさぼり、人が神の恵みの賜物によって生かされているということを忘れ、管理者としての使命を投げ出し、土くれから出来た者にすぎない者であるかということを見失って遂に一線を越えてしまった時。人類は自ら招く殺伐とした状況に直面することになりはしないでしょうか。
人が神とエデンの園で顔と顔を合わせるように生きていた時、人は神が「決して食べるな」と命じている木に対して、「それに手をつけて食べないという自由を選び取る」事ができた。そこに平安があったからです。エデンの園はまさしく楽園でありました。
しかし、人がその与えられた自由をむさぼり食った時、いのちの神との関係は大きく損なわれ、地は呪われるものとなったのです。それは寓話に過ぎないとは決していえない現状が今、私たちの前には数知れず拡がっています。
社会、政治、医療、あらゆる分野でそのことが問われています。科学や文明の発展の中でこそ、いのちの神に対する畏れの念をもつことが求められています。科学や文明の発展の中で益々拡がっていく選択肢の中から私たちが何を選び取っていくのか。その与えられた自由が滅びを招くことだけは避けたいものです。
今日は神が人をお造りになられた記事から、私どもの存在と使命について、もう一度創造主の前にあって、祈り立ち帰って、神の作品として存在し、その使命を託されていることを再確認いたしましょう。
最後になりますが。
先週もJR西日本あんしん社会財団による「いのち」を考える連続講座に参加し、西宮市社会福祉協議会・障害者総合支援センターにしのみやセンター長で、NHKのEテレ障害者情報バラエティ「バリバラ」にレギュラー出演され、著書に「生まれてきてよかった~てんでバラバラ半世紀」などございます玉木幸則さんのお話を伺う機会がありました。ご自身脳性マヒで言語障害があり、90分という講演時間を話しきるのは大変なことだと初め思ったのですが、あっという間の90分でした。この方は仮死状態でお生まれになり、4歳というまだ幼い頃親から「肢体不自由者の施設」に無理やり入れられるという経験をなさいます。しかし「そのつらい経験が、今の仕事を支えている」とおっしゃっていました。
玉木さんはそのお話で、「しあわせ」は世間や人が決めることはできないとおっしゃっていました。最近ニュースで、超軽量児の赤ん坊を出産したばかりのお母さんが、「この子は生きるために生まれた」とおっしゃったその言葉が、自分のことのようにうれしくて、強く心揺さぶられたそうです。
神さまは人を土のちりで造り、そこに命の息を吹き入れて、人が生きる者となった、と聖書は伝えます。命あるすべての人に、一人ひとりに、「生きるために生まれた」存在の意義と使命があります。今日私たちは聖霊の命の息吹をおぼえつつ、それぞれ世に遣わされてまいりましょう。今週の一日一日のうえに神の救いの御業が起こされていくことを祈り、期待しながら。お祈りいたします。
「お帰りなさい」。聖霊降臨おめでとうございます。この日、使徒言行録2章にありますように、聖霊がキリストを信じる群れに降り、神の救いの出来事福音を世界中に伝える教会が誕生いたしました。今日はこのうるわしき喜び出来事を感謝しつつ、礼拝を捧げてまいりたいと思います。
昨日は大阪ブロック女性一日修養会が当教会で開かれ、やすらぎの介護シャローム副社長の俣木聖子さんから貴重な体験に基づくお話を伺いました。その中で、特に心に留まりました言葉は、「神さまから頂いたビジョンを生きることは狭い道を選び取ることであったが、本当にこれでよかった」とおっしゃっていました。人はそれぞれ生かされている存在であり、何らかの使命をそれぞれに与えられているのです。
さて、本日は先程読んで頂いた創世記2章のところから、「人の存在と使命」と題し、御言葉に聞いていきたいと思います。
「人の存在(命)」
先の創世記1章では、神があらゆる被造物、野の草木などをお造になられた後で、動物などの生き物を従わせ治める者として、人をお造りになったという記事を読みましたが。
今日の箇所では、神が人を被造物の初穂としてお造りになったということが強調されています。
2章4節以降に、「主なる神が地と天をつくられたとき、地上にはまだ野の木も、野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。」
火星から探査機によって送られてきた映像など見ますと、草も生えていない荒涼とした赤土の地表に虫一匹も見当たらず、生命が感じられない世界とはこうも殺伐としたものなのか、と思いますが。そんな火星でもかつては水が流れていた運河だったのでは、というような痕跡が見られるということで、その地下には何らかの生き物が存在するかも知れないと、探索が続いているのだそうです。
6節に「水が地下から湧き出て、土の面すべてを潤した」とあります。
地下から泉が湧き出たことによって命が始まってゆくのですね。1章1節には「神の霊が水の面を動いていた」とあります。
神はこの潤された地に、「土のちり(アダマ)で人(アダム)を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられる」ことで、「人は生きる者となった」と、聖書は伝えます。
ここには、私たち人は神によって造られた大地の一部である「土くれ」から造られたことが示されております。人は生まれ、いずれは死に、その体はやがて大地に帰ります。それだけであるのなら何ら草木のような他の被造物と変わりありません。しかし、人は神の命の息が吹き込まれることで、霊を持って生きる者とされた霊的存在である、と聖書は伝えます。それは初めの人のみならず、今も、生きとし生けるすべての人は神の命の息を吹きこまれ生かされている霊的存在であり、そこに人の尊厳があるのです。
さて、8節で、「主なる神は、東の方のエデンに園を設けた」とございます。
このエデンの園が地理的にどこにあったのかは定かではありませんが、エデンには歓喜という意味があり、それは前回のお話になりましたように、神が「見よ、それは極めて良い」とされた見目うるわしい世界がそこに広がっていたことを想起させます。
主なる神は、園に「見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生えさせ」、人はそれを享受しながら生きる喜びを得ていた。それがエデンの園であったということです。今、私たちは流通も発達し、世界中の食べ物を口にすることが出来ますけれども。このエデン、歓喜あふれる世界の恵みを享受して生きる喜びをどこか見失っているような現実の社会であることを、考えさせられるわけです。
ところで、10節には、「エデンから1つの川が流れ、園を潤して、そこで分れて、4つの川になっていた」という記事があります。
先に、地下の湧水が地の面を潤していた、ということに触れましたが。水は命の源であり、それは人が生き、生活していくために不可欠な資源でもあります。旧約聖書の預言者エゼキエルは、幻を見て、水が神殿の敷居の下から湧き上がり、川となって流れゆくそのところはどこでも、群がる生き物すべてが生き返り、果実は絶えることなく実をつけるようすを謳っています。命の川の流れがあるところに、いやしと回復、豊かな食物の宝庫があるのです。
本日は聖霊降臨(ペンテコステ)の記念すべき礼拝を感謝のうちに捧げておりますが。ヨハネ福音書7章37節でイエスさまは、「わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる」と言われました。
これは、イエスさまを信じる人々が受ける聖霊であります。聖霊は生ける命の水であり、川のようにイエスさまを信じる人々からあふれ流れ、働かれるのであります。その豊かな恵みと神の臨在をいただいていることを体験できることは喜びであり、そこに私たちは「キリストにあるエデンの園」を見出すのであります。
「人の使命」
15節にうつりますが。ここで「主なる神は人を連れて来て、エデンの園に住まわせ、人がそこを耕し、守るようにされた」とあります。
先回の1章の創造の記事では、神は人に「動物や生き物を支配し、治めるように命じ、そこに神の「良い」という御声が響き渡ったのでありますが。この2章において神は、「人をそこに住まわせて、地を耕し、守るようにされた。」つまり、その管理を人に委託されたのです。
以前私が住んでいた九州の教会は畑があり、そこにナスやキュウリ、イチジクの木を植えていました。私はもっぱら食べるばかりで、たまに水をやる程度でしたが。それども時々土に触れ実のなってゆく様子を眺めるのは楽しいことでした。何でも土いじりはいやしの効果があるそうで、そういう時人はエデンの園にいた時のことを思い出すのでしょうか。
農園や菜園においてまず何より大事なのは、地を耕して命ある種や苗が育つためのよい土壌を作ることでしょう。そして水をやり日光に気をつけて肥料をやって守ってゆくことはむろん大事ですね。「地を耕し、地を守る。」そのことに心と体を使っていけば、それだけの報いがあるでしょうし、逆にそれを怠たり、その実りを乱獲するなら、その負は人の側に跳ね返ってきます。
福島の原発事故の直後、有機農法に取り組んで来られた農家の主(あるじ)が絶望し自ら命を絶つという痛ましい出来事がありました。長い年月をかけて耕し、手しおにかけてきた土壌が一瞬にして取り返しのつかないような汚染された地となってしまった。その無念というもの如何ばかりであったでしょうか。今も海に地に放射能汚染は繰り返され、それが地下水や井戸を経由し、又海産物や農産物を経由して人体にも及んでいることを危惧いたします。原発事故後、福島フィールドワークに参加した折、放射性物質が大気や水を汚染し、自然界の植物、生物、そして人体を汚染していることのそれが、目には見えないということに言いようのない怖れを強く感じました。
「神は人を住まわせ、人がそこを耕し守るようになれた。」神から管理を委託されたこの大地をどのように耕し、守っていくか。その真価がかつてないほどに問われている今の日本、私たちであります。
「自由と豊かさの中で」
さて、本日の箇所の16節以降を読みます。
主なる神は人に命じて言われた。「園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは、決して食べてはならない。食べると死んでしまう。」
この言葉を読んだ時、ある人たちは、すべての木から取って食べる自由があるなら善悪の知識の木からも取って食べてもいいじゃないか、というかも知れません。
けれども考えてください。エデンの園の所有者は一体誰でしょうか。それは人間ではなく神であります。神が人に生きるためのあらゆる恵みの賜物を与えておられるのです。それはただ神の一方的な恵みによるものです。にも拘わらず、人は自分がまるでそのすべての所有者であるかのようにむさぼり、人が神の恵みの賜物によって生かされているということを忘れ、管理者としての使命を投げ出し、土くれから出来た者にすぎない者であるかということを見失って遂に一線を越えてしまった時。人類は自ら招く殺伐とした状況に直面することになりはしないでしょうか。
人が神とエデンの園で顔と顔を合わせるように生きていた時、人は神が「決して食べるな」と命じている木に対して、「それに手をつけて食べないという自由を選び取る」事ができた。そこに平安があったからです。エデンの園はまさしく楽園でありました。
しかし、人がその与えられた自由をむさぼり食った時、いのちの神との関係は大きく損なわれ、地は呪われるものとなったのです。それは寓話に過ぎないとは決していえない現状が今、私たちの前には数知れず拡がっています。
社会、政治、医療、あらゆる分野でそのことが問われています。科学や文明の発展の中でこそ、いのちの神に対する畏れの念をもつことが求められています。科学や文明の発展の中で益々拡がっていく選択肢の中から私たちが何を選び取っていくのか。その与えられた自由が滅びを招くことだけは避けたいものです。
今日は神が人をお造りになられた記事から、私どもの存在と使命について、もう一度創造主の前にあって、祈り立ち帰って、神の作品として存在し、その使命を託されていることを再確認いたしましょう。
最後になりますが。
先週もJR西日本あんしん社会財団による「いのち」を考える連続講座に参加し、西宮市社会福祉協議会・障害者総合支援センターにしのみやセンター長で、NHKのEテレ障害者情報バラエティ「バリバラ」にレギュラー出演され、著書に「生まれてきてよかった~てんでバラバラ半世紀」などございます玉木幸則さんのお話を伺う機会がありました。ご自身脳性マヒで言語障害があり、90分という講演時間を話しきるのは大変なことだと初め思ったのですが、あっという間の90分でした。この方は仮死状態でお生まれになり、4歳というまだ幼い頃親から「肢体不自由者の施設」に無理やり入れられるという経験をなさいます。しかし「そのつらい経験が、今の仕事を支えている」とおっしゃっていました。
玉木さんはそのお話で、「しあわせ」は世間や人が決めることはできないとおっしゃっていました。最近ニュースで、超軽量児の赤ん坊を出産したばかりのお母さんが、「この子は生きるために生まれた」とおっしゃったその言葉が、自分のことのようにうれしくて、強く心揺さぶられたそうです。
神さまは人を土のちりで造り、そこに命の息を吹き入れて、人が生きる者となった、と聖書は伝えます。命あるすべての人に、一人ひとりに、「生きるために生まれた」存在の意義と使命があります。今日私たちは聖霊の命の息吹をおぼえつつ、それぞれ世に遣わされてまいりましょう。今週の一日一日のうえに神の救いの御業が起こされていくことを祈り、期待しながら。お祈りいたします。