
春の頃、町内の人と雑談をしていたら、キビの話になりました。以前、キビの粉をもらったことがありました。どうやって食べたか、あまり記憶にないのですが、おそらく団子のようなものにして食べたと思います。
キビの話は、鶏の餌の中に入っている丸い小さな、およそ仁丹、と言っても仁丹を知らない人もいますから、ほかのものにたとえると、米粒の三分の一くらいの大きさの茶色い粒のことからでした。昨年の夏、それがこぼれたのが芽を出したのか、鶏小屋の脇にトウモロコシのような葉をもった、トウモロコシほどはおおきくならないものが生えてきたのです。なんだろうと思って、抜かないで大きくしましたら、ザンバラな、その仁丹くらいの実をつけた房ができました。
町内の人は、ある日「こんにちは」と我が家に大きな袋を持ってきました。「キビやってみっか?」と、どさっ(?)と軽い音を出して袋をおきました。明けてみると乾いたザンバラな房を付けたものがたくさん入っています。しかし、鶏小屋の脇に育った、あの実とは違います。ということは。確かめてみると、それはモロコシだそうです。モロコシはコーリャンとも言うということは後で知りました。唐土(もろこし:中国)の方から来たので、そういう名前がついたのでしょうか。
それを、きちんと肥料をやって蒔いてみると、どうしてか芽が出たのですが、かなりムラがあります。それで、まだ間に合うので蒔き足したのですが、それでもまたムラ。ある日、畝のあたりにクシャクシャした土をかきまわしている跡がありました。ハウスの中にあるものと似ています。そうだ、スズメだ。
スズメに掘られて食べられていたのです。それでもめげずに何度も蒔き足しました。それでも成功率が低いので、だめで元々と思って、殺虫剤をかけてまいてみました。すると成功。今では、背の高さにはムラがありますが、それでもなんとか、あまりにも飛び飛びではないキビの列ができました。
問題は実ってからだそうです。スズメにまたねらわれるとか。それに雉も来るそうです。雉は思い体でキビを倒して食べるそうです。猟友会が離した雉が野生化したのが、けっこう悪さをするようになってきたとか。さて、まだ取らない狸の皮の見積もりをしているようなものですが、実ってきたらどのようにしたらよいか、悩みが目の前にぶら下がってきたような。










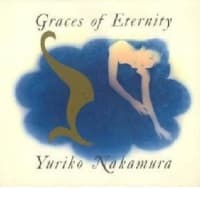










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます