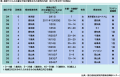東日本大震災で、沿岸の「防災林」としてのマツ林が津波の被害で根こそぎ倒れたことは皆さんご存じのことと思います。
1本だけ生き残ったマツも枯れてしまいました。
その際、生き残った樹木が注目されています。
もともとその地域に自生する広葉樹(タブノキなど)です。
特に「鎮守の森」として神社境内に植えられていたものは強く、神様を守りました。
広葉樹は地中に深く根を伸ばすので、倒れにくい。
一方、針葉樹は根の張り方が浅いので倒れやすい。
砂浜のマツ林は景観は美しいけれど、実は津波対策にはなり得なかったのです。
最近、自分の庭に植えたクスノキから落ちた種が芽吹いて苗木になったものを植え替えました。
ほんの30cmの木ですが、根っこはゆうに50cm以上伸びていてビックリ。「大地に根を張る」ことを実感した次第です。

うまく根付いてくれるといいのですが・・・。
「鎮守の森」の著書で有名な宮脇昭さんが立ち上がりました。
★ 瓦礫を活かす「森の防波堤」が命を守る: 植樹による復興・防災の緊急提言
がれきを埋め立てて土手を作り、そこに土地固有の広葉樹を植えるべしと指南しています。
すると、根っこが伸びて土手を自然の強固な防波堤にしてくれる、がれき処理もできると一石二鳥。
すばらしい!
がれき処理は日本全国の市町村がその受け入れを躊躇している難題です。
環境省には、そもそもがれきをその土地で活用するという視点がありません。
凝り固まった認識を新たにして、対応していただきたいと思います。
東北地方ではカキ養殖家の畠山重篤さんも活動しています。
彼も「森は海の恋人」としてカキを育てるのは豊かな森であることに着目して植林を続け、東日本大震災で大打撃を受けた養殖業が、森の力で見事に蘇った自然の力を実感していると見聞きしました。
「日本固有の広葉樹林による森の再生」
これは震災復興のみならず、日本再生のキーワードでもあると思います。
「花粉を作らないスギ」を研究している場合じゃない。
1本だけ生き残ったマツも枯れてしまいました。
その際、生き残った樹木が注目されています。
もともとその地域に自生する広葉樹(タブノキなど)です。
特に「鎮守の森」として神社境内に植えられていたものは強く、神様を守りました。
広葉樹は地中に深く根を伸ばすので、倒れにくい。
一方、針葉樹は根の張り方が浅いので倒れやすい。
砂浜のマツ林は景観は美しいけれど、実は津波対策にはなり得なかったのです。
最近、自分の庭に植えたクスノキから落ちた種が芽吹いて苗木になったものを植え替えました。
ほんの30cmの木ですが、根っこはゆうに50cm以上伸びていてビックリ。「大地に根を張る」ことを実感した次第です。

うまく根付いてくれるといいのですが・・・。
「鎮守の森」の著書で有名な宮脇昭さんが立ち上がりました。
★ 瓦礫を活かす「森の防波堤」が命を守る: 植樹による復興・防災の緊急提言
がれきを埋め立てて土手を作り、そこに土地固有の広葉樹を植えるべしと指南しています。
すると、根っこが伸びて土手を自然の強固な防波堤にしてくれる、がれき処理もできると一石二鳥。
すばらしい!
がれき処理は日本全国の市町村がその受け入れを躊躇している難題です。
環境省には、そもそもがれきをその土地で活用するという視点がありません。
凝り固まった認識を新たにして、対応していただきたいと思います。
東北地方ではカキ養殖家の畠山重篤さんも活動しています。
彼も「森は海の恋人」としてカキを育てるのは豊かな森であることに着目して植林を続け、東日本大震災で大打撃を受けた養殖業が、森の力で見事に蘇った自然の力を実感していると見聞きしました。
「日本固有の広葉樹林による森の再生」
これは震災復興のみならず、日本再生のキーワードでもあると思います。
「花粉を作らないスギ」を研究している場合じゃない。