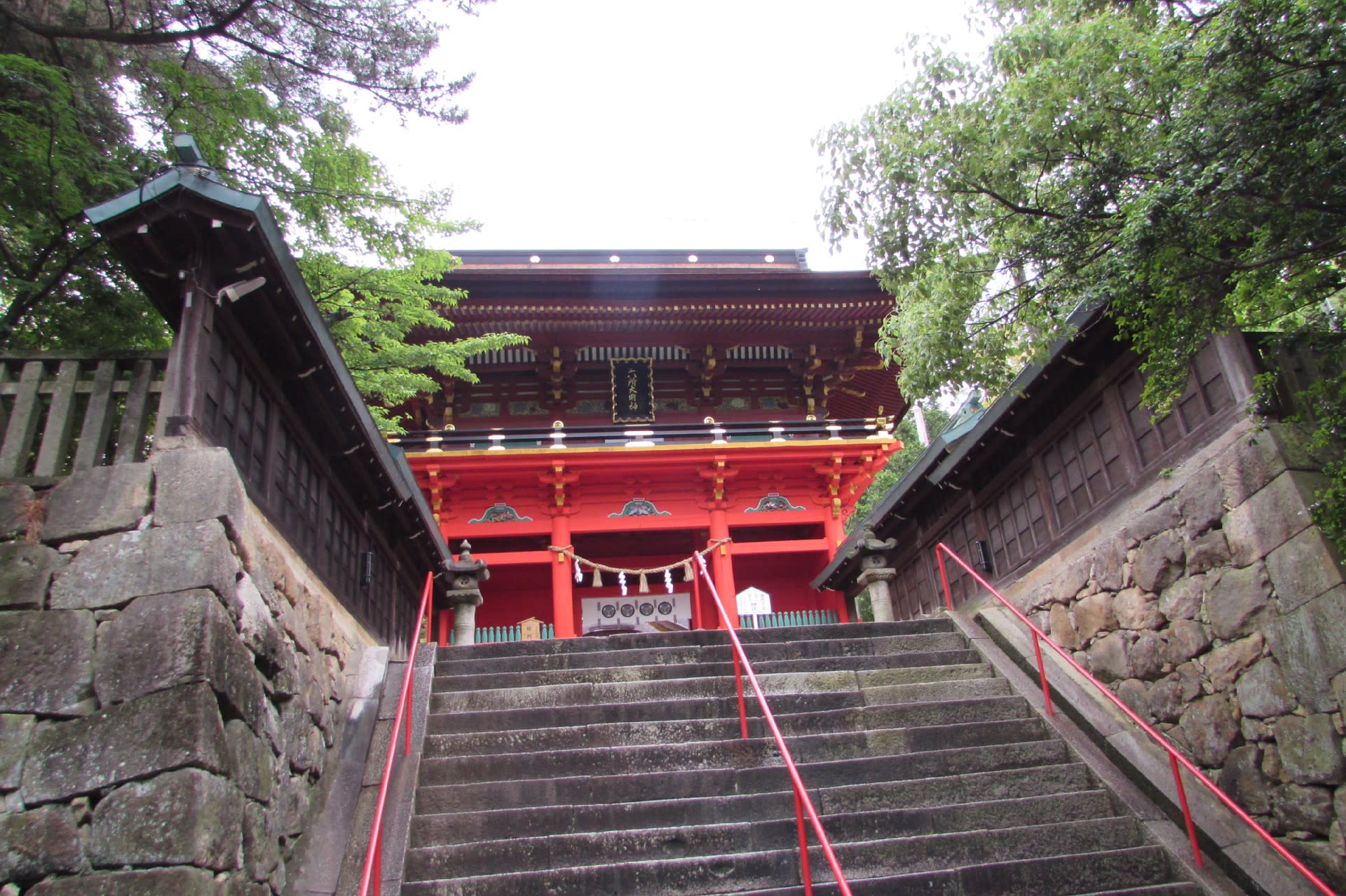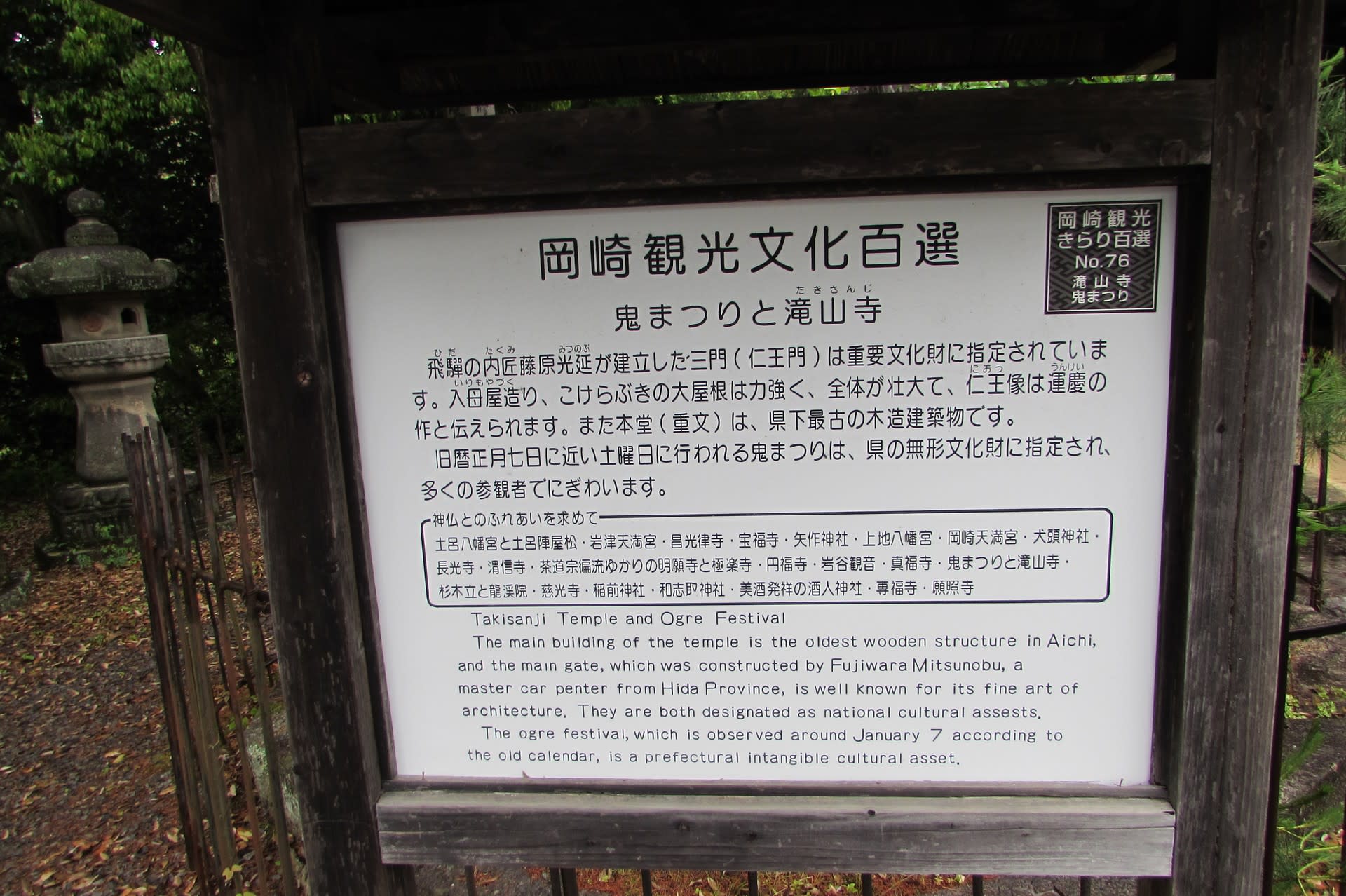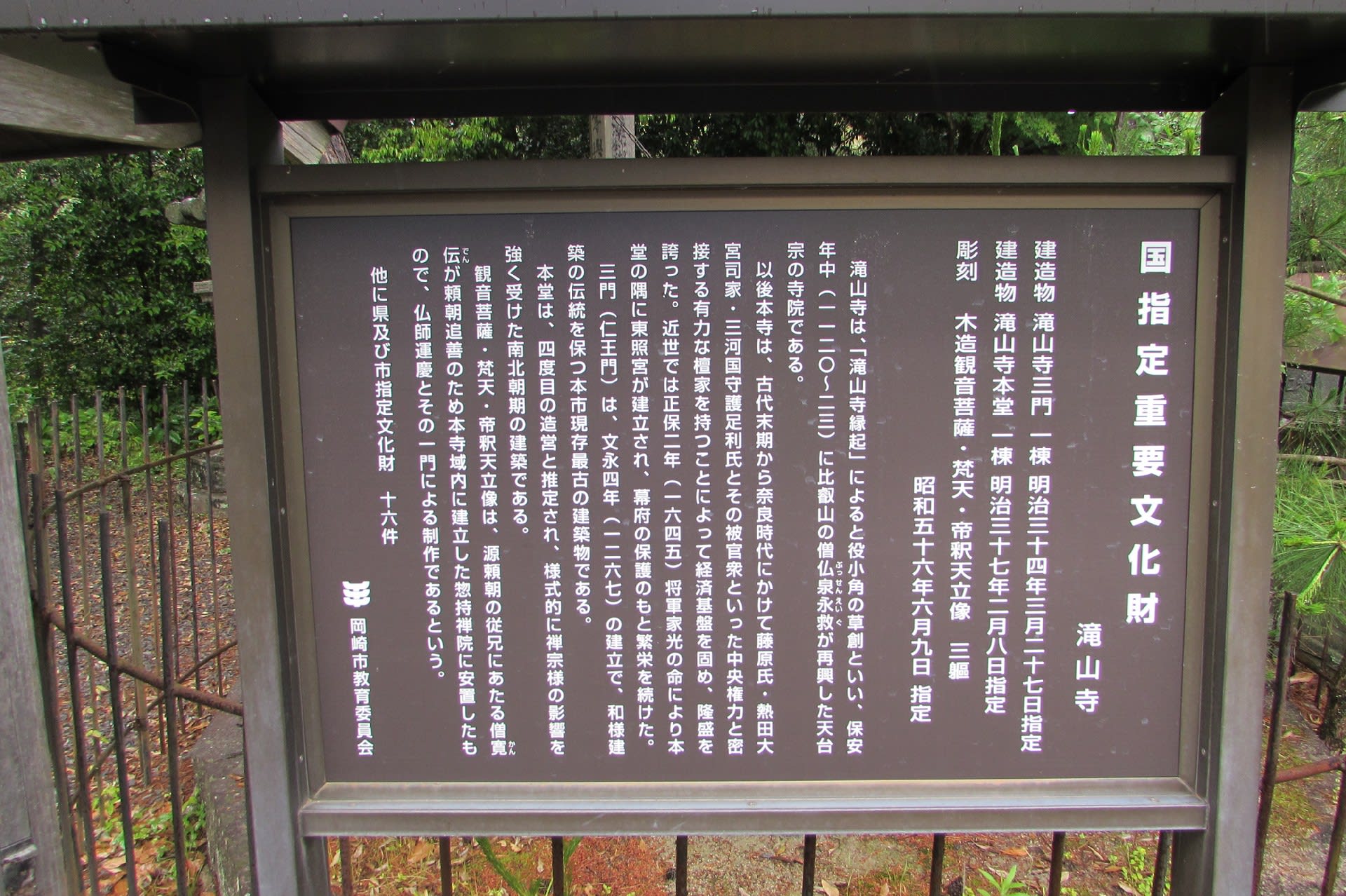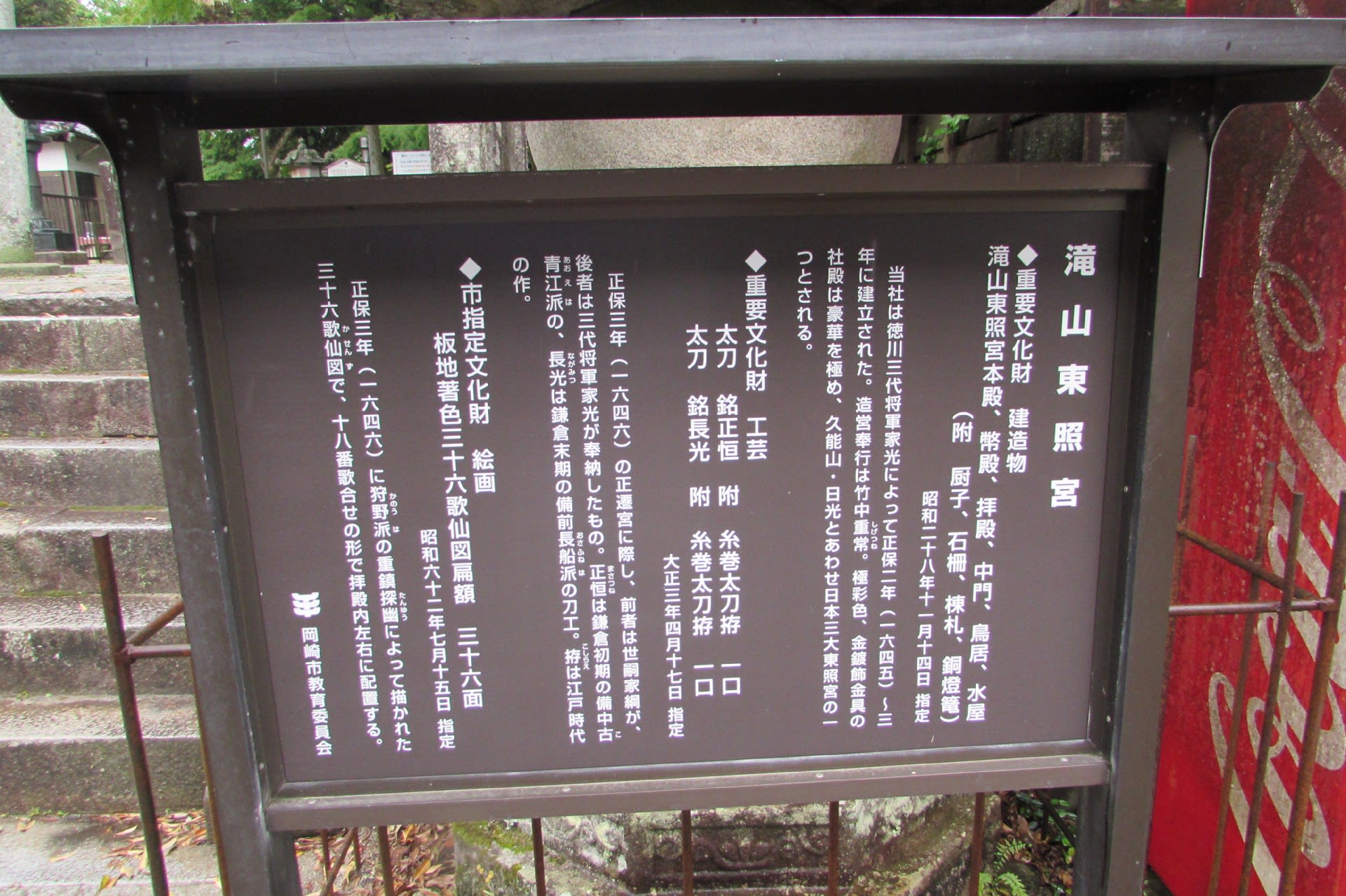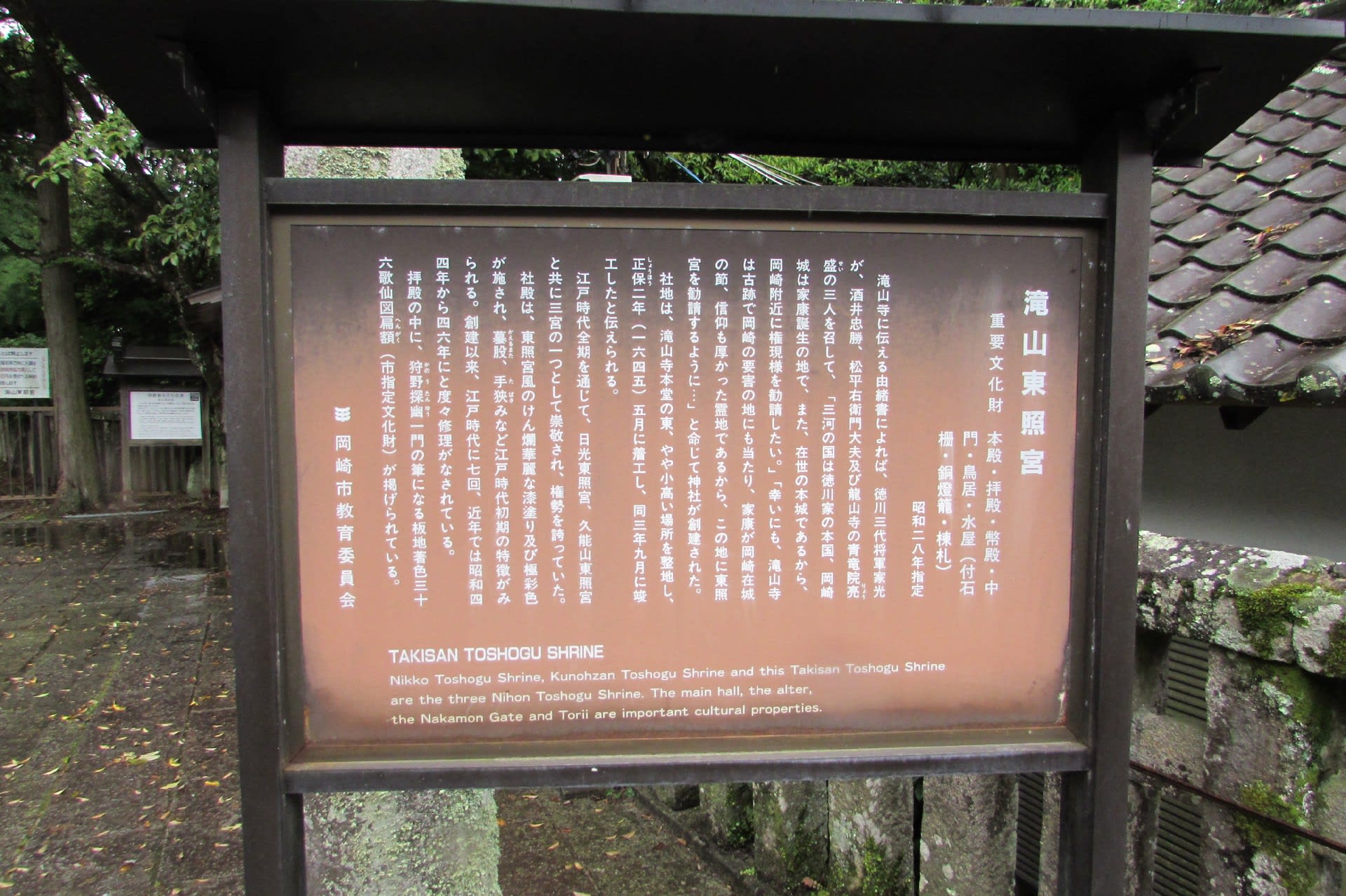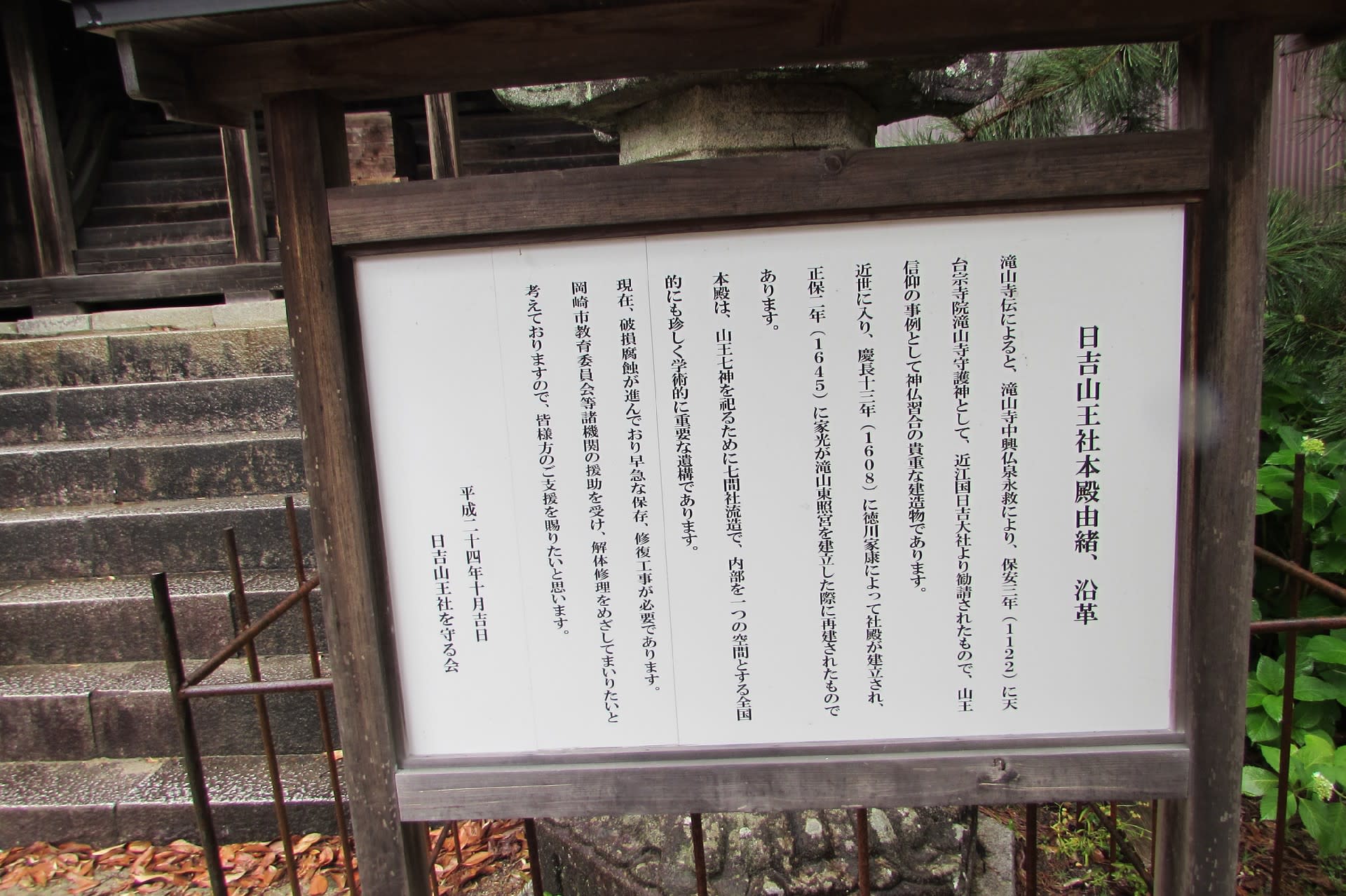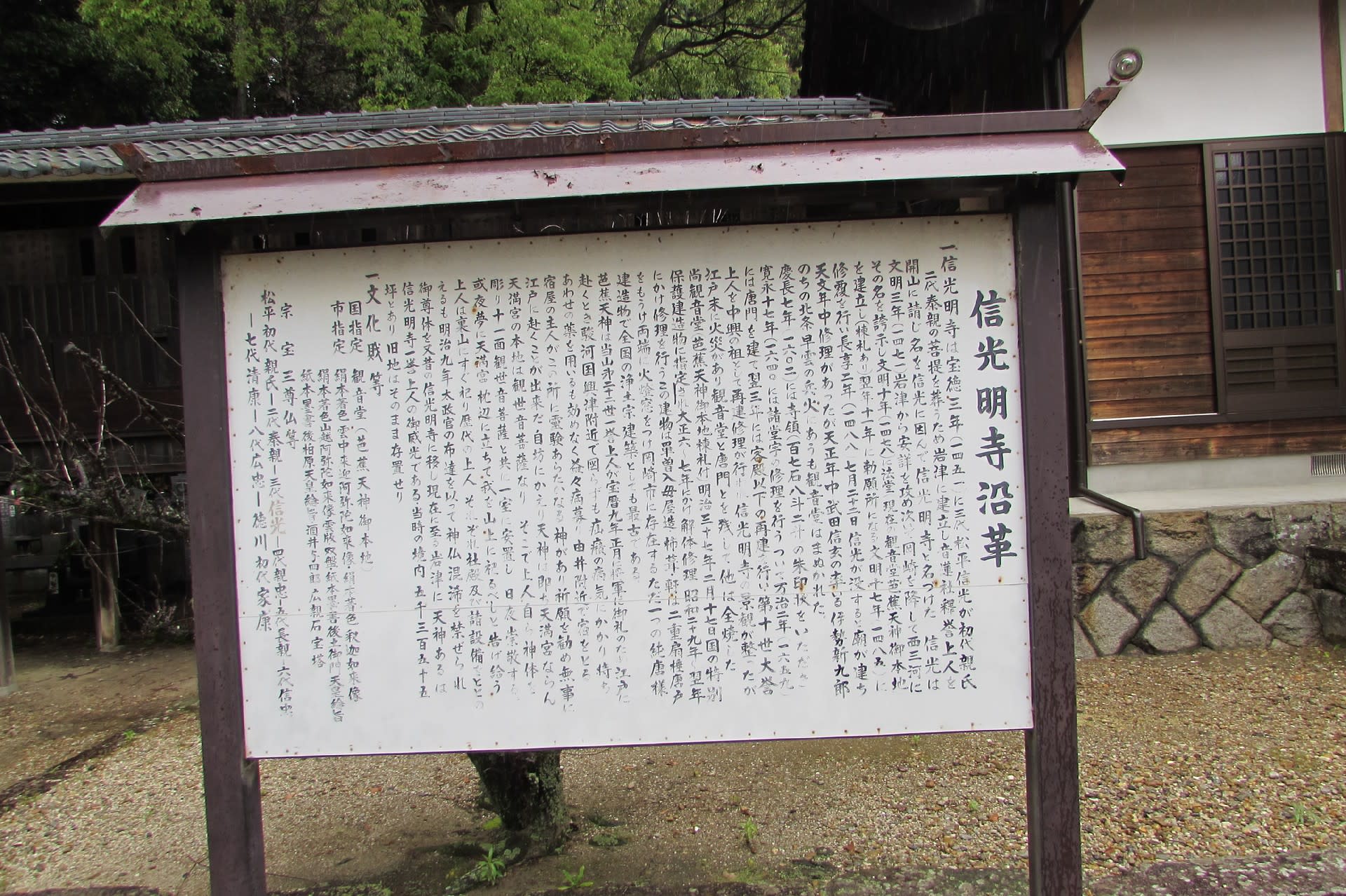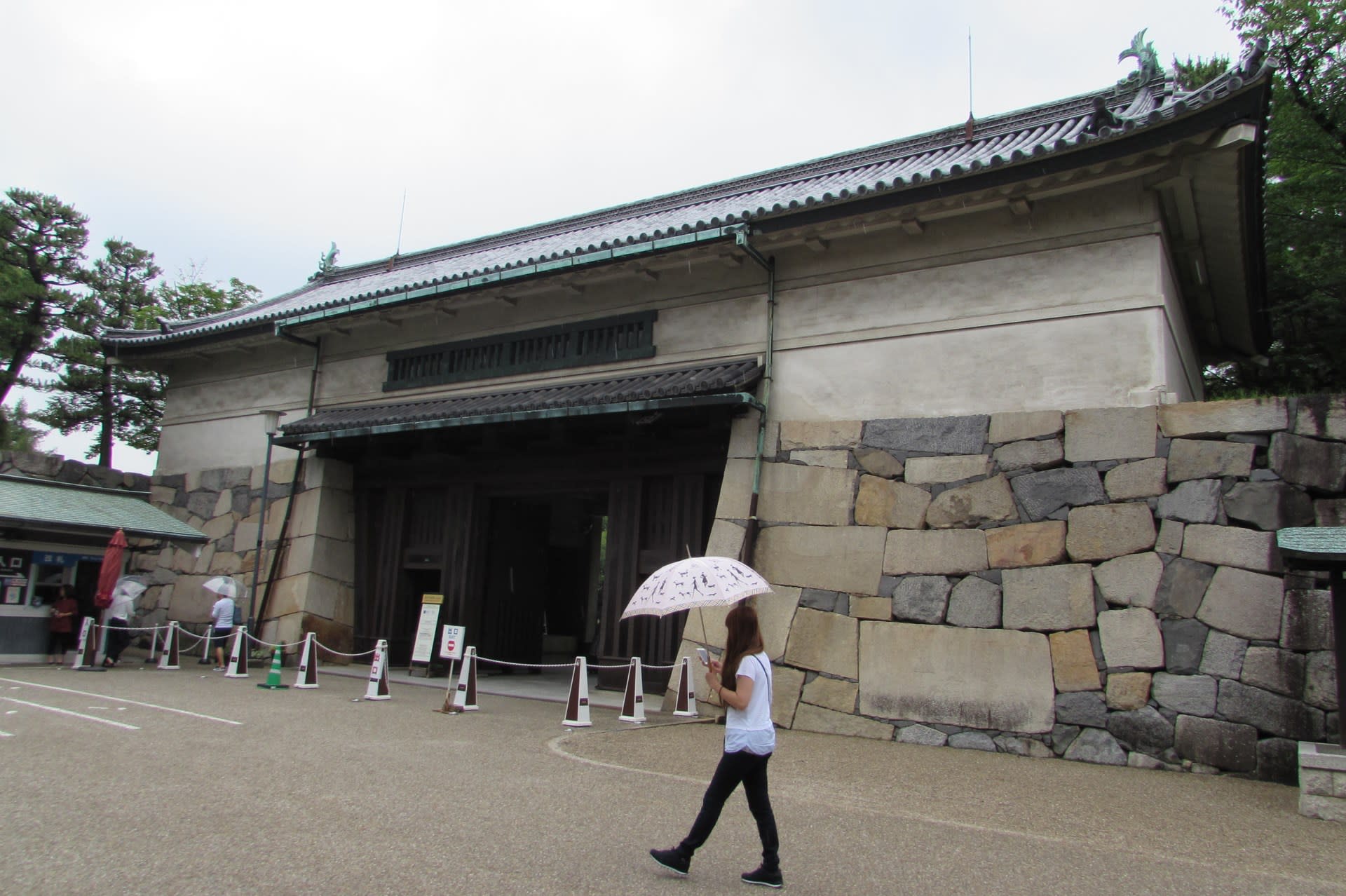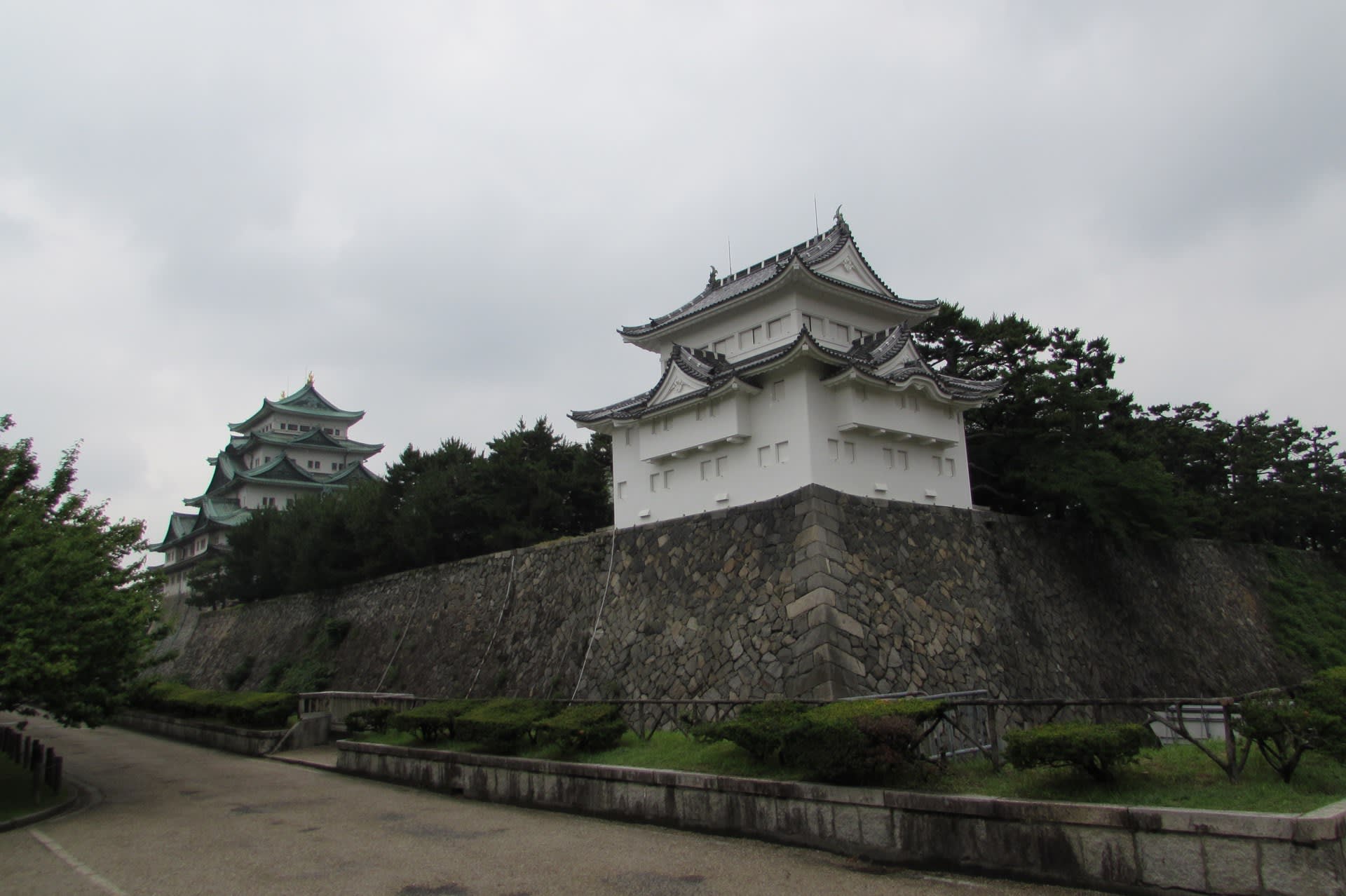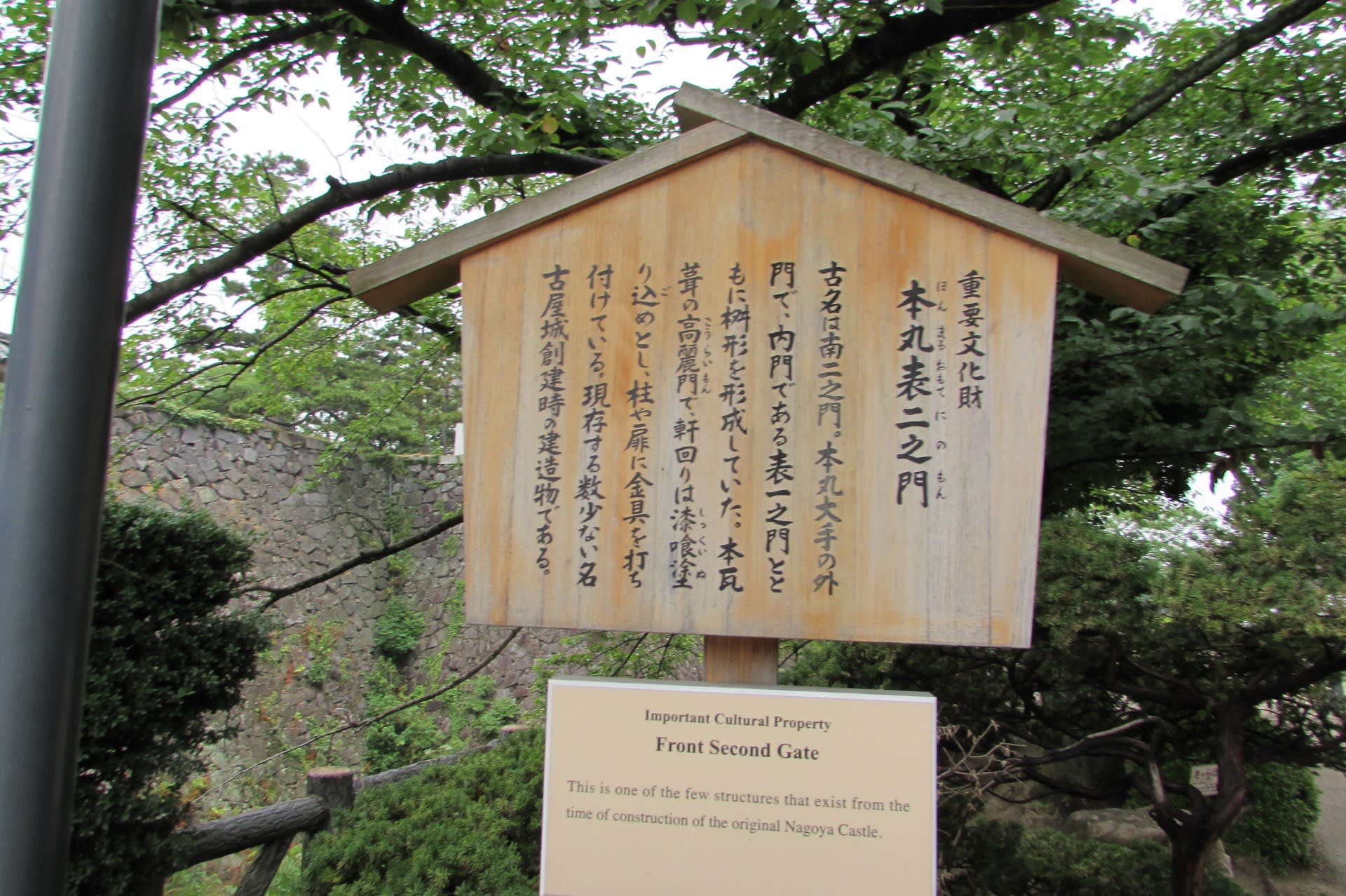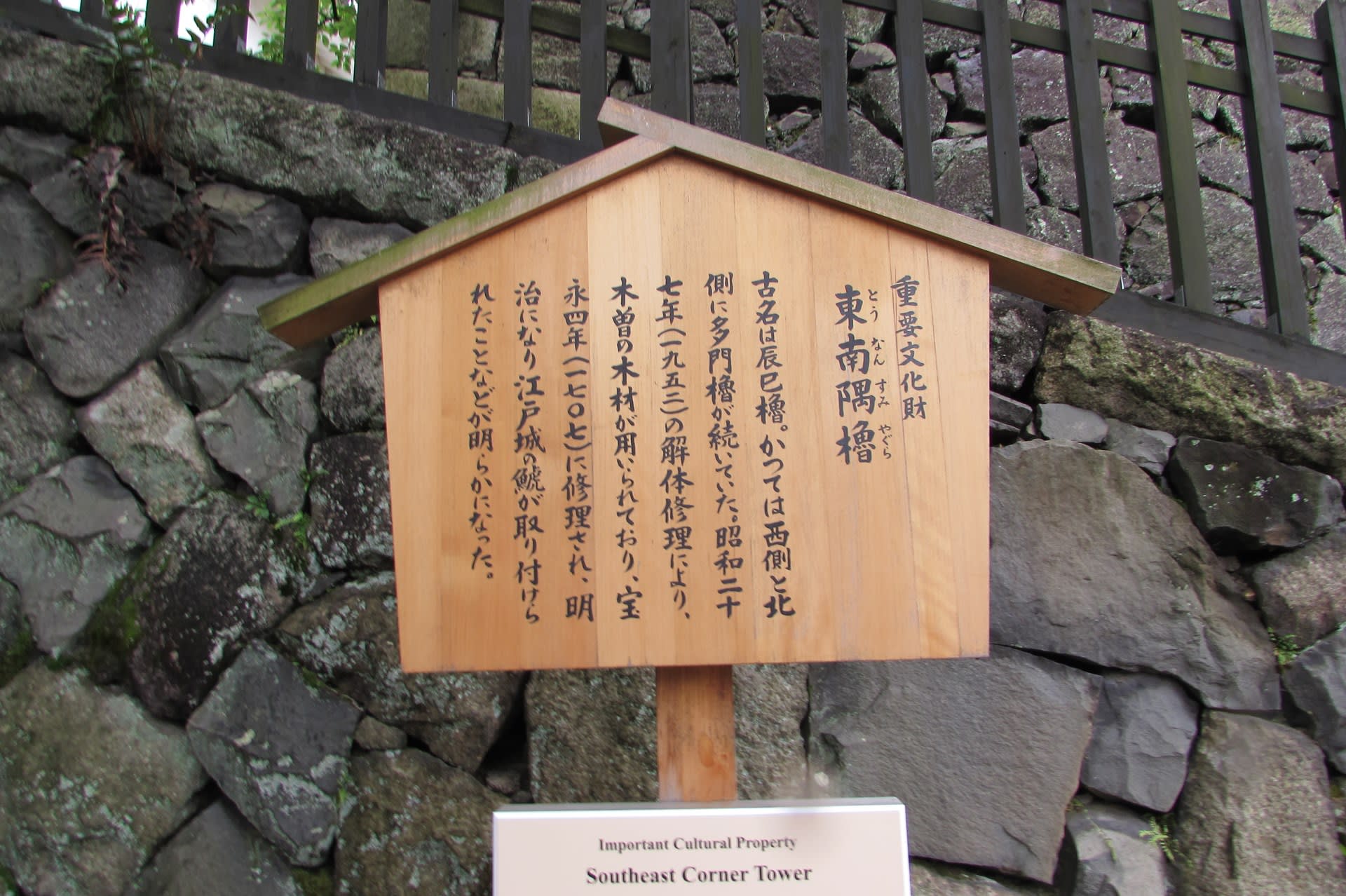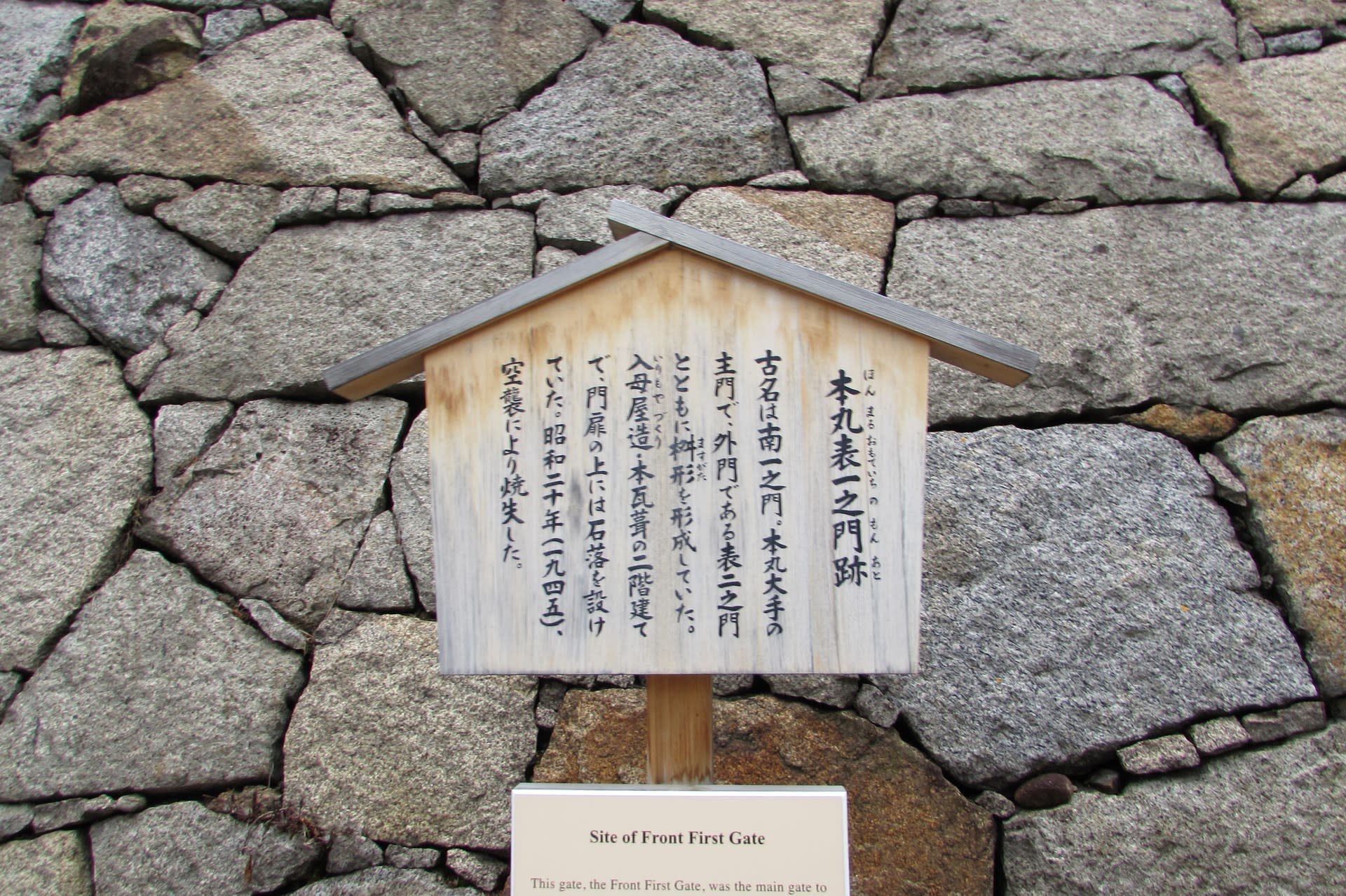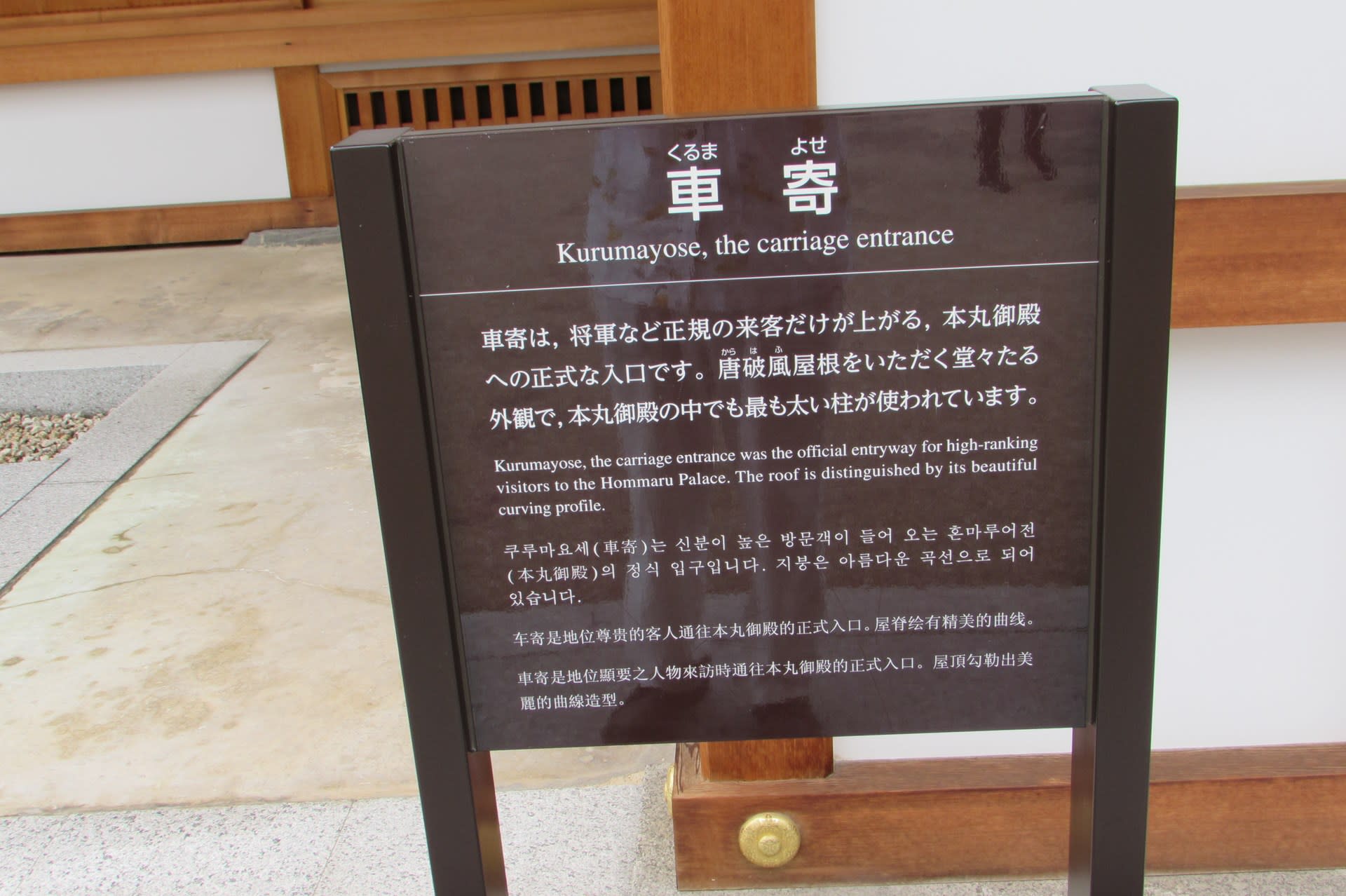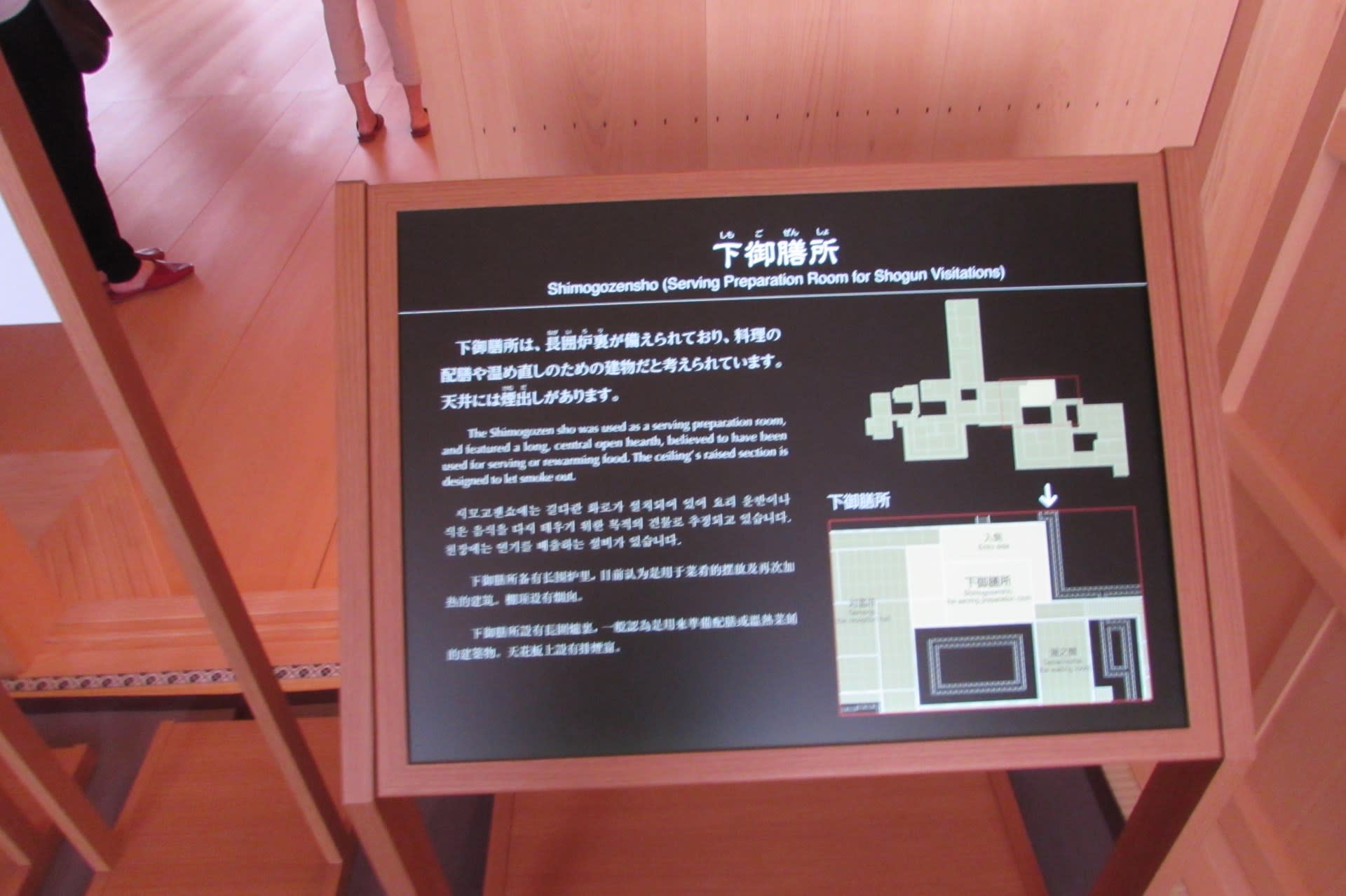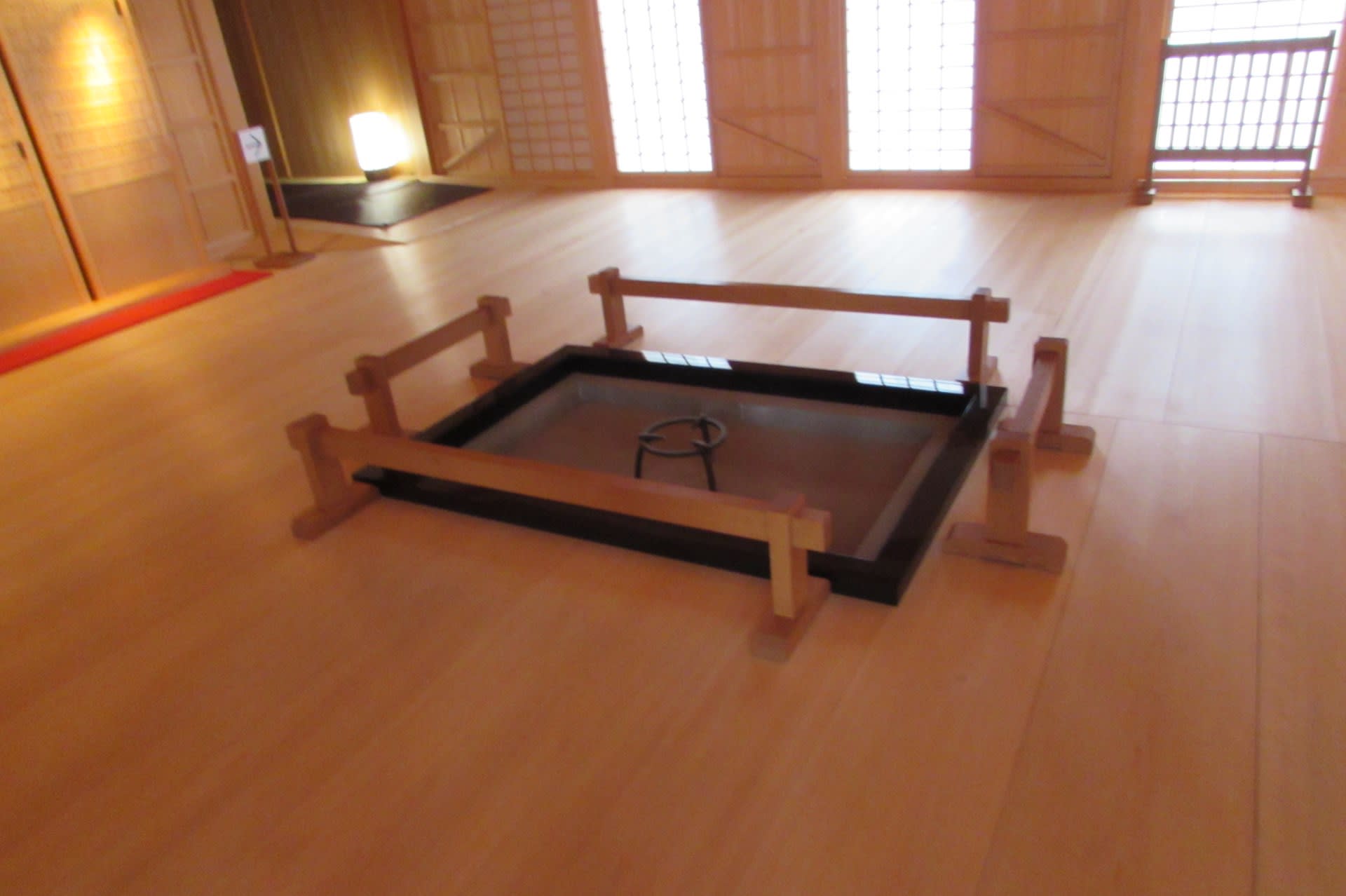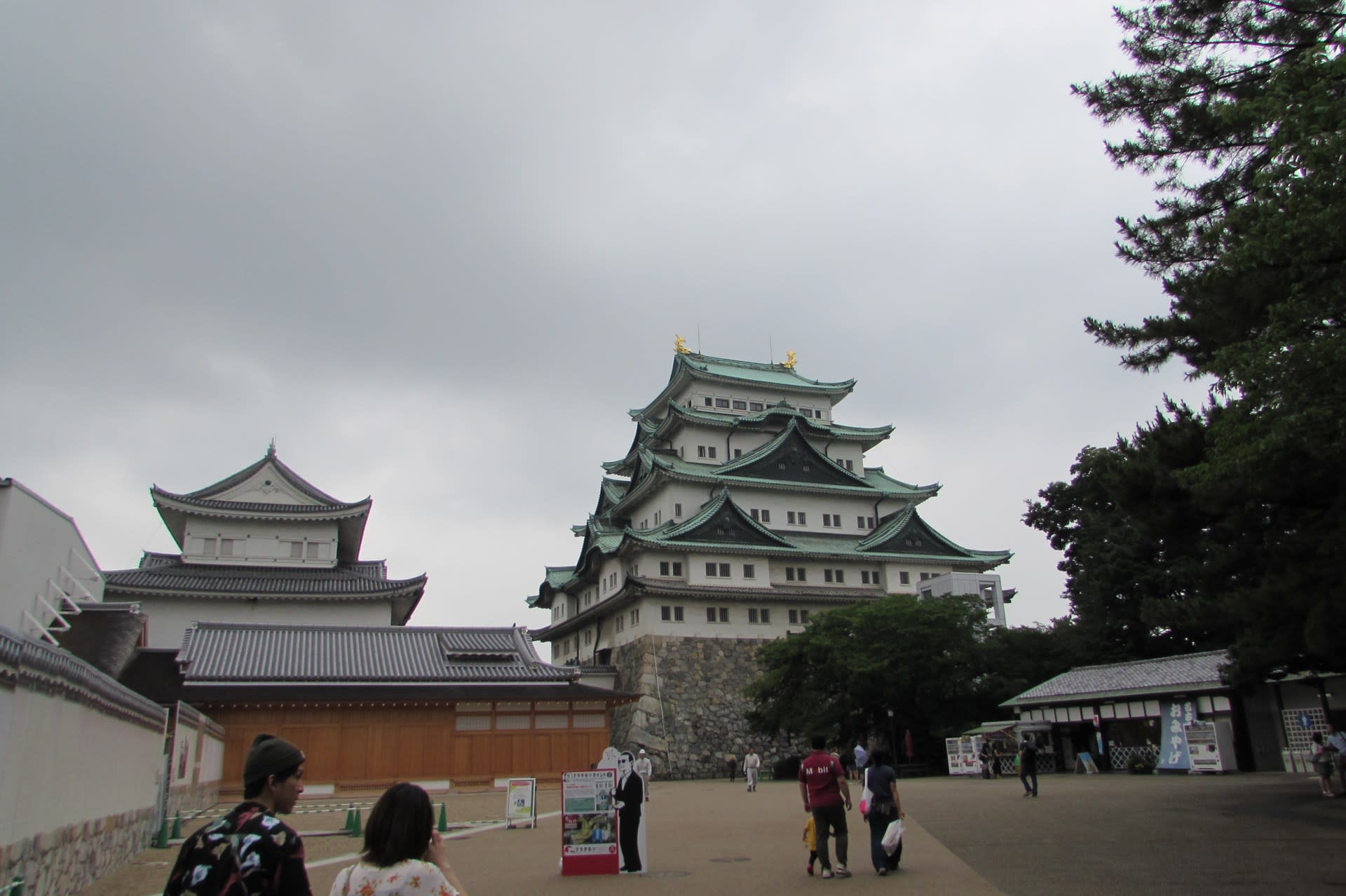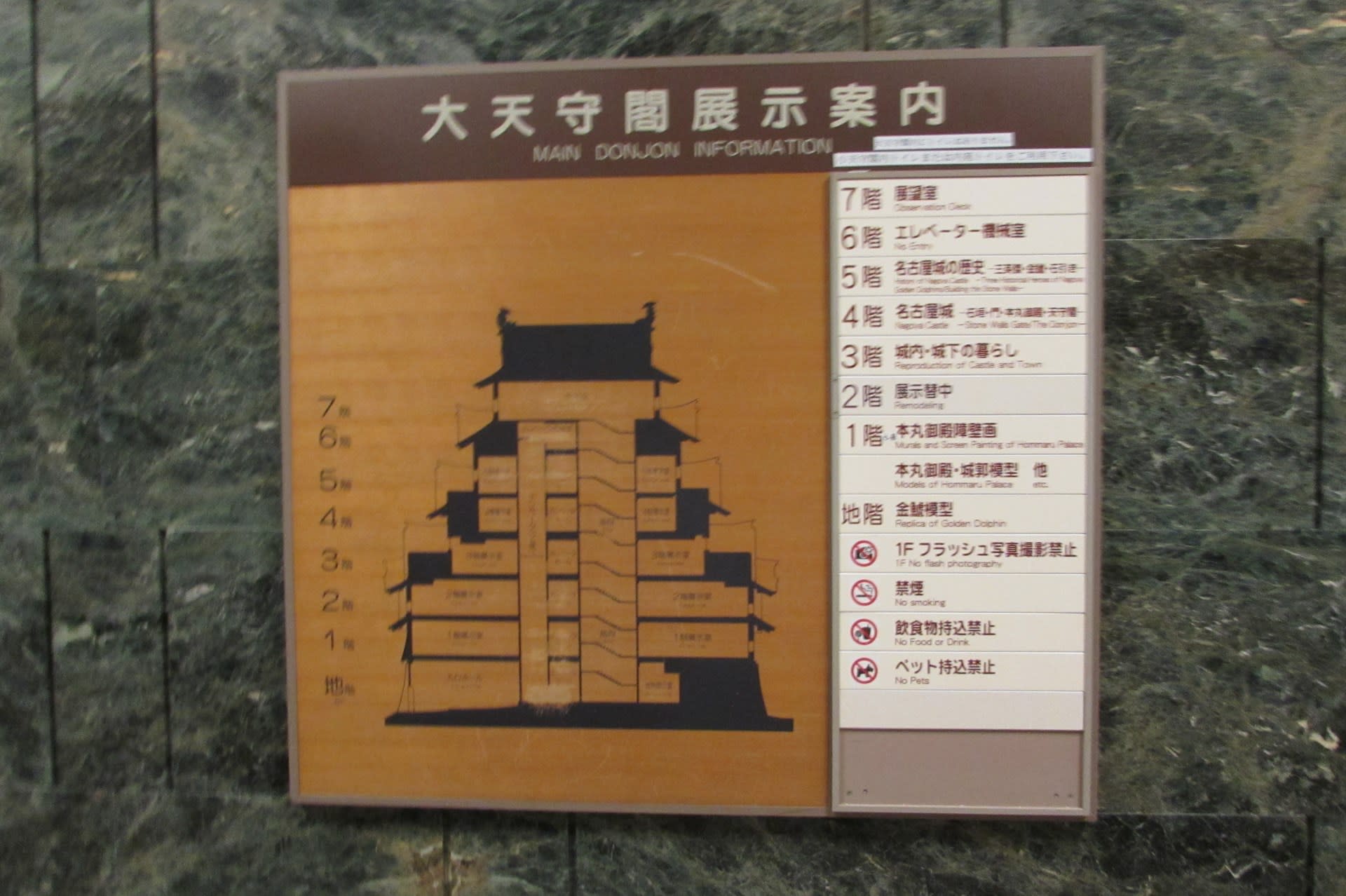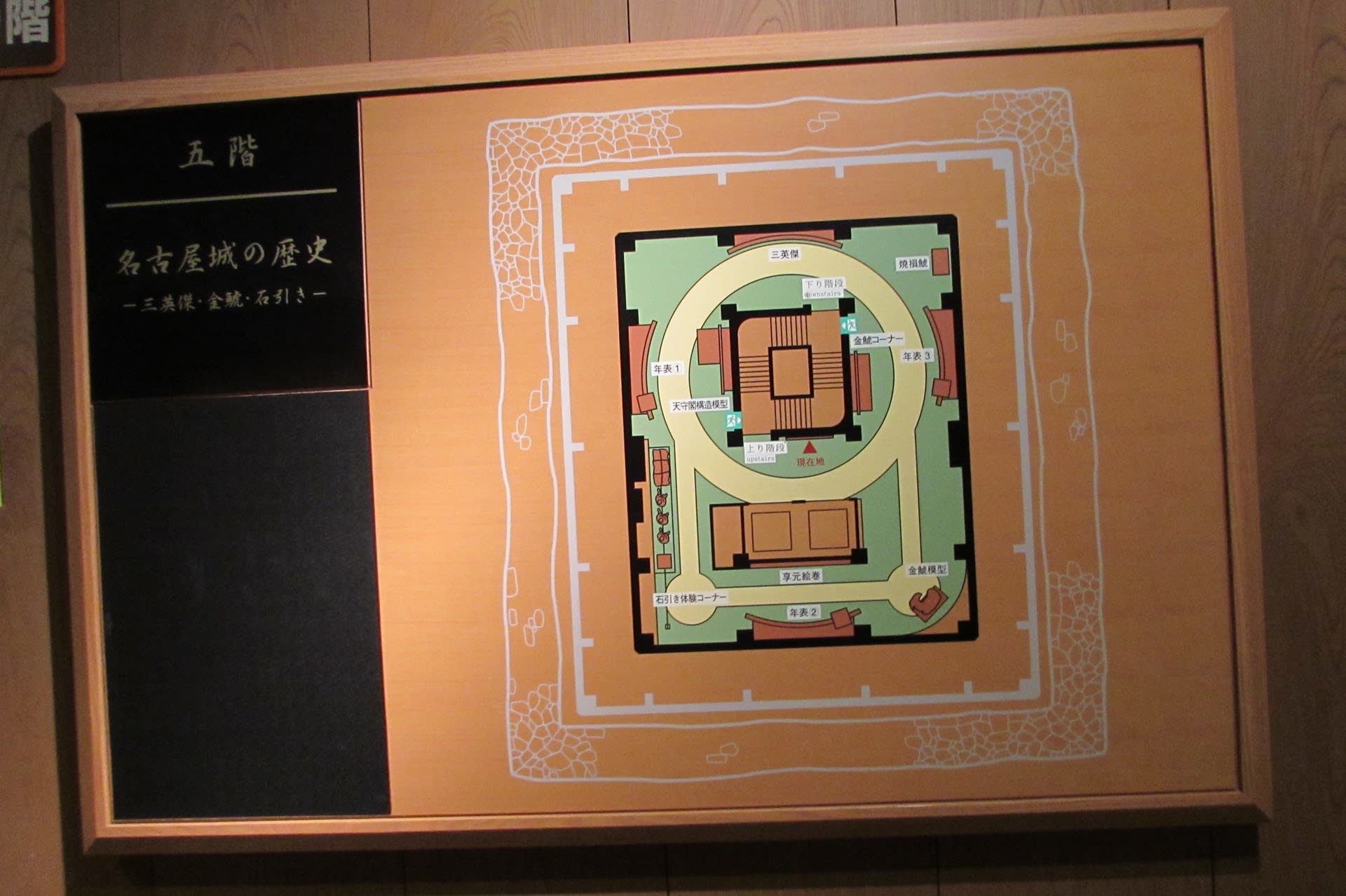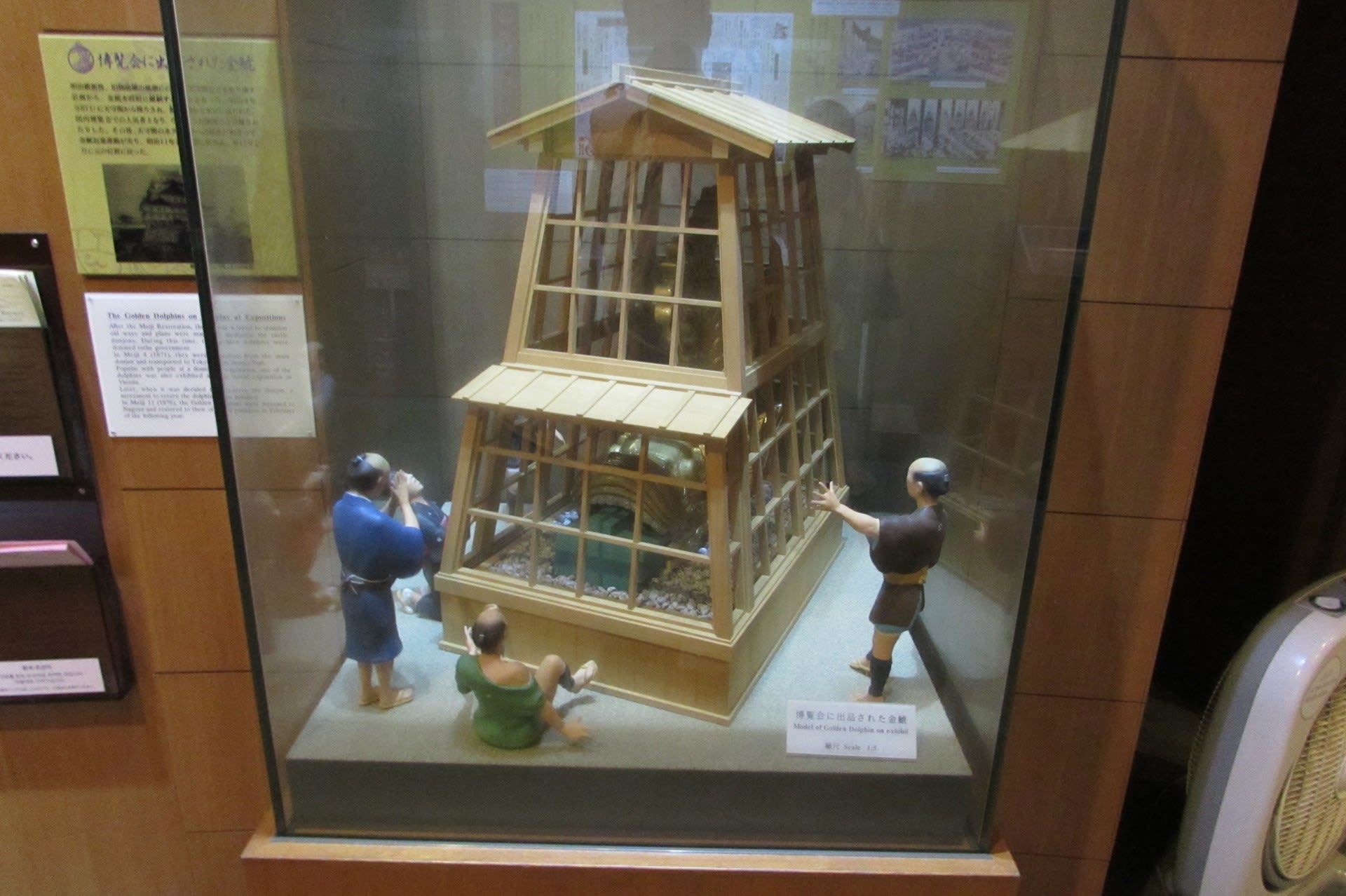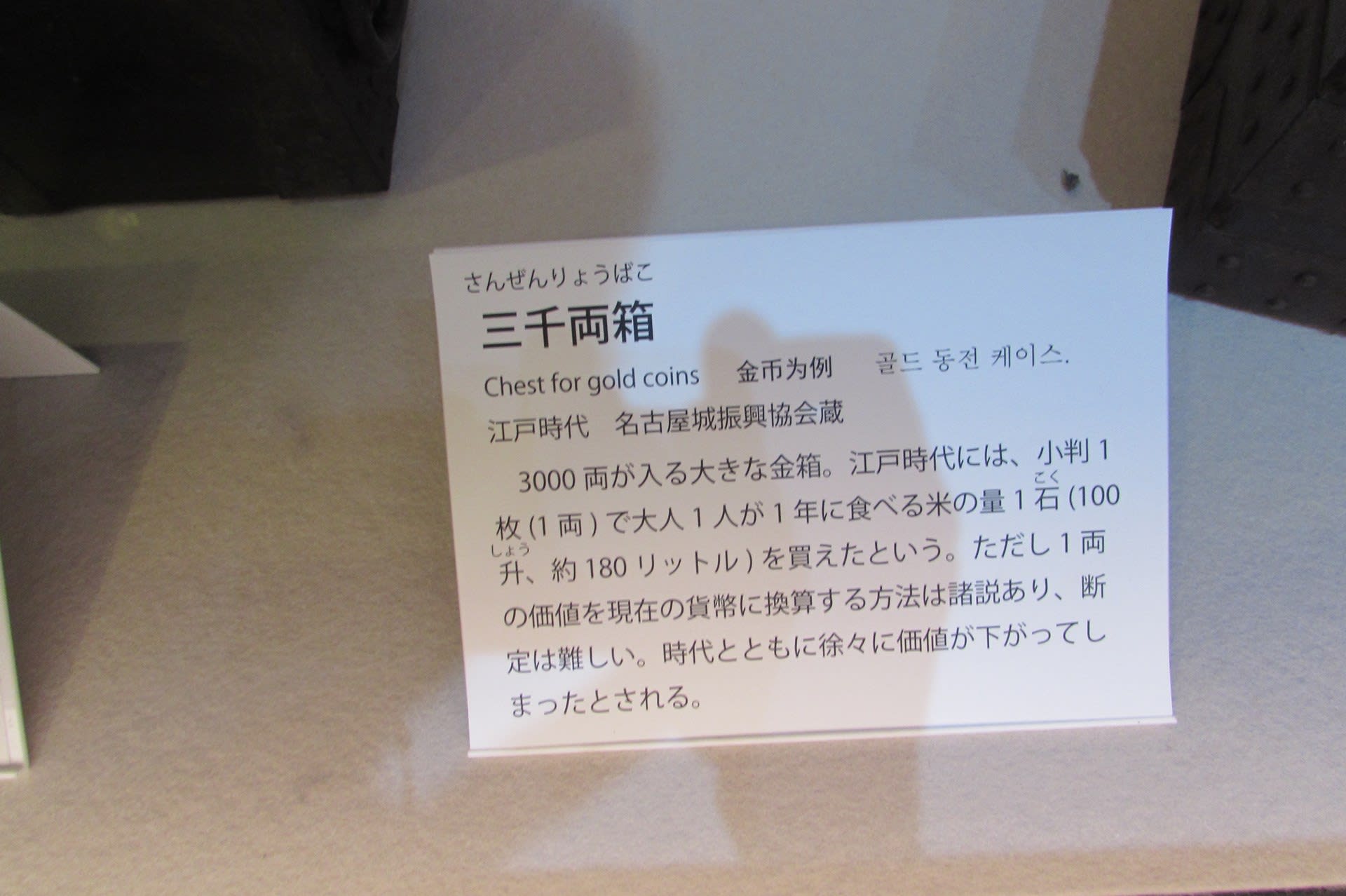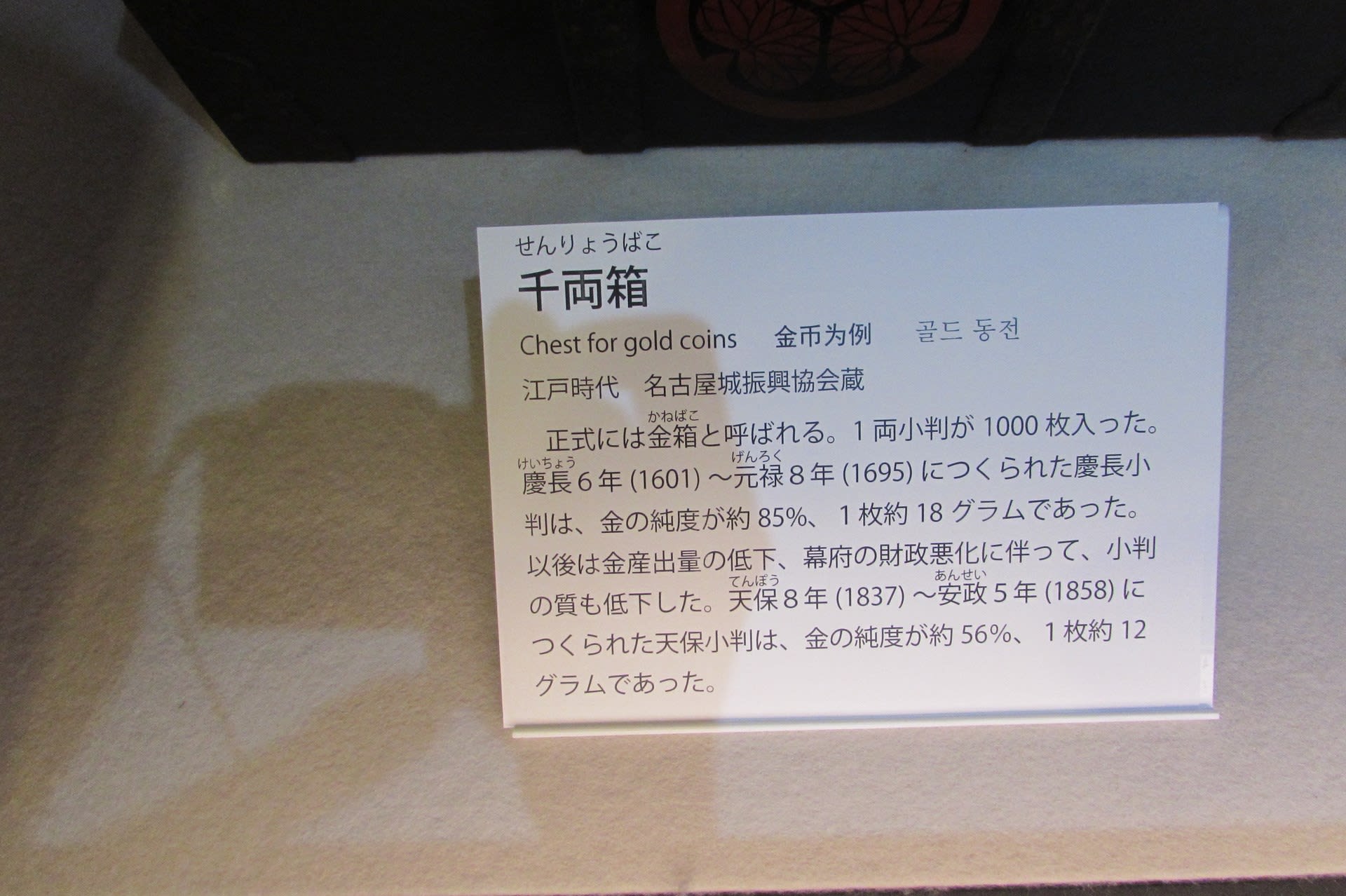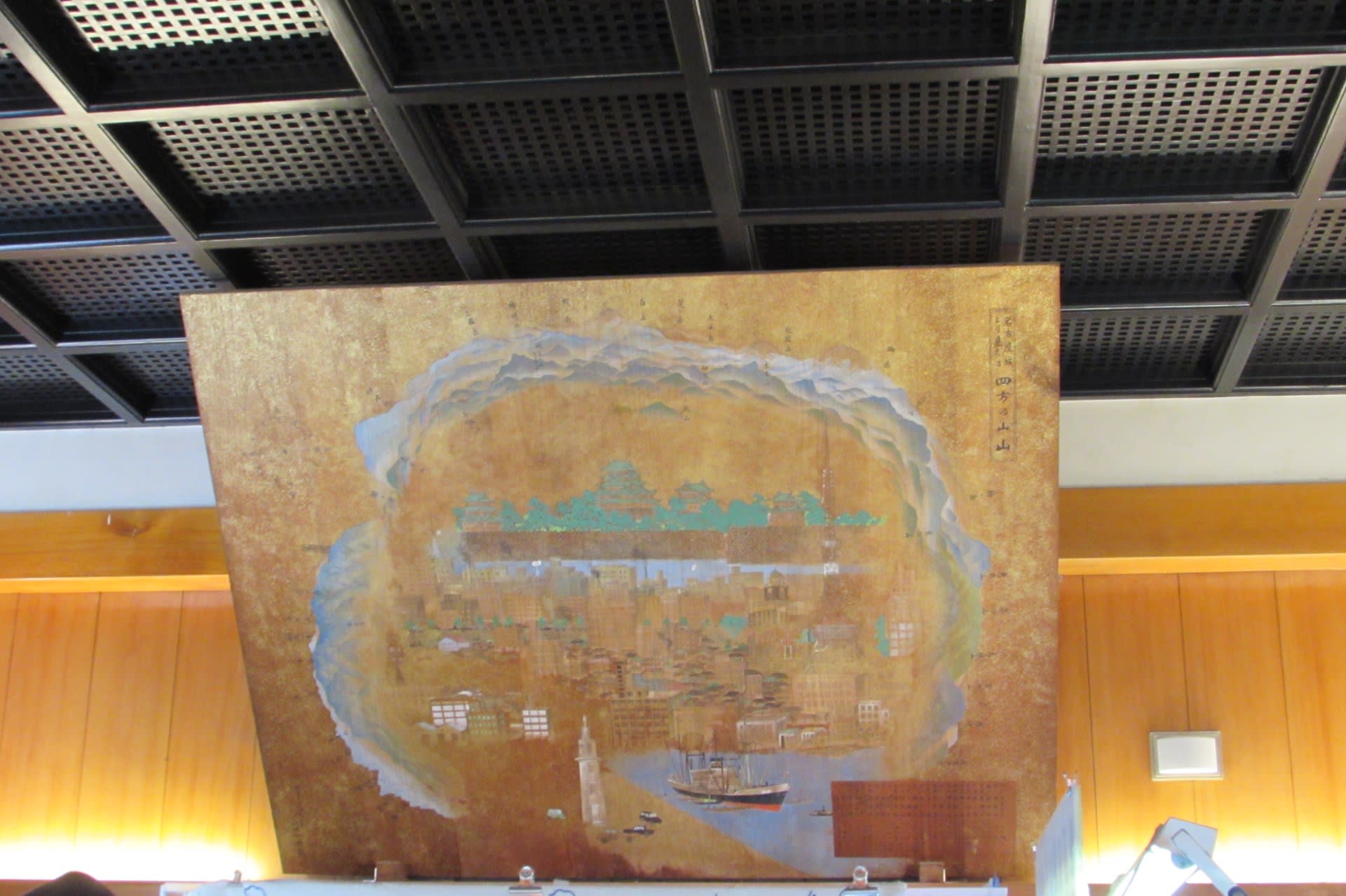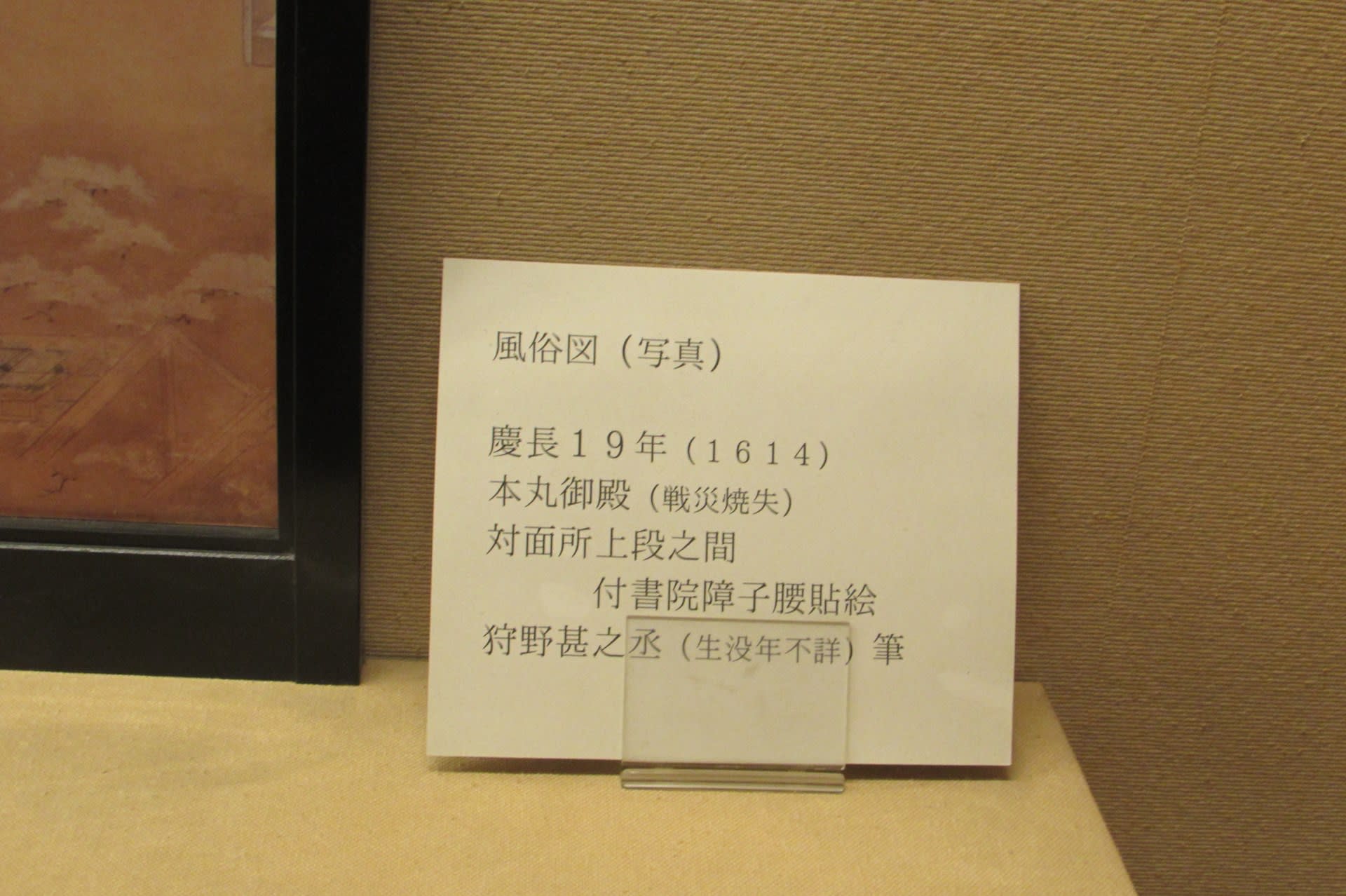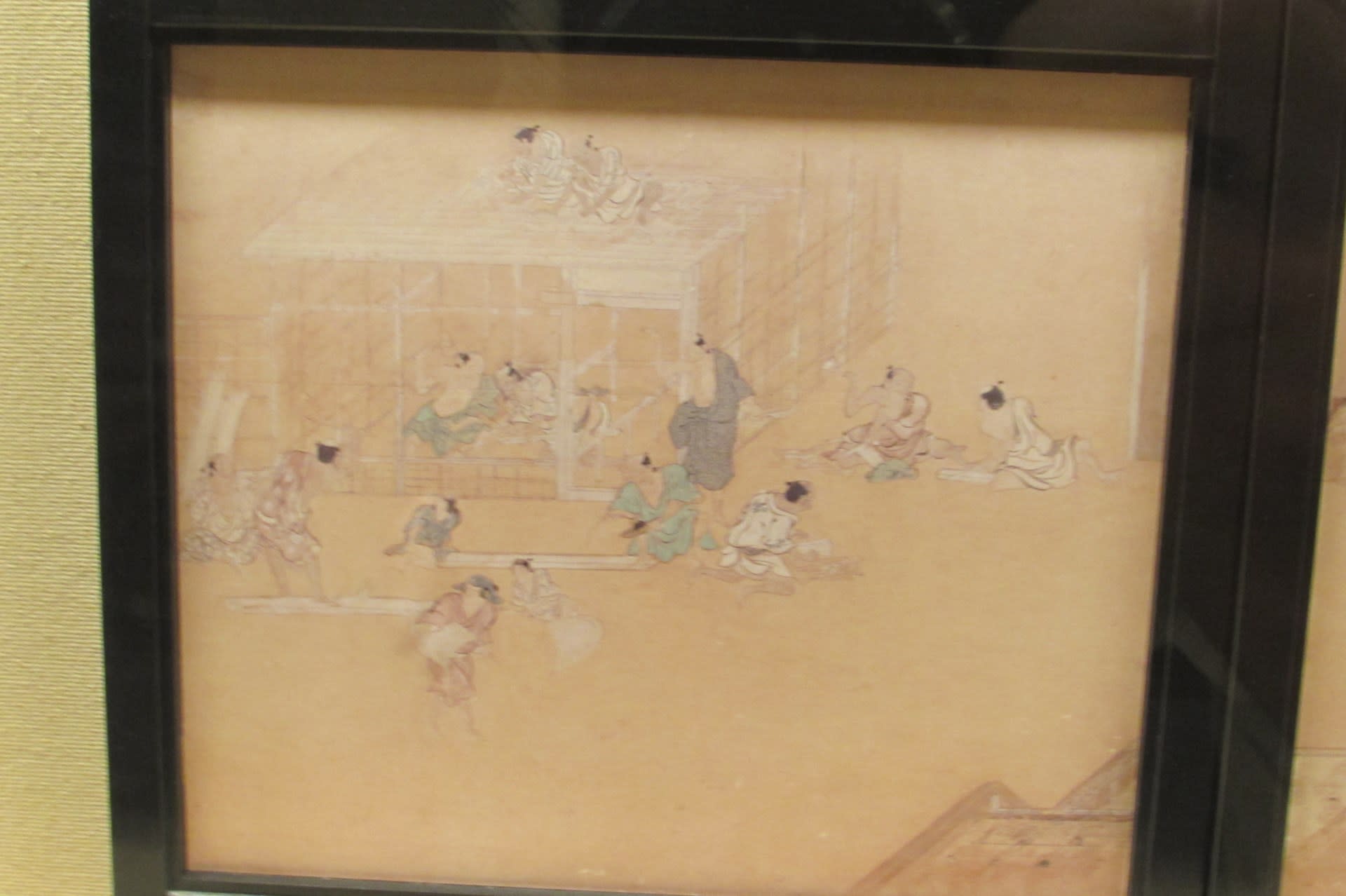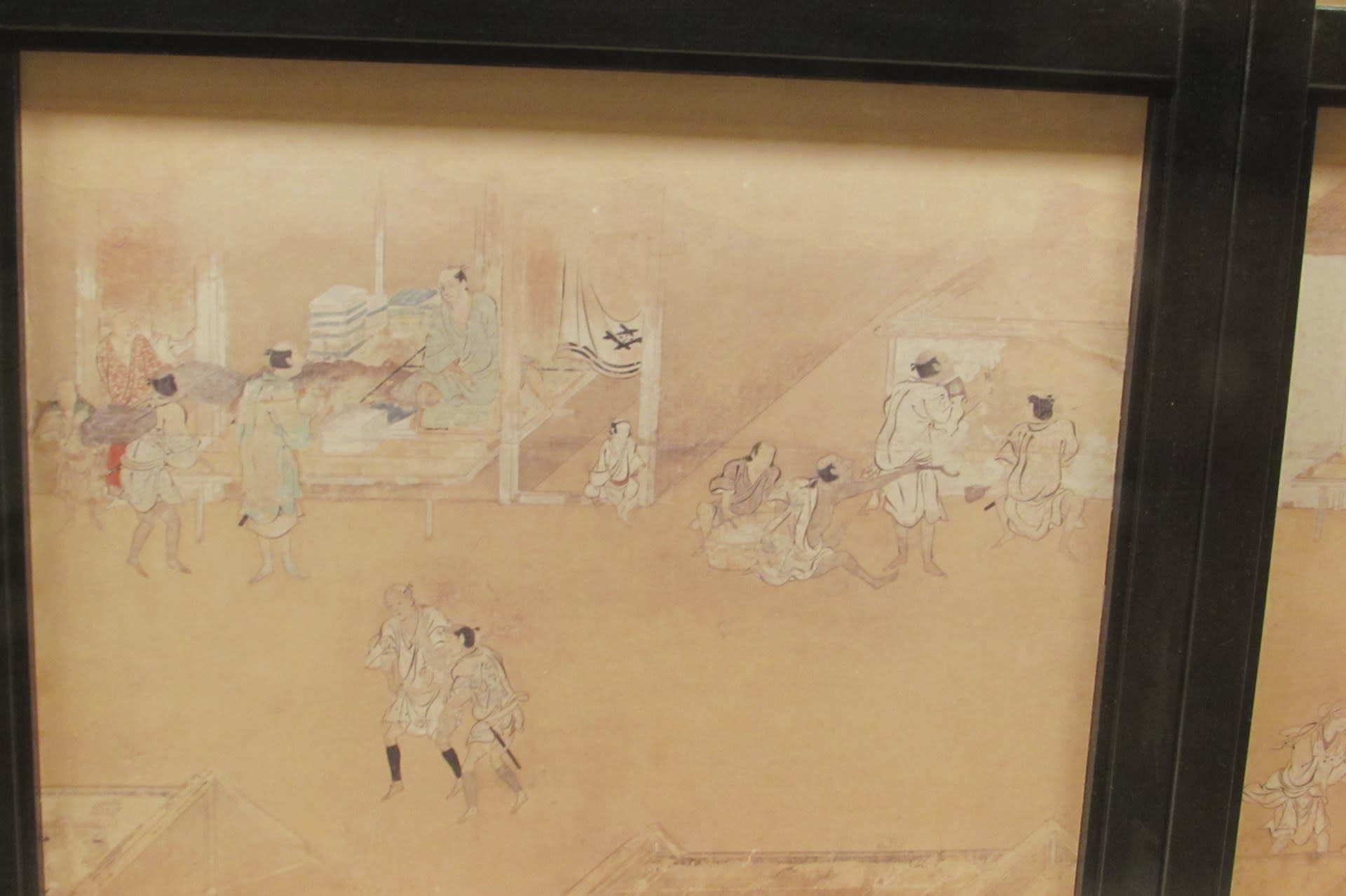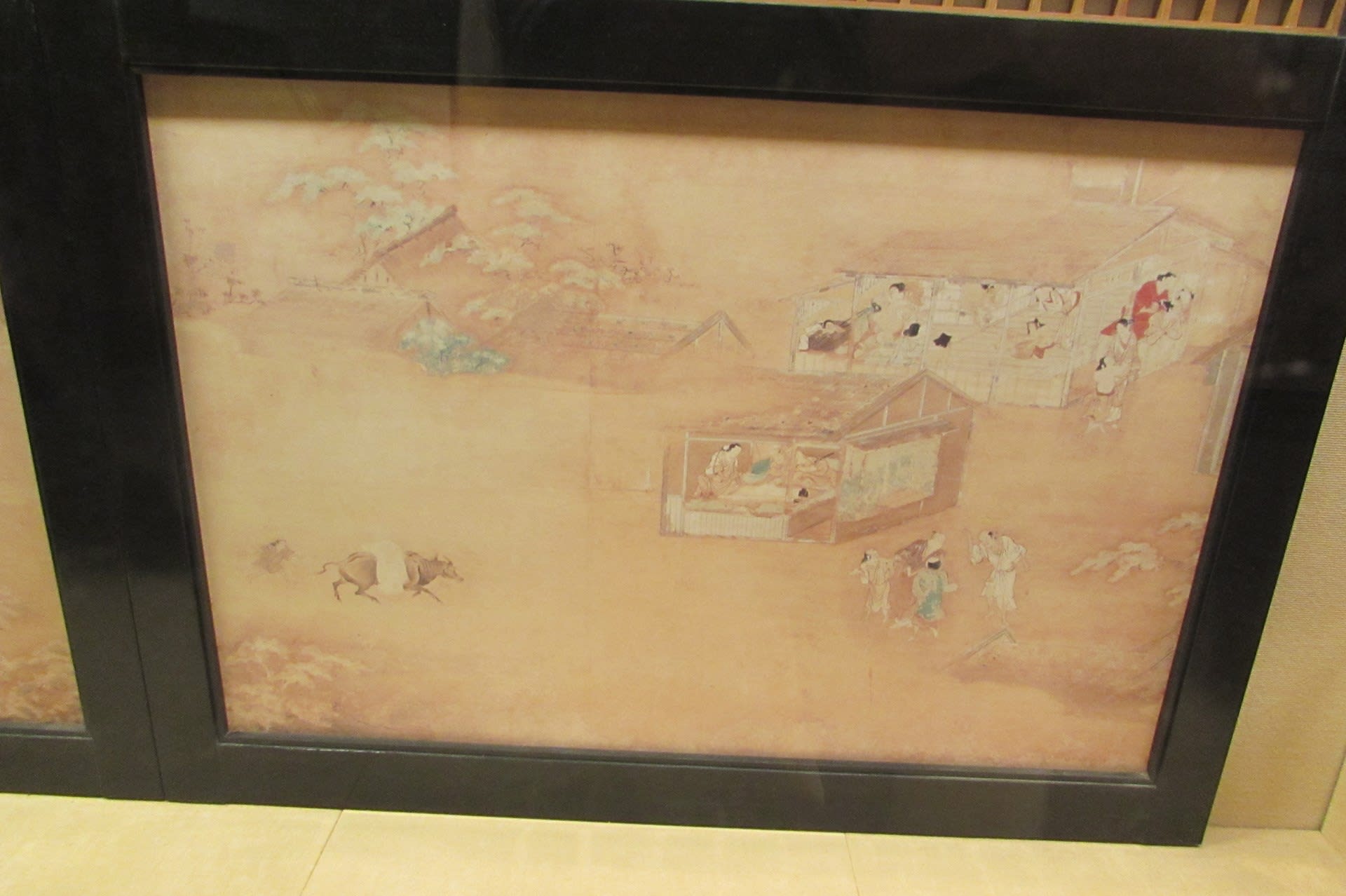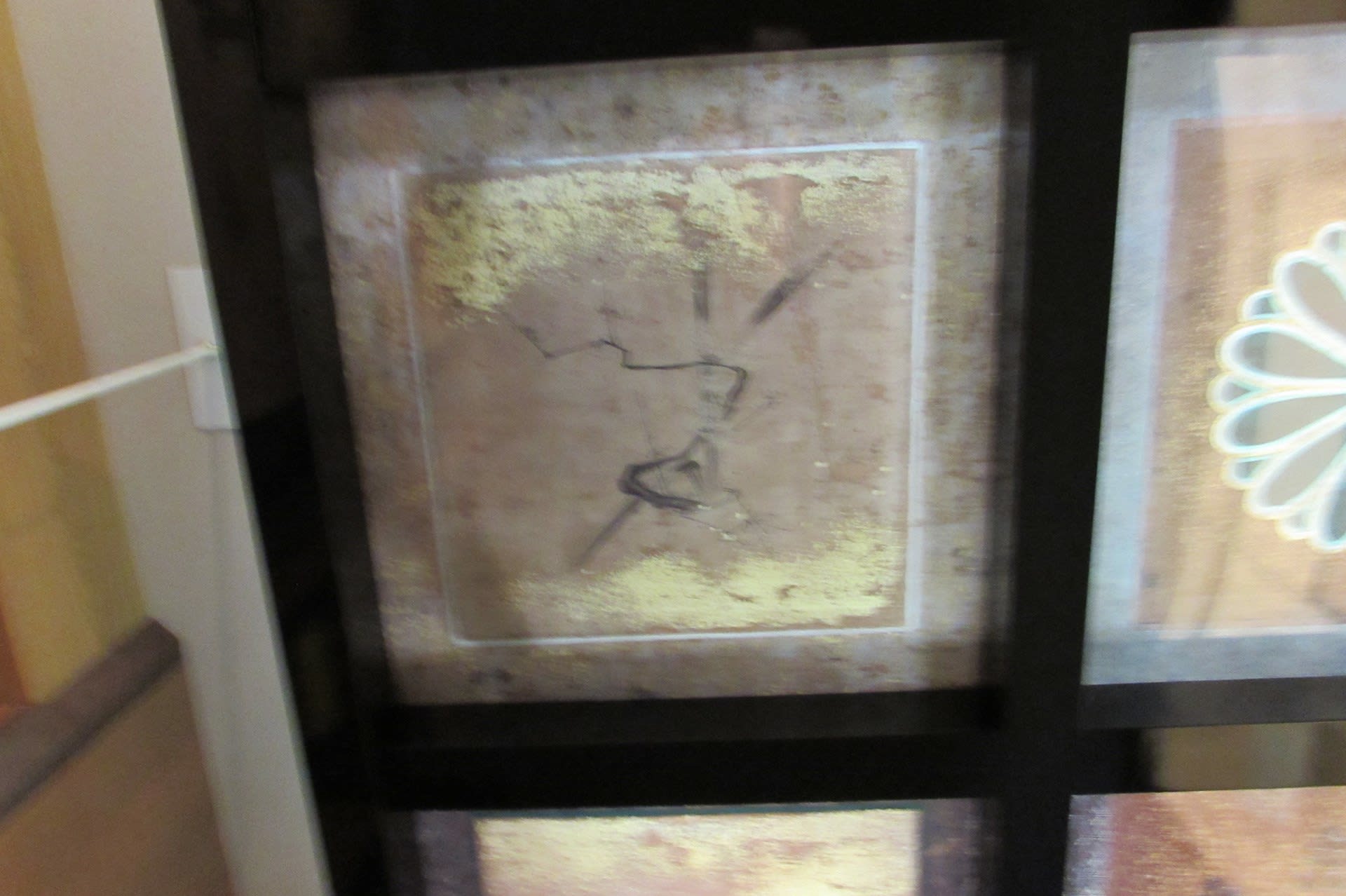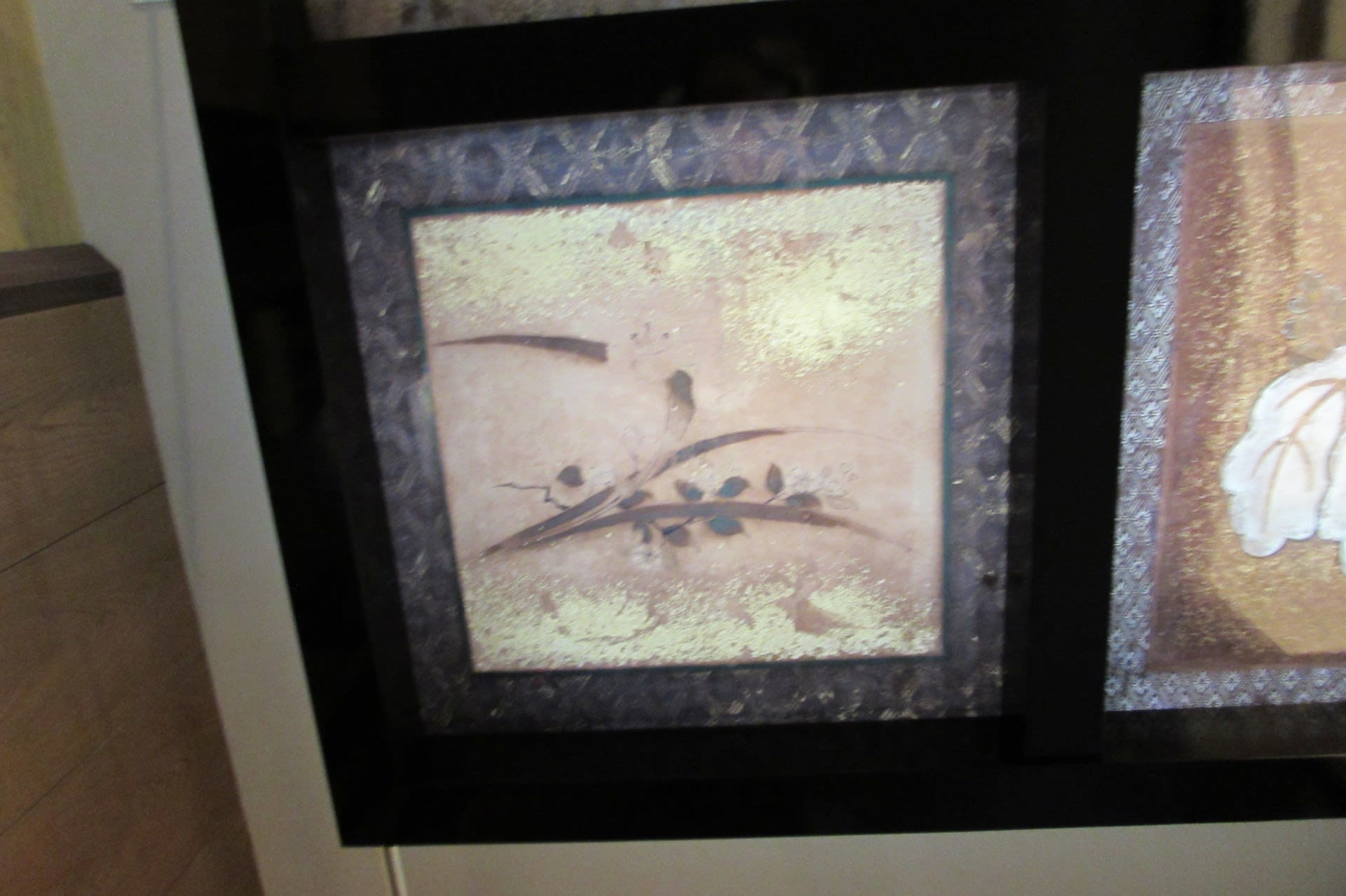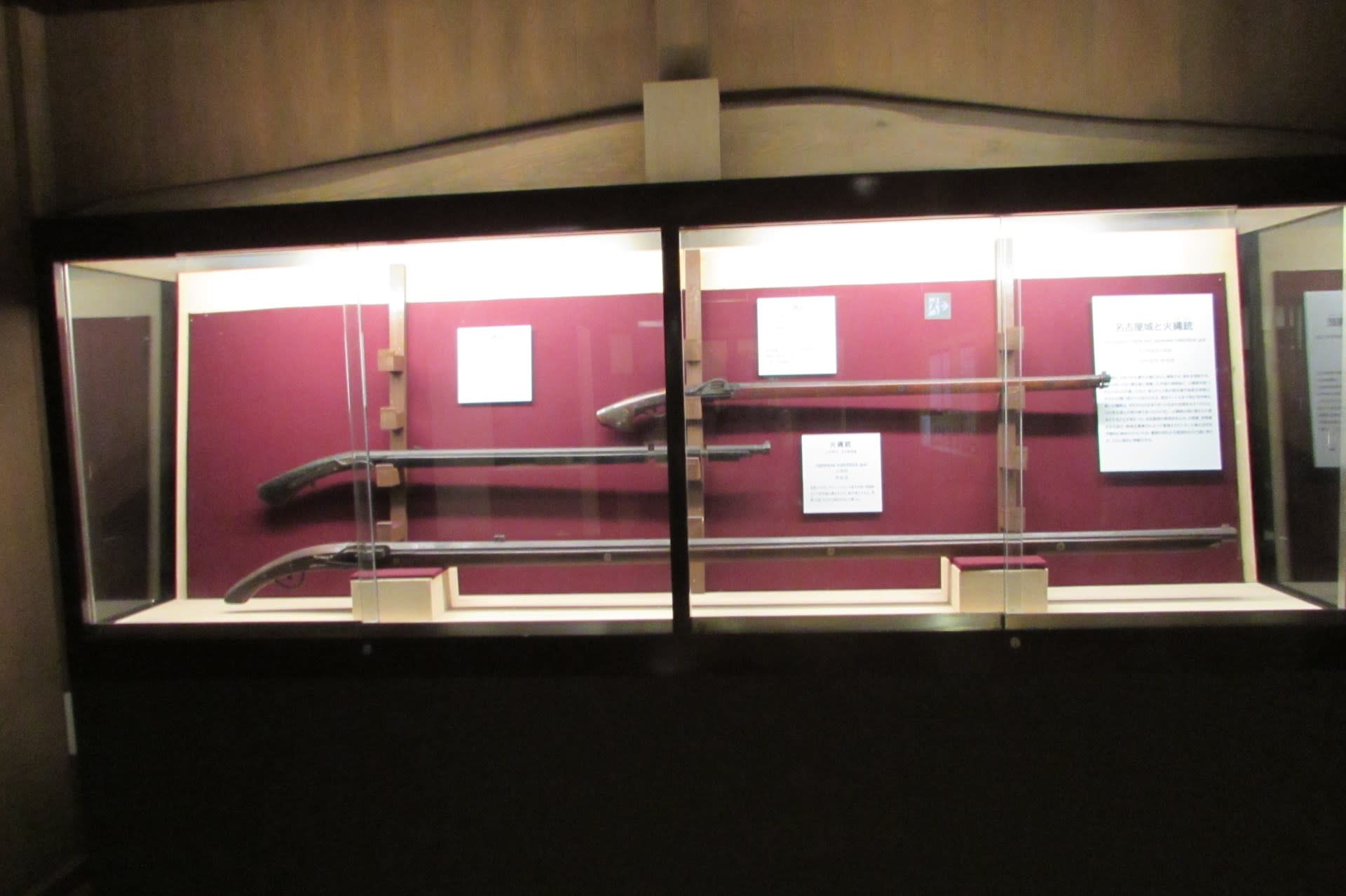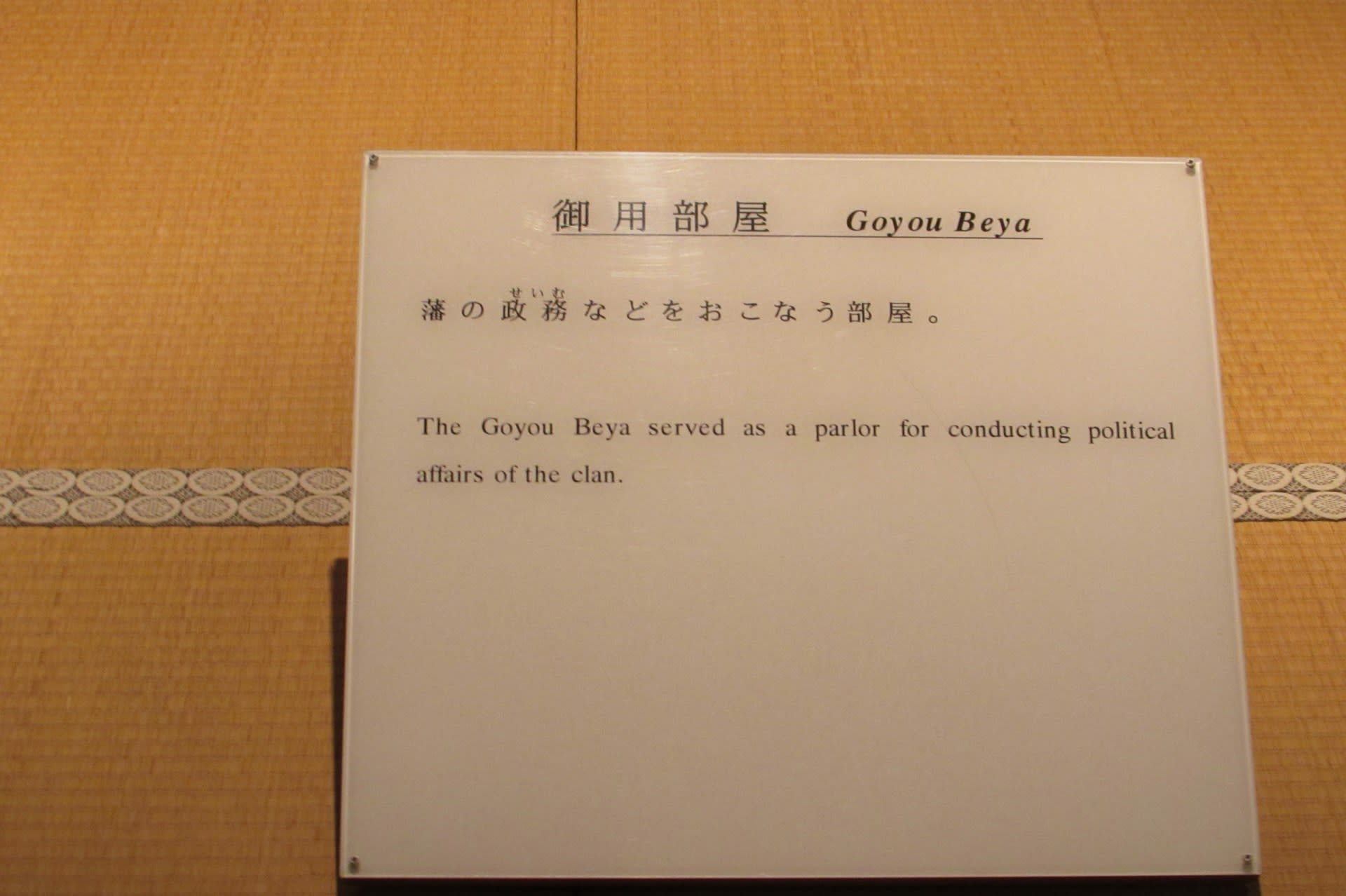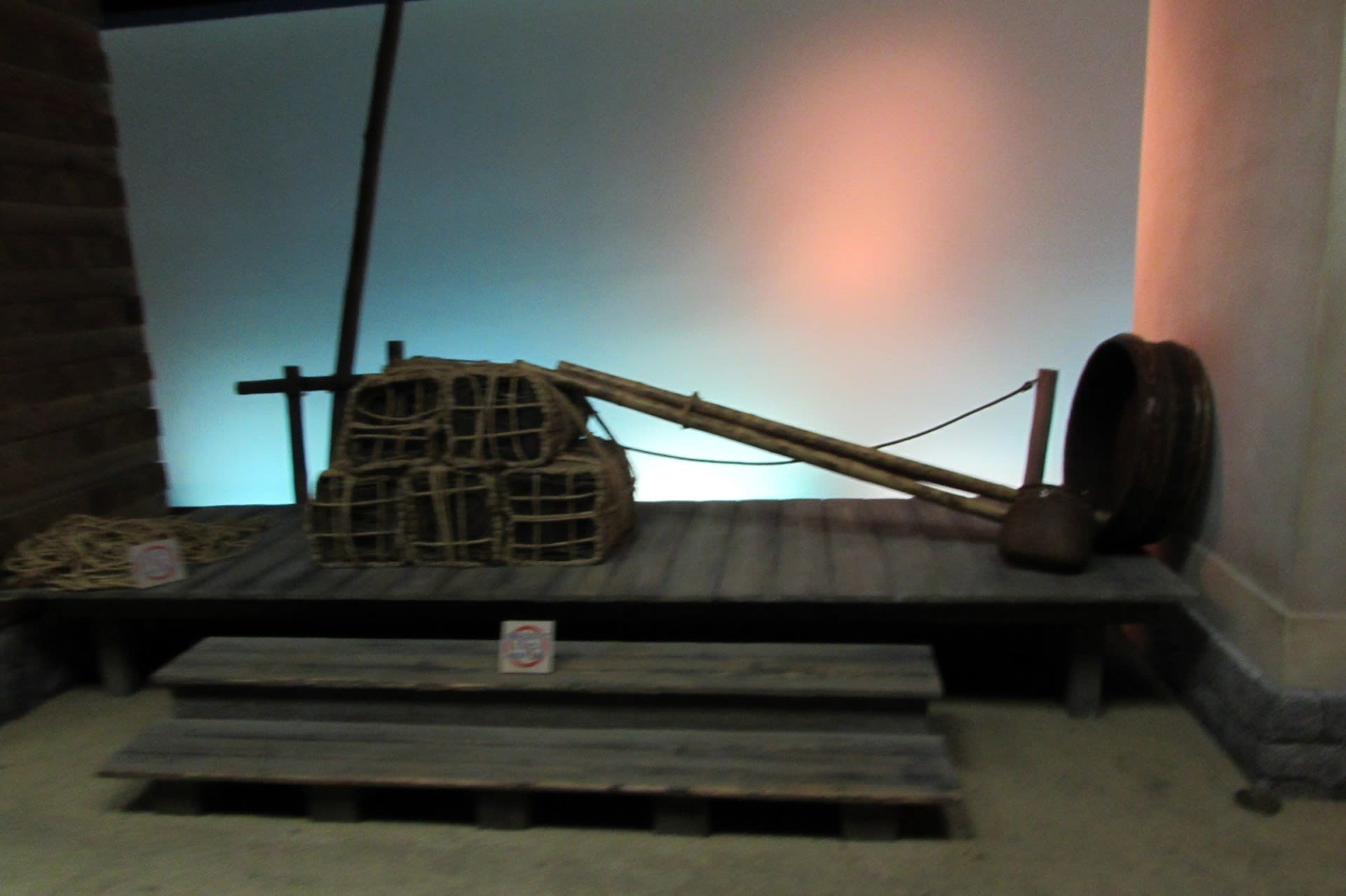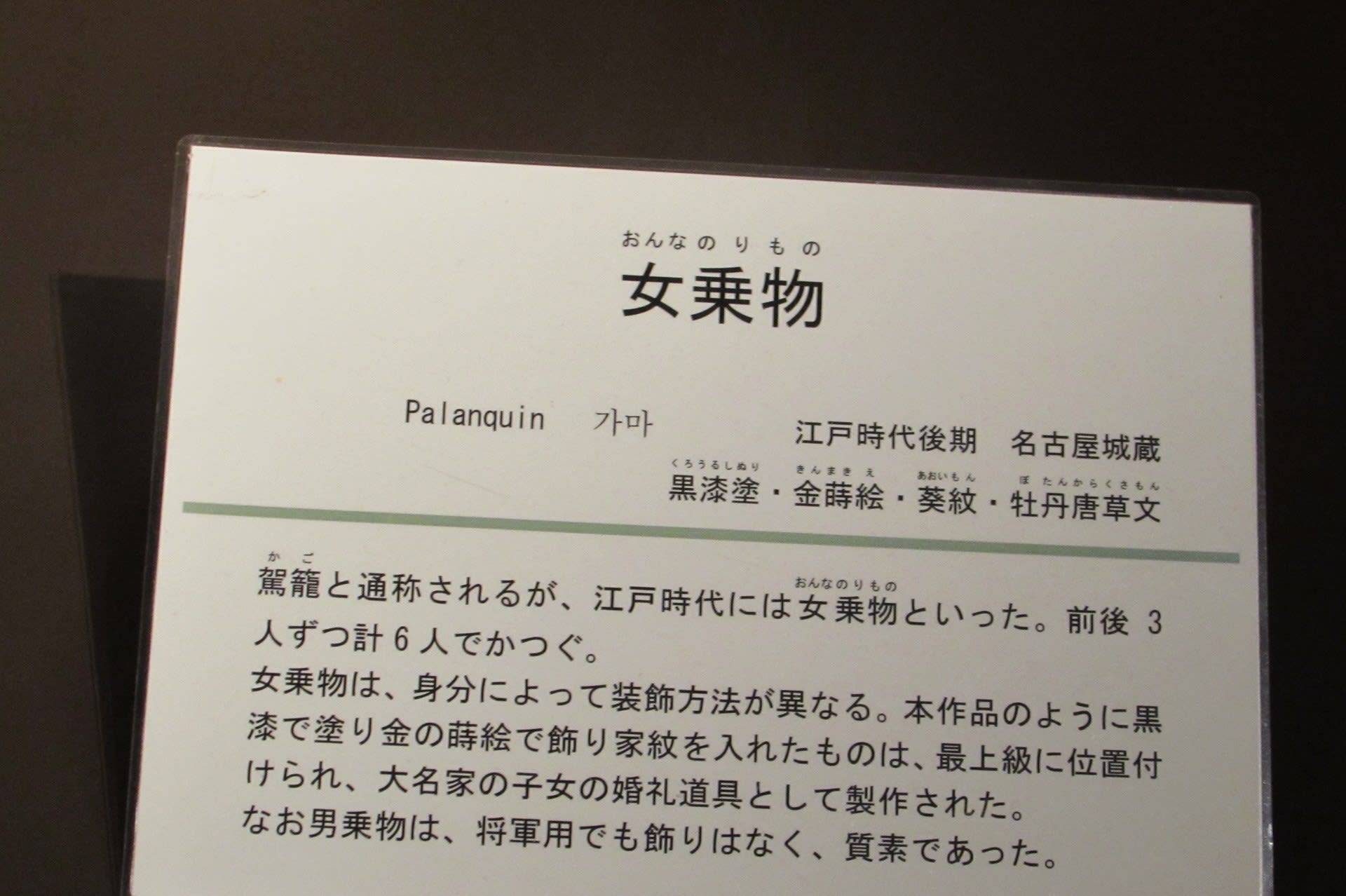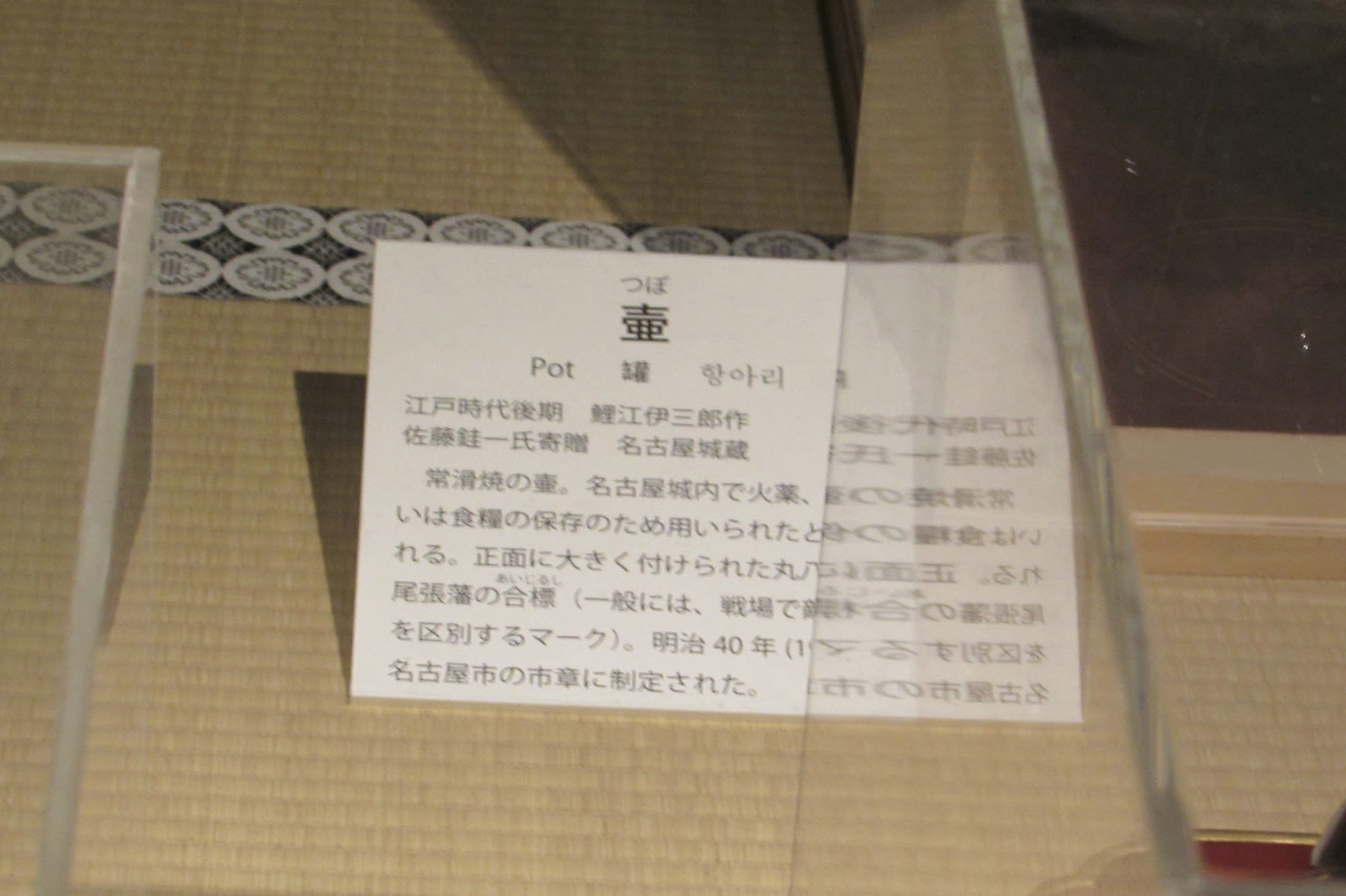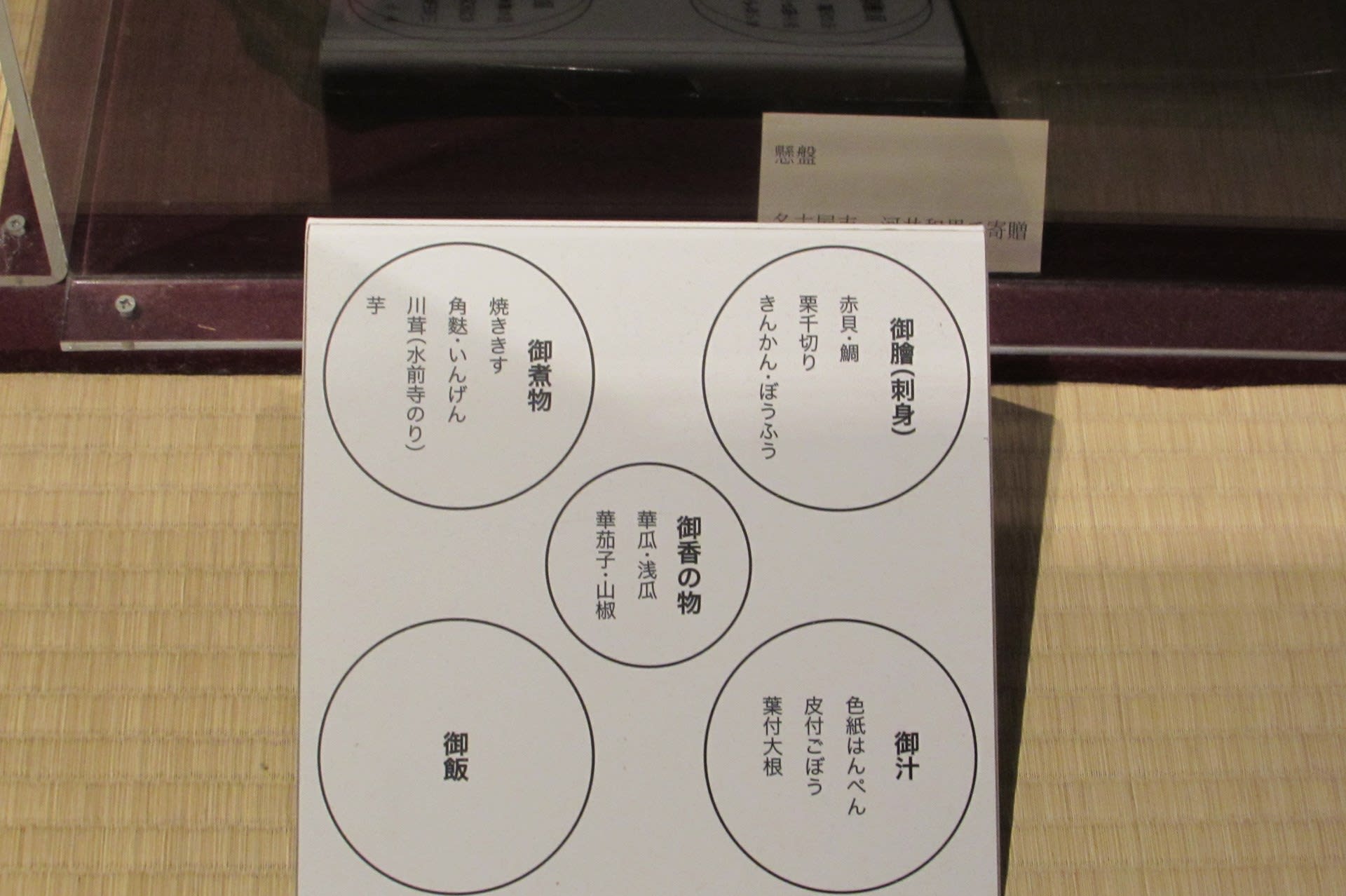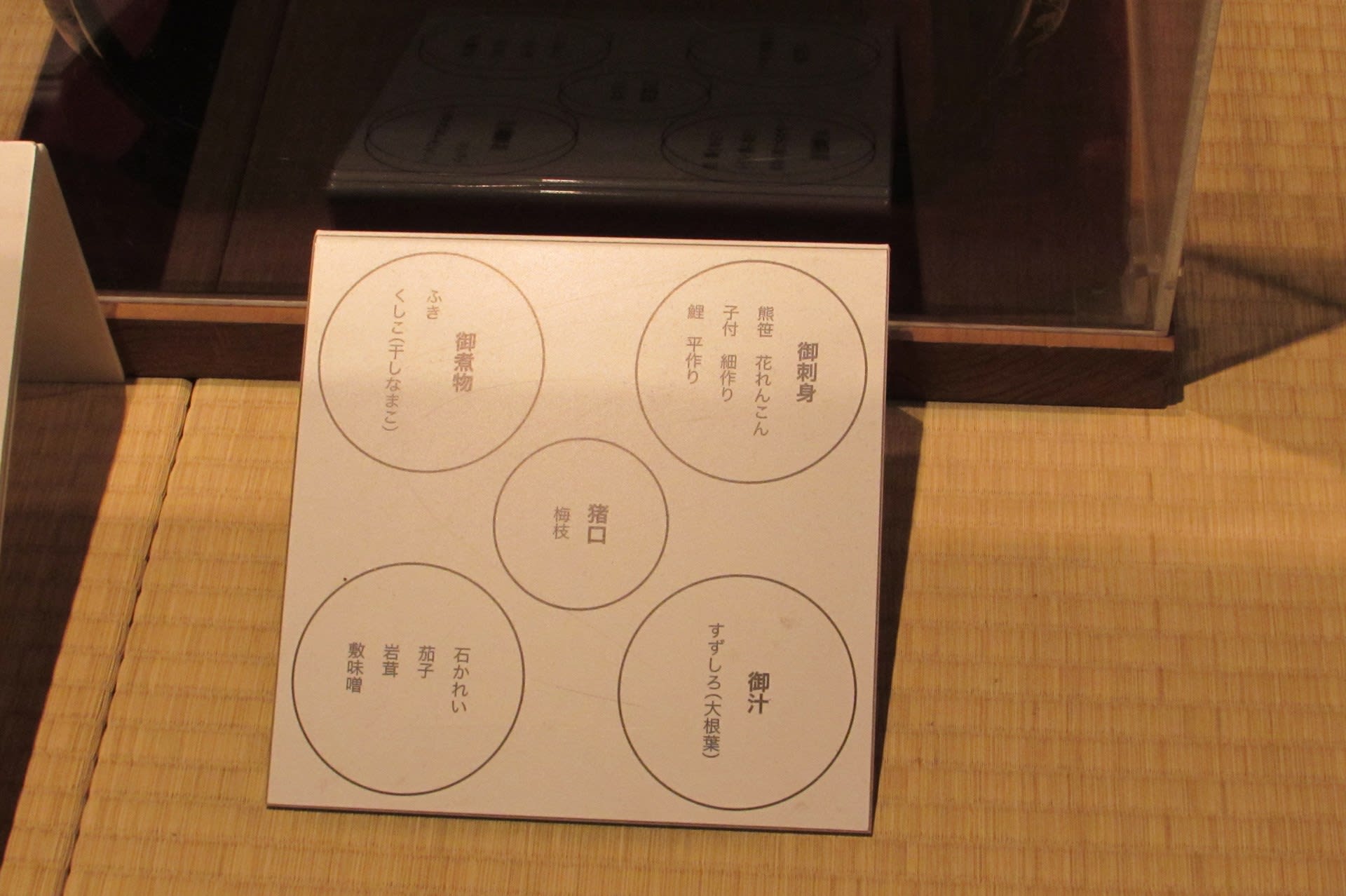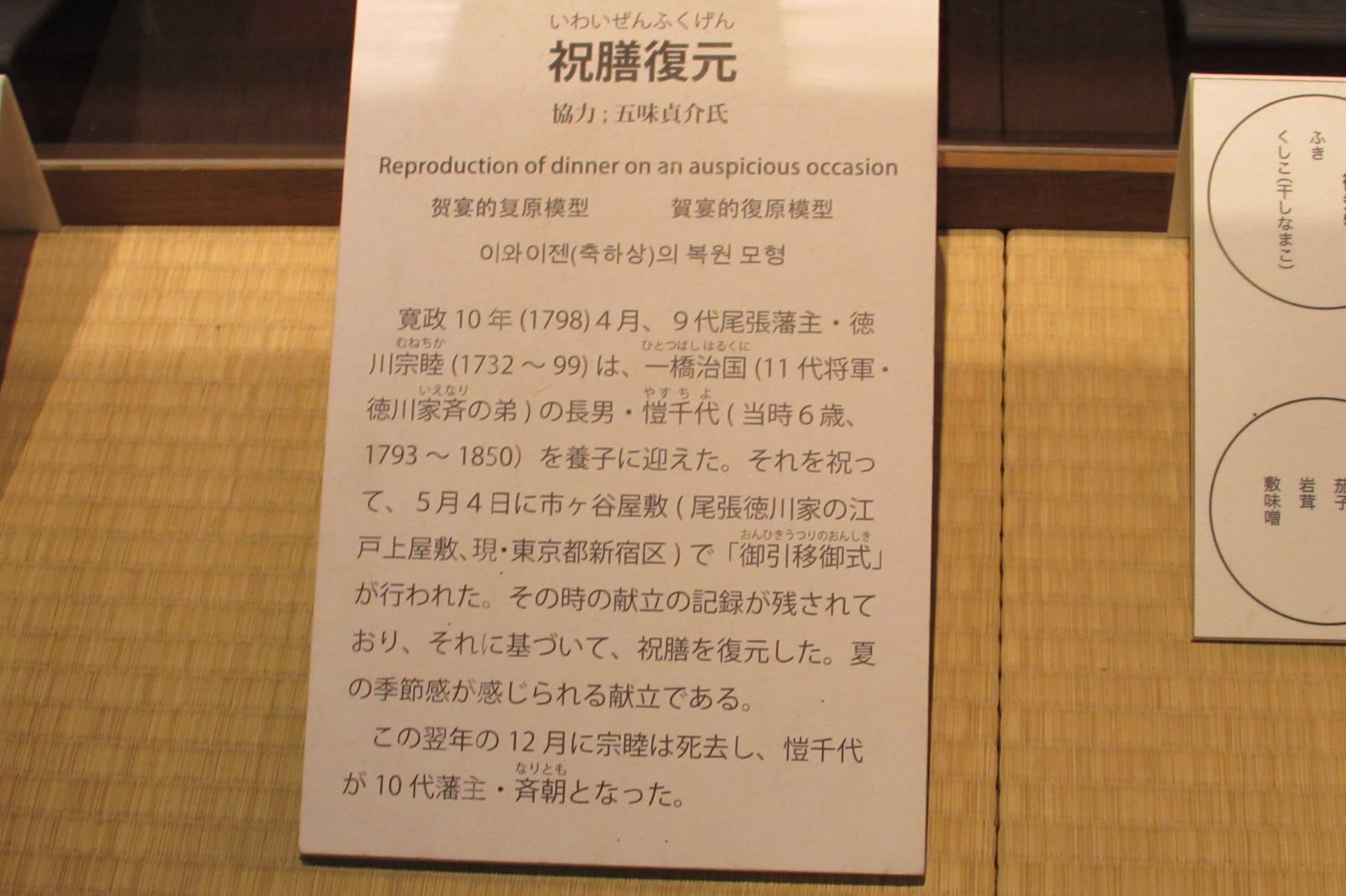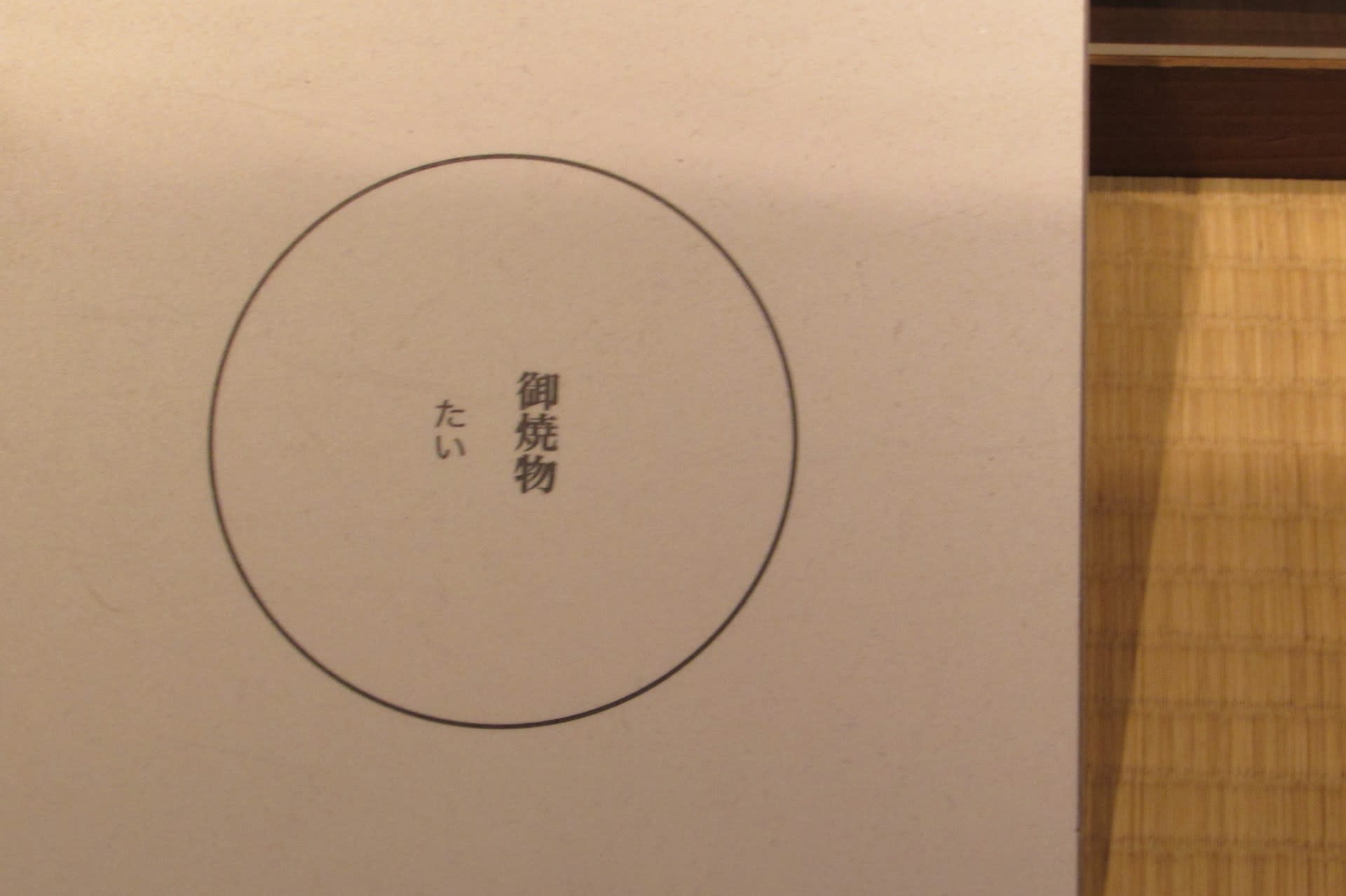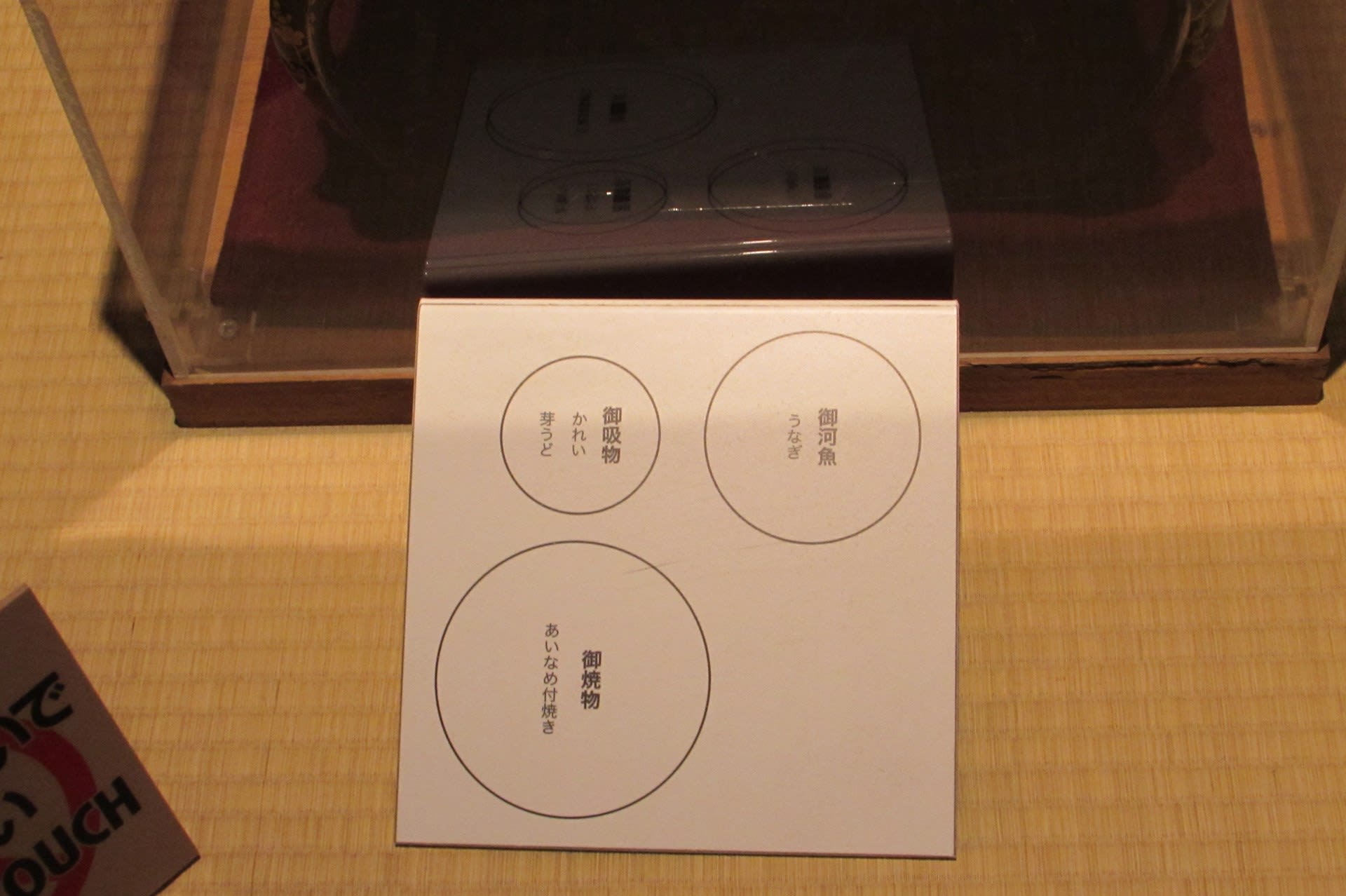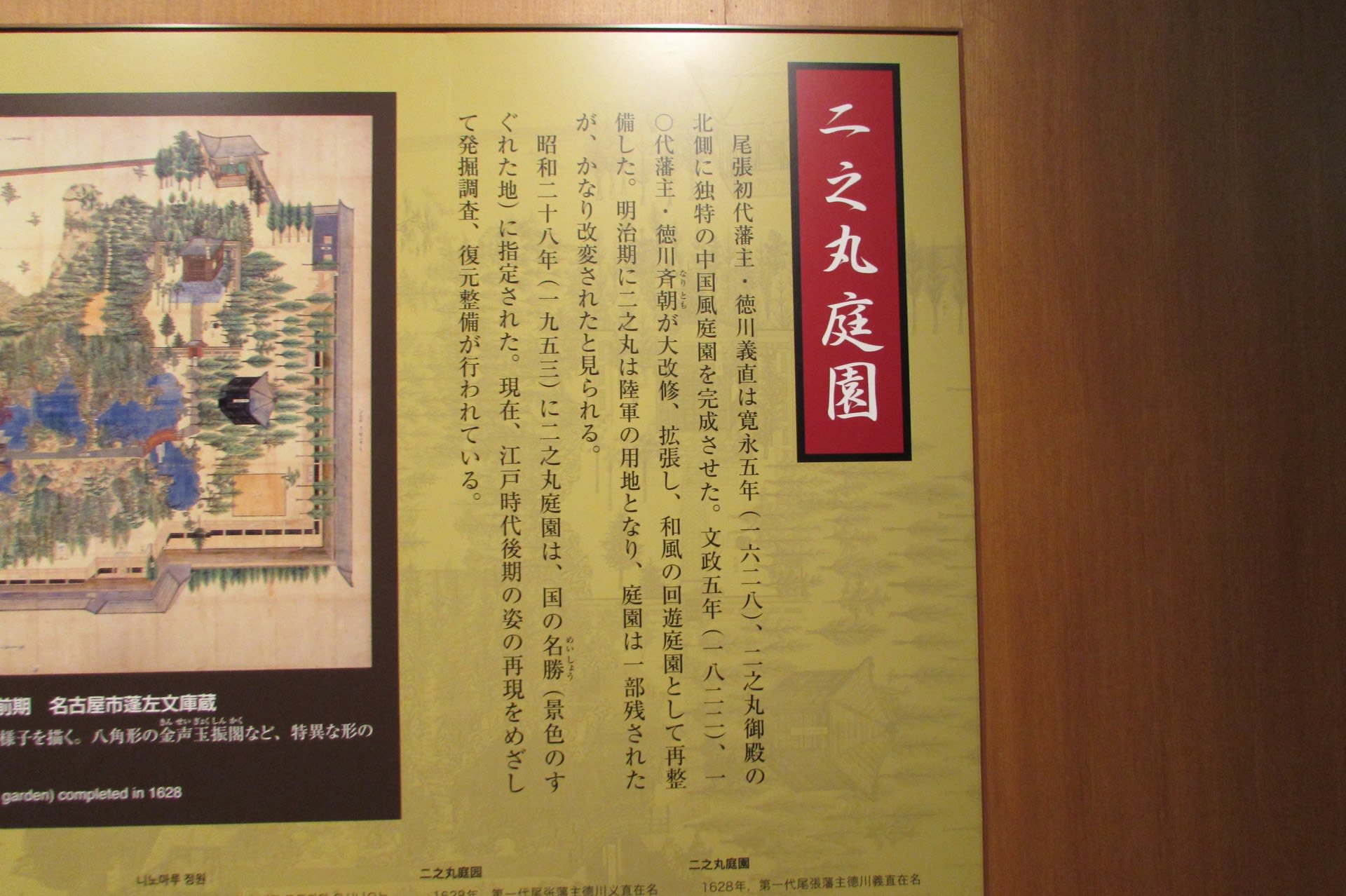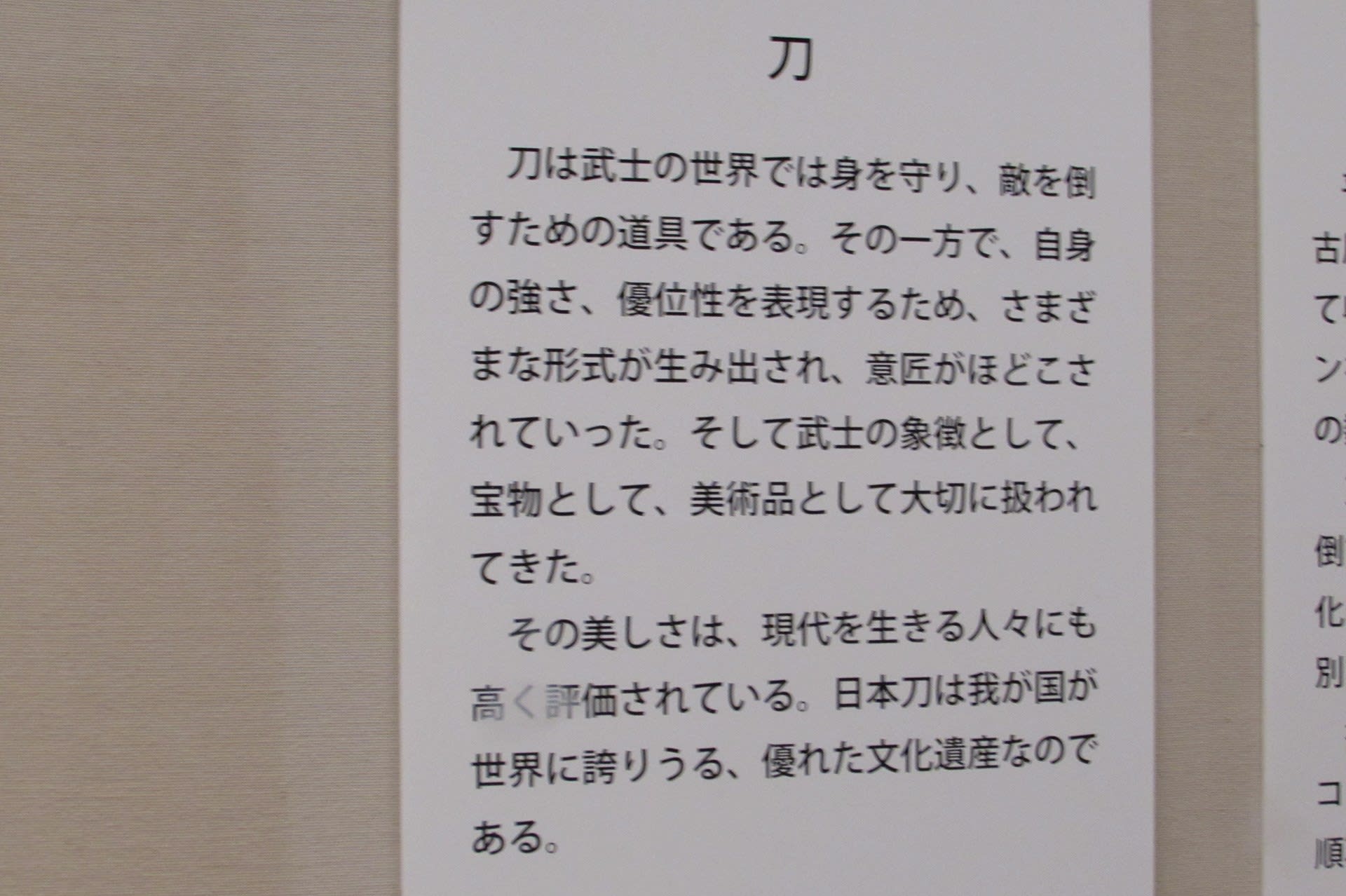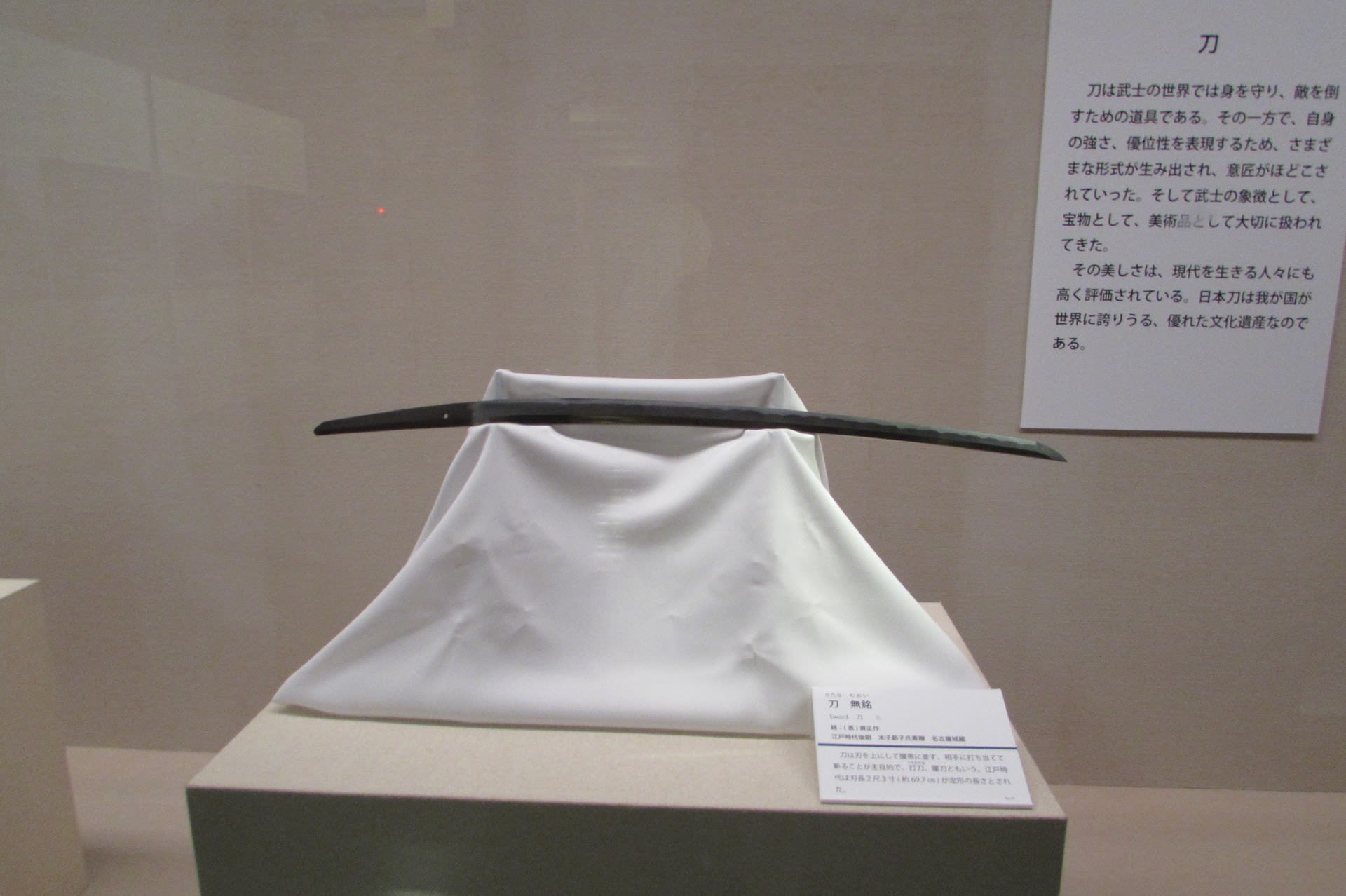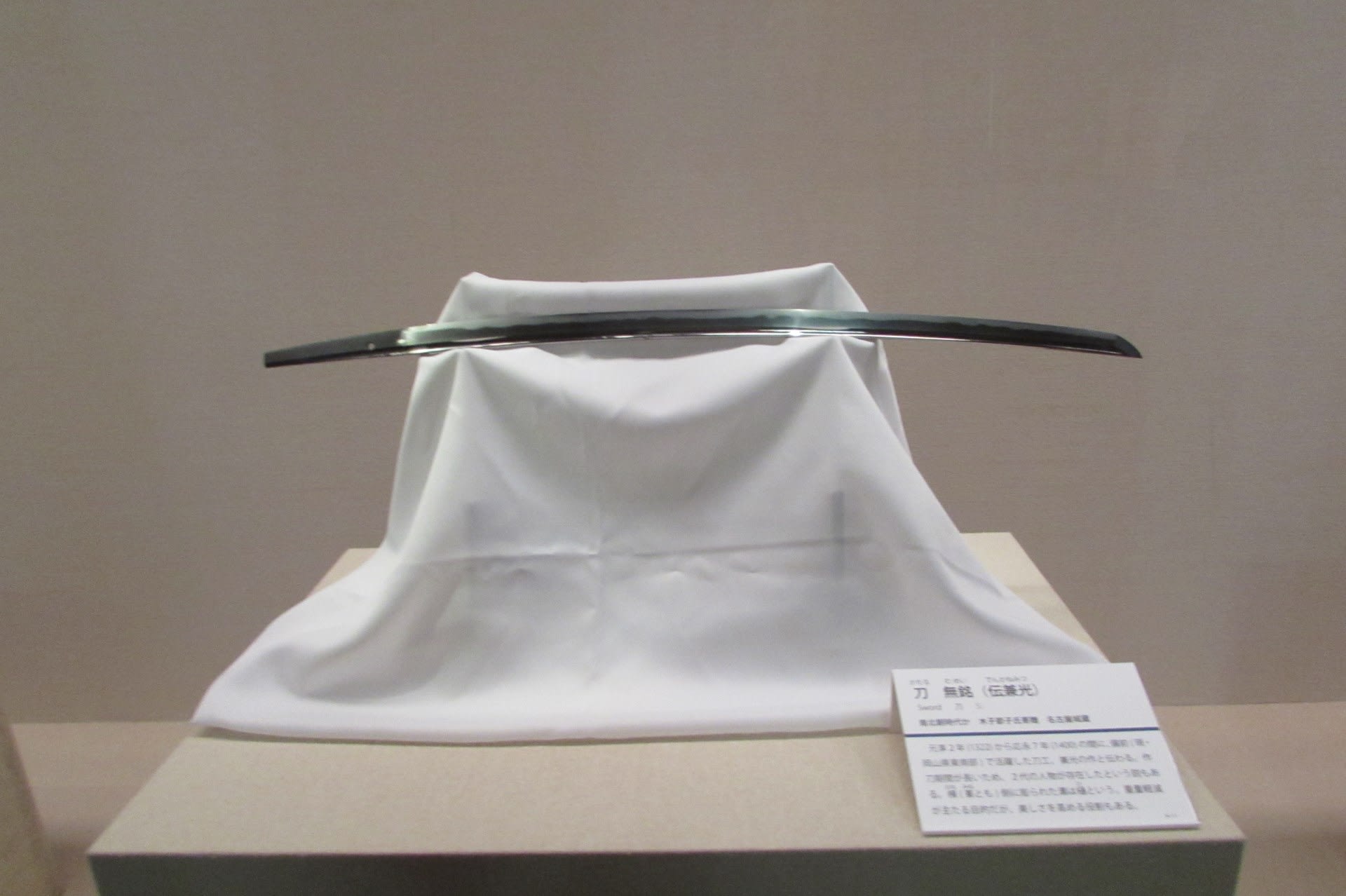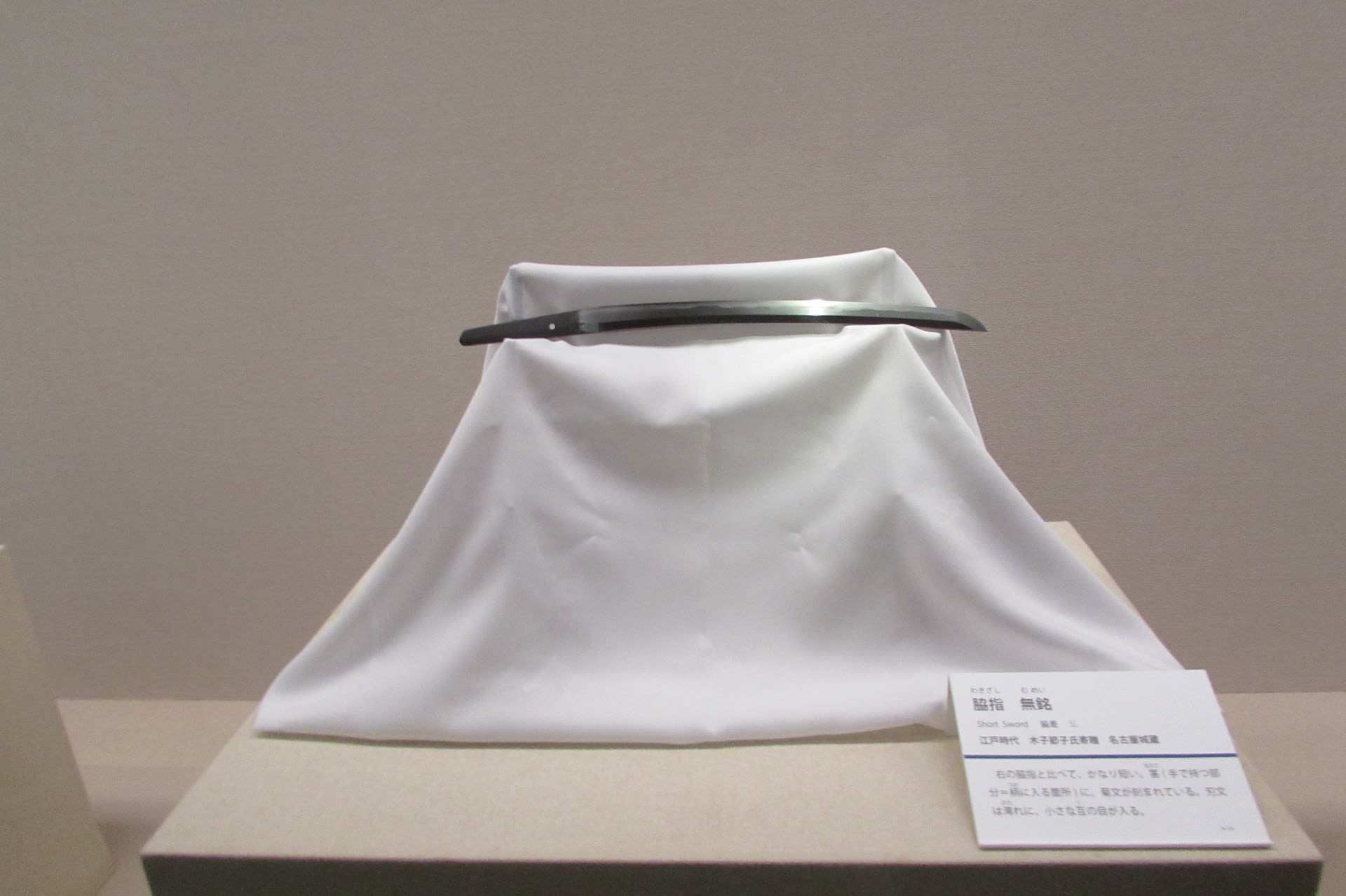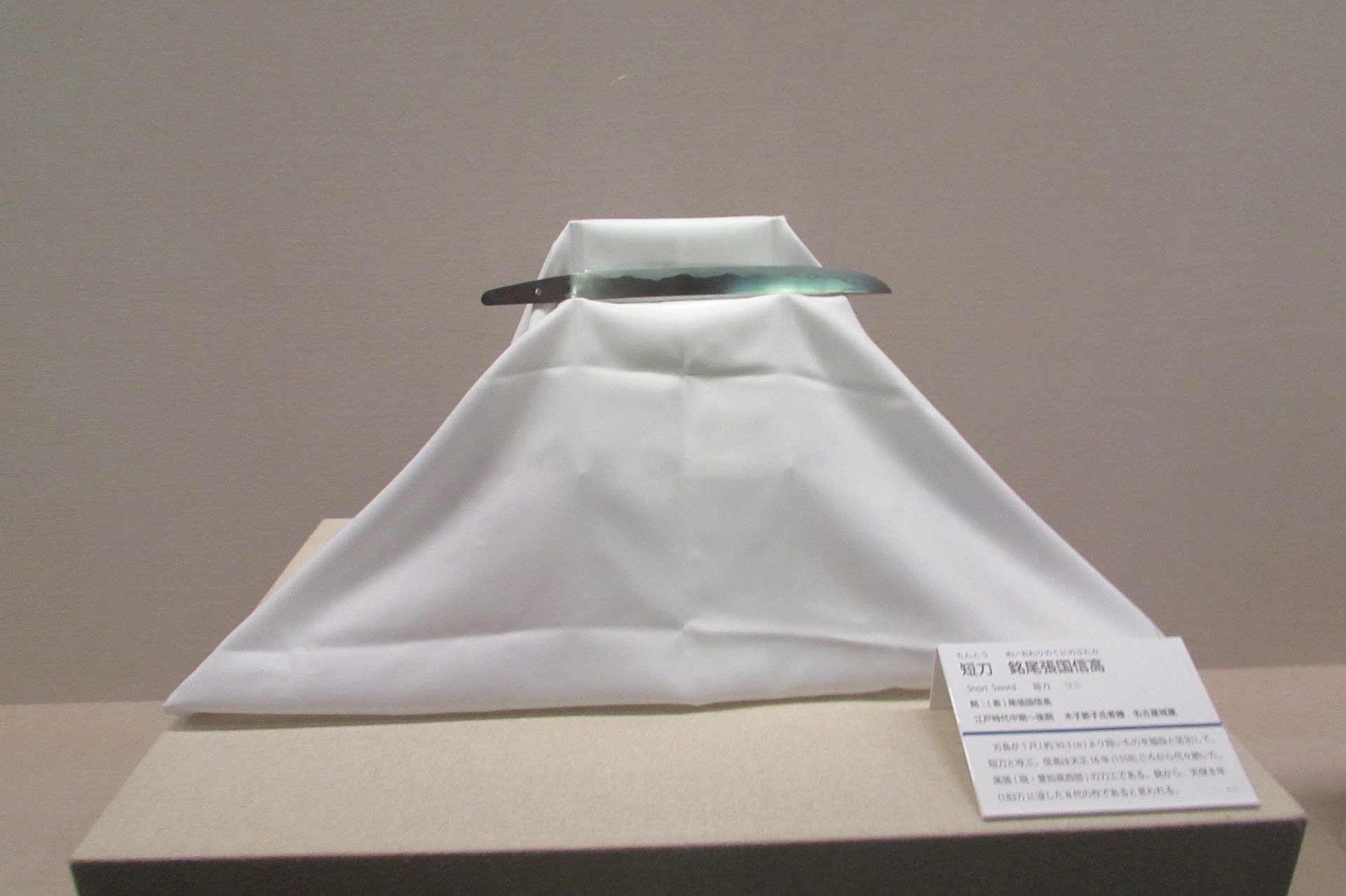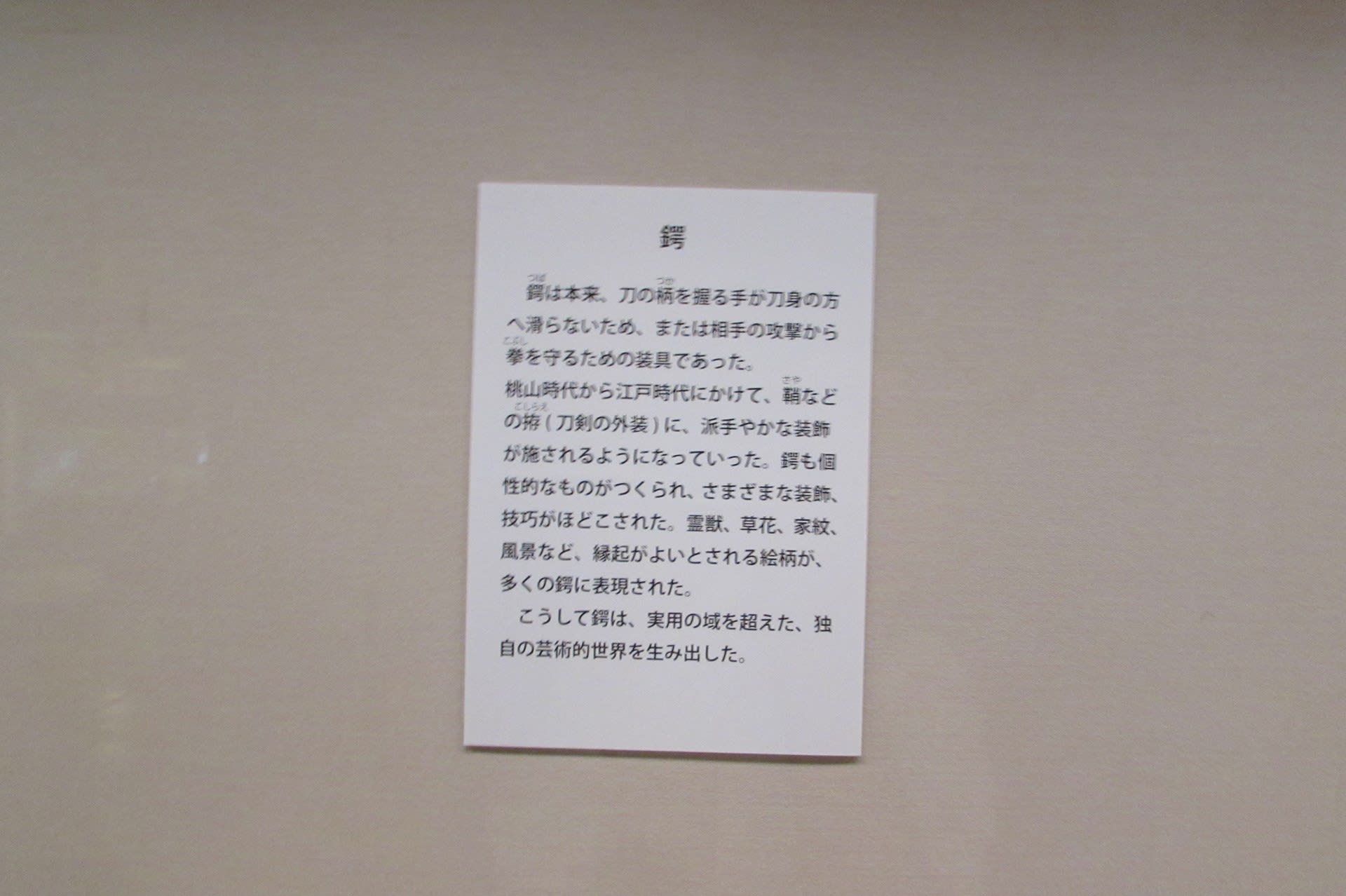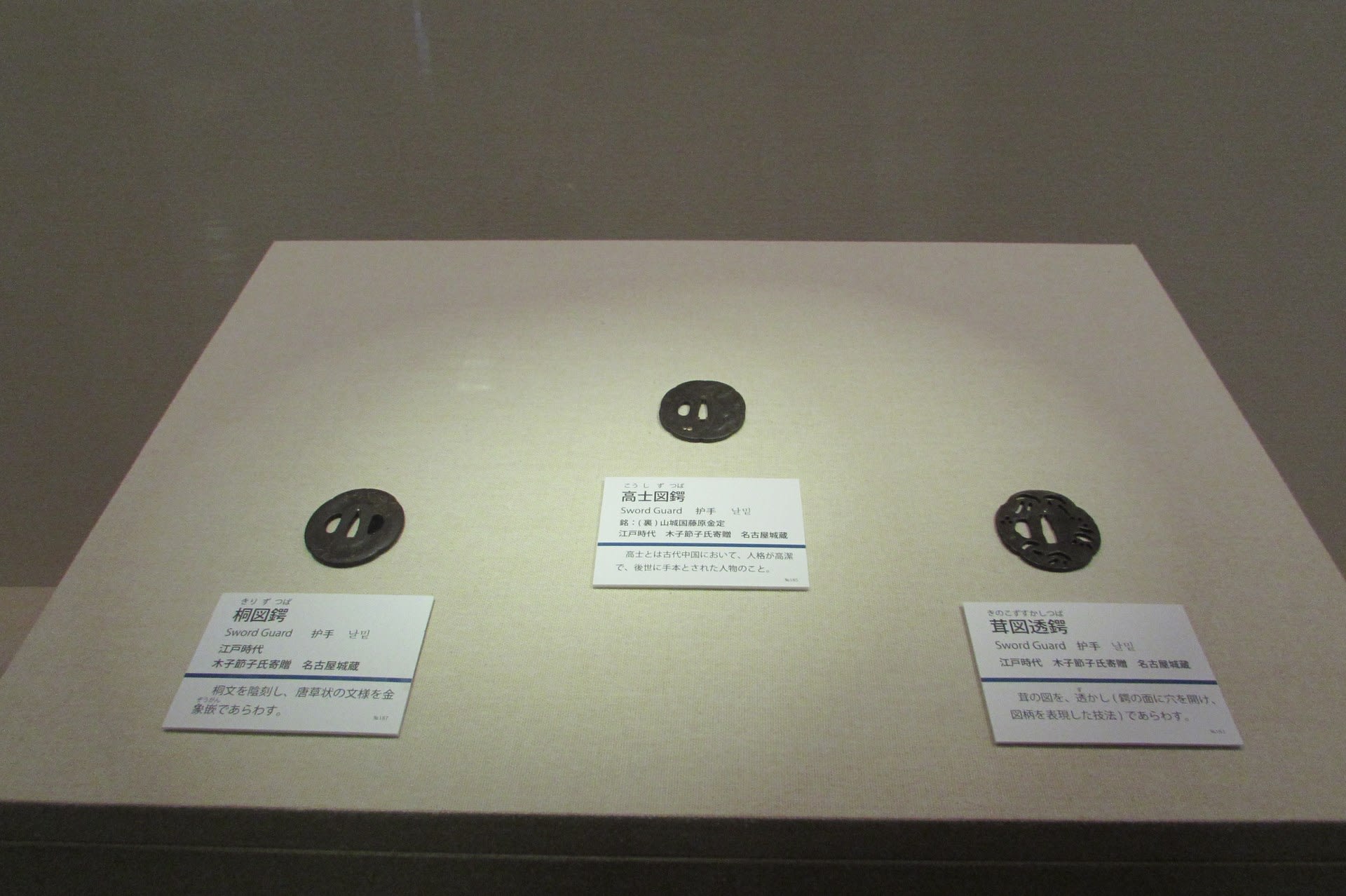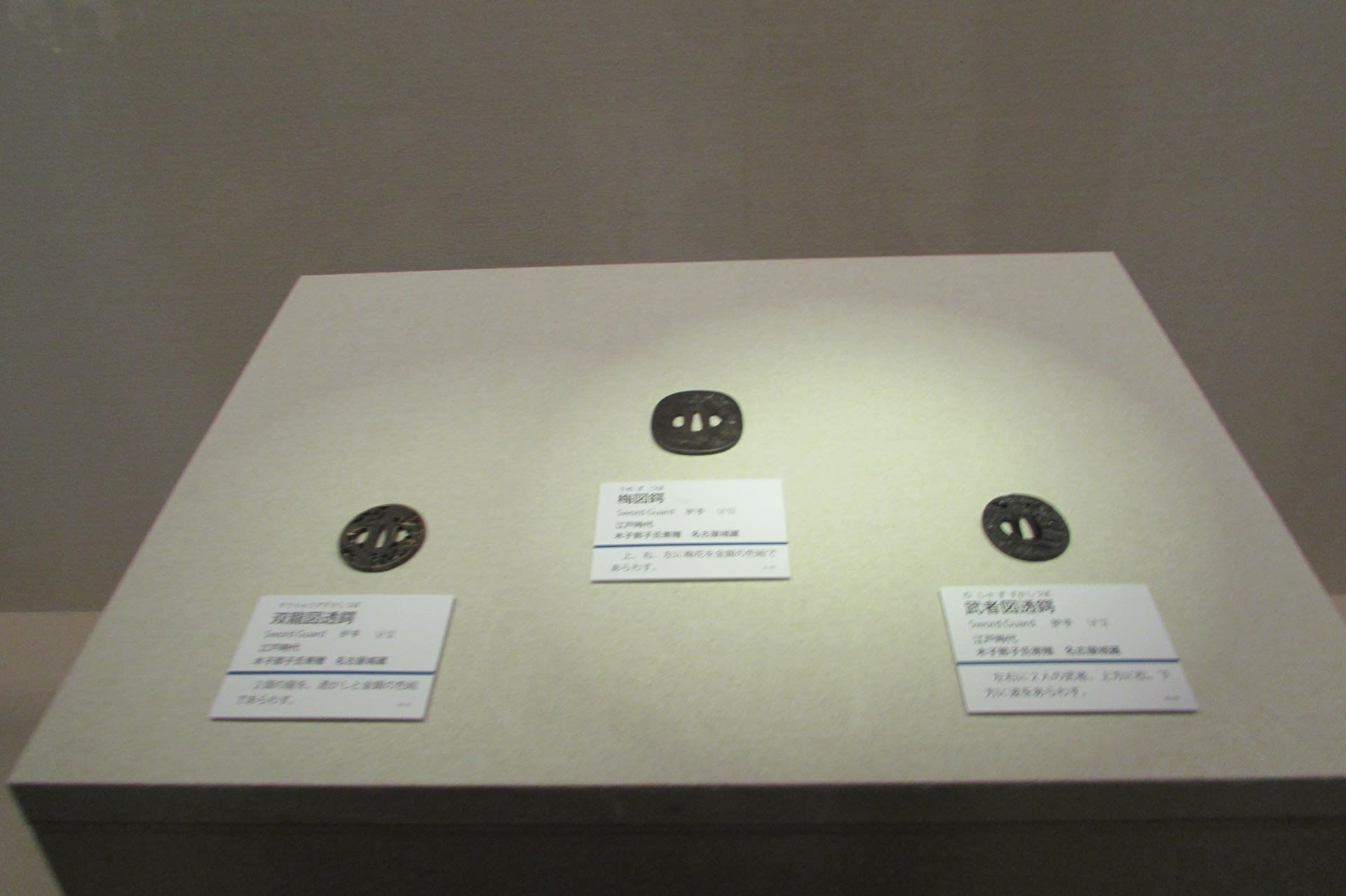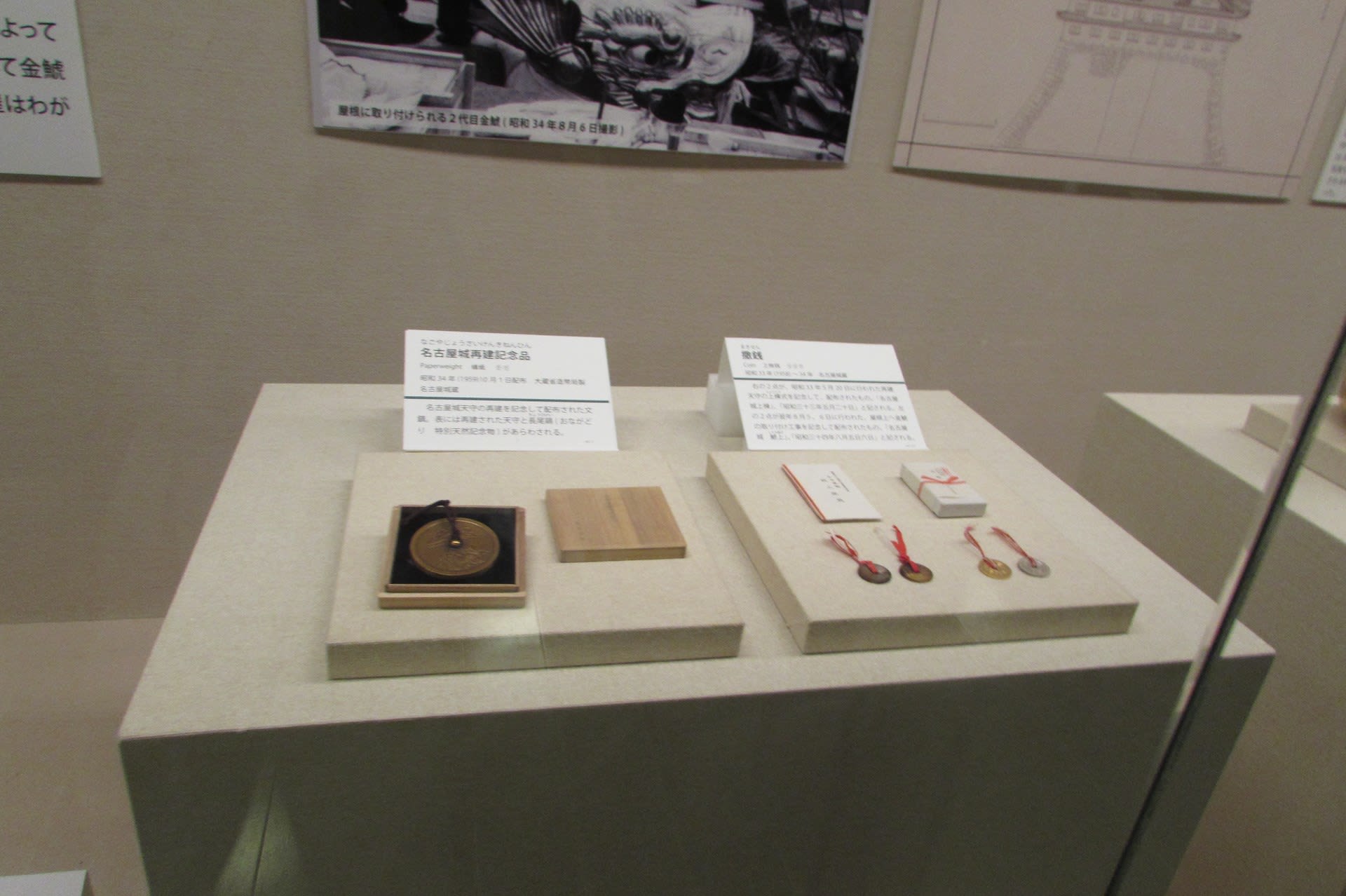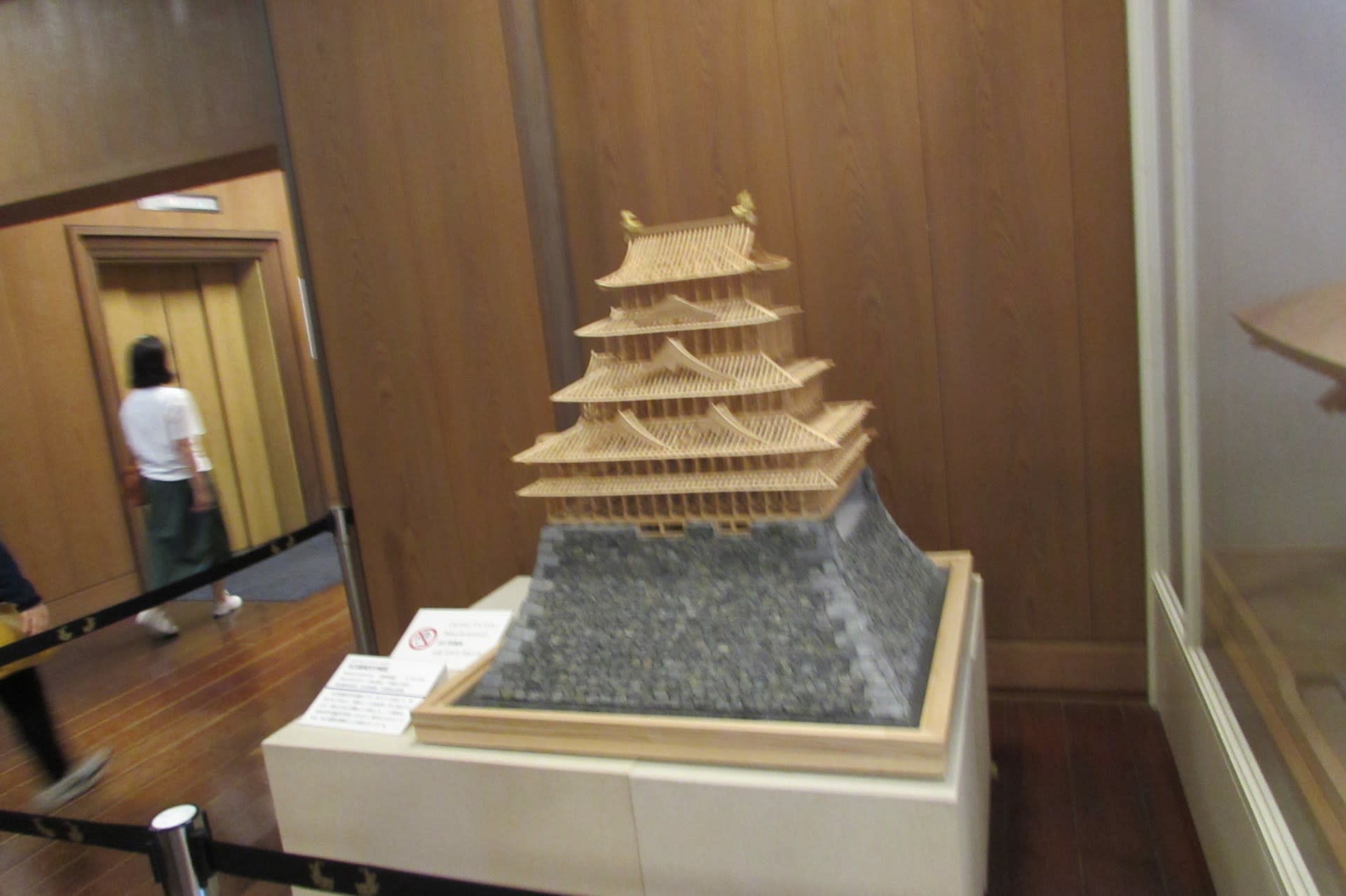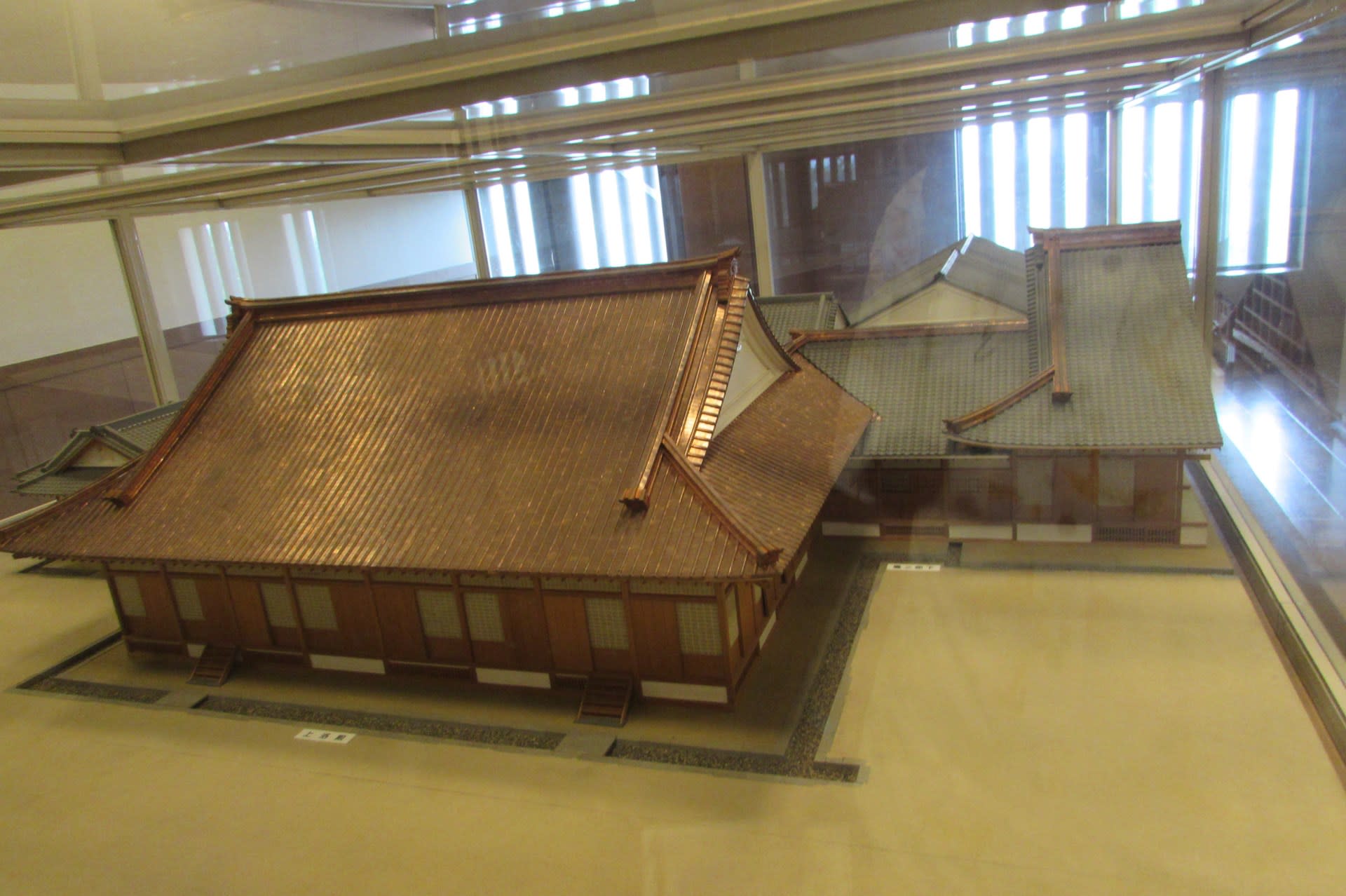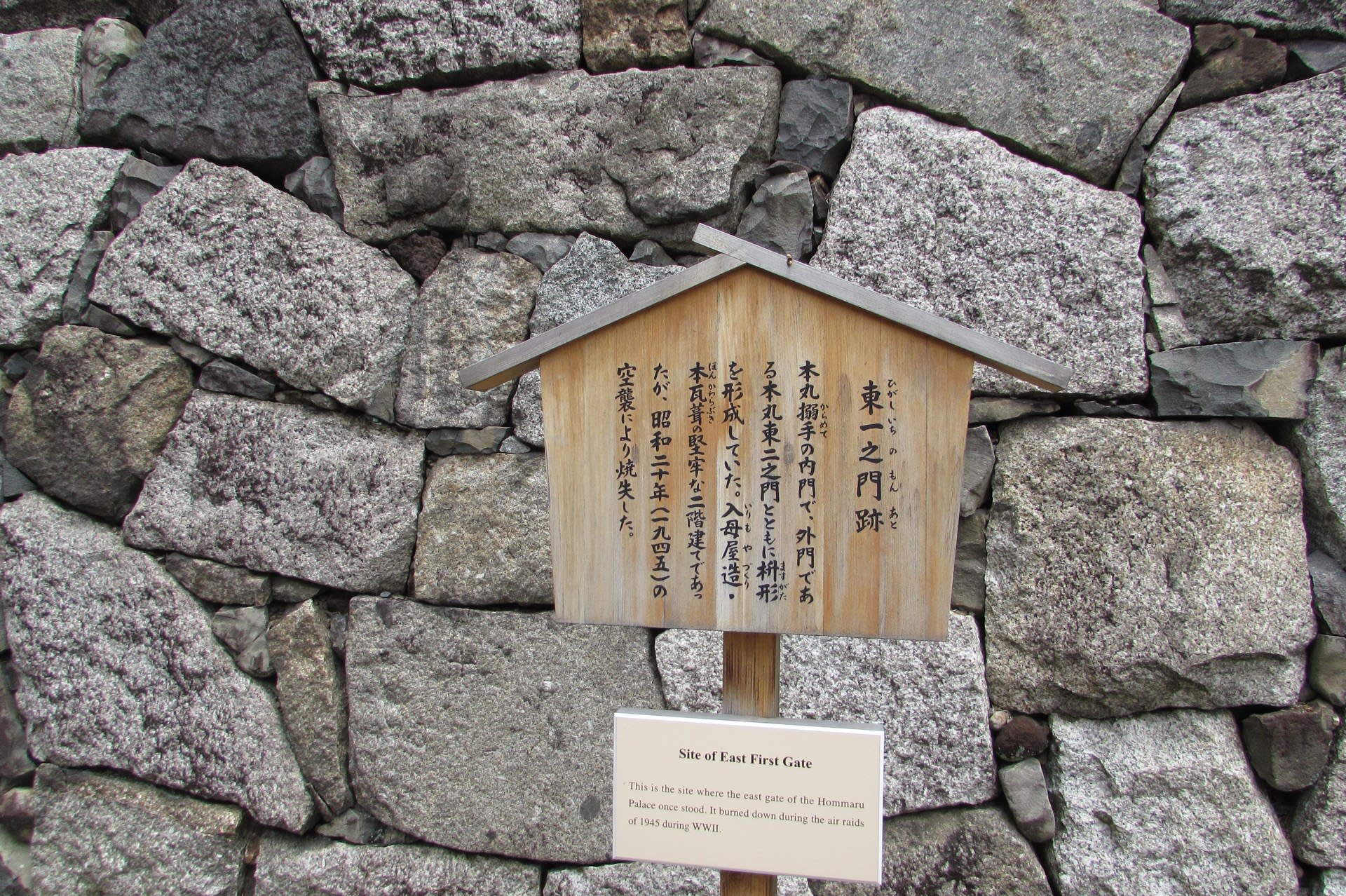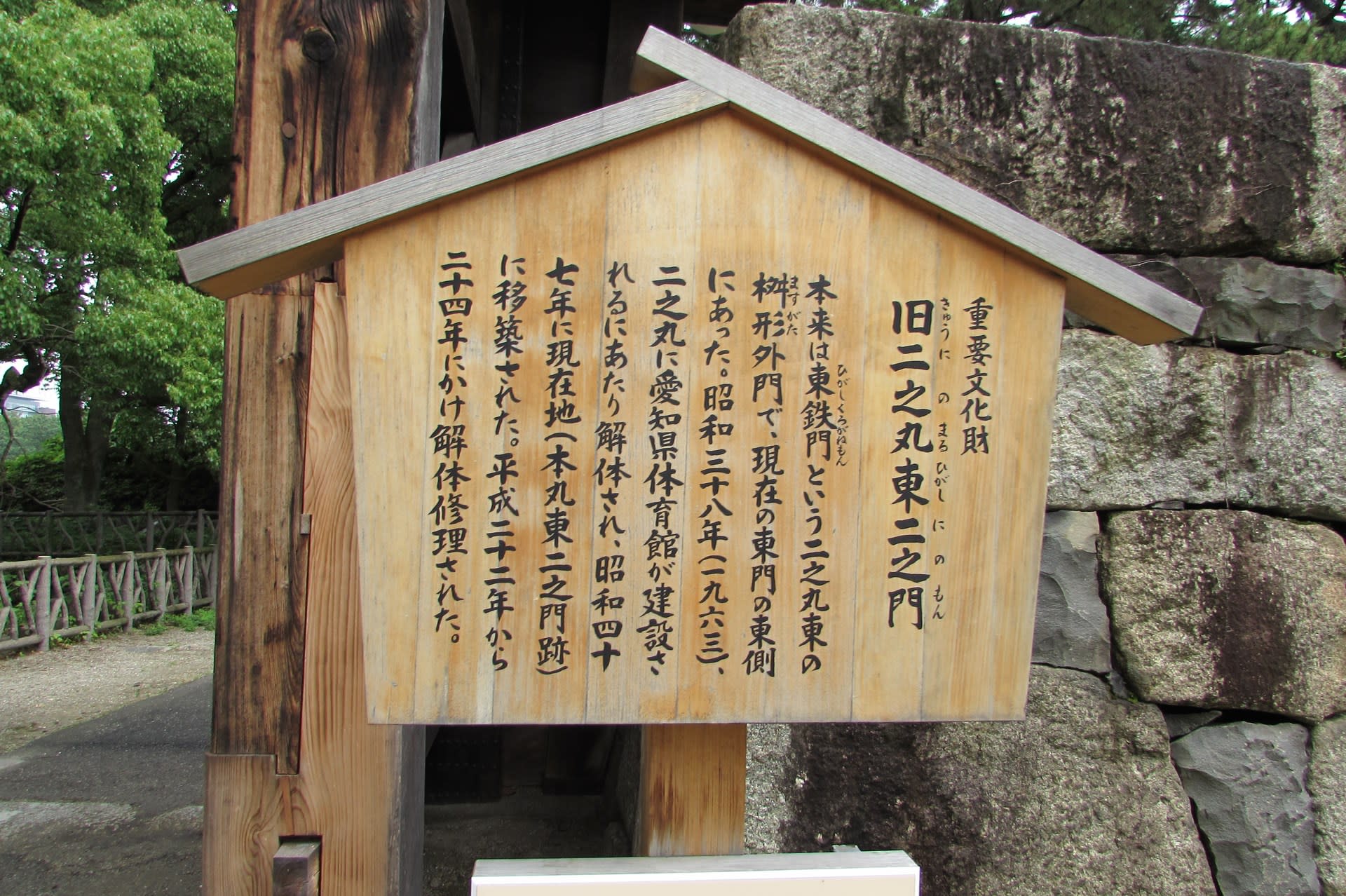2018年5月24日、愛知観光で重要伝統的建造物群保存地区の有松を散策しました。有松は、慶長13年(1608)東海道に生まれた町です。阿久比庄(現在の愛知県知多郡阿久比町)から移住した竹田庄九郎をはじめ8名により開かれ、絞りの名産地として発展しました。名古屋市内では珍しく、なまこ壁やうだつが上がる江戸時代の商家が建ち並ぶ町です。保存地区は、東海道に沿った約800メートルの範囲である。町並みを特徴づけるのは、敷地間口が大きい絞商の屋敷構えで、街道に面して主屋や土蔵を並べ、さらには門や塀を建てています。そのため、町家が並ぶ所々に、塀越しに庭木や隠居屋等を見越す景観が混じります。絞商の主屋は、東側(江戸側)に通り土間を設け、西側(京都側)に部屋を三列に並べる間取りを持つ。職人の町家は二列型を基本とし、一列型のものも見られます。集落の成立から現在まで、絞り染めを産業として継続し、旧の幅を残す東海道に沿って、意匠に優れた大規模な主屋や土蔵を有する絞商の豪壮な屋敷構えと職人の町家が混在して建ち並び、特色ある歴史的風致を良く伝えています。」名鉄有松駅の南側すぐに通りがあります。
map
案内図





































































有松天満宮
「有松天満社は寛政年間の始め(1789~)に旧東海道の祇園寺の四世文章卍瑞によって現在地に遷座され、文政7年(1824)現在の「八棟造」の社殿が造営され、今日まで守り続けられてきました。有待天満社は菅原道真公を祭神として祀られています。道真は平安時代の貴族で優れた学者であった事から朝廷では要職についていましたがある日、大宰府へ島流しとなり波乱の生涯を閉じました。道真の死後朝廷は「天満大自在天神」の神号を贈り神格化された人物です。江戸時代は寺子屋にも道真を祀り、天神さまは学問の神様として親しまれてきました。」













map
案内図





































































有松天満宮
「有松天満社は寛政年間の始め(1789~)に旧東海道の祇園寺の四世文章卍瑞によって現在地に遷座され、文政7年(1824)現在の「八棟造」の社殿が造営され、今日まで守り続けられてきました。有待天満社は菅原道真公を祭神として祀られています。道真は平安時代の貴族で優れた学者であった事から朝廷では要職についていましたがある日、大宰府へ島流しとなり波乱の生涯を閉じました。道真の死後朝廷は「天満大自在天神」の神号を贈り神格化された人物です。江戸時代は寺子屋にも道真を祀り、天神さまは学問の神様として親しまれてきました。」