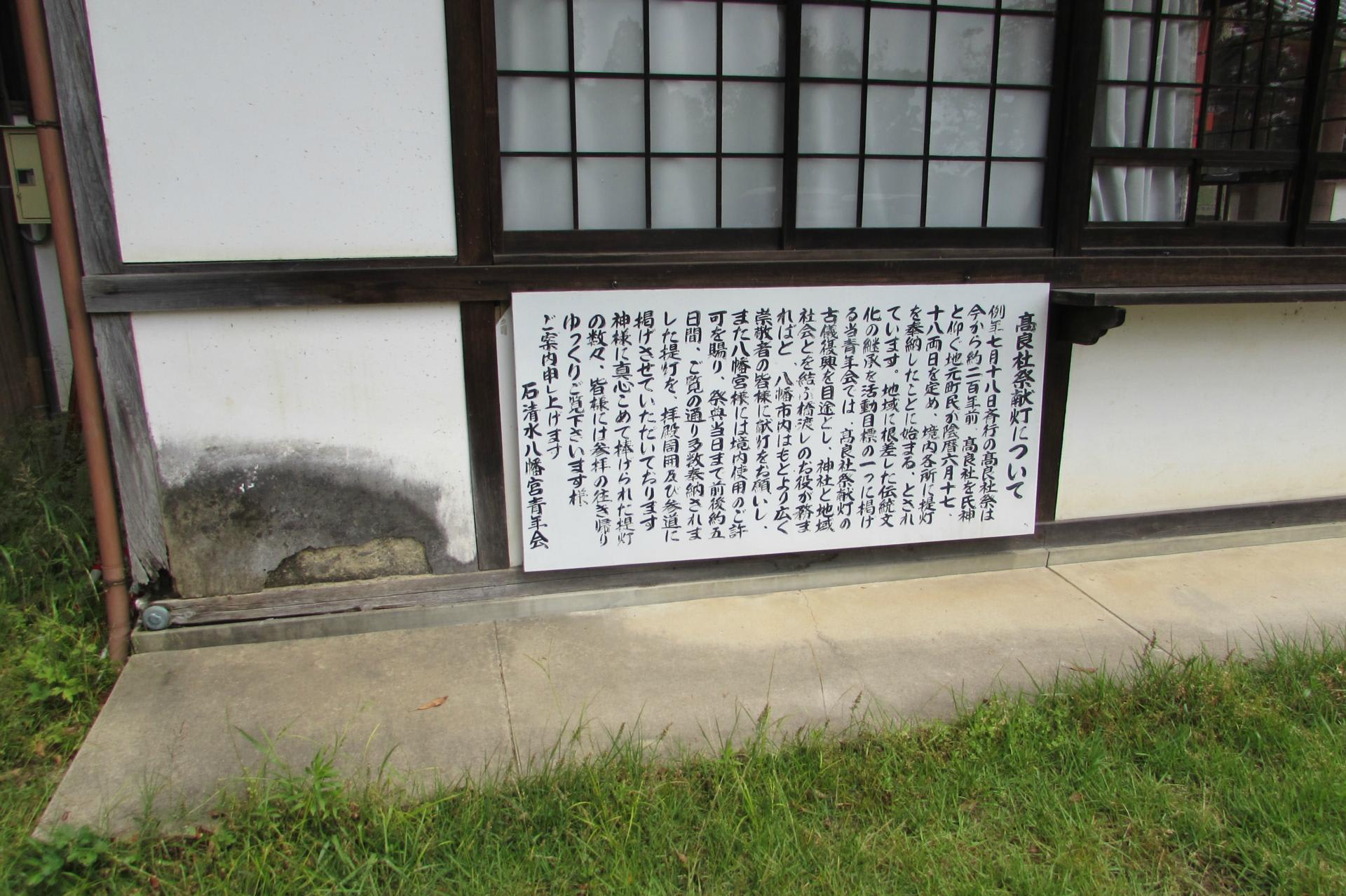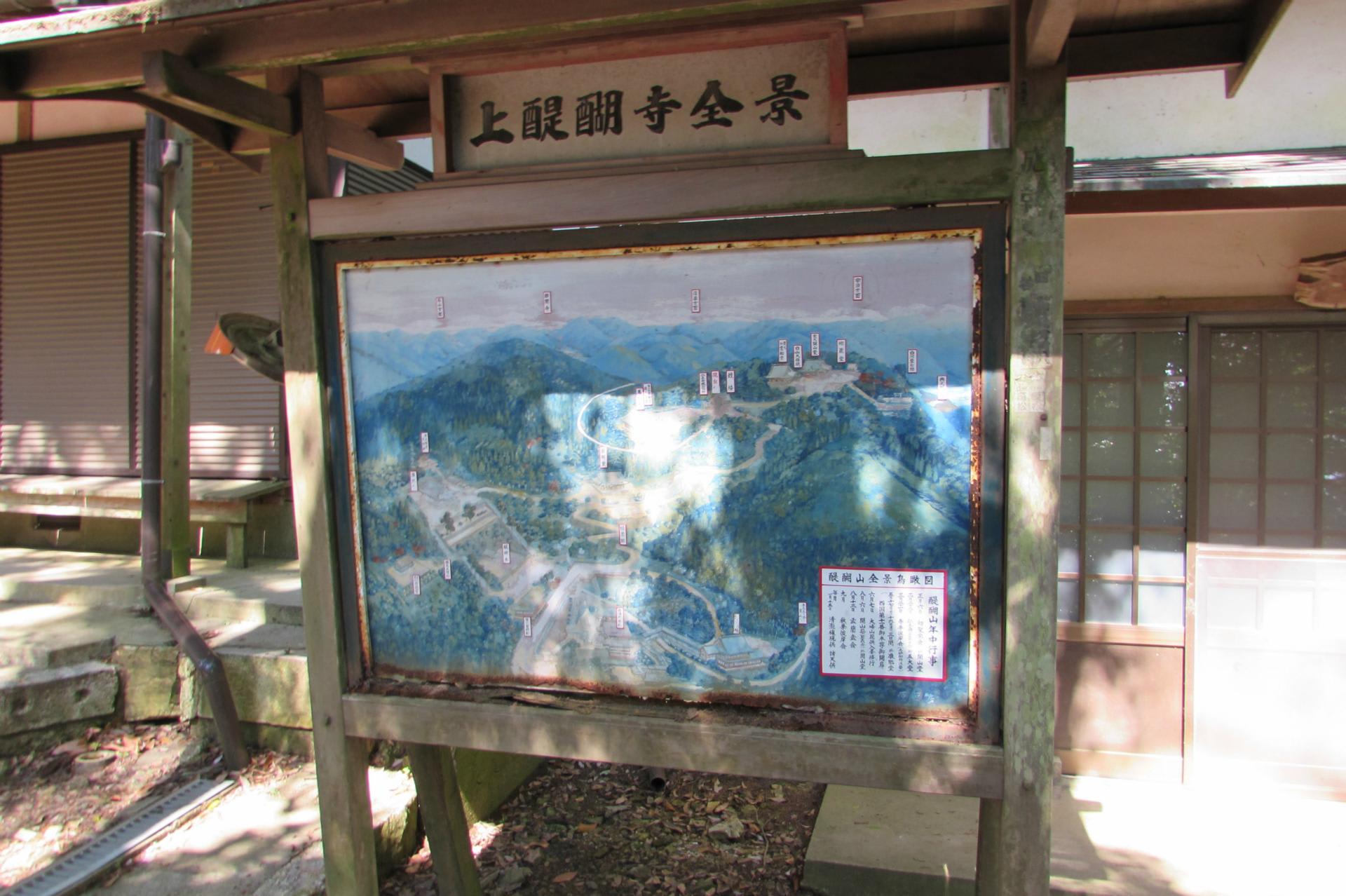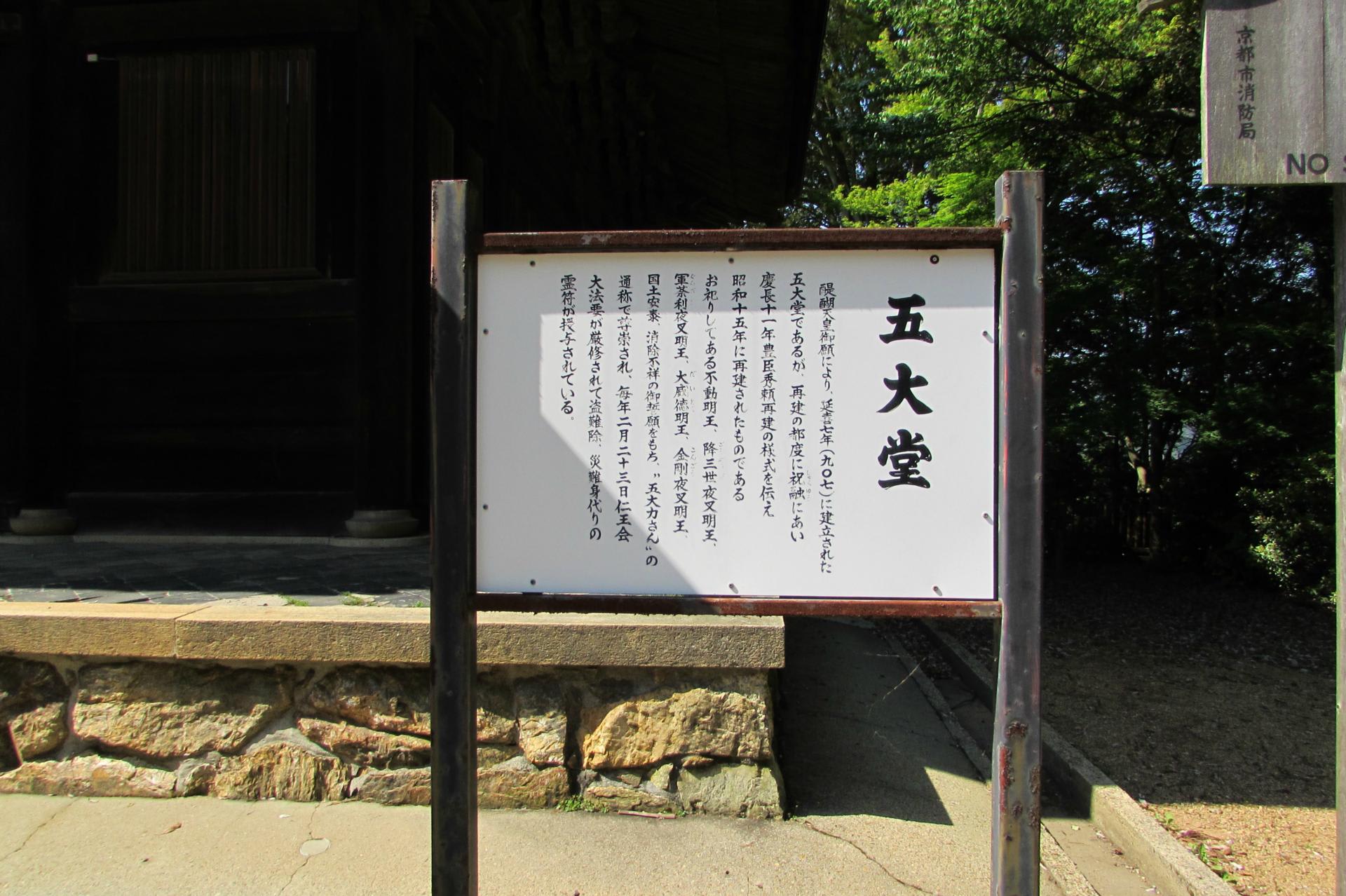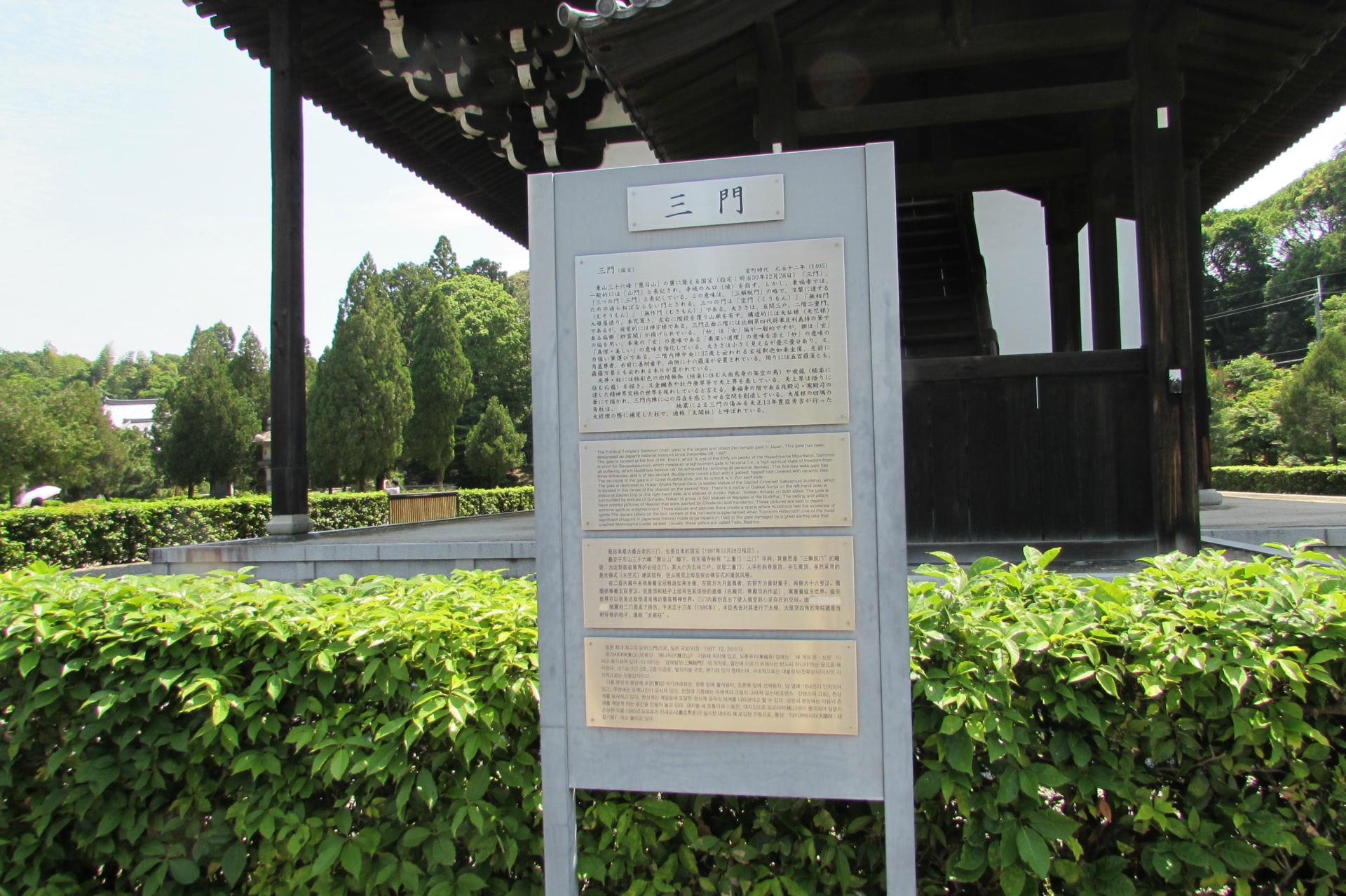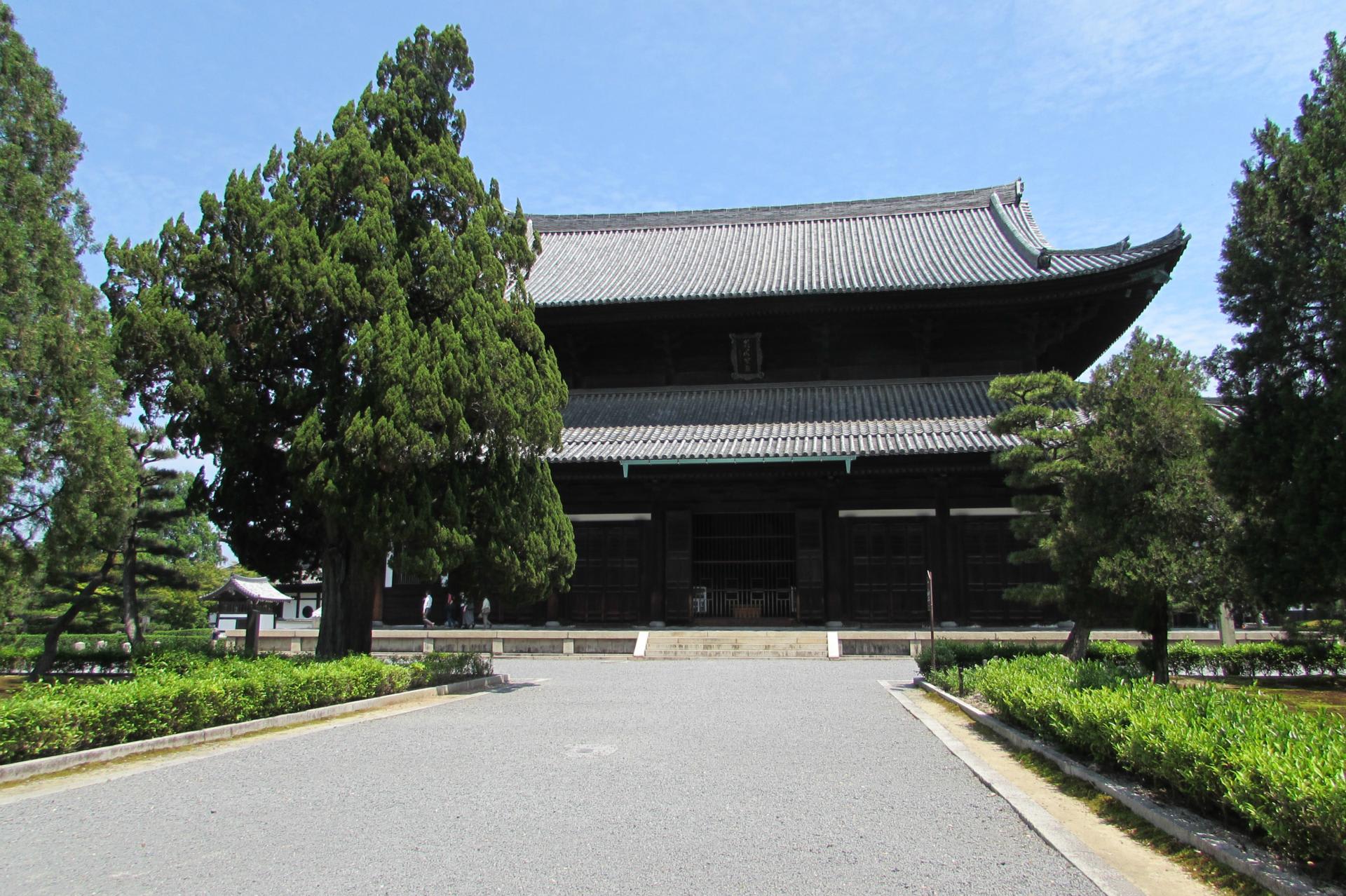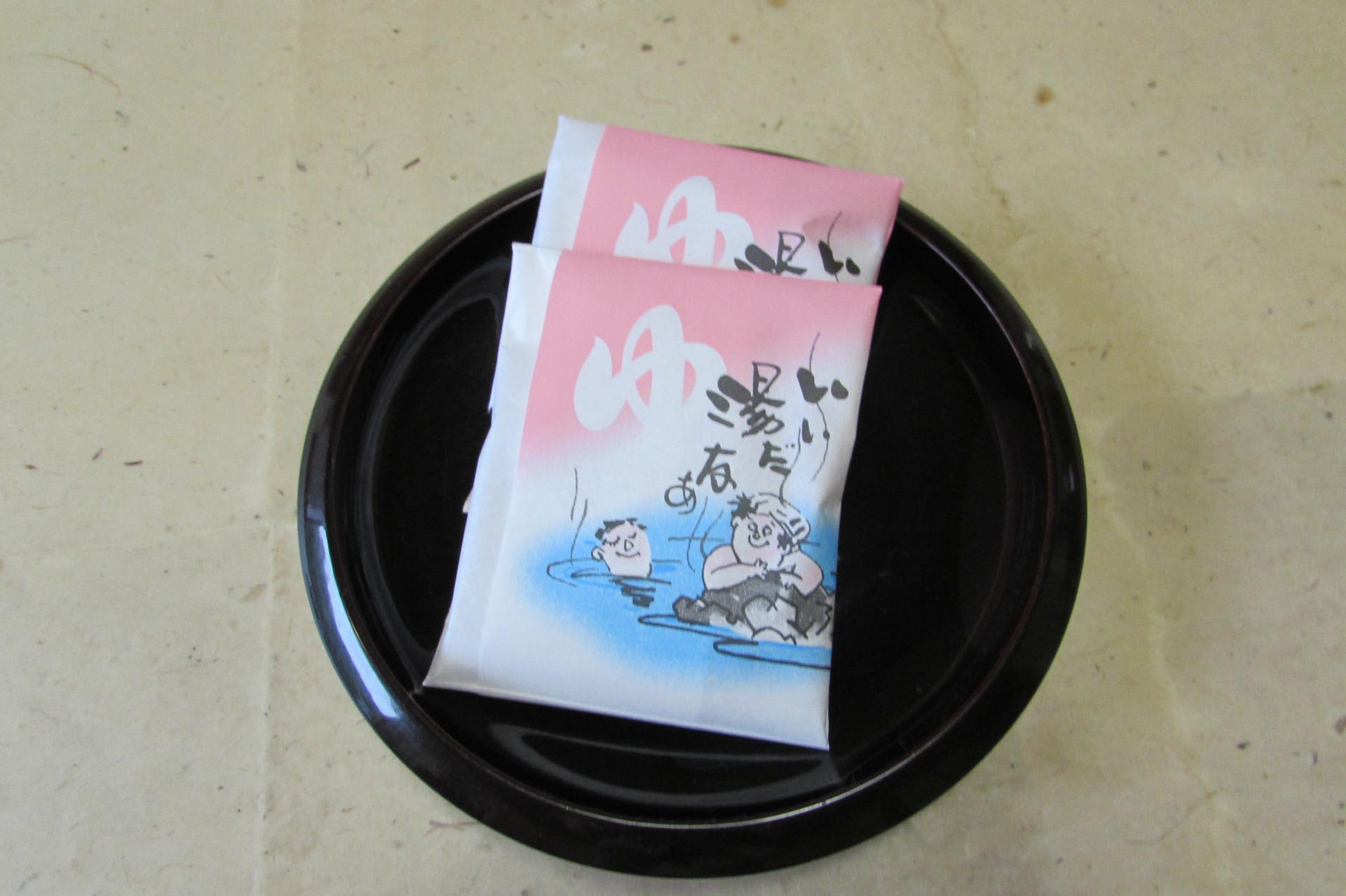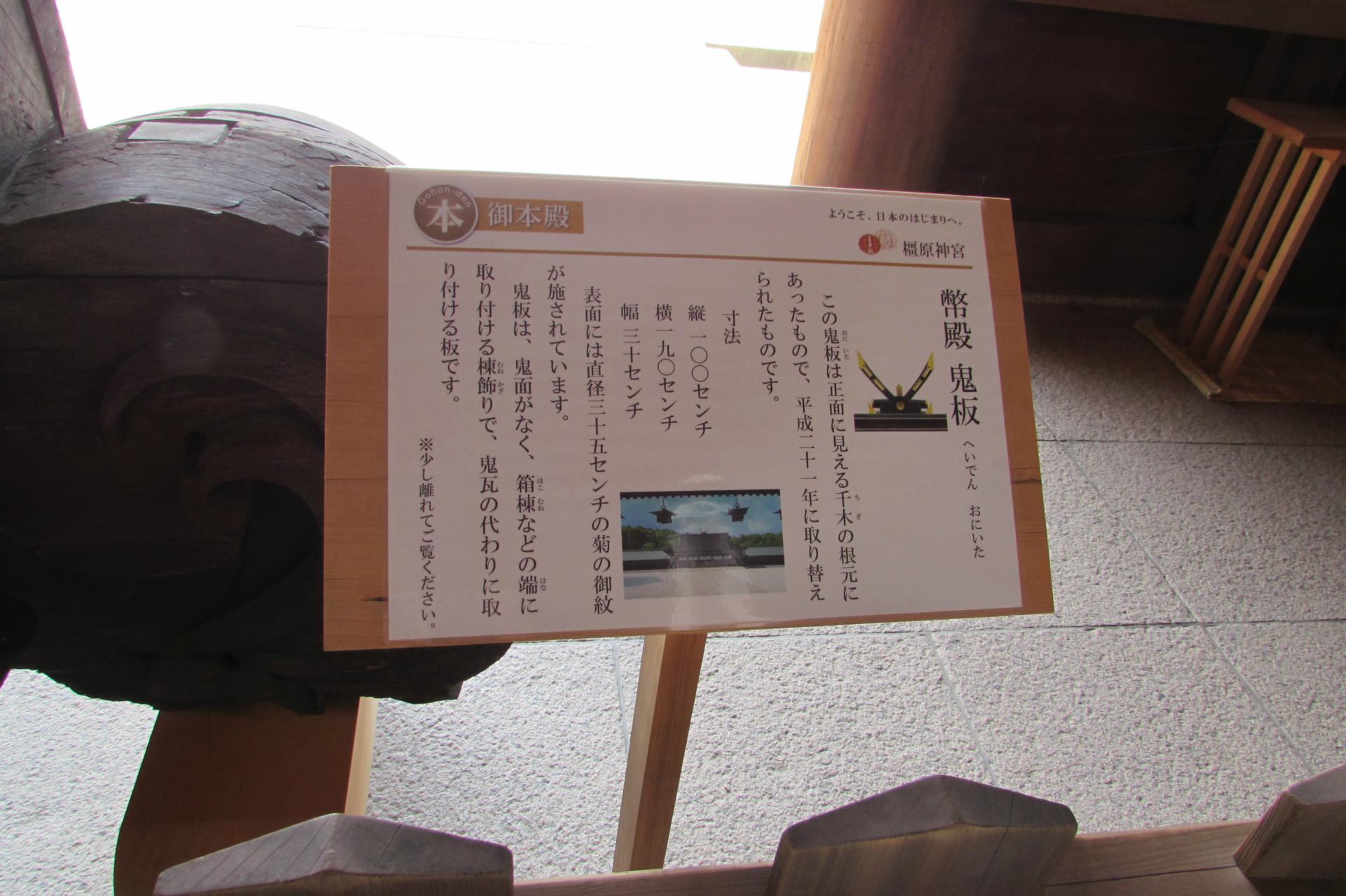2016年5月27日、伊丹の荒巻バラ公園に行きました。昨日には雨が結構降りましたので、どうかなと思いながら行きました。少し、散っていたものもありました。駐車料金は500円です。
「高低差がある地形を利用した立体的なバラ園で、世界のバラ約250種1万本が一望できます。」
5月15日から6月30日と10月から11月は休園日は無、他の月は火曜日が休園です。開園時間は9時から17時です。公園散策は無料です。
兵庫県伊丹市荒牧6丁目5
map


ゲート

案内図

バラを一杯、楽しんでください。






































































































売店



お疲れ様でした。
「高低差がある地形を利用した立体的なバラ園で、世界のバラ約250種1万本が一望できます。」
5月15日から6月30日と10月から11月は休園日は無、他の月は火曜日が休園です。開園時間は9時から17時です。公園散策は無料です。
兵庫県伊丹市荒牧6丁目5
map


ゲート

案内図

バラを一杯、楽しんでください。






































































































売店



お疲れ様でした。