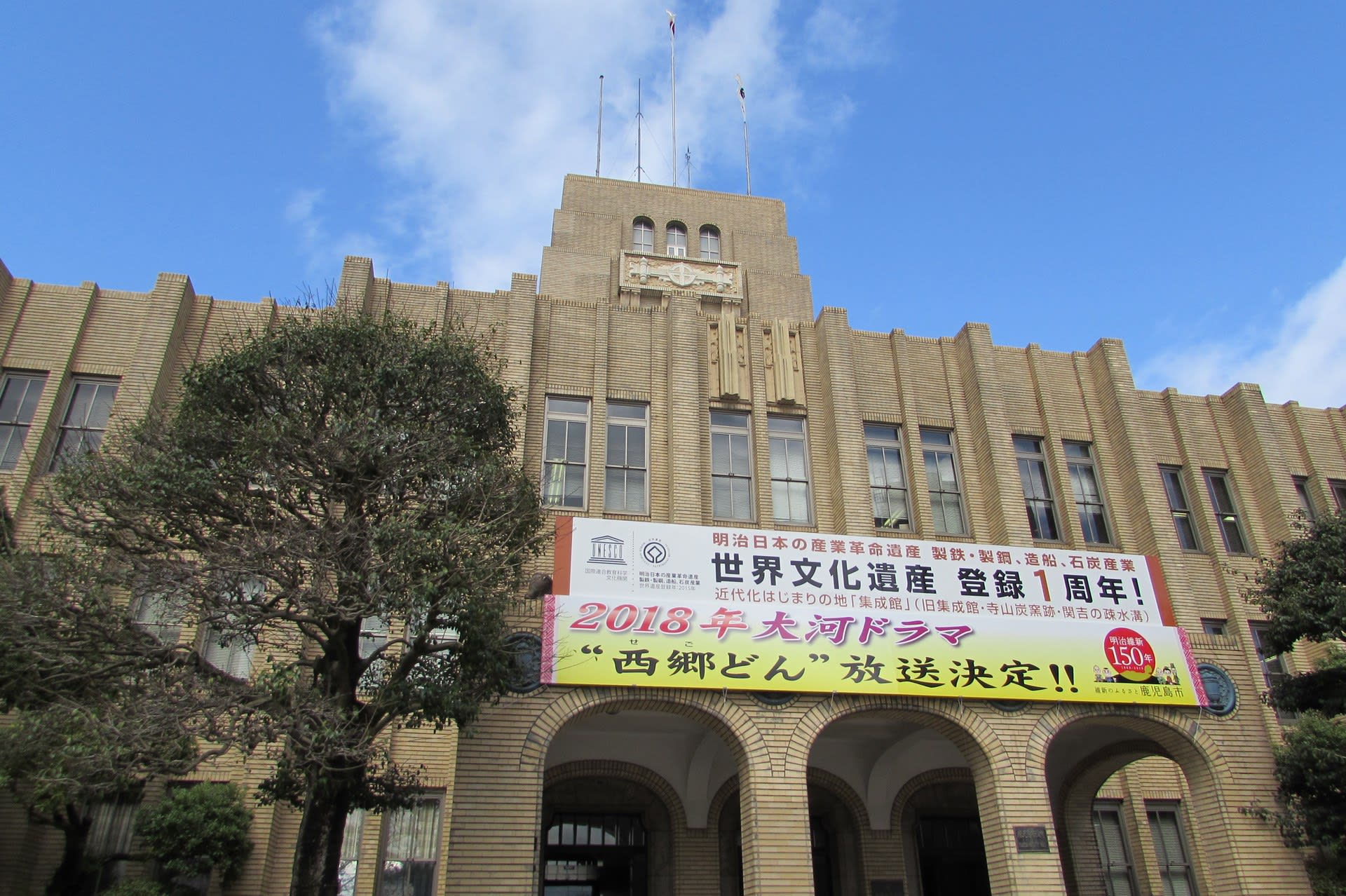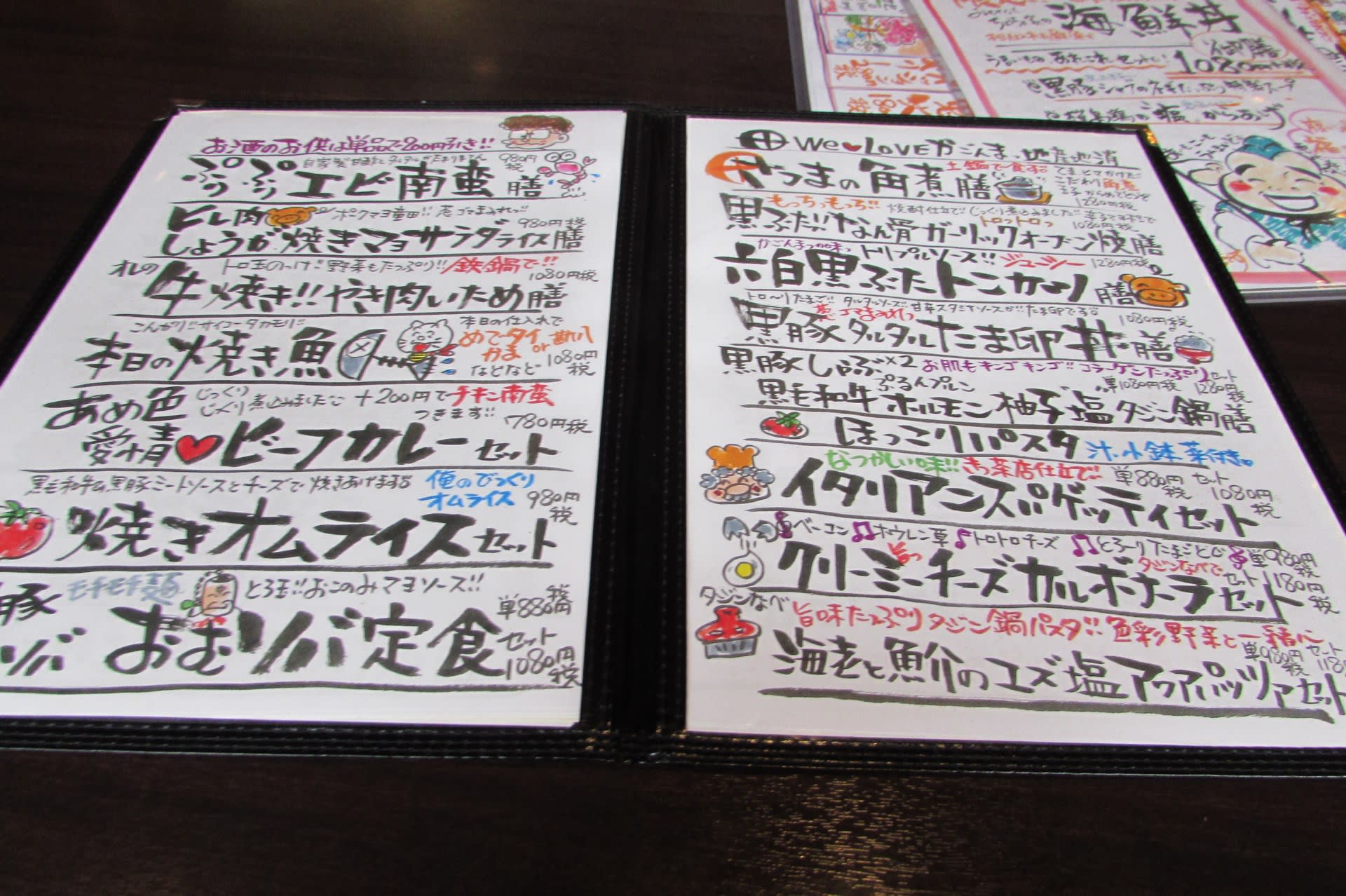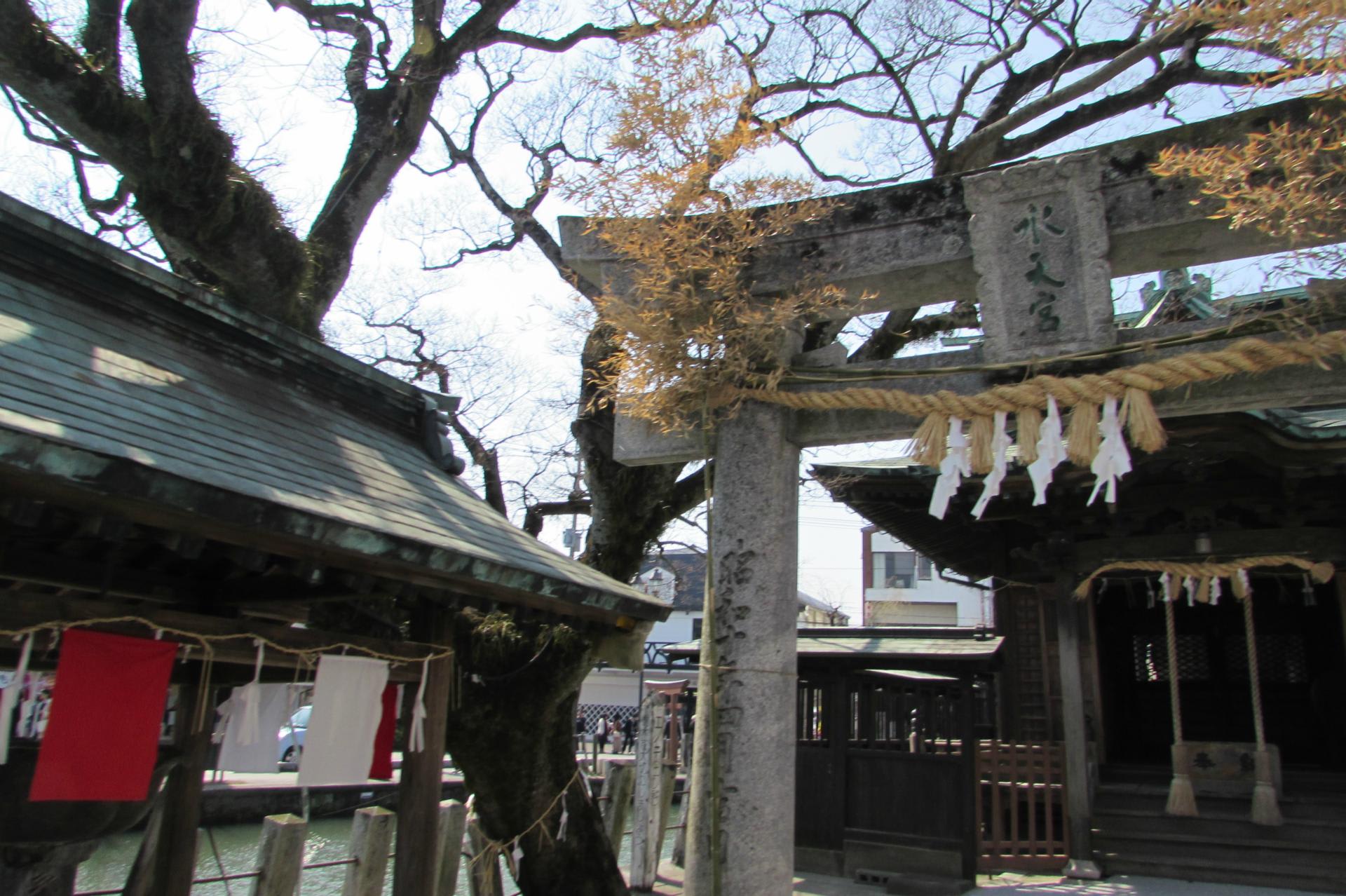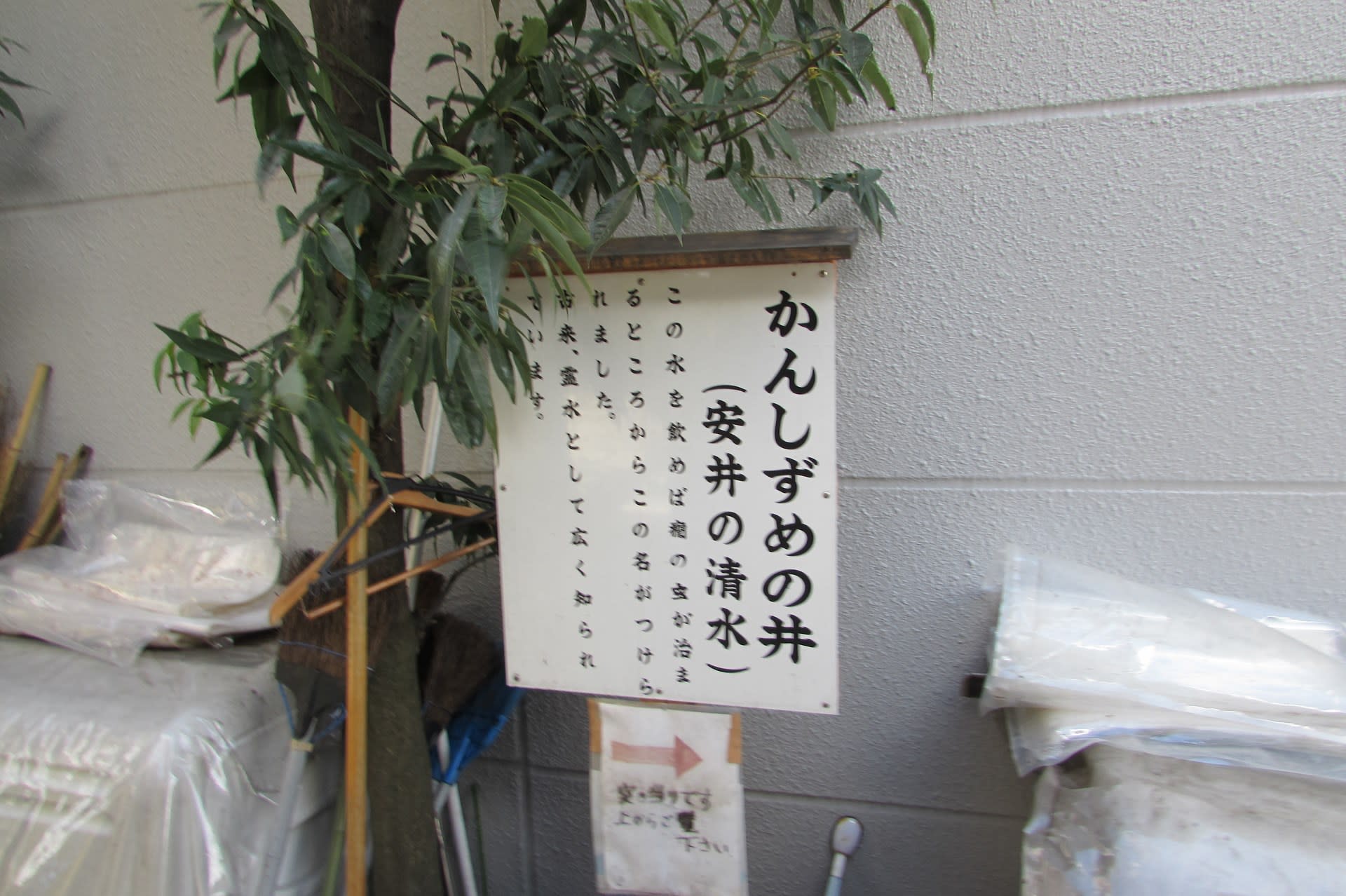2017年3月20日、阪急交通社の【往復新幹線利用】霧島・知覧・鹿児島3日間 南九州スペシャルでの3月19日から21日の2泊3日の旅行をしました。交通費、宿泊込みで一人3万円です。
知覧の武家屋敷群の散策の後、指宿の砂風呂体験のオプションがありましたが、こちらの西大山駅に来ました。1日に8本しかこない列車にも巡り合えました。
駅前には売店があり、西大山駅に到着しましたという証明書を有料で発行しています。
map
黄色いポスト、幸せを運ぶとか










指宿フェニックスホテル

こちらでオプション参加の方が砂風呂体験しました。ホテルの前に大きなアコウの樹があります。樹齢200年です。


知覧の武家屋敷群の散策の後、指宿の砂風呂体験のオプションがありましたが、こちらの西大山駅に来ました。1日に8本しかこない列車にも巡り合えました。
駅前には売店があり、西大山駅に到着しましたという証明書を有料で発行しています。
map
黄色いポスト、幸せを運ぶとか










指宿フェニックスホテル

こちらでオプション参加の方が砂風呂体験しました。ホテルの前に大きなアコウの樹があります。樹齢200年です。