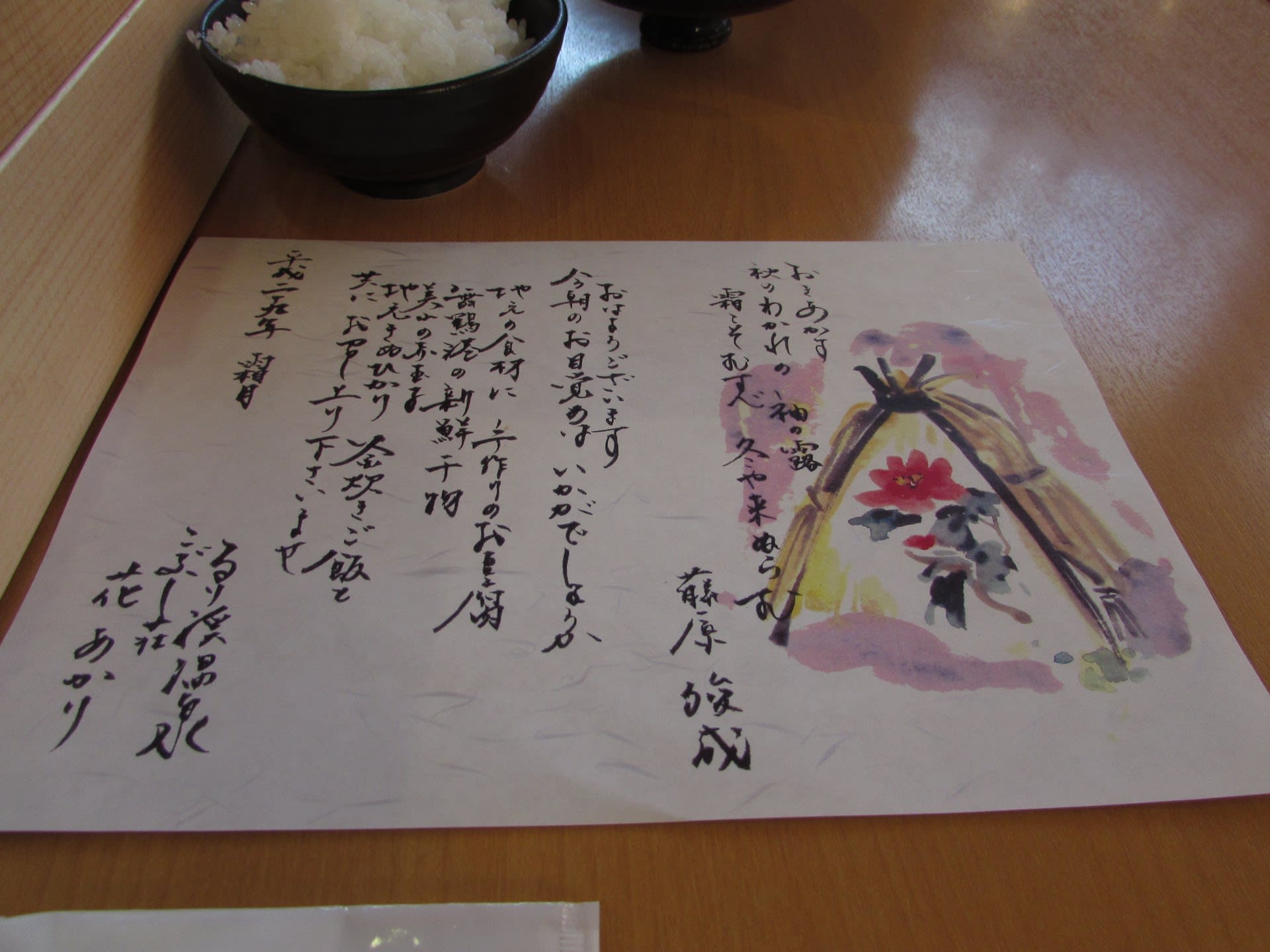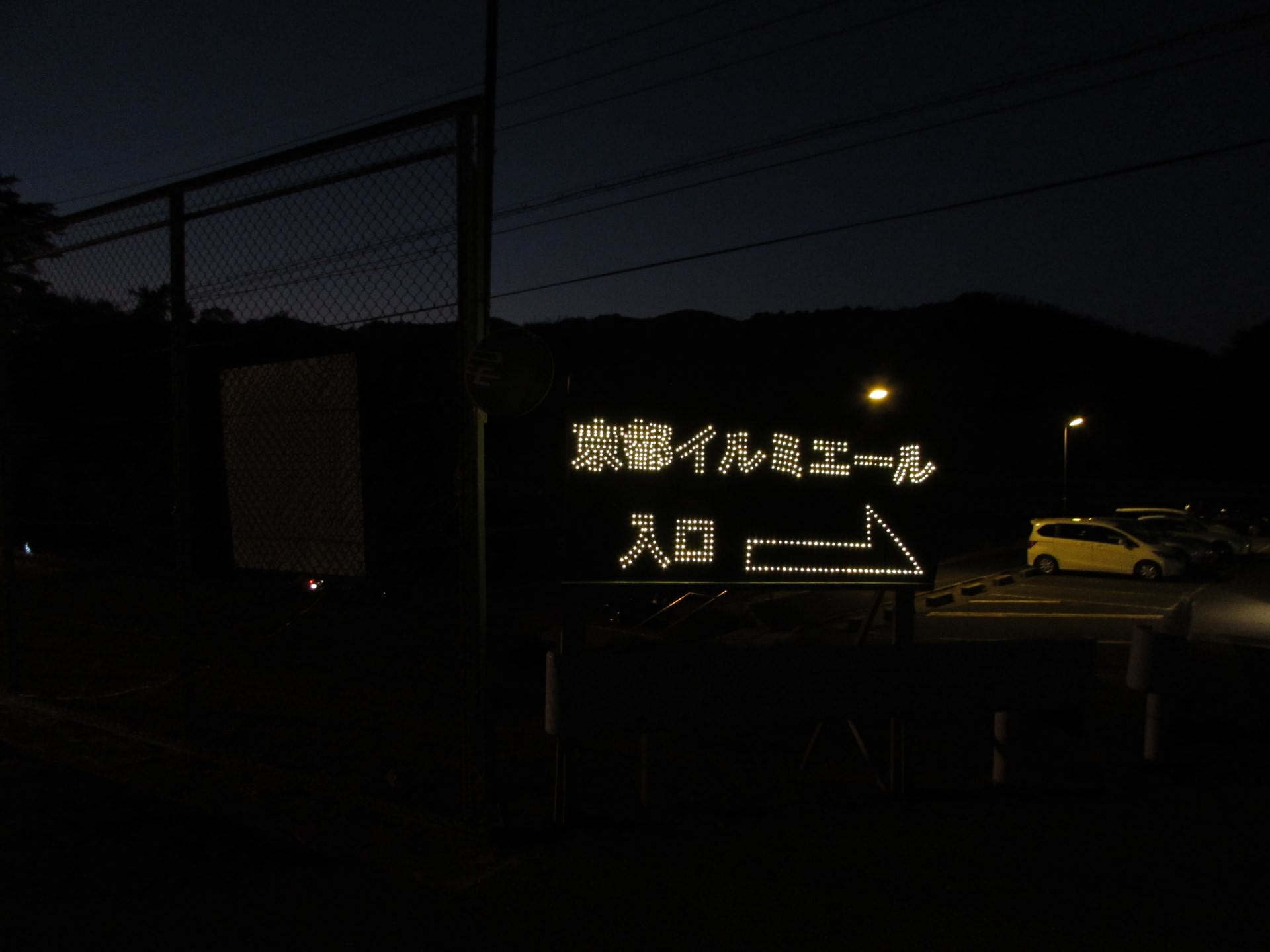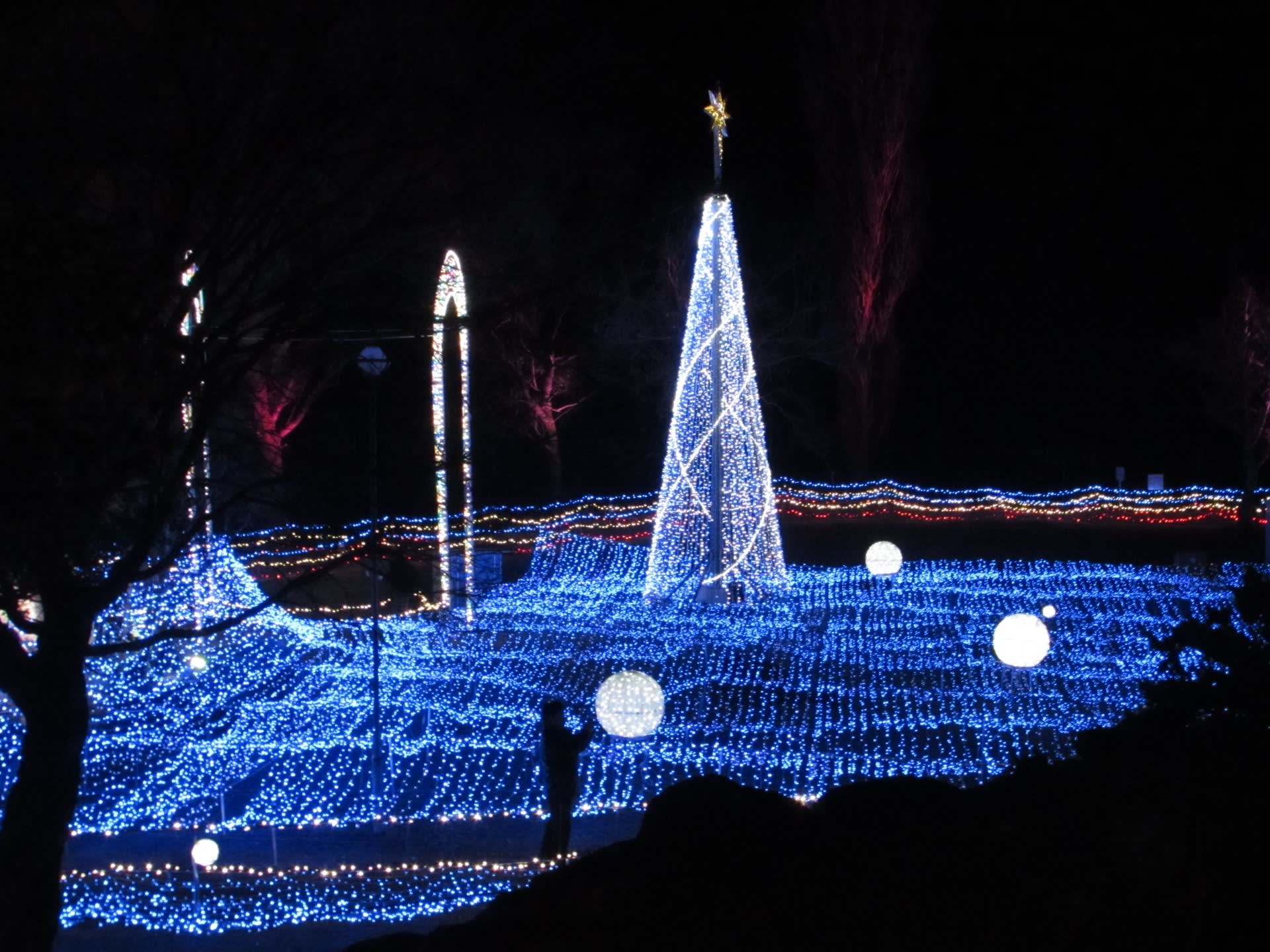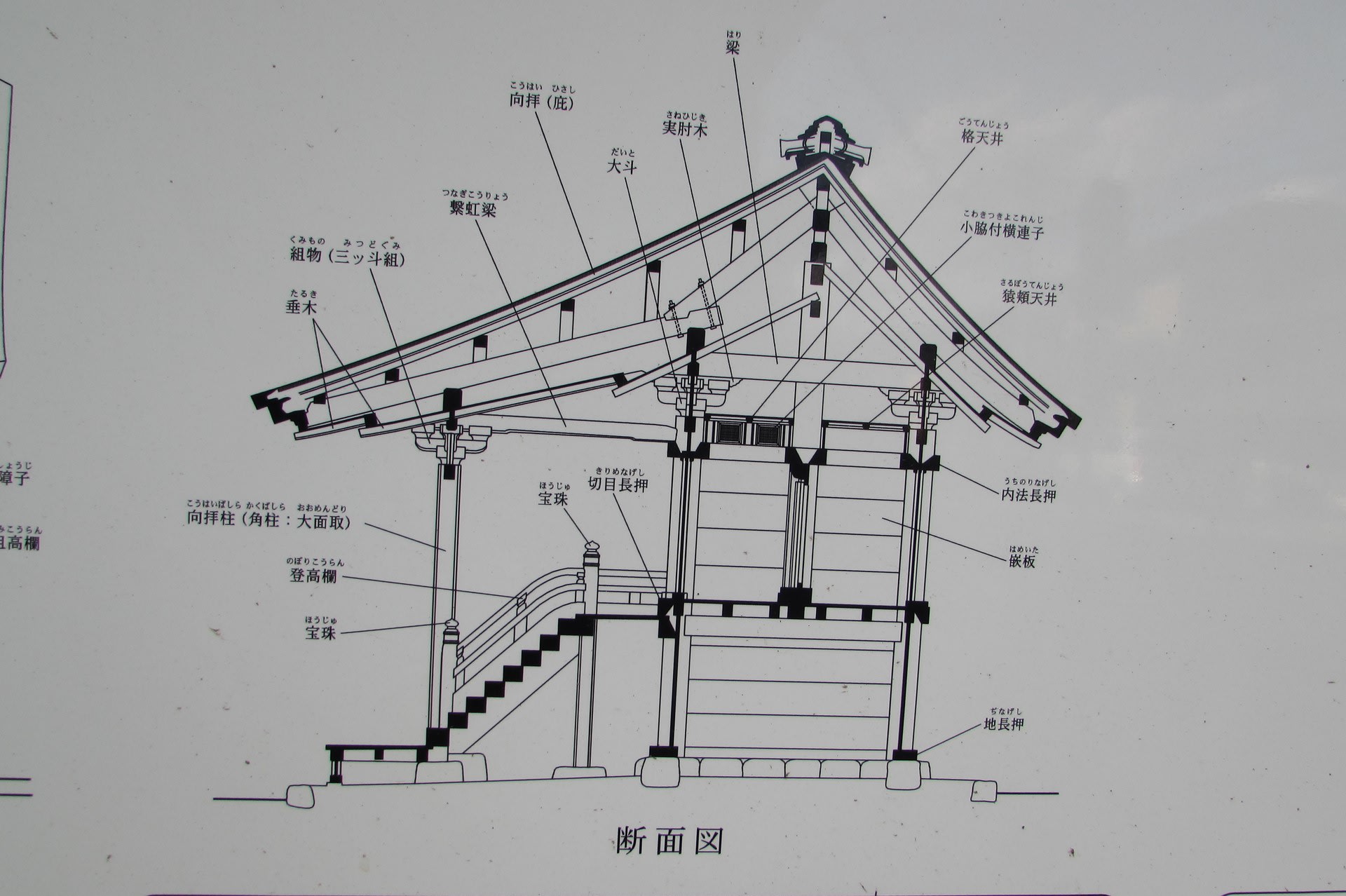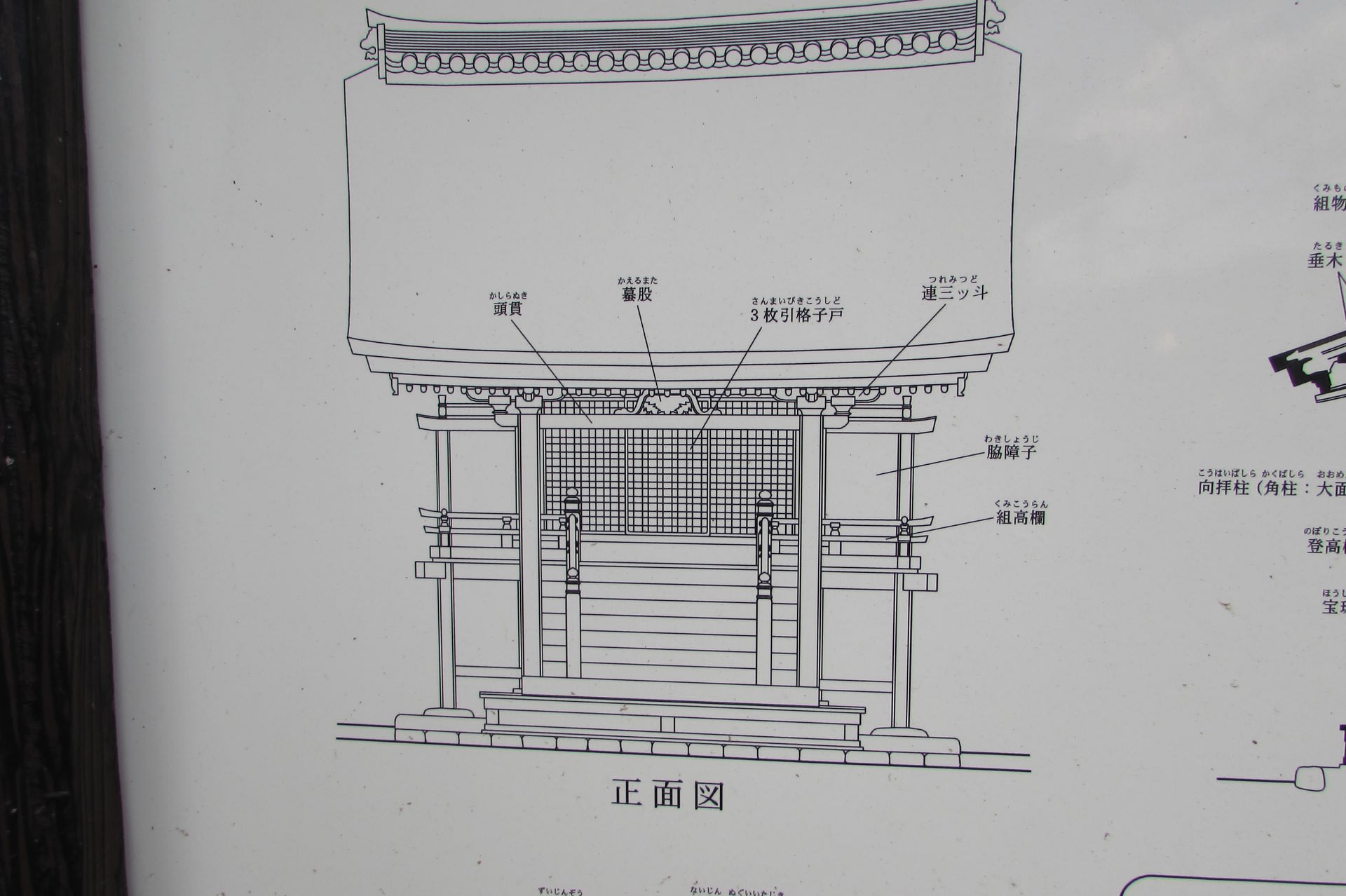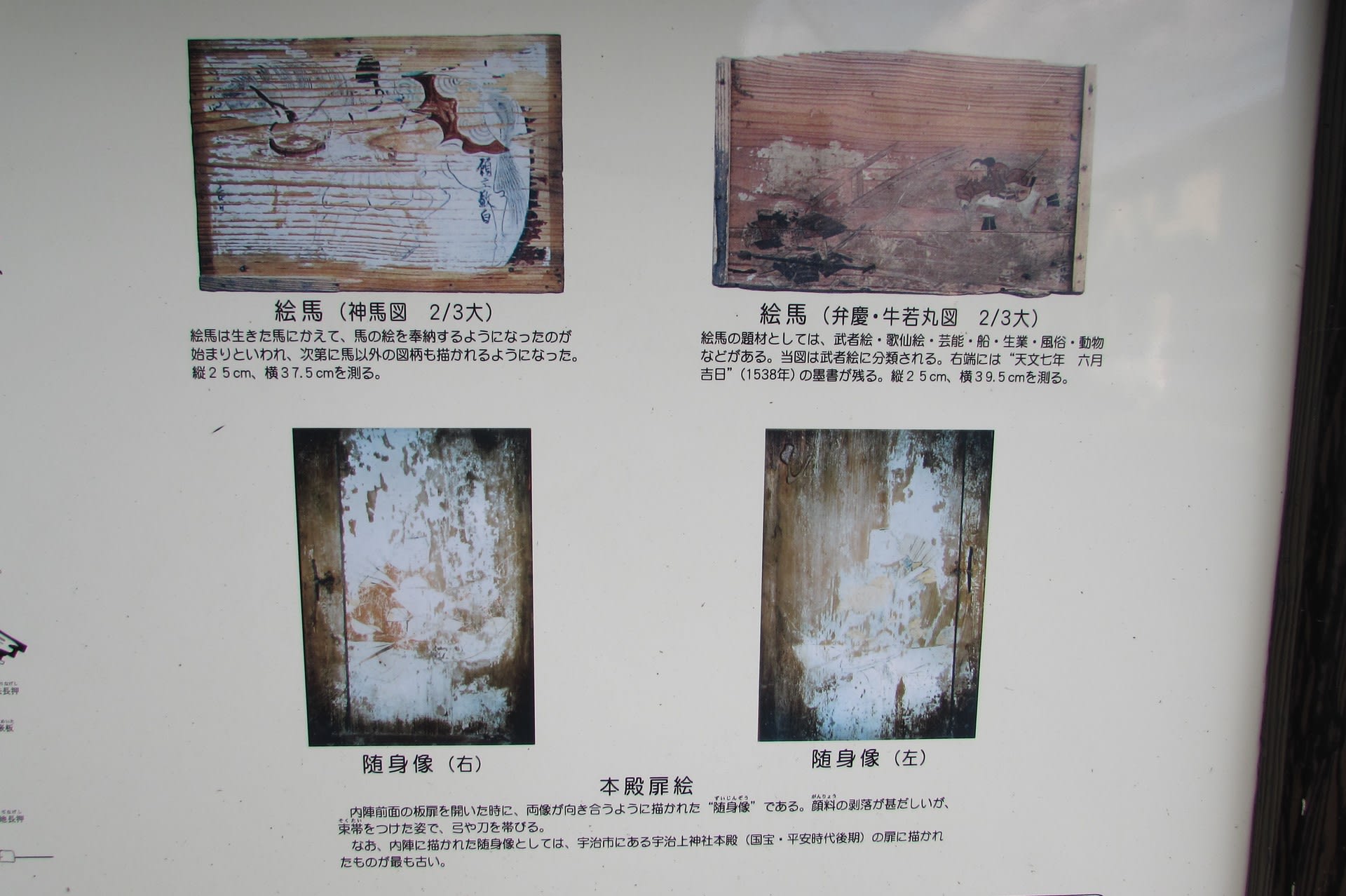2017年11月28日、散策しました。前日にるり渓温泉に宿泊し、送迎バスで渓谷の入り口まで行き、そこから約1時間の散策でした。
るり渓谷は、京都府南丹市園部町大河内に位置し、大堰川支流、園部川が流れる全長4kmの渓谷で、国の名勝に指定されています。
map
るり渓谷散策マップ



















[快刀厳]大きな岩の真ん中を、刀でスパッと割るように松の木が生えている。



[巨盆岩]お盆のような平らな大岩



[螮蝀泉]滝の水しぶきによって美しい虹ができる泉




[龍軻潭]龍が歌を歌っている深い淵



[渇虯澗]龍の水飲み場


[双龍淵]雌雄の龍が水中に泳いでいる深い淵

[沈虎潭]虎のように見える大きな岩がある淵

[玉走盤]岩の上を流れる水が、まるで盤上を転がる玉のよう


[高臥石]寝床のような平らな岩


[弾琴泉]広いせせらぎにいたるところに突き出た石が、たくさんの小さな滝をつくり、さながら琴を弾いているような様子


[玉裳灘]静かな浅瀬

[水晶簾]滝のおちる様子が、まるで水晶のすだれがかかっているような様子

[宝亀厳]亀のような形をした岩



[碁顚石]碁盤のような正方形な姿をした石


[千幻瀑]大きな岩を流れる飛瀑で、階段状になった岩である

るり渓谷は、京都府南丹市園部町大河内に位置し、大堰川支流、園部川が流れる全長4kmの渓谷で、国の名勝に指定されています。
map
るり渓谷散策マップ



















[快刀厳]大きな岩の真ん中を、刀でスパッと割るように松の木が生えている。



[巨盆岩]お盆のような平らな大岩



[螮蝀泉]滝の水しぶきによって美しい虹ができる泉




[龍軻潭]龍が歌を歌っている深い淵



[渇虯澗]龍の水飲み場


[双龍淵]雌雄の龍が水中に泳いでいる深い淵

[沈虎潭]虎のように見える大きな岩がある淵

[玉走盤]岩の上を流れる水が、まるで盤上を転がる玉のよう


[高臥石]寝床のような平らな岩


[弾琴泉]広いせせらぎにいたるところに突き出た石が、たくさんの小さな滝をつくり、さながら琴を弾いているような様子


[玉裳灘]静かな浅瀬

[水晶簾]滝のおちる様子が、まるで水晶のすだれがかかっているような様子

[宝亀厳]亀のような形をした岩



[碁顚石]碁盤のような正方形な姿をした石


[千幻瀑]大きな岩を流れる飛瀑で、階段状になった岩である