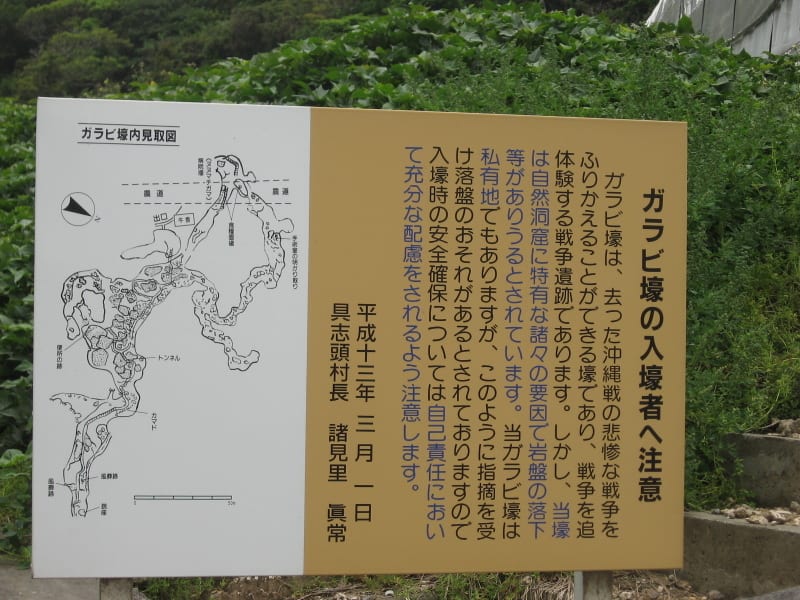2007.3.14(水)快晴
8:00 起床
9:00 北郷温泉丸新荘発~都井岬~えびの高原~
17:00 えびの高原荘着
佐多岬に行けなかったので、せめて都井岬に行ってみようと思い南に向かう。南国らしい海岸が続き、飽きない風景だ。都井岬には野生の馬が居ると聞く。本当に居るのだろうか、居たとして見る事が出来るのだろうか。心配ご無用、あちこちに草をはむ馬が居る。
北海道のどさんこの様なずんぐりとした馬たちだ。約90頭が放牧され野生の形で生息しているという。一体何のために放牧したのか、観光の為なのだろうか。とにかくあちらこちら、意外なところまで糞が落ちており、出没しているんのだろう。


都井岬に至る海岸と野生の馬
白蛇が居るというので、細い山道を辿ってゆくと神社があり、神妙にお祭りしてある。
もともと白蛇伝説のあるところに現れたと言うから、何ともありがたいことだ。岩国や東北で見たものと同様、社のような所でじっとしているが、ここは写真に撮れないのでお見せできない。
岬の近くに御岬神社があり、岩壁の凄いところに社がある。周りはソテツの群生で、自生としては北限ということである。このあたりにも馬の糞が落ちていて、どこにでも居るのだなあと感心する。都井岬灯台は有料なので、写真だけ撮って引き返す。


左:白蛇様神社 中:御岬神社とソテツの群生 右:都井岬灯台
帰り道には猿の軍団が現れ、車で来て良かったと思う。自転車だとちょっとやばい。
都井岬から北上し、都城、霧島を通過し、えびの高原に行く。自転車だと2日がかりの行程を数時間でこなす。文明の利器とは素晴らしい。えびの高原には鹿が多く住んでいる。雄の雉も現れ、今日は野生動物のオンパレードだ。
時間があるので、不動池、大地獄、小地獄など散歩する。かつての火山活動の遺物なのだが、噴煙の止まってしまった地獄はなんとも寂しい。宿の温泉も地下数百メートルから掘り出しているとか、火山の真っ只中としては、らしい温泉ではなかった。

不動池と硫黄山、死んでしまった地獄
走行距離 0Km 累計 7、164Km 経費9,000円
★えびの高原荘の湯 カルシューム、ナトリウム、マグネシューム硫酸塩化物炭酸塩泉
源泉掛け流し 露天風呂、サウナあり。透明で少し臭いがある。お湯の出口に錠剤が設置されており、厳密には源泉掛け流しとは言えないのではないか。立ち寄りは500円