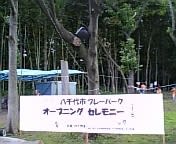自己点検報告書を作成中
ぴったり100ページに収めなければならない
11章あるので、どこかの章で、最後のページが
数行なんてのがあるはずと楽観していたが、すべての章で
最後のページが半分以上埋まっている
こりゃー困った!!
たった1ページのために、全文を読む羽目になりそう
まあーそれだけ完成度の高いものになるからいいか
理香ちゃん、助けてくれー
ぴったり100ページに収めなければならない
11章あるので、どこかの章で、最後のページが
数行なんてのがあるはずと楽観していたが、すべての章で
最後のページが半分以上埋まっている
こりゃー困った!!
たった1ページのために、全文を読む羽目になりそう
まあーそれだけ完成度の高いものになるからいいか
理香ちゃん、助けてくれー