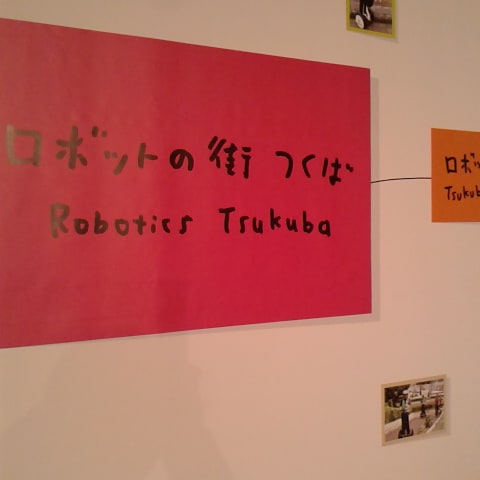「なぜ、日本人は日本人の研究を引用しないのか」
ノーベル賞の波及効果として、日本人の研究評価能力が今問われている。
まずは、日本人の研究をきちんと引用することからするべきであろう。
昔、ある先生がなぜ僕の研究のほうが先なのに外国人のほうを引用して僕のを無視するのだと抗議のメールを回す事件?があった。
事の真偽は不明だが日本人の研究を引用しない傾向はややはなはだしいところがあることは事実である。
心理学会だけではないらしい。なぜか。
・批判的な引用、論争を恐れる
アメリカでは、本当の論争のごと
き形であえて論争を挑んで話題作
りをするようなところがあるそうだ。
それを解説するのが日本人という図式もある。
・どうせその研究も外国にもとがあるはずと思い込む。
事実、そのケースが多い。
・引用の仕方がおかしいと抗議されるのを恐れる
・外国物なら気楽に引用できるし、権威づけになる
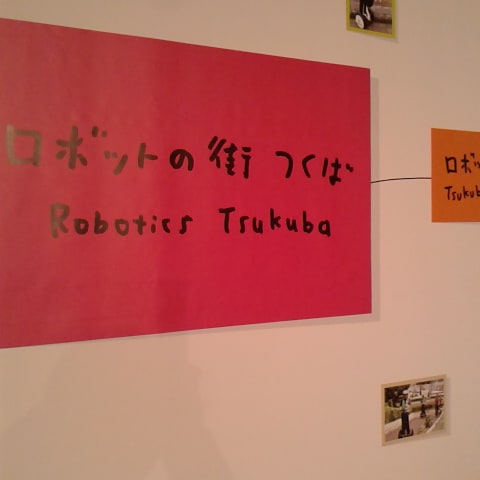
ノーベル賞の波及効果として、日本人の研究評価能力が今問われている。
まずは、日本人の研究をきちんと引用することからするべきであろう。
昔、ある先生がなぜ僕の研究のほうが先なのに外国人のほうを引用して僕のを無視するのだと抗議のメールを回す事件?があった。
事の真偽は不明だが日本人の研究を引用しない傾向はややはなはだしいところがあることは事実である。
心理学会だけではないらしい。なぜか。
・批判的な引用、論争を恐れる
アメリカでは、本当の論争のごと
き形であえて論争を挑んで話題作
りをするようなところがあるそうだ。
それを解説するのが日本人という図式もある。
・どうせその研究も外国にもとがあるはずと思い込む。
事実、そのケースが多い。
・引用の仕方がおかしいと抗議されるのを恐れる
・外国物なら気楽に引用できるし、権威づけになる