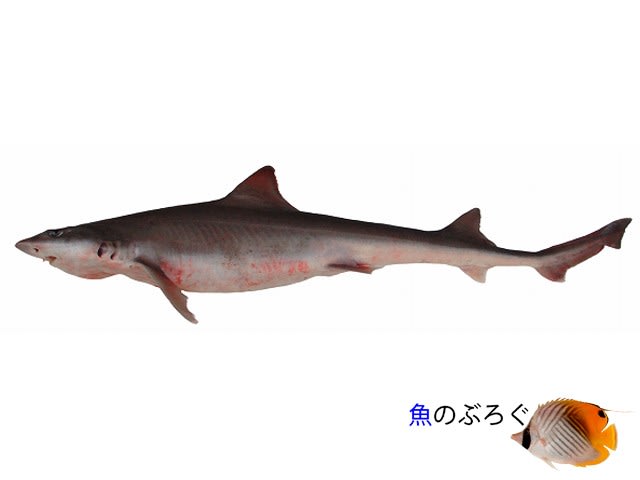今回の喜界島釣行は初日に足を怪我した結果、残念ながらもう「釣りたい」という気持ちもあまりなくなってしまっていた。二日目は船で釣りであったが、ほかの方はオジサンやらマルクチヒメジやらなんやら、色々釣っていたのだが私に釣れたのはアカハタ1匹のみ。しかも掌より少し大きいサイズで食べるには小さすぎる。

水深10数mもあるのだがとても海がきれいなので底の方までよく見える。

船釣りのあと港に戻って小物釣りをしてようやく紹介できる魚が釣れた。クロソラスズメダイ。
喜界島の海では魚がたくさん釣れるが、どのポイントでも同じ魚が釣れるわけではない。このクロソラスズメダイは港付近で釣ったのだがほかの場所では見たことがないのだ。しかしこの個体を採集した場所では多く見られるらしく、2010年にはじめて喜界島を訪れたときにも本種を見ている。WEB魚図鑑に登録された個体も、採集場所が明記されたものではほとんど同じ場所で釣れている。

クロソラスズメダイは体が真っ黒であまり特徴がないように見える。この属の魚の成魚は派手な模様、あるいは目立つ模様がなく、多くの場合一様に茶褐色であるので、ほかの種と見分けにくい。クロソラスズメダイの背鰭棘数は12である。これにより背鰭棘数がふつう13のアイスズメダイやフチドリスズメダイとは区別することができる。

背鰭の基底後端に小さな黒色斑があるのも特徴的である。これがあることにより同じ背鰭棘数が12のグループであるヨロンスズメダイや、セダカスズメダイ(ただし、たまに背鰭13棘のものがいるよう)と区別することができる。そしてこの黒色斑の前縁付近には明瞭な白色斑がないことでキオビスズメダイとも区別することができる。なお、本種は婚姻色を出すことがある。それは体の中央に幅広い白色帯が出ることと、眼の下付近に青白い縦線が出るというものである。

普段は地味ではあるのだが、黒い体に青く輝く斑があるのでよく観察するときれい。スズメダイの仲間の成魚は黒っぽくなっても、こういう綺麗さを見つけ出すという楽しみがあるのだが、写真だけでは種の同定さえ難しいものも多い。
食性は主に糸状藻類を食するが、その糸状藻類の生えている場所を縄張りとしてほかの魚を追い払い、大きく育ったら食べるという習性を有することで知られている。ただしもちろん、このような藻類だけを捕食しているわけではなく、この個体はオキアミで釣れたものである。結構何でも食うらしい。

このクロソラスズメダイが釣れた港でもミドリイシを多数みることができる。高水温や低水温、あるいは津波などで砂をかぶるなどしてサンゴが部分的に白化してしまうこともあるのだが、そのようなところに海藻が生え、それがクロソラスズメダイの好物となる。分布域はインド—太平洋域。紅海・東アフリカ~マルケサス(マルキーズ)諸島とかなり広い範囲に及ぶが、ハワイ諸島やイースター島には産しない。日本では和歌山県および長崎県以南にすむというが、ふつうに見られるのは奄美諸島以南であろう。サンゴ礁域に生息しているが、水深12m以浅、それもきわめて浅い場所に多くあまりダイビングでは見難いようだ。