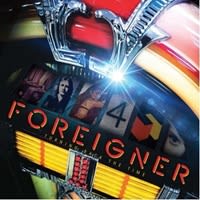以前、僕の携帯に特殊詐欺の電話がかかってきた一件は、当ブログでもネタにしたが、最近、またかかってきたので、皆さんに報告します(笑)
今回は、もちろんというか何というか、かけてきたのは前の時とは違う人だった(笑) もっと若いかな。今回は、警視庁の者と名乗って、宮崎県警から照会があったので○○さん(僕の本名)に確認の電話をさせて頂きました、と話を切り出した。で、詳しくは言わないけど、僕が犯罪に関与してる可能性がある、ついては宮崎県警に今すぐ来れるか、と言うので、「無理です」と答えると、「あなたは犯罪に関与している可能性があります。それでも来ないのですか。ならば、詳細を説明しますが、時間はありますか?」と畳みかけてくる。で、僕は「今ちょっと忙しいです。1分くらいで済みますか?」と聞いたら「1分では無理です。ならば、あとで都合良い時間に連絡します。何時ならいいですか?」と言うので、「じゃ、5時頃なら」と返すと、相手は何も言わずに電話を切った。失礼な奴だ(笑) もちろん、5時になっても電話はかかってこなかった(爆)
2回目だと、少し落ち着いて対応出来たかな(爆)
閑話休題。
唐突だが、最近買ったCDから。

最近、とある事がきっかけでポコを聴いてみようと思い立ち、色々調べたのだが、意外とポコって入手が難しい。超メジャー或いは超マイナーなら比較的簡単に入手できるけど、中間のそこそこメジャー、というクラスが実は最も入手が難しい、というのを当ブログでも何度も書いているが、ポコもそれに当てはまるようだ。が、そんな矢先、ソニーの「発掘!洋楽隠れ名盤 Hidden Gems in 60/70s」という再発企画の中に、ポコの『グッド・フィーリン』を見つけたので、喜び勇んでポチッとしたのであった(笑) ソニーさん、ありがとうございます。2弾3弾企画もお待ちしてます(笑)
ここで一応、このブログを見て下さっている若い人たちの為に、ポコについて簡単に説明させて頂く。ポコはアメリカのバンドで、1969年デビュー。結成時のメンバーは、リッチー・フューレイ(元バッファロー・スプリングフィールド)、ジム・メッシーナ(後に、ケニー・ロギンスとロギンス&メッシーナを結成)、ランディ・マイズナー(ご存知、後にイーグルスに加入)、ラスティ・ヤング、ジョージ・グランサム、の5人。デビュー・アルバム『Pickin' Up The Pieces』をレコーディング後ランディ・マイズナーが脱退、後任としてティモシー・B・シユミットが加入。その後、ジム・メッシーナ脱退→ポール・コットン加入を経ての通算5作目が、この『グッド・フィーリン』である。
『グッド・フィーリン』の後、もう一枚アルバム作ってリッチー・フューレイが脱退、ポコはラスティ・ヤング、ポール・コットン、ジョージ・グランサム、ティモシー・B・シュミットの4人で活動を続けて、『シマロンの薔薇』『インディアン・サマー』といったアルバムを発表するが、1977年にティモシー・B・シュミットがイーグルスに加入する事になり(脱退したランディ・マイズナーの後任。歴史は繰り返す)、バンドの存続が危ぶまれたものの、ポール・コットンとラスティ・ヤングを中心に1978年に『伝説』を発表、これがポコ最大のヒットとなった。実は僕も今まで『伝説』しか聴いた事なかった^^; が、この『伝説』名盤である。
その後解散状態になるが、1989年に再結成アルバム『Legacy』を発表、以後現在に至るまで活動を続けているが、2021年にラスティ・ヤングが亡くなって、現メンバーでオリジナル・メンバーどころか、かつての主要メンバーもいなくなってしまった。
という訳で、前説が長くなってしまったが(笑)、ようやく『グッド・フィーリン』である。前述した通り、ポコの通算5作目で1972年発表。もちろん僕は知らなかったけど、この時期ポコは非常にビミョーな状況にあったようで、中心人物のリッチー・フューレイからすると、ポコが今一つメジャーになり切れない間に、かつての仲間たち、すなわち、スティーブン・スティルス、ニール・ヤング、ランディ・マイズナー、ジム・メッシーナあたりは成功を収め、大きく水を開けられてしまったという訳で、かなり焦っていたのでは、という話だ。で、その局面を打開すべく、気合入れてこの『グッド・フィーリン』を作ったものの、思ったほど売れず、フューレイは非常にショックを受け、次作『Crazy Eyes』を最後に脱退してしまう訳だ。やはり、かなりの自信作だったのだろう。結果が出ないとショック大きいよな。
ただ、初めて聴いてみた『グッド・フィーリン』だけど、実に良いアルバムと思う。ポコをカントリー・ロックとかウエスト・コーストとかに分類していいのかどうか、よく分からんけど、本作で聴ける音は正しくアメリカン・ロックである。個人的には、こういう感じ好きだな。ロックンロール風だったりカントリー風だったりブルース風だったり、そんなアーシーな雰囲気の曲たちが交互に登場して、またそれぞれ曲の出来も良いし、実に楽しめるアルバムだ。洗練というより、ややいなたさを感じさせる演奏もいいと思う。ラストの「スイート・ラビン」は、イントロがパイプ・オルガンの讃美歌風で、当時のファンにはあまり評判良くなかったらしいが、これはこれで良いんじゃないのと思うけどね。
ただ、例のランディ・マイズナーとティモシー・B・シュミットのいきさつもあって、良くない事とは思いつつ、ついイーグルスと比較してしまうのだが、そうなると、やはりキャッチーさに欠ける気がする。ポコがイーグルスと比べて作曲能力が劣っているなんて事は全然ないのだが、アルバムとして聴くと、やはり曲ごとの印象度が弱い感じがするのだ。フックが効いてないというか、ここでちょっとサビがあれば印象違うのに、なんて思ったりもして。こうしてみると、グレン・フライとドン・ヘンリーのコンビって、実は凄かったんだな、と思ってしまう。ほんと、ちょっとした事ではないのかという気がするけど、そのちよっとした事が明暗を分けてる感もある。惜しいなぁ。
とはいうものの、良いアルバムなのは確かだと思う。何度も言ってるけど、曲も良いし。個人的には、「ライド・ザ・カントリー」「キーパー・オブ・ザ・ファイア」「アーリー・タイムス」「リストレイン」あたりが好きだな。一度聴いてのインパクトは少々弱いかもしれないが、聴けば聴くほど良さがにじみ出てくるアルバムではなかろうか。ハーモニーも良いしね。
ポコについては、次は、ラスティ・ヤング、ポール・コットン、ティモシー・B・シュミット、ジョージ・グランサムの4人で活動してた時期のアルバムを聴いてみたい。聞く話によると、この時期は、作品の質が安定していて、佳作が多いそうな。入手困難ではあるけれど(笑)