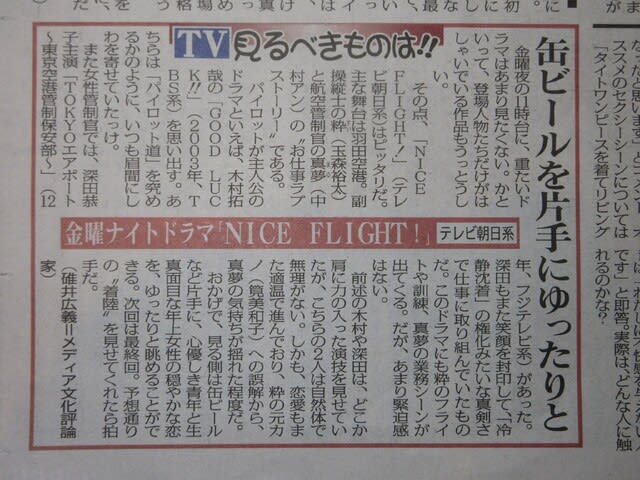『ワルイコあつまれ』がトライした、
異色の「原爆特集」
8月のテレビを振り返ってみると、例年通り、戦争をめぐる特集番組がたくさん流れました。
その中に、強く印象に残ったものがあります。
77年前、広島に原爆が投下された8月6日。NHKは「原爆特集」を2本放送しました。
1本はNHKスペシャル『原爆が奪った“未来”~中学生8千人・生と死の記録~』です。
あの日、広島市の中心部で、空襲の延焼を防ぐための「建物疎開」に動員されていた、たくさんの中学1年生が犠牲となりました。
番組では、学校や遺族の元に遺されていた「死没者名簿」や「被災記録」を独自に収集。
それらを分析することで、生徒たちがどこで被爆し、どのように亡くなったのかを初めて可視化したのです。
画面上で点滅する1つの光が、1人ひとりの生徒たちです。
何が起きるのかも知らずに作業場へと向かう、8000個の光を止めたくなりました。
異色の「原爆特集」
6日に放送された2本目は、Eテレ『ワルイコあつまれ』でした。
これが、異色の「原爆特集」だったのです。
『ワルイコあつまれ』は、稲垣吾郎さん、草彅剛さん、香取慎吾さんによる「教育バラエティー番組」。
普段は「慎吾ママの部屋」など楽しいコーナーが並んでいます。
しかし、この日は、番組の半分に当たる15分間を使って、「子ども記者会見」という場を設けていました。
広島で原爆を体験した竹本秀雄さんに、子ども記者たちが質問したのです。
会見の司会を稲垣さんが務め、記者席には「しんごちん記者」として香取さんの姿がありました。
原爆の記録映画に使われていた、1枚の写真。
頭に包帯を巻いた幼い男の子と、その子を背負って歩く少年の姿が写っています。
今年6月、竹本さんは「包帯の子」が当時3歳の自分だと名乗り出たのです。背負ってくれたのは、お兄さんでした。
そのお兄さんからは、「お前を助けた」とか「原爆でこうだった」といった話は、ひと言も聞いていないそうです。
子ども記者が「覚えていることは?」と訊くと、「橋が燃えていたこと、そして横たわった女の人が水をくださいと言ったこと」。
そして「戦争についてどう思いますか」という質問には、「犠牲になるのは一般の人や子ども。頭を冷やして話し合いで解決できないかと思う」と答えていました。
時に涙を流しそうになりながら、自らの経験を語る竹本さん。
子ども記者たちも真剣に聞いていましたが、この番組を見た子どもたちも多くのことを感じ取ったのではないでしょうか。
制作者と出演者の意欲があれば、バラエティー番組ならではの手法で、こうしたトライができることを示す好企画でした。