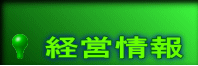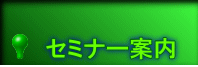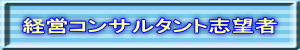■■【経営コンサルタントのトンボの目】 無駄遣いと後悔の法則<o:p></o:p>
経営コンサルタント事務所
B・M・S・21代表 山本 修 先生
日本経営士協会 理事 関西支部長
<o:p></o:p> 山本先生は、美容サロンを独立開業され、その経験を元にサロン経営者に「商品管理」「顧客管理」「計数管理」を提案し、サロン経営の生産性向上に成果を上げてこられました。近年は中小企業のコンサルタントとしてもご活躍中です。
<o:p></o:p> また「日本経営士協会 関西支部長」として活躍されておられます。
<o:p></o:p> ※筆者詳細情報→ http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/0060.htm
<o:p> 今年は、ほぼ60年に一度行われる出雲大社の遷宮(5月10日)や、20年毎の伊勢神宮の式年遷宮(10月)等が行われる節目の年であるが、神話に根ざしたもう一つの神事が、5月8日に皇室の三種の神器「草薙の剣」(くさなぎのつるぎ)を祭る熱田神宮(名古屋市熱田区)で営まれた。
</o:p>
<o:p> 景行天皇43(113)年、九州や東国を平定した「ヤマトタケルノミコト」の「草薙の剣」が、熱田神宮に祭られて1900年の大祭である。大和政権による列島統治を示すヤマトタケル伝説は、各地に伝承や地名が残り、今でも篤く信仰されている。
</o:p>
<o:p> この件につき産経新聞の記事を頼りに調べてみた。
</o:p>
<o:p>■ ヤマトタケルを守った草薙の剣
</o:p>
<o:p> 「ヤマタノオロチを退治したスサノオノミコトは、オロチの尾から一本の剣を見つけ出し、天上の神、天照大御神に献上した」と、草薙の剣について古事記や日本書紀にはこの様に記している。オロチには常に雲がかかっていたことから「天の叢雲の剣」(あめのむらくものつるぎ)と呼ばれたという。
</o:p>
<o:p> 天上の神々が地上世界の日向(九州)へ降る「天孫降臨」の際には、勾玉と鏡とともに草薙の剣がもたらされ、三種の神器となったという。現在では、勾玉は皇居、鏡は伊勢神宮の内宮、草薙の剣は熱田神宮に祭られていると言われる。
</o:p>
<o:p> 天孫降臨を経て初代・神武天皇の東遷で大和に都が築かれると、12代景行天皇の子、ヤマトタケルは熊襲(南九州)や出雲、東国に遠征したのである。東国へ赴く際に、叔母のヤマトヒメから受け取ったのが草薙の剣であった。
</o:p>
<o:p> 相模の国(日本書紀では駿河国)では、豪族に騙されて原野に火を放たれたが、剣で草を薙ぎ倒して火を振り払った為、「草薙の剣」と呼ばれるようになった。また、ヤマトタケルが豪族の領地を焼き尽くした地は「焼津」(静岡県焼津市)となったのである。
</o:p>
<o:p> ヤマトタケルはさらに東へ進んだが、荒れる海に悩まされその窮地を救うために妻のオトタチバナヒメが海に身を投げた。「ああ吾が妻よ」とヤマトタケルが3度嘆いたことから、東国のことを「吾妻=東(あづま)」。更に「君さらず袖しが浦に立つ波のその面影を見るぞ悲しき」と詠んだ場所が「君さらず=木更津」(千葉県)になったと言われているなど、ゆかりの地が多くある。
</o:p>
<o:p>■ 熱田神宮のはじまり
</o:p>
<o:p> 東国平定を果たして、手元に残った草薙の剣を熱田の地に祭ったのが、熱田神宮の始まりとされている。飛鳥時代の668年に盗まれそうになったために、一時宮中に移されたが、686年に熱田の地に戻され、その後は同神宮で祭られている。
</o:p>
<o:p> 熱田神宮とヤマトタケルの結び付きは深く、神宮の約500メートル西方にある白鳥古墳(全長70メートルの前方後円墳)は、ヤマトタケルを葬ったとの伝承があり、熱田神宮は毎年ヤマトタケルの命日と言われる5月8日に「御陵墓祭」を行っている。
</o:p>
<o:p> 列島平定に力を尽くしたヤマトタケルは古墳時代の大和王権が国の基礎を築いた足跡をも示す。今回の「1900年大祭」もこの5月8日に行われた。
</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> 神話の舞台は今も地名として残り、私たちの先祖からの生活や習慣、伝統や文化が大切に受け継がれている。神話には生活に欠かせない教えが込められており、今後も子孫に伝えてゆきたいものである。
</o:p>■■ 経営コンサルタントの独り言 ←クリック<o:p></o:p>
経営コンサルタントの視点から、経営や人生のヒントになりそうなことやブログの中から選りすぐった文章を掲載しています。<o:p></o:p>
それを実現するには、簡単に、短期間に出版できる方法があります。<o:p></o:p>






![]() 毎日複数本発信
毎日複数本発信 ![]()

















 経営コンサルタント歴35年の経験から、
経営コンサルタント歴35年の経験から、