演目や体格で使い分けます
またひとつ、帯止(おびと)が完成しました。
帯止はむかし、帯籐(おびとう)と言ったそうです。
現在でも枕の下の U 字の部分が籐で出来ているからなのですが、現在では「帯止」といいます。
衣裳方にとって、帯止は羽根を作るための小道具です。
演目や体格で帯止の大きさを決めます。
踊りやお芝居の早変わりなどによく使われる作り帯は、身体を巻く部分と羽根の部分が分かれています。
ですからあらかじめ羽根の部分を作っておいて、本番では身体に巻く帯だけを決めて、羽根の部分は後ろから差し込めばいいわけです。
時間短縮と出来上がりは帯止の方がきれいです。
私の作る帯止の U 字の部分はプラスティック製になっています。ですから帯籐(帯止)ではなく、帯プラかもわかりません。

 ●
● ●
●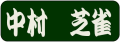 ●
●
 ●
●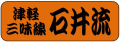 ●
● ●
●
 ●
● ●
●
最新の画像[もっと見る]
-
 山門奎州一門が、「山門流奎州瓠(ひさご)の会」。
4日前
山門奎州一門が、「山門流奎州瓠(ひさご)の会」。
4日前
-
 山門奎州一門が、「山門流奎州瓠(ひさご)の会」。
4日前
山門奎州一門が、「山門流奎州瓠(ひさご)の会」。
4日前
-
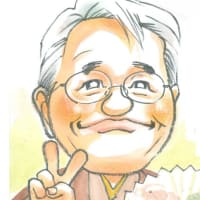 1月28日(火)に、広島特別講座…アステールプラザで
3週間前
1月28日(火)に、広島特別講座…アステールプラザで
3週間前
-
 1月28日(火)に、広島特別講座…アステールプラザで
3週間前
1月28日(火)に、広島特別講座…アステールプラザで
3週間前
-
 1月28日(火)に、広島特別講座…アステールプラザで
3週間前
1月28日(火)に、広島特別講座…アステールプラザで
3週間前
-
 1月28日(火)に、広島特別講座…アステールプラザで
3週間前
1月28日(火)に、広島特別講座…アステールプラザで
3週間前
-
 1月28日(火)に、広島特別講座…アステールプラザで
3週間前
1月28日(火)に、広島特別講座…アステールプラザで
3週間前
-
 2025年の「日本舞踊着付け専門講座」…広島と福岡で5講座。
3週間前
2025年の「日本舞踊着付け専門講座」…広島と福岡で5講座。
3週間前
-
 創業以来45年…2025年の幕開きです。
2ヶ月前
創業以来45年…2025年の幕開きです。
2ヶ月前
-
 創業以来45年…2025年の幕開きです。
2ヶ月前
創業以来45年…2025年の幕開きです。
2ヶ月前

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます