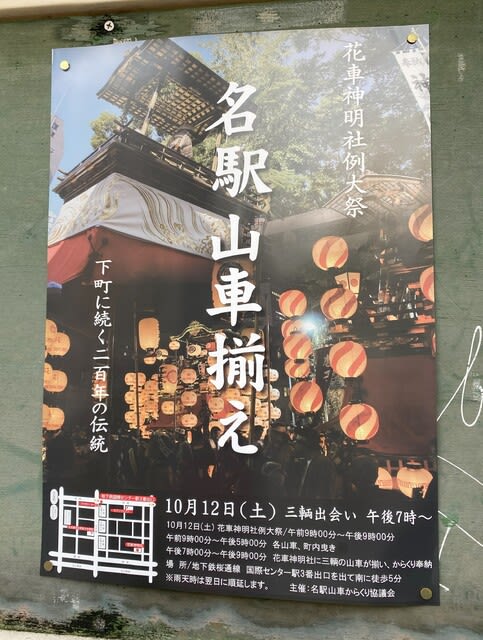今日も高気圧に覆われ、朝から青空が広がっていた。

春のような陽光が降り注ぎ、気温も15度まで上昇し春のような暖かさが続いている。


この暖かさで、荒子梅苑のロウバイが満開を迎えていた。

近づくと、ふくよかで甘い香りを放っている。

紅梅の蕾は、少し赤みを帯びているがまだ固く開花はもう少し先になりそう。

荒子観音寺で2月2日(日)に節分豆まきが行われる。

円空仏彫刻木端の会は、毎年この時期に節分祭準備の手伝いをしている。
会員有志が福豆の箱詰めや、桝詰めの作業をした。
炒り豆の香ばしい匂いが部屋に漂い、節分に先立って福をいっぱい貰った気分になった。