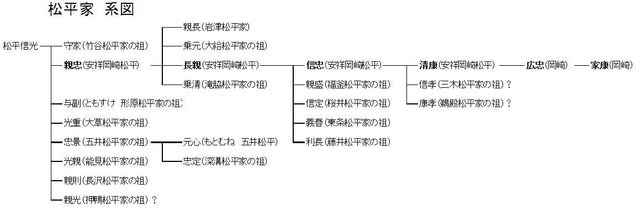浅井西城址を見学したついでに、松平康孝の菩提寺という源空院を訪ねました。

源空院山門
源空院は松平康孝の墓所であるばかりでなく、枝垂れさくらでも有名なようです。

源空院の枝垂れ桜 枝垂れ桜は3月下旬に咲くので、訪れた時はかなり花は散っていて、若葉が出ていました。

松平康孝の墓所であることを表示する石碑

松平康孝の墓(左側)右側は初代住職の一雲の墓です。松平康孝がこの源空院を開いたとき、一雲という高僧を招致したそうです。ちなみに松平康孝の法名は「宝琳院礼翁善忠」というそうです。寺内の案内板に説明してあったので、ようやく松平康孝の墓を見つけることができました。
改めて言うまでもないのですが、昔の武家は、菩提寺をだいたいは持っていることが分かりました。今NHKで放映している井伊氏は龍潭寺、松平太郎左衛門家は高月院、織田家は万松寺等々、セットになっている場合が多いことが分かりました。

源空院山門
源空院は松平康孝の墓所であるばかりでなく、枝垂れさくらでも有名なようです。

源空院の枝垂れ桜 枝垂れ桜は3月下旬に咲くので、訪れた時はかなり花は散っていて、若葉が出ていました。

松平康孝の墓所であることを表示する石碑

松平康孝の墓(左側)右側は初代住職の一雲の墓です。松平康孝がこの源空院を開いたとき、一雲という高僧を招致したそうです。ちなみに松平康孝の法名は「宝琳院礼翁善忠」というそうです。寺内の案内板に説明してあったので、ようやく松平康孝の墓を見つけることができました。
改めて言うまでもないのですが、昔の武家は、菩提寺をだいたいは持っていることが分かりました。今NHKで放映している井伊氏は龍潭寺、松平太郎左衛門家は高月院、織田家は万松寺等々、セットになっている場合が多いことが分かりました。