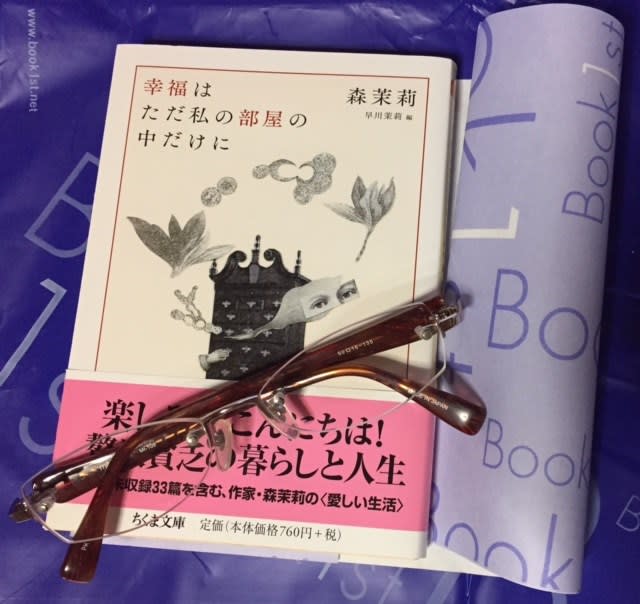外では、つくつく法師が、声を張り上げて鳴いています。行く夏に別れを惜しむかのように。
完全に夏が去ったわけでもないのに、何故だか、不思議な『春』を感じてしまう風。
春みたいな秋の始まり・・・。
昨日、お隣(・・・といっても、100m位は、離れているのだけれど)の奥さんから、新栗をいただいた。
たくさんいただいたので、本日は、栗ご飯にしようかと、6つばかり剥いた。
鬼皮を剥き易いように、一晩浸水しておいたのだった。
残りは、茹で栗にしようか・・・と思ったのだけれど、茹で栗にしても、2~3日では、食べきれないくらいあったので、インターネットで調べてみると、生栗は、鬼皮、渋皮ともに、剥いて、お砂糖をまぶして1時間程経ってから、冷凍すると長持ちする・・・との記載があった。
コレ・・・全部、剥くのも・・・(今日の栗ご飯の分6つ剥いただけでちょっとイヤだったんだけれど)・・・と思ったのだけれど、6つ剥くのに15分くらいだったから、残りは、1時間で、剥けるかもしれない・・・と思い立ち、夕刻から、剥き始めたのだった。
栗の両サイドの鬼皮を剥がすと、栗の表面の鬼皮は、割と簡単に外せる。
ただし、チカラがいるので、特に親指が、痛くなってくる。
親指が痛くなってきたら、今度は、ピーラーに持ちかえて、渋皮を剥ぐ。
やっていると、渋皮の方が、面倒くさい・・・。
チマチマ、鬼皮と渋皮を分けて、剥いていた。
手が疲れたら、お米を研いだり・・・などなど、夕飯の支度をしながら、手を休ませて、また剥き始める。
そのうち、鬼皮をむいたあと、渋皮をむいた方が、包丁を持つ右手の親指の連続使用を阻止できるので、効率が良いことがわかってきた。
こういう仕事は、何も考えずに出来る・・・というより、どうやったら、効率良く出来るのかを考えながら、やっていると面白い。
ピーラーの使い方も慣れてきて、垂直に、スパっと渋皮が剥けたときには、嬉しいのだった。
都合1時間10分。
個数にして、34個。
本日の成果↓ 形がいびつで、渋皮が残っているあたりは、御愛嬌。
手に小傷3箇所。

コレに砂糖をまぶし、砂糖が溶けたら、出来るだけ空気を抜いて、冷凍庫へ・・・。
お正月用の栗きんとんなど、製造しているところは、どうやって剥いてんだろうか???
機械化されているだろうか・・・鬼皮、渋皮剥き機とかあったりで・・・。
人手なんてかけらんないだろうなぁ・・・1時間で、コレだけで、形も悪いから商品にならない。
もしかすると、化学薬品に浸けて、溶かすとか、柔らかくするとか・・・なのかもしれない。
ミカンの缶詰なんかも、塩酸だか、硫酸だか・・・ちょっと忘れたが、薬品に浸けて、皮と筋を溶かすそうで、何やら、恐ろしい気がする。
手仕事の方が、安全だよな・・・なんて、栗剥きをしながら、考える・・・。