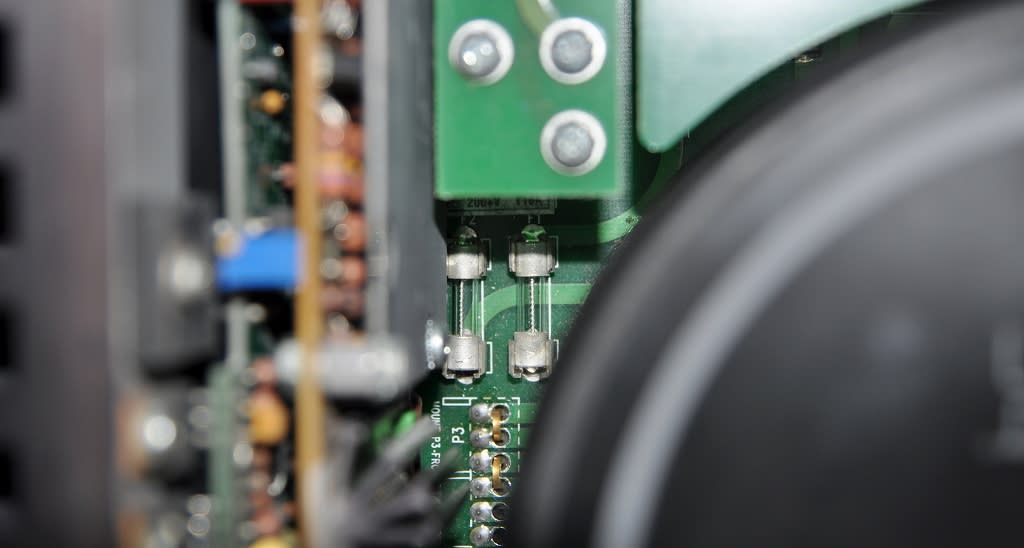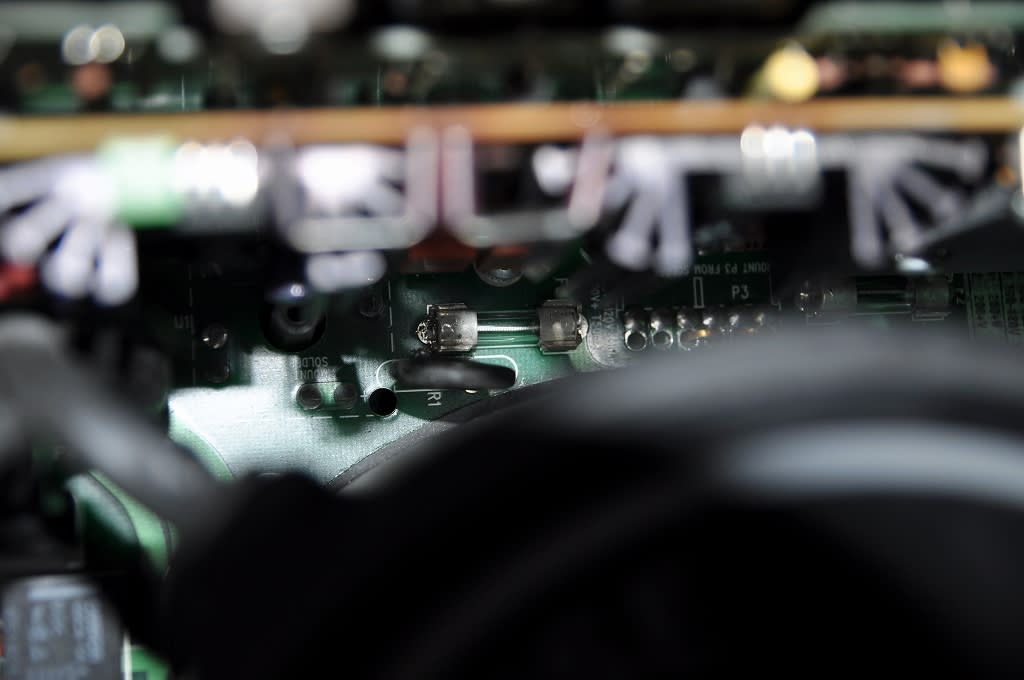「絶対音質」とも関連するのですが、全てのシステムには「オリジナル」なサウンドが有る。「音質向上」を目指すにはいくつかの指標が有る。
1)週波数レンジ・・・使うユニットによって低域・高域のレンジが変わってくるが、30Hz~100KHzくらいがカバーできれば相当優秀なシステムではないかと思う。一般のシステム表示は20Hz~20KHzで有るが、30Hz以下の低音がどんなものか?判っている方は少ないのでは? また、一般的な「音楽」には30Hz以下の低音は少ない。高域は「空気感」等の要素で既成のSPに追加で20KHz以上を出せるユニットを加えるべきだと思う。
2)ダイナミックレンジ・・・如何にぶっといサウンドを出せるか?これもSPユニットやソース機器・電源・ケーブル材のグレードの問題で大きく変わってくる。
3)SN比・・・如何に静かで透明感のあるサウンドに出来るか?・・・メーカー既成のSPやアンプ、電源・ケーブル材では制約(コスト、デザイン、スキル等)が有る。この制約を突破する事も重要。完全な機器など存在しない。
4)音数の多さ・音の厚み・音の太さ・・・生演奏の雰囲気を出せるか?が一つの試金石と思う。生音にはとんでもない音数や音の伝わり方が有る。
5)音のキレ・ヌケ・ノビの確保・・・音の分解能や粒立ち、音の見通しの良さ、一音一音の音の伸び具合等、システムの完成度を計る指標である。
6)音色・音色・・・如何に生音に近づけるか? 或いは意図的に好みの音色や音色に出来るか?だと思う。
まだまだ色々な項目が有ると思うが、自分が気にかけているモノを列記して見た。他にも「生演奏型」のサウンドと「音場型」のサウンドの好みの問題も有る。
「音変換ロス」対策や「伝送ロスの極小化」対策の中で自分なりに掴んだモノが有る。一つの機器がシステムを支配するのではなく、システムを構成する全ての機器・ケーブル材・パーツ・素材・元素の集合体としてそのシステムの「音」として出て来る。単純にシンプルなシステムではシンプルな音がし、複雑なシステムでは複雑な音がする。特に「元素」は非常な重みを持ってくる。
どんなに複雑なシステムでも使っている「元素」が単純なら「単純な」音になる。ただこの元素は「使う量」を過てば手痛いしっぺ返しが有る。まだ自分でも何んとなくしか掴めていない。どんなアンプやケーブル材でも1種類の元素で出来ている訳ではない。「元素」の話まで行くのは急ぎ過ぎか? この辺の話は、自分と同程度のスキルの有る方や、同じ経験をされた方でなければ理解できない話だろう。
1)週波数レンジ・・・使うユニットによって低域・高域のレンジが変わってくるが、30Hz~100KHzくらいがカバーできれば相当優秀なシステムではないかと思う。一般のシステム表示は20Hz~20KHzで有るが、30Hz以下の低音がどんなものか?判っている方は少ないのでは? また、一般的な「音楽」には30Hz以下の低音は少ない。高域は「空気感」等の要素で既成のSPに追加で20KHz以上を出せるユニットを加えるべきだと思う。
2)ダイナミックレンジ・・・如何にぶっといサウンドを出せるか?これもSPユニットやソース機器・電源・ケーブル材のグレードの問題で大きく変わってくる。
3)SN比・・・如何に静かで透明感のあるサウンドに出来るか?・・・メーカー既成のSPやアンプ、電源・ケーブル材では制約(コスト、デザイン、スキル等)が有る。この制約を突破する事も重要。完全な機器など存在しない。
4)音数の多さ・音の厚み・音の太さ・・・生演奏の雰囲気を出せるか?が一つの試金石と思う。生音にはとんでもない音数や音の伝わり方が有る。
5)音のキレ・ヌケ・ノビの確保・・・音の分解能や粒立ち、音の見通しの良さ、一音一音の音の伸び具合等、システムの完成度を計る指標である。
6)音色・音色・・・如何に生音に近づけるか? 或いは意図的に好みの音色や音色に出来るか?だと思う。
まだまだ色々な項目が有ると思うが、自分が気にかけているモノを列記して見た。他にも「生演奏型」のサウンドと「音場型」のサウンドの好みの問題も有る。
「音変換ロス」対策や「伝送ロスの極小化」対策の中で自分なりに掴んだモノが有る。一つの機器がシステムを支配するのではなく、システムを構成する全ての機器・ケーブル材・パーツ・素材・元素の集合体としてそのシステムの「音」として出て来る。単純にシンプルなシステムではシンプルな音がし、複雑なシステムでは複雑な音がする。特に「元素」は非常な重みを持ってくる。
どんなに複雑なシステムでも使っている「元素」が単純なら「単純な」音になる。ただこの元素は「使う量」を過てば手痛いしっぺ返しが有る。まだ自分でも何んとなくしか掴めていない。どんなアンプやケーブル材でも1種類の元素で出来ている訳ではない。「元素」の話まで行くのは急ぎ過ぎか? この辺の話は、自分と同程度のスキルの有る方や、同じ経験をされた方でなければ理解できない話だろう。