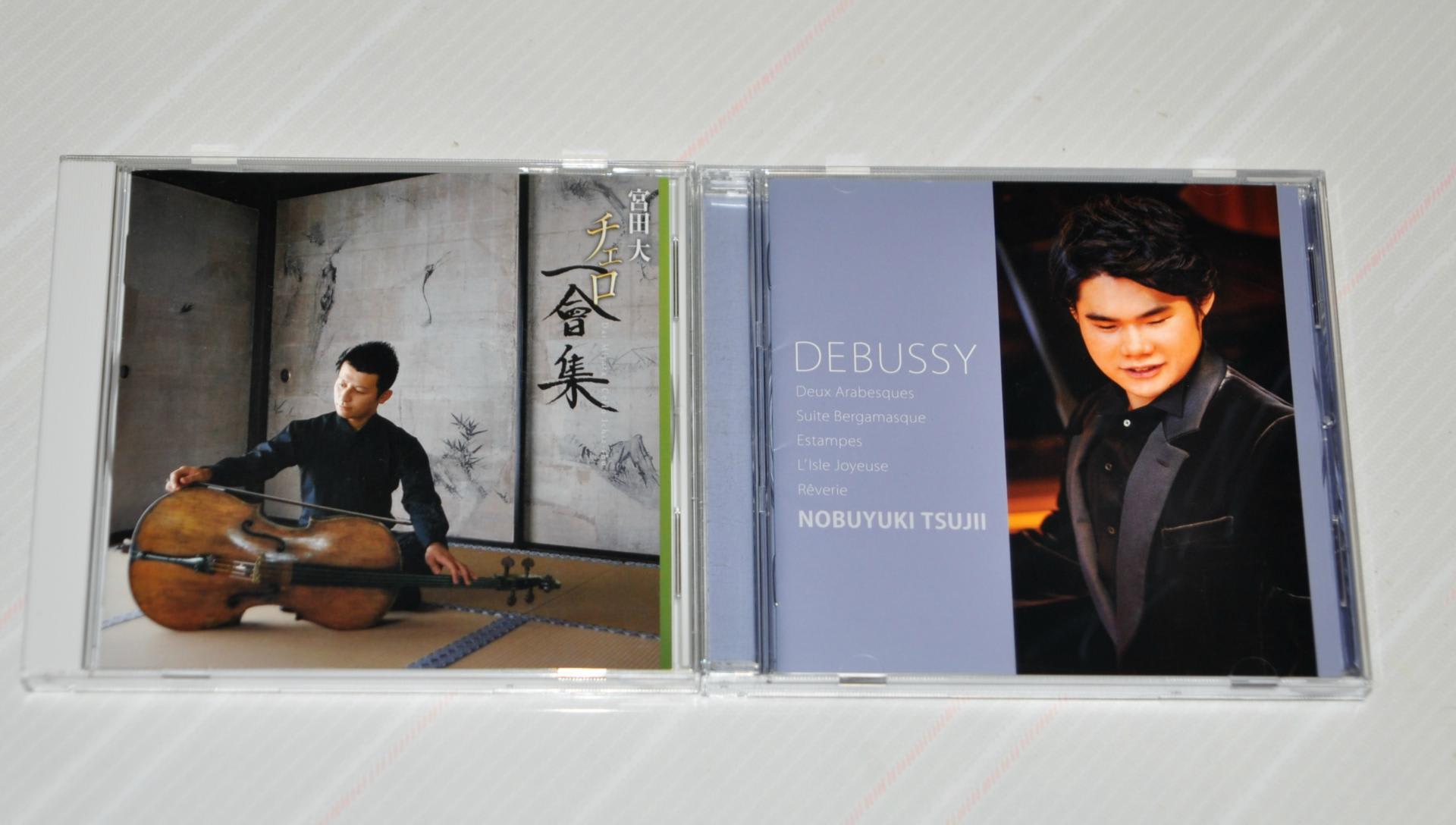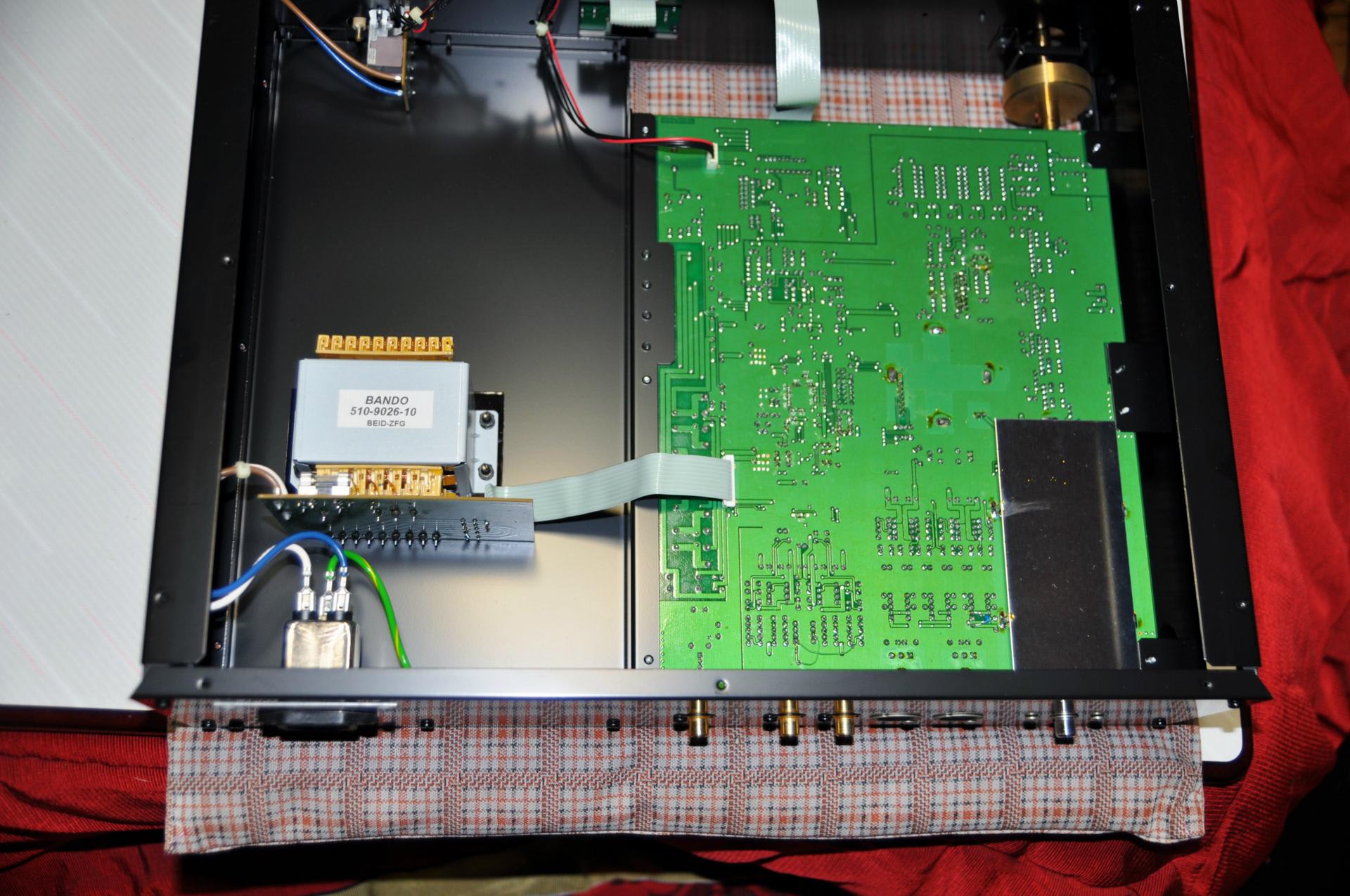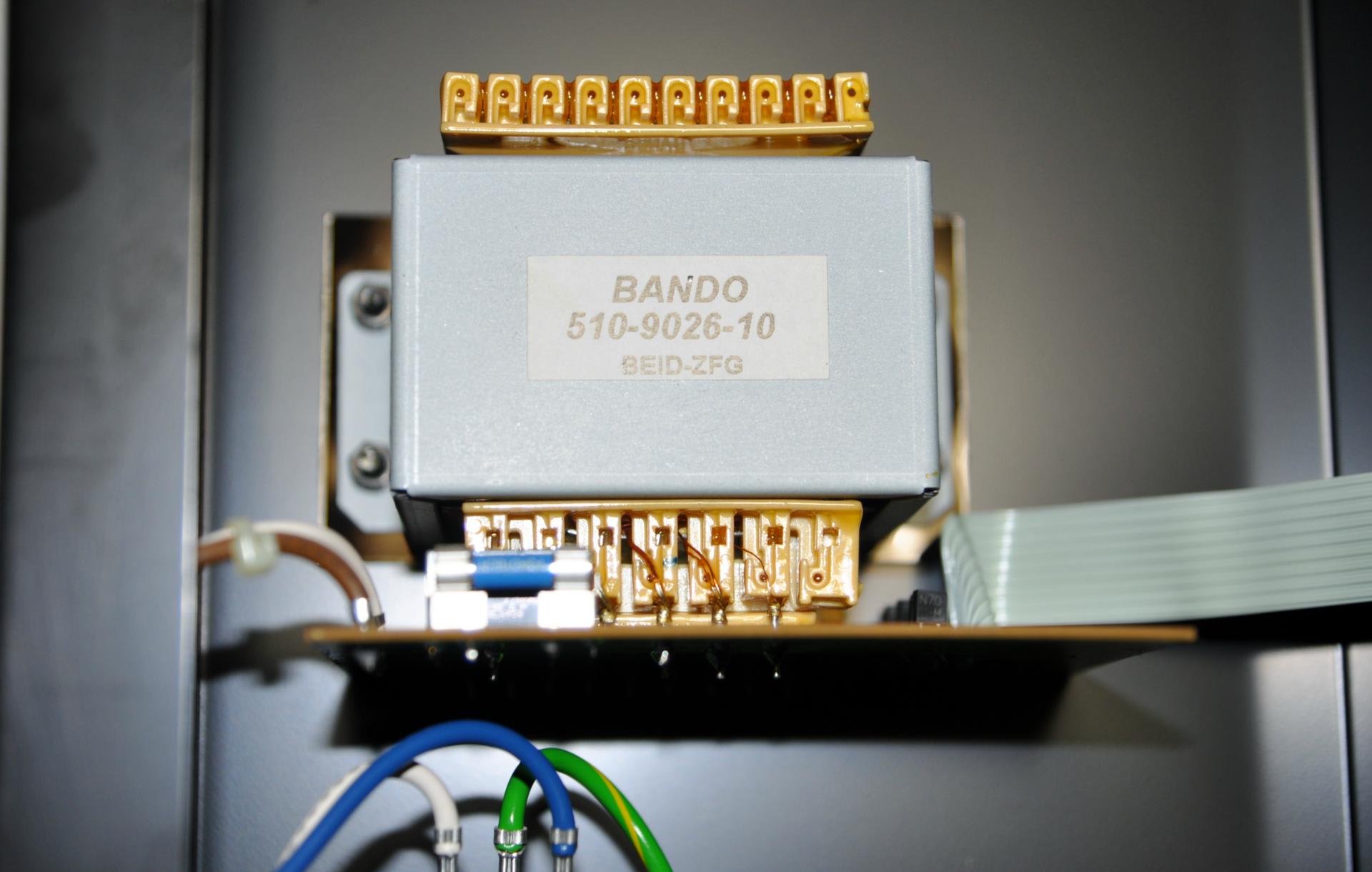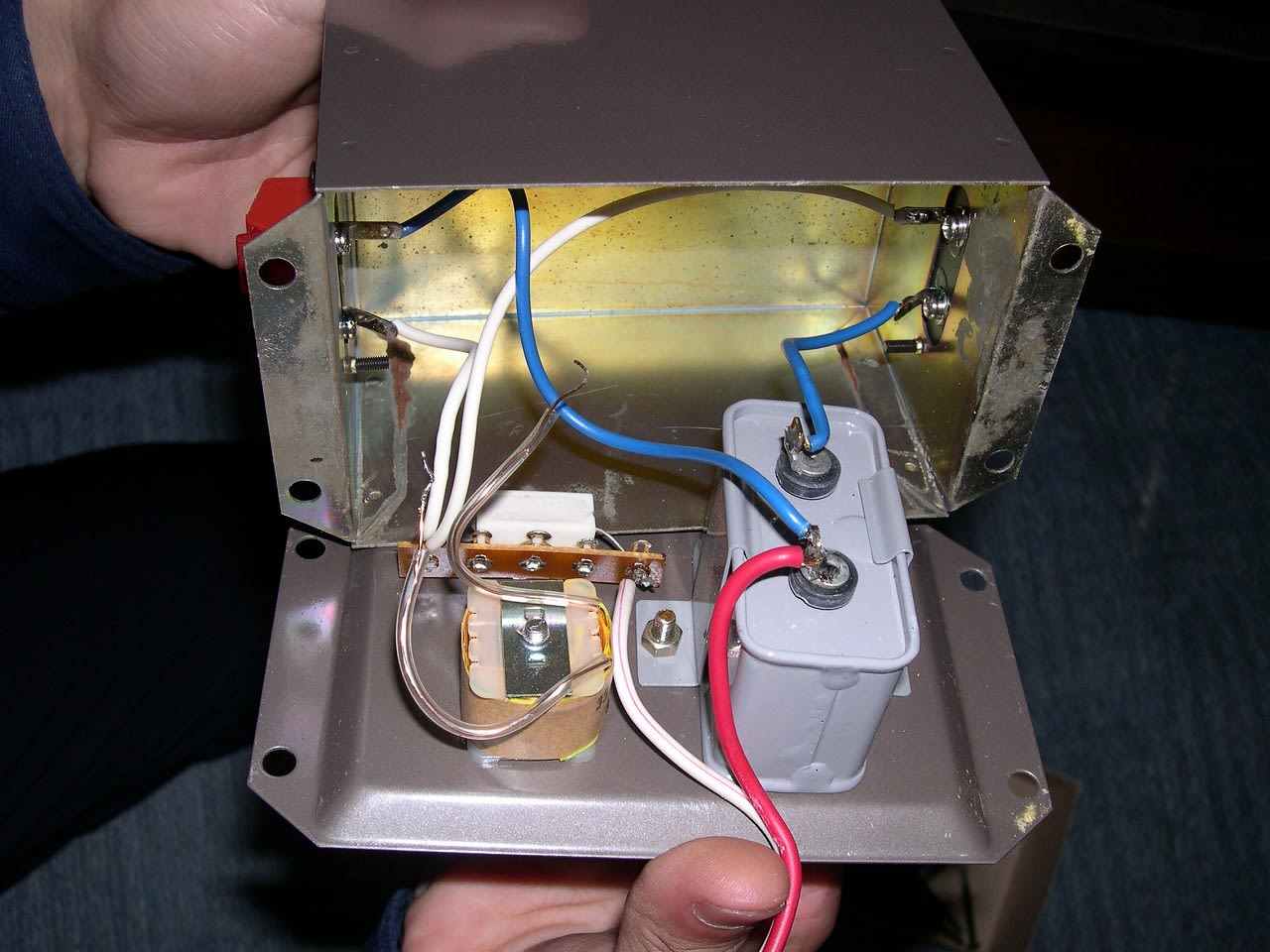やっと重い腰を上げて「サブシステム」の手直しをしました。先日メインで要らなくなったソース機器(MD・DAT・オープンテール類、チューナー等)をサブシステムに組み込みましたが、「音質」的にチョッと物足りなさを感じていました。パアーアンプの裏側のSPケーブル交換ですので、チョッとめんどくさいのです。それで延び延びになっていました。

「不満な部分」その原因は「D208ユニット」に有ります。D208ユニットはD130(38㎝)の20㎝版になります。その為に非常に軽いコーン紙を使って有ります。能率も98dbと非常に高能率です。良い点ばかり書きましたがデメリットも有ります。それは下限の再生周波数帯域が60Hzぐらいしかない事です。「低域不足」を感じます。この部分への対策を施されたのが「LEシリーズ」と云うもので、「LE8T」ユニットがその典型です。LE8Tなら40Hzくらいまで伸びています。

D208システムのユニットは交換しないで低域を伸ばす方法は、SPケーブルをよりグレードの高いモノに交換してやる事です。今まではNo2クラスのSPケーブル(D208 SP箱内配線と同クラス)を使っていましたが、それを「オリンパスシステムと同じクラス」のSPケーブルに交換しました。低域の再生帯域・エネルギー感とすべての音の密度が変わります。

結果は、音数が飛躍的に増えて、エネルギー感も増し、「低域不足を感じない」モノになりました。おそらく50Hzくらいまで再生帯域が下がっています。音の密度が半端なく濃くなっていますので、音のバランスも良くなり、低域不足を感じなくなりました。これで安心して使えるどころか「メイン」として音楽を楽しめるサウンドになりました。
FM放送をメインのオリンパスシステム(隣の部屋)と共に一緒にかけて、部屋を往復しても何の違和感も感じません。質感までもほとんど同じ様になりました。