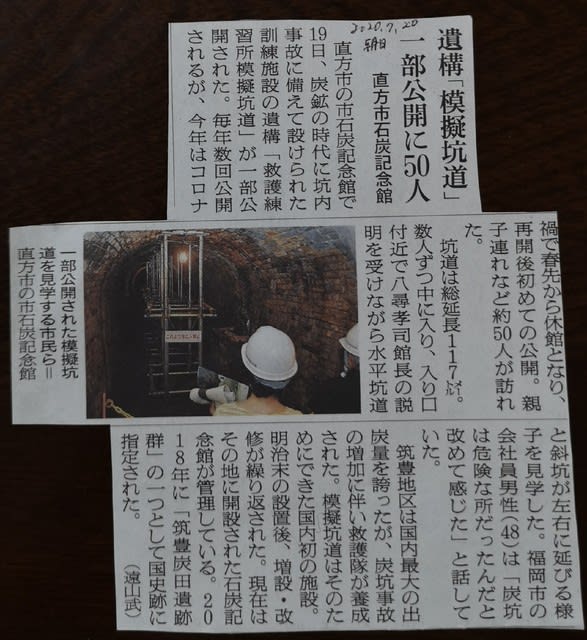「福岡工業大付属城東高(福岡市東区)の生徒が、自分たちで開発した【自動アルコール噴射ロボット】2台を、近くの『コミセンわじろ』に貸与した」そうです。
どんなロボットでしょうか?
「ロボットの前にて手をかざすと自動でボトルのトリガーを引き、新型コロナ感染予防のアルコール消毒液を適量噴射する仕組み」だそうで、その「ユニークな動きが利用者の人気を呼びそうだ」と評判のようです。「ロボットを開発したのは電気科・電子情報科の生徒を中心に16名で活動する〈ロボット競技プロジェクト〉のメンバー」で、「昨年度は国際的なロボットコンテスト《WRO Japan2019福岡大会》で準優勝した実力を持つ」そうです。「3月に今年の同大会がなくなることを伝えられた生徒たちは、大会出場の代わりに実生活で役に立つロボット製作を思い立った」とのことです。このロボット製作で難しかったところは、「なるべく手入れがしやすいよう」という工夫だったそうです。〜なるほど!このロボットを使うのはまだまだロボットには不慣れの人たちですから〜。若い科学者頑張れ〜!
(下:2020年7月31日西日本新聞-床波昌雄「福岡工大城東高生16人アルコール噴出ロボ開発 2台貸与 手入れしやすいよう工夫」より)

どんなロボットでしょうか?
「ロボットの前にて手をかざすと自動でボトルのトリガーを引き、新型コロナ感染予防のアルコール消毒液を適量噴射する仕組み」だそうで、その「ユニークな動きが利用者の人気を呼びそうだ」と評判のようです。「ロボットを開発したのは電気科・電子情報科の生徒を中心に16名で活動する〈ロボット競技プロジェクト〉のメンバー」で、「昨年度は国際的なロボットコンテスト《WRO Japan2019福岡大会》で準優勝した実力を持つ」そうです。「3月に今年の同大会がなくなることを伝えられた生徒たちは、大会出場の代わりに実生活で役に立つロボット製作を思い立った」とのことです。このロボット製作で難しかったところは、「なるべく手入れがしやすいよう」という工夫だったそうです。〜なるほど!このロボットを使うのはまだまだロボットには不慣れの人たちですから〜。若い科学者頑張れ〜!
(下:2020年7月31日西日本新聞-床波昌雄「福岡工大城東高生16人アルコール噴出ロボ開発 2台貸与 手入れしやすいよう工夫」より)