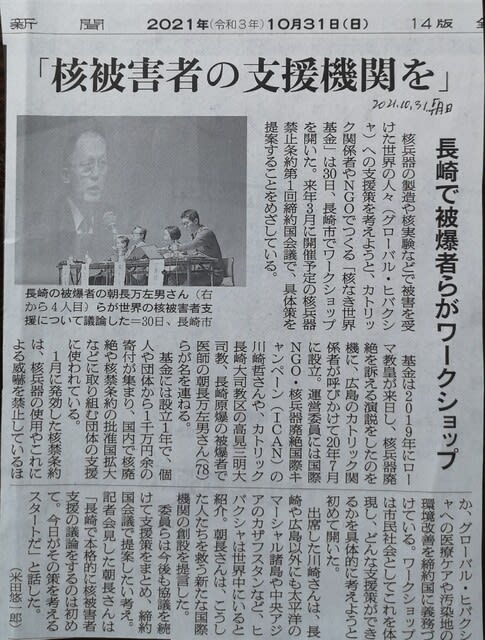「核兵器の製造や核実験などで被害を受けた世界の人びと(グローバル・ヒバクシャ)への支援策を考えようと、カトリック関係車やNGOでつくる【核なき世界基金】は(10月)30日、長崎市でワークショップを開」かれたそうです。
「【核なき世界基金】は2019年にローマ教皇が来日し、核兵器廃絶を訴える演説をしたのを機に、広島のカトリック関係者が呼びかけて20年7月に設立。運営委員には国際NGO・核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)の川崎哲さんや、カトリック長崎大司教の高見三明大司教、長崎原爆の被爆者で医師の朝長万左男さん(78)らが名を連ねる」とのことです。「基金には設立1年で、個人や団体から1千万円余の寄付が集まり、国内で核廃絶や核禁条約の批准国拡大などに取り組む団体の支援に使われている」そうです。
「出席した川崎さんは、長崎や広島以外にも太平洋のマーシャル諸島や中央アジアのカザフスタンなど、被爆者は世界中にいると紹介」されています。〜グローバル・ヒバクシャの意味あいですね。
この日の協議を「スタートに、協議を続け」、「来年3月に開催予定の核兵器禁止条約第1回締約国会議で、具体策を提案することを目指」されるそうです。
(下:2021年10月31日 朝日新聞-米田悠一郎「『被爆者の支援機関を』長崎で被爆者らがワークショップ」より):
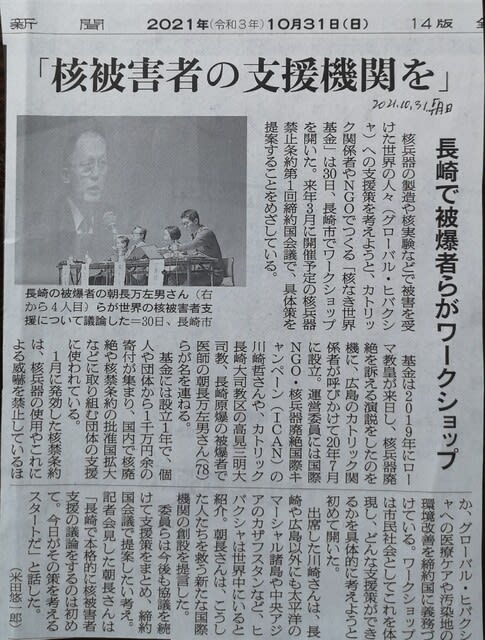
「【核なき世界基金】は2019年にローマ教皇が来日し、核兵器廃絶を訴える演説をしたのを機に、広島のカトリック関係者が呼びかけて20年7月に設立。運営委員には国際NGO・核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)の川崎哲さんや、カトリック長崎大司教の高見三明大司教、長崎原爆の被爆者で医師の朝長万左男さん(78)らが名を連ねる」とのことです。「基金には設立1年で、個人や団体から1千万円余の寄付が集まり、国内で核廃絶や核禁条約の批准国拡大などに取り組む団体の支援に使われている」そうです。
「出席した川崎さんは、長崎や広島以外にも太平洋のマーシャル諸島や中央アジアのカザフスタンなど、被爆者は世界中にいると紹介」されています。〜グローバル・ヒバクシャの意味あいですね。
この日の協議を「スタートに、協議を続け」、「来年3月に開催予定の核兵器禁止条約第1回締約国会議で、具体策を提案することを目指」されるそうです。
(下:2021年10月31日 朝日新聞-米田悠一郎「『被爆者の支援機関を』長崎で被爆者らがワークショップ」より):