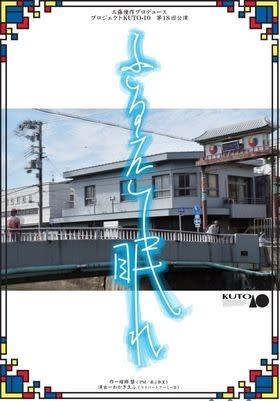
たぶん台本の遅れのせいであろう。役者たちは台本を手にしたまま演じる(芝居をする)というスタイルになったことによって、芝居自体が結果的に内向きのものになる。会話劇なのだが、台本を待つことで動きが制限され、視線も相手に対してではなく、うつむいて言葉を発する場面が多くなる。
テキストを離したなら彼らの関係性がもっと前面に出てくるはずではないか。でも、このもどかしさがなんだか、とても面白い。夫と妻、夫の秘密、友人たちとのこと、子供たち(彼が妻以外の女性に産ませた子供も、やってくる)。そんないくつものちょっとしたことが、淡いタッチで見え隠れする。そこにテキストを持つことが介在したことで、自閉的な芝居となった。そのことが必要以上に(たまたまだろうけれど)この作品とマッチする。
死んでいこうとしている神部(保)は、ゆっくりとその事実を受け入れていくはずだった。なのに、それでも生にこだわってしまう。人間っていろんな意味で愚かだ。病院のベッドに横たわる男は現世のにおいをぷんぷんさせる。ストレートに相手と向き合うことがなくなり、死と向き合うことからも避ける。神部という男の弱さを中心にして、誰もが死と向き合わない。工藤俊作演じる医者まで含めてである。これはそんな芝居になっている。
だけど、それがみっともないことではなく、とても自然なことに思える。ふるえて眠れ、というタイトルがそんなことのすべてを象徴している。

























