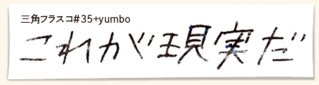
この世界にはもう夢も希望もない。だけど、ここに止まっているのではなく、この先にむかって旅しなくてはならない。そこにはきっと何かがある。
この手のタイプのSFは枚挙に暇がない。『ザ・ロード』や『ウォーカー』という終末を描いたSF映画が今年も公開されている。荒涼とした世界を旅する親子や男たちを主人公にした人間ドラマやアクションは70年代からずっと作り続けられてきた。今回、三角フラスコが描く近未来には、バス停が出てきて、1日2回くらいバスがやってきて、これに乗れば、この先に行けるみたいだ。ただ本数があまりに少なく、漠然としている。歩いて行ってもバスに乗っても同じくらいでこの先にたどり着くことが出来る。そこには何があるのかは明確にされない。先に書いたSF映画と較べると設定はなんだかのんびりしている。終末の風景というよりも、今の現実の風景と言う方が、納得がいくほどだ。これだけの情報では、今、世界では何が起きていて、彼らを巡る現実がどうなっているのかはよくわからない。だが、このくらいの緩さがとても好ましい。そこに映画と演劇の差が明確に示される。
ここにたどりつく夫婦。彼らががやってくるところから芝居は始まる。やがて、もうひとり男がやって来て、彼は行き倒れになる。そこに自転車に乗った地元の青年が現れ彼を助ける。青年は空き家ならこの町にはたくさんあるから、そこで暮らせばいいと言う。
三角フラスコとyunboというバンドによるコラボレーションである。芝居とライブが半々になっている。後半になると、yunboのボーカルである高柳あゆ子さん(彼女が歌う時の無表情がとてもいい。でも、時々一瞬だけ、表情が緩む、そんな瞬間もいい)も芝居の世界に入ってくる。yunboのフラットで硬質の(ある意味脱力系でもある)歌の世界と、生田恵さんが描くこのさらりとした芝居の世界がやがてひとつになっていく。ここに描かれる重い現実をあっさりと投げ出して描いていく。そこには特別な感慨は何もない。今世界がどうなっているのかも、だから、どうしなくてはならないというのかも、描かれない。明確な方向性を示すのではない。ただ、すべてをひっくるめて、「これが現実だ」と言うのである。その突き放したようなスタンスが、なぜかとても心に優しい。
この手のタイプのSFは枚挙に暇がない。『ザ・ロード』や『ウォーカー』という終末を描いたSF映画が今年も公開されている。荒涼とした世界を旅する親子や男たちを主人公にした人間ドラマやアクションは70年代からずっと作り続けられてきた。今回、三角フラスコが描く近未来には、バス停が出てきて、1日2回くらいバスがやってきて、これに乗れば、この先に行けるみたいだ。ただ本数があまりに少なく、漠然としている。歩いて行ってもバスに乗っても同じくらいでこの先にたどり着くことが出来る。そこには何があるのかは明確にされない。先に書いたSF映画と較べると設定はなんだかのんびりしている。終末の風景というよりも、今の現実の風景と言う方が、納得がいくほどだ。これだけの情報では、今、世界では何が起きていて、彼らを巡る現実がどうなっているのかはよくわからない。だが、このくらいの緩さがとても好ましい。そこに映画と演劇の差が明確に示される。
ここにたどりつく夫婦。彼らががやってくるところから芝居は始まる。やがて、もうひとり男がやって来て、彼は行き倒れになる。そこに自転車に乗った地元の青年が現れ彼を助ける。青年は空き家ならこの町にはたくさんあるから、そこで暮らせばいいと言う。
三角フラスコとyunboというバンドによるコラボレーションである。芝居とライブが半々になっている。後半になると、yunboのボーカルである高柳あゆ子さん(彼女が歌う時の無表情がとてもいい。でも、時々一瞬だけ、表情が緩む、そんな瞬間もいい)も芝居の世界に入ってくる。yunboのフラットで硬質の(ある意味脱力系でもある)歌の世界と、生田恵さんが描くこのさらりとした芝居の世界がやがてひとつになっていく。ここに描かれる重い現実をあっさりと投げ出して描いていく。そこには特別な感慨は何もない。今世界がどうなっているのかも、だから、どうしなくてはならないというのかも、描かれない。明確な方向性を示すのではない。ただ、すべてをひっくるめて、「これが現実だ」と言うのである。その突き放したようなスタンスが、なぜかとても心に優しい。

























