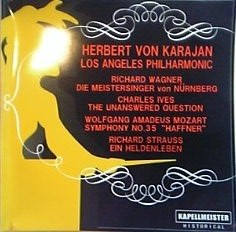◎J.カークパトリック(P)(COLUMBIA)1945・LP
使徒カークパトリックによる同曲の初録音盤。譜面のとっ散らかり含め難解な「曲」を史上初、弾けて聴ける形に校訂しただけあり・・・協会が出来て決定版が出るまでは交響曲すら氏の手書きスコアのコピーが通用していたくらい「貢献」しているのだが、改変と言える部分も多く、この曲の(必須ではなかったと思うが)フルートやヴィオラを省いた主観的な校訂も批判の対象となった・・・密度の高い音楽の細部まで非常にこなれた演奏に仕上がっている。
ライヴ感に溢れ、アーティキュレーションが強く付けられており、テンポ・ルバートも自然ではあるがかなり派手目で印象的だ。ロマンティックな起伏ある流れや美しく感傷的な響きを強調することで非凡なるアイヴズの才能の唯一の欠点「人好きしない」ところを補うことに成功している。完全にミスタッチに聞こえる(しかも細かくたくさんある)重音が随所に聴こえるはずなのに、ラヴェルが狙った”寸止め”の範疇として受け止められる。衝突する響きとして気にならない。
カークパトリックの技術力も高く表現も的確で、確かに同時代アメリカのルビンシュタイン的な押せ押せドライなピアニズムの影響もあるにせよ、思い入れの強さが心を揺さぶる音に現れている。とくにアイヴズの真骨頂と言える静かな音楽、懐かしくも逞しいメロディ、解体され織り込まれた運命のリズム、南北戦争後・世界大戦前のアメリカイズムを宗教的・哲学的側面から体言した、やはりもう「過去」となってしまった世界を音楽にうつしたものとしてセンチメンタリズムのもとに整理し、表現している。
シェーンベルクと同い年だったか、ドヴォルザーク・インパクトが強かった頃のアメリカである、つまりは完全に前時代の空気の中で活動した人である。ロマンティックな香りや膨らんだスコアリングも無理も無い。この演奏は多分譜面がどうであれアイヴズの内面的本質を突いている。コンサートには行かなくなったけどマーラーの指揮するときだけは出かけたという、そういう時代の人である。ウェーベルン後の無駄の無い抽象音楽と比較して批判するのはおかしい。戦後派ではない、戦後に評価されただけである。
ステレオの薄盤による新録(1968)が知られているが、旧録のほうが壮年なりの力感があり、揺れも小気味よく、アイヴズを前衛と捉えた、もしくは「真面目な音楽」と捉えた後発他盤には絶対に聴かれない世界観が私は好きだ。モノラル。
使徒カークパトリックによる同曲の初録音盤。譜面のとっ散らかり含め難解な「曲」を史上初、弾けて聴ける形に校訂しただけあり・・・協会が出来て決定版が出るまでは交響曲すら氏の手書きスコアのコピーが通用していたくらい「貢献」しているのだが、改変と言える部分も多く、この曲の(必須ではなかったと思うが)フルートやヴィオラを省いた主観的な校訂も批判の対象となった・・・密度の高い音楽の細部まで非常にこなれた演奏に仕上がっている。
ライヴ感に溢れ、アーティキュレーションが強く付けられており、テンポ・ルバートも自然ではあるがかなり派手目で印象的だ。ロマンティックな起伏ある流れや美しく感傷的な響きを強調することで非凡なるアイヴズの才能の唯一の欠点「人好きしない」ところを補うことに成功している。完全にミスタッチに聞こえる(しかも細かくたくさんある)重音が随所に聴こえるはずなのに、ラヴェルが狙った”寸止め”の範疇として受け止められる。衝突する響きとして気にならない。
カークパトリックの技術力も高く表現も的確で、確かに同時代アメリカのルビンシュタイン的な押せ押せドライなピアニズムの影響もあるにせよ、思い入れの強さが心を揺さぶる音に現れている。とくにアイヴズの真骨頂と言える静かな音楽、懐かしくも逞しいメロディ、解体され織り込まれた運命のリズム、南北戦争後・世界大戦前のアメリカイズムを宗教的・哲学的側面から体言した、やはりもう「過去」となってしまった世界を音楽にうつしたものとしてセンチメンタリズムのもとに整理し、表現している。
シェーンベルクと同い年だったか、ドヴォルザーク・インパクトが強かった頃のアメリカである、つまりは完全に前時代の空気の中で活動した人である。ロマンティックな香りや膨らんだスコアリングも無理も無い。この演奏は多分譜面がどうであれアイヴズの内面的本質を突いている。コンサートには行かなくなったけどマーラーの指揮するときだけは出かけたという、そういう時代の人である。ウェーベルン後の無駄の無い抽象音楽と比較して批判するのはおかしい。戦後派ではない、戦後に評価されただけである。
ステレオの薄盤による新録(1968)が知られているが、旧録のほうが壮年なりの力感があり、揺れも小気味よく、アイヴズを前衛と捉えた、もしくは「真面目な音楽」と捉えた後発他盤には絶対に聴かれない世界観が私は好きだ。モノラル。