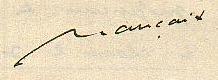ロザンタール指揮ORTF(ina配信)1968/2/15放送
かつてのアメリカの騒音主義的な(ジャズのイディオムや打楽器主義込の)音響に接近しながらも、オネゲルからジョリヴェ(ガムラン要素など近い)、さらにその先の世代の作風まで取り入れた、ないし先んじすらした非常に多彩多様式的な印象を与える黛世界を象徴する作品。魅力的な旋律も忍ばせられているところがこの人の聴衆への態度を明確に示している。ロザンタールにうってつけの開放的な響きの饗宴で、作品自体がしっかり書かれていることもあるのだろうが、拡散し過ぎて瓦解するのを防ぐ手綱さばきが巧い。当時のフランス音楽に近接した作品であり、なおかつそれを越えて耳を惹く要素を多々知的に組み込んだところが、聴衆にも非常に受けた様子がうかがえる(ina配信音源で新作や稀作が入っているときは決まってそうなのだが、作曲家が臨席していると思われる)。パリには一旦背を向けた人ではあるが、これだけの短い中に語られることの多きの中に、フランス音楽への意識が無いとはとても言えない。良い機会に良い演奏家により良い聴衆の前で演奏された幸福の記録と思う。
かつてのアメリカの騒音主義的な(ジャズのイディオムや打楽器主義込の)音響に接近しながらも、オネゲルからジョリヴェ(ガムラン要素など近い)、さらにその先の世代の作風まで取り入れた、ないし先んじすらした非常に多彩多様式的な印象を与える黛世界を象徴する作品。魅力的な旋律も忍ばせられているところがこの人の聴衆への態度を明確に示している。ロザンタールにうってつけの開放的な響きの饗宴で、作品自体がしっかり書かれていることもあるのだろうが、拡散し過ぎて瓦解するのを防ぐ手綱さばきが巧い。当時のフランス音楽に近接した作品であり、なおかつそれを越えて耳を惹く要素を多々知的に組み込んだところが、聴衆にも非常に受けた様子がうかがえる(ina配信音源で新作や稀作が入っているときは決まってそうなのだが、作曲家が臨席していると思われる)。パリには一旦背を向けた人ではあるが、これだけの短い中に語られることの多きの中に、フランス音楽への意識が無いとはとても言えない。良い機会に良い演奏家により良い聴衆の前で演奏された幸福の記録と思う。