ヴォルフ指揮ラムルー管弦楽団(timpani/naxos配信他)1929-33・CD
酷いSP起こしノイズを前提として同時代の指揮者の録音と比較するとピエルネより技術が勝るのは明白で、国は違うがダムロッシュのような専門指揮者として聴かせる力、オケの統率力の強さは感じるが、何よりラヴェルの「仕掛け」を的確にとらえ、それをしっかり構築させて特有の管弦楽の魅力を届かせている点が違う。勢い任せ、情感に訴える、そういったスタイルではない(かといって情感に訴えないことは無い、スコアから本来的に訴える力を引き出している)。この時代の録音でここまで立体的な構築性を、キラキラしたやわらかなフランスオケの音をもって表現したものは他にあるまい。コッポラほどではないが骨董時代にフランス音楽の網羅的録音を任されただけのものはある(ラムルー管という手兵は技術的にはやや弱いが指揮者とのコンビネーションは板についている)。同曲、もっと新しい繊細な録音のほうが良いことは確かだが、同時代のものに興味あるならトスカニーニなど外国の「作曲家よりも権威のあった」有名指揮者とともにこちらにも触れておき、差異を確かめるのも良いと思う。
酷いSP起こしノイズを前提として同時代の指揮者の録音と比較するとピエルネより技術が勝るのは明白で、国は違うがダムロッシュのような専門指揮者として聴かせる力、オケの統率力の強さは感じるが、何よりラヴェルの「仕掛け」を的確にとらえ、それをしっかり構築させて特有の管弦楽の魅力を届かせている点が違う。勢い任せ、情感に訴える、そういったスタイルではない(かといって情感に訴えないことは無い、スコアから本来的に訴える力を引き出している)。この時代の録音でここまで立体的な構築性を、キラキラしたやわらかなフランスオケの音をもって表現したものは他にあるまい。コッポラほどではないが骨董時代にフランス音楽の網羅的録音を任されただけのものはある(ラムルー管という手兵は技術的にはやや弱いが指揮者とのコンビネーションは板についている)。同曲、もっと新しい繊細な録音のほうが良いことは確かだが、同時代のものに興味あるならトスカニーニなど外国の「作曲家よりも権威のあった」有名指揮者とともにこちらにも触れておき、差異を確かめるのも良いと思う。












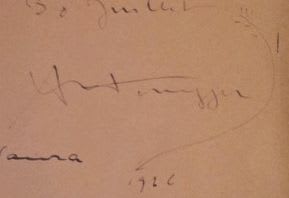 ツィピーヌ指揮パリ音楽院管弦楽団(EMI)CD
ツィピーヌ指揮パリ音楽院管弦楽団(EMI)CD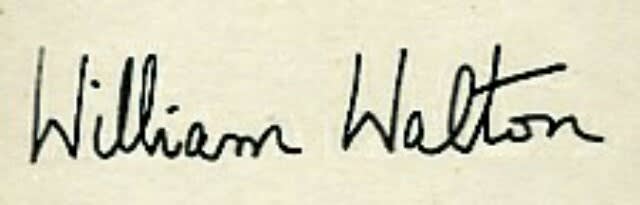 ◎ボールト指揮フィルハーモニック・プロムナード管(ロンドン・フィル)(NIXA/PYEほか)
◎ボールト指揮フィルハーモニック・プロムナード管(ロンドン・フィル)(NIXA/PYEほか) コンドラシン指揮モスクワ・フィル(eternities)1969/2/26live
コンドラシン指揮モスクワ・フィル(eternities)1969/2/26live コンドラシン指揮モスクワ・フィル(eternities)1967/5/12
コンドラシン指揮モスクワ・フィル(eternities)1967/5/12




