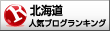北海道の原子力発電比率は国内電力10社平均の26%(2008年度)を上回る40%である。
しかも泊原発1か所に40%依存しているわけです。
北海道内の主要発電所の多くは海岸にあります。
事故対策は勿論、早急に電力の「多様化・分散化」を検討すべきだ。
泊原発の安全対策を申し入れ 高橋知事と周辺4町村長 原発は「評価」 (北海道新聞)
高橋知事は「(泊原発の)地元住民の不安が広がっている。安全性向上について国や事業者に要請していきたい」と強調。
高橋道政3期目へ 「新生」は大きな構想力で(4月11日北海道新聞)
知事選の高橋知事の公約には、「21世紀バックアップ拠点構想」という項目がある。大災害発生時における官民のデータのバックアップセンターや食料・資材の備蓄、運輸・流通拠点の整備を、北海道で進めるという。
泊原発沖に活断層か 東洋大教授が学会発表へ共和・泊原発の直下活断層を報道せよ 北海道新聞の若い記者諸君への手紙(大沼安史の個人新聞)
YouTube - 泊原発近くに未知の活断層か
地元の原発の安全性もあやしいこの段階で、危機感が無さすぎると思います。
北電 泊原発で緊急安全対策 津波想定15メートルに ポンプ電動機は予備も 北海道新聞 4/17朝刊の記事です。
北電が、4月中に経済産業省原子力安全・保安院に提出する緊急安全対策の内容が報じられました。
●泊原発3基は、海岸沿いの標高10メートル以上にある。
●15メートルの津波を想定すると、原子炉ごとに2台ずつ設置している非常用ディーゼル発電機が故障する恐れがある。
●対策の概要
1.移動発電機車1台を高台に初めて配備(3月18日に実施済)
2.原子炉を冷却するポンプ電動機などの故障に備え、新たに高台に予備機を置く。
3.全電源喪失の場合も「蒸気を動力にする補助給水ポンプ」があるので「原子炉内の燃料棒を冷やせる」としている。
4.使用済み燃料貯蔵プールは2台の消防車(2008年配備)で給水して冷やす。
5.中長期的な対策:原子炉建屋の海側の敷地内に防潮壁を造ったり、建屋の入り口に浸水を防ぐ工事を施したりすることも検討する。
最も心配なのは、3です。
加圧水型、電源喪失時どう冷やす 最後の「命綱」故障想定なし (福井新聞)
重要な点だけは写させてもらうと、
「外部の電源を失い非常用発電機も動かない「全交流電源喪失」に陥った場合、蒸気で動く補助給水ポンプで蒸気発生器に水を送り、1次冷却水を通して原子炉を冷やす。圧力が高くなれば、蒸気の一部は主蒸気逃がし弁で外に放出する。この補助給水系統は冷却機能の最後のとりでとなる重要設備のため、関電は以前から配管などの耐震補強や系統の多重化を検討している。 しかし「全交流電源喪失時、使用可能なすべての設備が機能を失うとは考えられない」(関電)とし、補助給水系統の故障は想定していない。」
ということである。美浜3号機2次給水管破断事故の経過安全性の観点から 京都大学原子炉実験所 海老澤徹氏
地震で配管が損傷すれば役に立たないと言うことです。
性能試験・運転における事故・トラブル等の事例とその対応 独立行政法人日本原子力研究開発機構による「もんじゅ」のトラブル対応マニュアルらしい。配管の損傷は地震がくれば何処でもあることです。
副題は“配管の破損(水・蒸気系復水配管)”となっています。
周辺環境への影響はない。安全上の問題はない。となっていますが、「全交流電源喪失」の時にこうなったらどうするのでしょうか?
また、 関西電力株式会社美浜発電所1号機における運転上の制限の逸脱についてという、原子力安全・保安院の文書が出てきました。
(関西電力(株)からの報告内容)
美浜発電所1号機は定格熱出力一定運転中のところ、本日、月1回定期に実施しているタービン動補助給水ポンプの起動試験のため、9時16分に当該ポンプを起動しました。
起動後の当該ポンプの吐出圧力を確認したところ、通常時約8MPa以上の吐出圧力となるところ、約4MPaしかないことが確認されました。
このため、起動試験を中断し、9時21分に当該ポンプを停止しました。
吐出圧力が低い値を示していることから、原子炉施設保安規定の要求事項であるタービン動補助給水ポンプが動作可能であることを満たされなくなったことから、9時30分
に運転上の制限からの逸脱を宣言しました。
タービン動補助給水ポンプの運転上の制限の逸脱に伴う措置として、当該逸脱から4時間以内に、その後は8時間以内に2系統の電動補助給水ポンプを起動し、動作可能であることを確認します。
(当院の対応)
当院では現地駐在の保安検査官により、保安規定に定める措置状況について確認します。
なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。
運転上の制限とは、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数が定められているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させるか、または出力低下などの予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
なぜ吐出圧力が低下したのか、全く問題にしていません。国民の安全などどうでもよいのです。規定に違反していなければ!
しかも泊原発1か所に40%依存しているわけです。
北海道内の主要発電所の多くは海岸にあります。
事故対策は勿論、早急に電力の「多様化・分散化」を検討すべきだ。
泊原発の安全対策を申し入れ 高橋知事と周辺4町村長 原発は「評価」 (北海道新聞)
高橋知事は「(泊原発の)地元住民の不安が広がっている。安全性向上について国や事業者に要請していきたい」と強調。
高橋道政3期目へ 「新生」は大きな構想力で(4月11日北海道新聞)
知事選の高橋知事の公約には、「21世紀バックアップ拠点構想」という項目がある。大災害発生時における官民のデータのバックアップセンターや食料・資材の備蓄、運輸・流通拠点の整備を、北海道で進めるという。
泊原発沖に活断層か 東洋大教授が学会発表へ共和・泊原発の直下活断層を報道せよ 北海道新聞の若い記者諸君への手紙(大沼安史の個人新聞)
YouTube - 泊原発近くに未知の活断層か
地元の原発の安全性もあやしいこの段階で、危機感が無さすぎると思います。
北電 泊原発で緊急安全対策 津波想定15メートルに ポンプ電動機は予備も 北海道新聞 4/17朝刊の記事です。
北電が、4月中に経済産業省原子力安全・保安院に提出する緊急安全対策の内容が報じられました。
●泊原発3基は、海岸沿いの標高10メートル以上にある。
●15メートルの津波を想定すると、原子炉ごとに2台ずつ設置している非常用ディーゼル発電機が故障する恐れがある。
●対策の概要
1.移動発電機車1台を高台に初めて配備(3月18日に実施済)
2.原子炉を冷却するポンプ電動機などの故障に備え、新たに高台に予備機を置く。
3.全電源喪失の場合も「蒸気を動力にする補助給水ポンプ」があるので「原子炉内の燃料棒を冷やせる」としている。
4.使用済み燃料貯蔵プールは2台の消防車(2008年配備)で給水して冷やす。
5.中長期的な対策:原子炉建屋の海側の敷地内に防潮壁を造ったり、建屋の入り口に浸水を防ぐ工事を施したりすることも検討する。
最も心配なのは、3です。
加圧水型、電源喪失時どう冷やす 最後の「命綱」故障想定なし (福井新聞)
重要な点だけは写させてもらうと、
「外部の電源を失い非常用発電機も動かない「全交流電源喪失」に陥った場合、蒸気で動く補助給水ポンプで蒸気発生器に水を送り、1次冷却水を通して原子炉を冷やす。圧力が高くなれば、蒸気の一部は主蒸気逃がし弁で外に放出する。この補助給水系統は冷却機能の最後のとりでとなる重要設備のため、関電は以前から配管などの耐震補強や系統の多重化を検討している。 しかし「全交流電源喪失時、使用可能なすべての設備が機能を失うとは考えられない」(関電)とし、補助給水系統の故障は想定していない。」
ということである。美浜3号機2次給水管破断事故の経過安全性の観点から 京都大学原子炉実験所 海老澤徹氏
地震で配管が損傷すれば役に立たないと言うことです。
性能試験・運転における事故・トラブル等の事例とその対応 独立行政法人日本原子力研究開発機構による「もんじゅ」のトラブル対応マニュアルらしい。配管の損傷は地震がくれば何処でもあることです。
副題は“配管の破損(水・蒸気系復水配管)”となっています。
周辺環境への影響はない。安全上の問題はない。となっていますが、「全交流電源喪失」の時にこうなったらどうするのでしょうか?
また、 関西電力株式会社美浜発電所1号機における運転上の制限の逸脱についてという、原子力安全・保安院の文書が出てきました。
(関西電力(株)からの報告内容)
美浜発電所1号機は定格熱出力一定運転中のところ、本日、月1回定期に実施しているタービン動補助給水ポンプの起動試験のため、9時16分に当該ポンプを起動しました。
起動後の当該ポンプの吐出圧力を確認したところ、通常時約8MPa以上の吐出圧力となるところ、約4MPaしかないことが確認されました。
このため、起動試験を中断し、9時21分に当該ポンプを停止しました。
吐出圧力が低い値を示していることから、原子炉施設保安規定の要求事項であるタービン動補助給水ポンプが動作可能であることを満たされなくなったことから、9時30分
に運転上の制限からの逸脱を宣言しました。
タービン動補助給水ポンプの運転上の制限の逸脱に伴う措置として、当該逸脱から4時間以内に、その後は8時間以内に2系統の電動補助給水ポンプを起動し、動作可能であることを確認します。
(当院の対応)
当院では現地駐在の保安検査官により、保安規定に定める措置状況について確認します。
なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。
運転上の制限とは、多重の安全機能を確保するため、予備も含めて動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数が定められているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行うことが求められます。なお、定められた時間内に当該機器を復旧させるか、または出力低下などの予め定められた措置を講ずれば、保安規定違反に該当するものではありません。
なぜ吐出圧力が低下したのか、全く問題にしていません。国民の安全などどうでもよいのです。規定に違反していなければ!