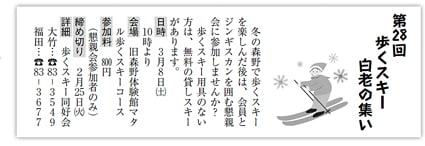少し固まった雪の上には色んなモノが落ちているのが良くわかる。
今日の散歩で見つけた。雪上の落とし物 キハダ 冬を楽しく元気に里山散歩 に書いた、キハダの実を野鳥が食べているらしい。

となりにあるのは赤い実だ。

萩の里自然公園にまだ残っている赤い実は、カンボクとガマズミをよく見かける。
公園の外の街路樹ナナカマドにも赤い実が付いている。
学校の校庭の周囲のナナカマドの下。ヒヨドリが数羽騒がしく鳴いていた。

ナナカマドの実と種 ↓ 米粒型を見ると 先?が曲がっている。

カンボクの実を潰してみた。種は平たい形をしていた。

ガマズミは


野鳥が栄養分を取り込むようにはいかないが、ガマズミではないだろうか。
http://www.specialsite.city.niigata.jp/akihaku/zukan/shinrin/cat44/
ウヨロ川の河畔にもう一つ赤い実が落ちていた。


食べこぼしたツルウメモドキの実もあり、上には蔓に残っているのが見えるので間違いないだろう。
もったいない? グルメ? 野鳥の食べ方
木と森と野鳥たち(千葉県野鳥の会会長 富谷 賢三氏)に興味深いことが書かれています。
http://homepage3.nifty.com/kinoinochi/bulletin/bird.html
野鳥は空を飛ぶために体が軽くなる工夫をしている。骨が中空で特殊な構造をしている。重たい歯もなくしてしまった代わりに、餌もカロリーが高く、消化の良いものを食べ、いつまでも体内に残しておかないように、前胃(腺胃)と筋胃(砂嚢、いわゆる砂肝)という鳥特有の消化器を備えている。食べられた樹の実は、果肉や果皮は鳥の体内で消化されますが、ほとんどの種子は消化されず、ペリットとして吐き出されるか、糞として排泄され、もとの親の樹から数十mから数百m、条件が揃えば数kmも離れたところに落とされます。そして発芽し、その種に適した環境で成長したものが新たな樹となります。(極一部を転載)
このBlogをしばしば訪問していただいている秋櫻(コスモス)さんによると、キハダの実はエゾモモンガの好物でもあるといいます。
野鳥と高病原性鳥インフルエンザ (日本野鳥の会)には、そう気にするものでは無いらしいが、念のために、ペリットや糞には触らないように注意している。
樹木種子写真図鑑 http://fox243.hucc.hokudai.ac.jp/moni1000/fieldguide/seed_guide/seed_guide.html
樹のタネ http://www6.ocn.ne.jp/~yoinaegi/