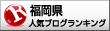(つづき)
過去記事に光を当てるシリーズの3回目。
今回は、過去に書いた記事に一部加筆&再構築することにより、天神地区の「バス乗り場」について思うところをまとめたみた。
---------------------------
西鉄バスの現在の「天神北」バス停は、かつて「天神(ショッパーズ前)」だった。
また、現在の「天神警固神社三越前」は「警固神社前」であり、「天神南」と「天神一丁目」はかつては「渡辺通四丁目」だった。
この変更は、1997年9月、ソラリアターミナルビルのオープンとともに行われた。
すなわち、「天神(ショッパーズ前)」が「天神北」となることで、マツヤレディス、フタタ、ショッパーズダイエーなどがあるエリアは天神地区の「はずれ」として位置づけられたことになった。
逆に、天神の南側の「警固神社前」や「渡辺通4丁目」など、それまで天神の名を冠していなかったエリアに「天神」の名がついた。
それまでのパラダイムが大きく転換した瞬間である。
ここ10年~15年の天神地区は、人の流れが変化し、「天神地区の重心が南に動いている」と言われてきた。
この背景には、バス停名を変えることによる心理的な誘導作戦もあったのではないだろうか。
現在、「天神」地区にはたくさんのバス停があり、「乗り場番号」で区別されるとともに、「天神協和ビル前」「天神新天町入口」「天神大和証券前」など、「天神」の下に様々なコトバが付くことによっても区別されている。
ただ、「天神○○」というのが、「天神」という大きなカテゴリーの中のひとつの乗り場である場合(Aとする)と、「天神」とはまた別のバス停として扱われる場合(Bとする)がある。
「天神協和ビル前」「天神新天町入口」「天神大和証券前」などはAであり、ここではその意味で、「天神(協和ビル前)」「天神(新天町入口)」「天神(大和証券前)」と表現することにする。
「天神コア前」もAなのだが、「天神コア」という建物の前にあるバス停なので、意味的には「天神(天神コア前)」となり、呼び方を厳密にすれば「天神天神コア前」ということになる。
「天神バスセンター三越前」も同様に、「天神天神バスセンター三越前」ということになる。
ただし、「天神郵便局前」は、その前にある郵便局は「天神郵便局」ではなく「福岡中央郵便局」なので、意味が「天神(郵便局前)」だと考えれば、呼称が「天神郵便局前」でも一応問題はない。
この考えを援用すると、「天神三丁目」もAなので、意味は「天神(天神三丁目)」、呼び方は「天神天神三丁目」ということになるのだが、「天神(三丁目)」だと解釈すれば「天神三丁目」という呼び方でも一応矛盾はない。
一方で「天神四丁目」はBであり、「天神(四丁目)」ではなく、意味的にも呼び方的にも「天神四丁目」で正解となる。
「天神北」は、もともと「天神(ショッパーズ前)」でありAであったものが、先に述べた「天神の重心を南に移そう」という「策略」(?)のもと、「天神」から外れたような名前に変わったものであり、AからBに一歩足を踏み入れたような位置付けになっているのだが、運賃などの面からみると依然Aに属すると考えられるので、意味的には「天神(北)」ということになる。
もともと「渡辺通四丁目」だったバス停のうち、現在の「天神南」はB、現在の「天神一丁目」はAに、それぞれ属している。
上記「策略」により、外見上どちらもAになったようにもみえるが、実態は依然として「天神南」はB、現在の「天神一丁目」はAであり、前者は「天神(南)」ではなく「天神南」、後者は「天神(一丁目)」ということになる。
ちなみに、北九州市戸畑区の「天神四角」は「天神(四角)」ではなく「天神四角」、春日市の「天神山」は「天神(山)」ではなく「天神山」、熊本市の「味噌天神」は「(味噌)天神」ではなく「味噌天神」である。
ここ最近まで続いてきた北天神地区の衰退を伴う天神の重心の南下は、今後もずっと続いていくという訳でもなく、ある程度のところで限界点を迎えている感がある。
また、南とともに西にも及んでいた面的な拡大も、天神地区以外のライバルの台頭もあり、波がひくように再び東に戻ってきている(なお、ここでの方角は、実際の方角ではなく福岡仕様)。
今後、天神地区の来街者数を維持し、バスによる回遊性をより高めていくためには、上で述べたような「天神」という名前を冠していても「天神」とは扱われないバス停があるというようなわかりにくい状況に早々にピリオドを打ち、「天神」というバス停をもう少し拡大解釈する必要があるのではないかと思う。
例えば、現在Bに属している「市役所北口アクロス福岡前」「天神四丁目」「西鉄グランドホテル前」「那の津口」「渡辺通二丁目」などもAに編入すれば、博多駅~西鉄グランドホテル前間や赤坂門~市役所北口アクロス福岡前(西鉄イン福岡最寄りのバス停)などが100円で移動できるようになり、都心部内をバスで移動することの後押しになるのでは?といつも考えている。
また、かつての「8番 荒江循環線」のように、「赤坂門~天神~警固神社前(現在の天神警固神社三越前)」のような、「天神をまたぐカタチでの都心部内の移動(以下、TMIと呼ぶことにする)」の手段を提供していくことも必要なのではないだろうか。
現在、天神地区にこれだけ大量のバスが乗り入れているにもかかわらず、「TMI」が可能な方向は限られており、天神で一回降りて、乗り換えのために乗り場の間をかなり歩くということも多い。
「60番 桧原循環線」が健在の頃(厳密には、その後を受けた「61番」西公園行きの廃止まで)は、「赤坂門~天神~渡辺通一丁目」という移動が可能であったし、「72番」の渡辺通一丁目行き、「34番」の福岡競艇場行きなどがあった頃は、天神より東側の昭和通り(蔵本方面)から天神の南北地区への移動ができた訳で、今と比較すれば「TMI」の選択肢がかなり多様だったといえる。
「TMI」の選択肢が増えることは、すなわち、天神地区の交差点でいろんな方向に曲がるバスが出てくることを意味するため、そのことが「さらなる渋滞の原因になる」という懸念や批判もあるだろう。
ただ、何事も「バランス」なので、現時点で過剰と思われるものを調整するなどして「TMI」を高めて、バスを都心部内の移動手段としてもっと有用なものとすることについても検討する余地はあるのではないだろうか。
---------------------------
(つづく)
過去記事に光を当てるシリーズの3回目。
今回は、過去に書いた記事に一部加筆&再構築することにより、天神地区の「バス乗り場」について思うところをまとめたみた。
---------------------------
西鉄バスの現在の「天神北」バス停は、かつて「天神(ショッパーズ前)」だった。
また、現在の「天神警固神社三越前」は「警固神社前」であり、「天神南」と「天神一丁目」はかつては「渡辺通四丁目」だった。
この変更は、1997年9月、ソラリアターミナルビルのオープンとともに行われた。
すなわち、「天神(ショッパーズ前)」が「天神北」となることで、マツヤレディス、フタタ、ショッパーズダイエーなどがあるエリアは天神地区の「はずれ」として位置づけられたことになった。
逆に、天神の南側の「警固神社前」や「渡辺通4丁目」など、それまで天神の名を冠していなかったエリアに「天神」の名がついた。
それまでのパラダイムが大きく転換した瞬間である。
ここ10年~15年の天神地区は、人の流れが変化し、「天神地区の重心が南に動いている」と言われてきた。
この背景には、バス停名を変えることによる心理的な誘導作戦もあったのではないだろうか。
現在、「天神」地区にはたくさんのバス停があり、「乗り場番号」で区別されるとともに、「天神協和ビル前」「天神新天町入口」「天神大和証券前」など、「天神」の下に様々なコトバが付くことによっても区別されている。
ただ、「天神○○」というのが、「天神」という大きなカテゴリーの中のひとつの乗り場である場合(Aとする)と、「天神」とはまた別のバス停として扱われる場合(Bとする)がある。
「天神協和ビル前」「天神新天町入口」「天神大和証券前」などはAであり、ここではその意味で、「天神(協和ビル前)」「天神(新天町入口)」「天神(大和証券前)」と表現することにする。
「天神コア前」もAなのだが、「天神コア」という建物の前にあるバス停なので、意味的には「天神(天神コア前)」となり、呼び方を厳密にすれば「天神天神コア前」ということになる。
「天神バスセンター三越前」も同様に、「天神天神バスセンター三越前」ということになる。
ただし、「天神郵便局前」は、その前にある郵便局は「天神郵便局」ではなく「福岡中央郵便局」なので、意味が「天神(郵便局前)」だと考えれば、呼称が「天神郵便局前」でも一応問題はない。
この考えを援用すると、「天神三丁目」もAなので、意味は「天神(天神三丁目)」、呼び方は「天神天神三丁目」ということになるのだが、「天神(三丁目)」だと解釈すれば「天神三丁目」という呼び方でも一応矛盾はない。
一方で「天神四丁目」はBであり、「天神(四丁目)」ではなく、意味的にも呼び方的にも「天神四丁目」で正解となる。
「天神北」は、もともと「天神(ショッパーズ前)」でありAであったものが、先に述べた「天神の重心を南に移そう」という「策略」(?)のもと、「天神」から外れたような名前に変わったものであり、AからBに一歩足を踏み入れたような位置付けになっているのだが、運賃などの面からみると依然Aに属すると考えられるので、意味的には「天神(北)」ということになる。
もともと「渡辺通四丁目」だったバス停のうち、現在の「天神南」はB、現在の「天神一丁目」はAに、それぞれ属している。
上記「策略」により、外見上どちらもAになったようにもみえるが、実態は依然として「天神南」はB、現在の「天神一丁目」はAであり、前者は「天神(南)」ではなく「天神南」、後者は「天神(一丁目)」ということになる。
ちなみに、北九州市戸畑区の「天神四角」は「天神(四角)」ではなく「天神四角」、春日市の「天神山」は「天神(山)」ではなく「天神山」、熊本市の「味噌天神」は「(味噌)天神」ではなく「味噌天神」である。
ここ最近まで続いてきた北天神地区の衰退を伴う天神の重心の南下は、今後もずっと続いていくという訳でもなく、ある程度のところで限界点を迎えている感がある。
また、南とともに西にも及んでいた面的な拡大も、天神地区以外のライバルの台頭もあり、波がひくように再び東に戻ってきている(なお、ここでの方角は、実際の方角ではなく福岡仕様)。
今後、天神地区の来街者数を維持し、バスによる回遊性をより高めていくためには、上で述べたような「天神」という名前を冠していても「天神」とは扱われないバス停があるというようなわかりにくい状況に早々にピリオドを打ち、「天神」というバス停をもう少し拡大解釈する必要があるのではないかと思う。
例えば、現在Bに属している「市役所北口アクロス福岡前」「天神四丁目」「西鉄グランドホテル前」「那の津口」「渡辺通二丁目」などもAに編入すれば、博多駅~西鉄グランドホテル前間や赤坂門~市役所北口アクロス福岡前(西鉄イン福岡最寄りのバス停)などが100円で移動できるようになり、都心部内をバスで移動することの後押しになるのでは?といつも考えている。
また、かつての「8番 荒江循環線」のように、「赤坂門~天神~警固神社前(現在の天神警固神社三越前)」のような、「天神をまたぐカタチでの都心部内の移動(以下、TMIと呼ぶことにする)」の手段を提供していくことも必要なのではないだろうか。
現在、天神地区にこれだけ大量のバスが乗り入れているにもかかわらず、「TMI」が可能な方向は限られており、天神で一回降りて、乗り換えのために乗り場の間をかなり歩くということも多い。
「60番 桧原循環線」が健在の頃(厳密には、その後を受けた「61番」西公園行きの廃止まで)は、「赤坂門~天神~渡辺通一丁目」という移動が可能であったし、「72番」の渡辺通一丁目行き、「34番」の福岡競艇場行きなどがあった頃は、天神より東側の昭和通り(蔵本方面)から天神の南北地区への移動ができた訳で、今と比較すれば「TMI」の選択肢がかなり多様だったといえる。
「TMI」の選択肢が増えることは、すなわち、天神地区の交差点でいろんな方向に曲がるバスが出てくることを意味するため、そのことが「さらなる渋滞の原因になる」という懸念や批判もあるだろう。
ただ、何事も「バランス」なので、現時点で過剰と思われるものを調整するなどして「TMI」を高めて、バスを都心部内の移動手段としてもっと有用なものとすることについても検討する余地はあるのではないだろうか。
---------------------------
(つづく)