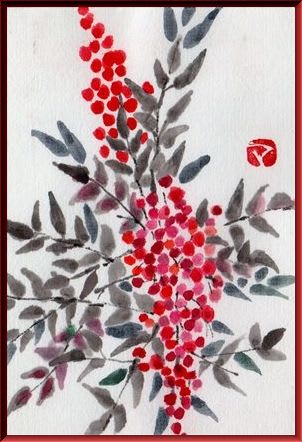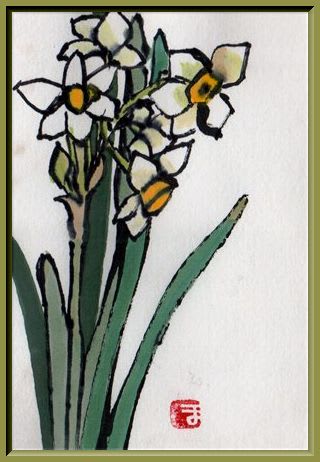さまざまな出来事が集中して、心身ともに疲れ気味です。
夜が十分に眠れませんし、物忘れもひどく、何もやる気がでないので、ブログもしばらくお休みにさせていただいています。
引きこもりがちなのを心配したケアマネージャーの勧めもあって、気分転換と体力維持のためと思って、私も午後から3時間だけのリハビリ専門のデイサービスに通い始めました。
あるじがデイサービスに出かける日に、予定では週二日、送迎付きで出かけることになっています。
開設2年目の施設は快適で、ウォーターベッドやホットパックのほか、1対1のPTさんの施術もあり、後は渡されたプログラムを、機具を使っての自主トレです。
うっすらと汗をかいて、なんとなく体が軽くなるような気がしています。
体調が戻りましたら、ブログも月末位には再開できるかと思います。ご訪問くださる方には申し訳なくお詫び申し上げます。



夜が十分に眠れませんし、物忘れもひどく、何もやる気がでないので、ブログもしばらくお休みにさせていただいています。
引きこもりがちなのを心配したケアマネージャーの勧めもあって、気分転換と体力維持のためと思って、私も午後から3時間だけのリハビリ専門のデイサービスに通い始めました。
あるじがデイサービスに出かける日に、予定では週二日、送迎付きで出かけることになっています。
開設2年目の施設は快適で、ウォーターベッドやホットパックのほか、1対1のPTさんの施術もあり、後は渡されたプログラムを、機具を使っての自主トレです。
うっすらと汗をかいて、なんとなく体が軽くなるような気がしています。
体調が戻りましたら、ブログも月末位には再開できるかと思います。ご訪問くださる方には申し訳なくお詫び申し上げます。