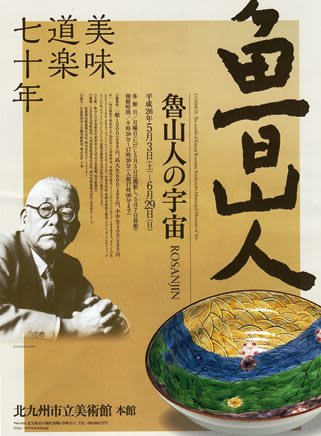今回の旅を記念してアルバムに残しました。その中のメモリーです。愉しかった団欒風景は、人物像が多くて憚りがありUPできないので、思い出に残る風物をブログにも残します。
部屋の窓から眺めたスカイツリーの一日の変貌する姿。東京博物館の「国宝展」。浅草寺の朝詣り。改装なった羽田空港の中の小さな美術館の催し。4日間、毎日のホテルレストランでの食事などなどです。ただ、場所柄もあり。写真を撮るのを遠慮したので控えめです。
計画されていたのは、到着の日は休息。ホテルのレストランで夕食。2日目の日曜日は朝はホテルで静かな和食レストラン「歌留多」。昼食は歩いて数分の「今半」。夜はホテルの最上階27階の「唐紅花」で中華料理でお祝いの席。3日目と、4日目は、名高いこのホテルの朝食バイキング。昼食と夕食は は外出先で。となっていたみたいですが、予定の、歌舞伎見物も、夜のツリーから夜景を眺めるというのも、疲れたからというのでキャンセル。車いすで久しぶりに浅草寺の朝詣りをして、「蕎麦」をいただいてきました。
夜も、「あなただけでも出かけたら」と勧められましたが、またの機会に取っておくことにして部屋で過ごしました。最後の日の夕食はまた和食の「歌留多」の懐石になりました。
部屋の窓から眺めたスカイツリーの一日の変貌する姿。東京博物館の「国宝展」。浅草寺の朝詣り。改装なった羽田空港の中の小さな美術館の催し。4日間、毎日のホテルレストランでの食事などなどです。ただ、場所柄もあり。写真を撮るのを遠慮したので控えめです。
計画されていたのは、到着の日は休息。ホテルのレストランで夕食。2日目の日曜日は朝はホテルで静かな和食レストラン「歌留多」。昼食は歩いて数分の「今半」。夜はホテルの最上階27階の「唐紅花」で中華料理でお祝いの席。3日目と、4日目は、名高いこのホテルの朝食バイキング。昼食と夕食は は外出先で。となっていたみたいですが、予定の、歌舞伎見物も、夜のツリーから夜景を眺めるというのも、疲れたからというのでキャンセル。車いすで久しぶりに浅草寺の朝詣りをして、「蕎麦」をいただいてきました。
夜も、「あなただけでも出かけたら」と勧められましたが、またの機会に取っておくことにして部屋で過ごしました。最後の日の夕食はまた和食の「歌留多」の懐石になりました。