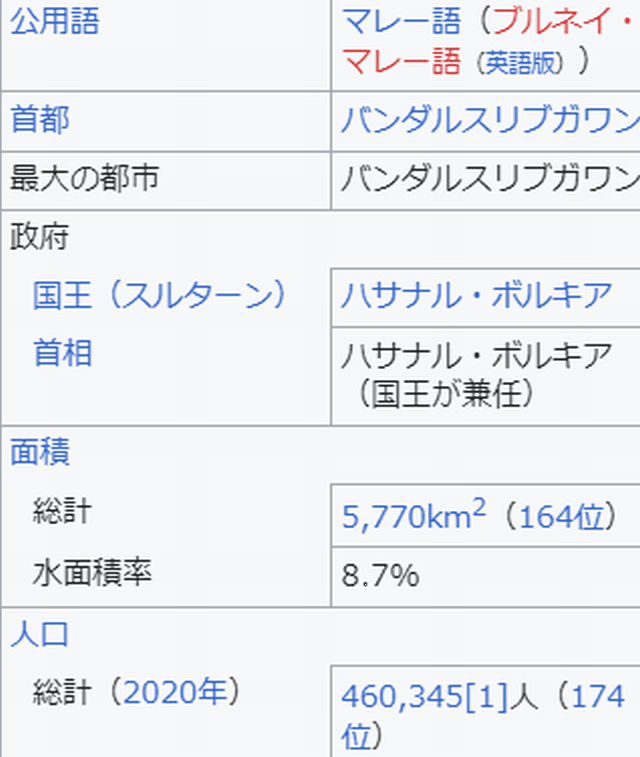🌸檀家制度全廃、郵送で納骨、葬儀や戒名料金を定額化
☆埼玉県の住職が手掛けるお寺の大改革と「お寺のコンビニ化」
⛳売り上げ低迷から回復できていない寺院業界
☆仏教界全体のコロナ前の総収入は約5700億円
*2020年には半分以下の約2700億円に激減
*2023年は、4000億円程度だが、コロナ前の数字には程遠い
*廃寺を考える寺院も出始めている
☆業界の常識を覆す経営方針で、関係者の注目を集めるている寺
☆寺の将来を考えた、曹洞宗見性院の橋本英樹住職
*見性院を引き継ぎ、2年かけて檀家制度を廃止した
*檀家といえば月々の檀家料などを払ってくれる、“お寺の生命線”
*橋本住職は「実は足かせにもなるんです」と語った
*父から代替わりして、見性院の檀家さんは400軒ほど
*高齢化など影響もあって檀家は減少傾向だったという
⛳寺の存続が危ぶまれる状況
☆抜本的な改革が必要だと感じた橋本英樹住職
*何かやろうとすると、互助会の総意を取り付ける必要がある
*なかなか思うようなことができない
☆檀家そのものを廃止して
*やりたいようにやろうと考えた
⛳変化を望まない勢力からの大きな抵抗
☆変化を望まない勢力の抵抗は大きかった
*檀家で結束して住職を追い出したほうが
*見性院のためになるのでは、といった議論まで出た
☆本山からはお叱りを受けたが
*信念を曲げずに、説明と説得を続け、檀家制度の廃止にこぎつけた
*信徒と寺の付き合いが途絶えるわけではない
*檀家料や互助会費のかからない会員制度に移行した
*定期的に入っていた檀家料などがゼロになったわけで
*寺としての新たな収入を確立する必要があった
⛳橋本英樹住職は、供養墓の安置は1年1万円で計算した
☆橋本住職が考えたのが「送骨」のサービス
*通夜・葬儀を省略した直葬や炉前葬などを選ぶ人
*増える流れを踏まえての考えだった
☆都市部ではお墓を持たない人が増えている
*火葬したお骨の納め場所に悩む人も増えている
*ゆうパックなどでお骨を送ってもらい
*こちらで供養、納骨する『送骨』を始め、費用は3万円
*「送骨」は問い合わせから契約まで、ネット・電話で済ませられる
*3万円と送料を振り込むと後日お骨の発送に必要となる
*段ボールなどのセットが送られてくる
☆供養が終わったお骨は、供養墓に安置され数年後に合祀墓へ移される
☆長期間、供養墓に置いておきたいという方には
*10年、20年、30年コースを用意し、料金は1年1万円の計算
*『送骨』を始めて今年で8年目、700霊ほどをお預かりしている
⛳橋本住職が目指すのは「お寺のコンビニ化」
☆橋本住職は、葬儀や戒名にかかる料金を定額化している
*領収書を発行等、葬送にかかるお金の見える化もいち早く行なった
☆橋本住職は語る
*業界の一部からは白い目で見られているが
*しかし、改革のスピードを緩めるつもりはない
*誰もが自由に使えるお寺運営を今後も続けていこうと思っていると
*檀家を収入源とする業界の常識を覆すことで
☆突破口を開いた、橋本住職の試みは続く
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『マネーポスト』

檀家制度の廃止とお寺のコンビニ化
(『マネーポスト』記事より画像引用)