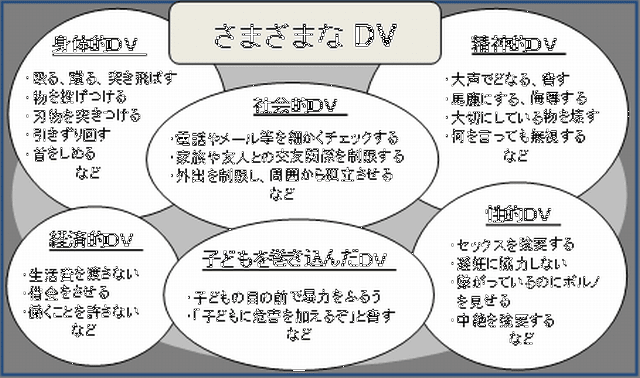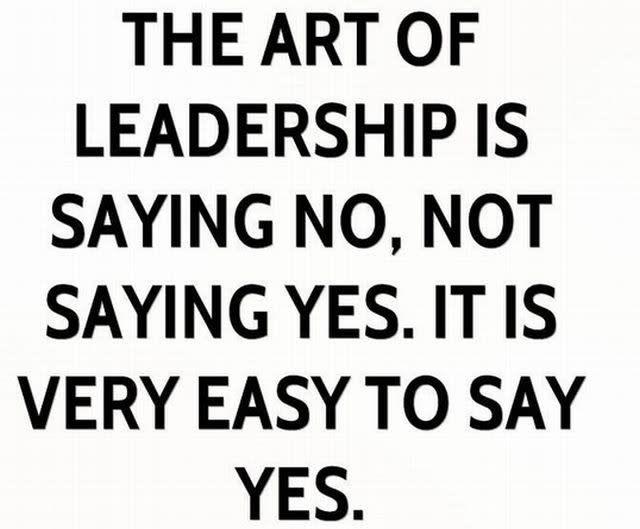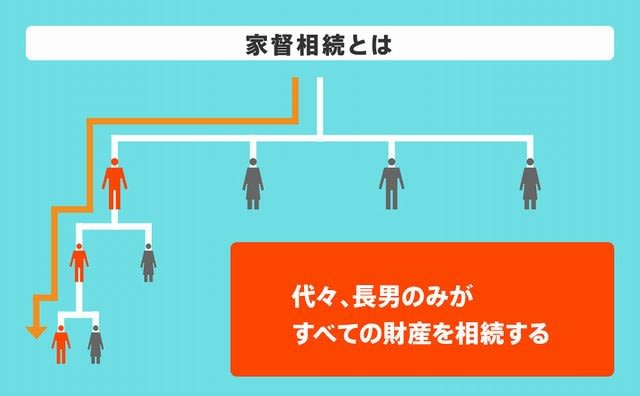🌸ポリコレと言葉づかい2
⛳身体的暴力から心理的暴力へ
☆ポリコレとは、わたしたちが試行錯誤しながらつくりあげている
*グローバル空間のルール・規範
☆誰かがルールを設定すれば、それは別の誰かの
*「俺たちのルール」を踏みにじったり、既得権を侵している
*結果「正しさ」を巡る政治闘争が勃発することになった
☆最初にアメリカでポリコレが生まれたのは
*多様な人種・民族が混在する「人工国家」であり
*グローバル世界の縮図だったからだ
☆アメリカでつくられたポリコレのルール
*グローバルスタンダードになることを
*「陰謀」のようにいうのは正しくない
☆アメリカでは、人種問題で抗議運動が繰り返されるように
*アメリカは差別にきわめて敏感な社会である
*そこで決まった約束事が世界中で共有されている
☆ルールが定まれば、それに反する言動は不道徳・不適切とされ
*場合によつては処罰の対象になる
☆生存への最大の脅威は、いうまでもなく暴力だ
*暴力・性暴力は忌むべきものとされている
☆学校や家庭内での暴力(体罰やしつけ)
*夫婦や恋人間での性暴力などは、ある程度黙認されていた
*それが犯罪であるとの認識が広がったのは近年のことだ
☆近代国家がひとびとから支持された理由
*暴力の脅威に効果的に対処したからだ
*軍隊や警察によって暴力を独占し
*私闘を禁じて、紛争は法によって解決することを強制した
*法治国家、市民は司法で理不尽な暴力から保護されている
☆第二次世界大戦が起されば人類は絶減する理由で
*先進諸国は長い平和と経済成長を謳歌した
*殺人や強盗などの重犯罪も一貫して減少しており
*わたしたちは人類史上、もっとも安全な社会で暮らしている
☆近代国家の前身は身分制社会
*身分の低い者や女性、黒人などのマイノリティには
*完全な人権や市民権はなかった
☆リベラリル(自由主義)の原則
*国家は国民を無差別(平等)に扱わなければならず
*特定の集団を支配層として、別の集団を従属させることは許されない
☆現在でも、中国(新彊)やミャンマー(ロヒンギャ族)などで
*国家による人権抑圧が行なわれているものの
*欧米や日本のような先進国では法制度をめぐる対立は
*より微妙なものに移行している
☆日本では刑法の性犯罪規定の見直しが議論になっている
*同意のない性行為の犯罪化を目指す被害者団体と
*客観的な証拠なしに「同意していない」との主張だけで
*処罰されるのでは冤罪の温床になると懸念する人権派弁護士の
*「リベラル」同士の対立が起きている
☆アメリカで、過去男子選手だったトランスジェンダーの水泳選手
*大学選手権で優勝し、社会を二分する議論を引き起こしている
*同様の事態は他の競技でも起きている
☆法制度による差別が解消していくにつれて
*それでは、救済できない差別が強く意識されるようになる
☆社会的な存在であるヒト
*他者に傷つけられることにものすごく敏感だ
*「制度的な暴力」解決すれば、社会的・文化的に構築された
*「心理的な暴力」が前景にせり出してくる
⛳日本は「さん」づけでアメリカは呼び捨て
☆小学生の娘が学校での出来事を話すのを聞き
*筆者の知人は強い違和感を抱いたという
☆ジェンダーフリーが徹底された最近の公立学校
「男も女も「さん」づけなんですよ」と知人はぼやいた
☆会社でも、かっては上司が部下を、先輩が後輩を呼び捨でにし
*上司を役職で呼ぶのが当たり前だった
*いまでは役職や年齢、入社年次にかかわらず
*「さん」づけで統一するところが増えている
*社長が平社員を呼び捨てにするとパワハラだと思われそうだ
☆欧米では、役職にかかゎらず、社員同士
*フアーストネームを呼び捨てにするのが常識になっている
*日本の会社で、新入社員が社長に「一郎」などと呼びかけたら
*その場が凍りつくだけではすまないだろう
☆日本とアメリカの呼称の変化には共通するものがある
*それは、「全員を平等に扱う」ことだ、誰かを呼び捨てにして
*別の誰かに「さん」や「ミスター」をつけること
*現在の価値観では不適切だと見なされる
☆なぜ全員の呼称を統一しなければならない理由
*相手との「距離」を同じにするためだ
☆リベラル化する社会、パブリックな場で呼称の使い分け
*恣意的に距離を操作することは許されなくなってきた
⛳敬語を使うと失礼になる場合もある
☆敬語や敬称は、相手への尊敬を示す言葉だとされいるが
*マジョリティとは異なる扱いをマイノリティが受けるとき
*それが敬語・敬称であっても「差別」になり得る
☆わたしたちは言葉づかいを微妙に変えることで
*つねに相手との距離を調整している
☆敬語や敬称には、相手との距離を遠くする効果がある
*これが「近づきがたい」という印象を生じさせる
☆「敬して遠ざける」といわれるように
*敬語には相手を疎外・排除する効果もあ
*白人社員たちから自分だけが敬称で呼びかけられたら
*黒人社員は強い疎外感を覚えるにちがいない
☆「さん」や「ミスター」などの呼称は相手との距離を広げ
*愛称や呼び捨ては距離を縮める
☆日本では、目上の者に親称を使うのはインポライト(失礼)
*親しい問柄で敬称を使うこともインポライトだ
☆敬語・敬称の遠隔化効果によって相手と距離をとることは
*「ネガティブ・ポライトネス」と呼ばれる
☆「ポジティブ・ポライトネス」は
*タメ語や親称の近接化効果によって相手との距離を詰めることだ
*相手との距離が適切であれば「ポライト」になる
☆現代の言語学では、わたしたちは言葉づかいを微妙に変え
*つねに相手との距離を調整している
☆ポリコレのコードでは
*役職や(男女のような)属性にかかわらず
*社内全員の言語的な距離を同じにしなければならない
☆日本では、ネガティブ・ポライトネスによって
*社長から平社員まですべての社員を「さん」づけするようになった
☆アメリカでは、同じことをポジティブ・ポライトネスで行なっている
*いまは、黒入社員は「ジム」「ジミー」などと呼ばれている