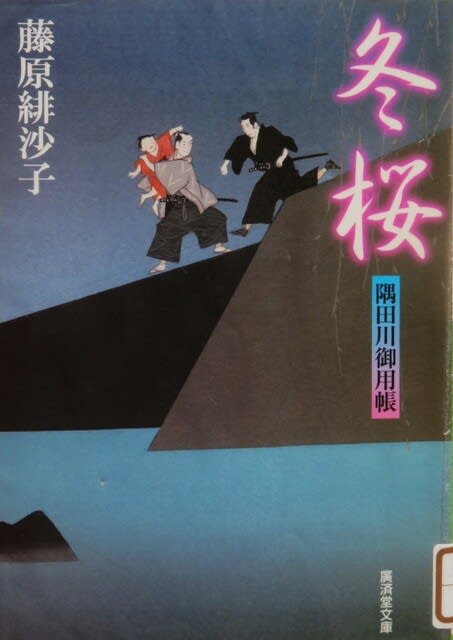図書館から借りていた、葉室麟著 「無双の花」(文藝春秋)を、読み終えた。本書は、九州戦国史を代表する武将の一人、立花宗茂(たちばなむねしげ)の半生と、その妻誾千代(ぎんちよ)を題材にして描いた、長編時代小説だった。
読んでも読んでも、そのそばから忘れてしまう老脳。
読んだことの有る本を、うっかりまた借りてくるような失態を繰り返さないためにも、
その都度、備忘録として、ブログ・カテゴリー「読書記」に、書き留め置くことにしている。

▢目次
(一)~(十七)
▢主な登場人物
立花左近将監宗茂(豊後大友宗麟の家臣筑前宝満城城主高橋紹運の嫡子、立花誾千代の婿養子となり立花城城主、柳川城城主、赤館城城主、再び柳川城城主、立斎)
誾千代(豊後大友宗麟の重心立花(戸吹)道雪の娘、立花城女城主、立花宗茂の正室)、かの、由ゑ
八千子(立花宗茂の側室、矢島石見の姉)、菊子(公家葉室家の姫、後に、立花宗茂の妻となる)
立花(戸吹)道雪(誾千代の父、筑前立花城城主)
由布雪下(ゆふせっか)、矢島石見(やじまいわみ)、十時摂津(とときせっつ)
黒田如水、加藤清正、田中忠政
豊臣秀吉、本田平八郎忠勝、
真田左衛門佐信繁(幸村)、利世、大八(後に、伊達忠宗の家臣片倉守信となる)、阿梅(後に、片倉小十郎の妻となる)、阿菖蒲、おかね、
長宗我部盛親、
徳川家康、徳川秀忠、徳川家光、本田正信、本田正純、
伊達政宗、片倉小十郎重綱、
▢あらすじ等
筑前宝満城城主高橋紹運の嫡男として生まれた宗茂だったが、15歳で大友宗麟の重臣、立花城城主戸次(立花)道雪の娘誾千代の婿養子となり、立花山城主となった。城主になってまもなく、九州の雄、島津勢の猛攻を受けるが、これに耐え切り、駆け付けた豊臣秀吉から、「西国無双の武将」と褒め称えられ、戦功により筑後柳川十三万石の大名に抜擢された。
その恩義が有り、関ヶ原の戦いでは、西軍に加担、敗軍の大名となり、徳川家康の時代になり、当然、改易、浪人となる。家臣を引き連れて、京、江戸へ。耐えに耐え、窮乏の日々を送ることになるが、人を裏切らず、生き抜き、「立花の義」を貫き、大名に返り咲く望みを捨てず、家康をも動かし、伊達政宗とも渡り合い、改易から20年後、家康の意を受け継いだ2代将軍秀忠により、ついに、旧領筑後柳川の大名に再封される。関ヶ原の戦いで西軍に加担し改易になり、浪人となった大名で、徳川家からも絶大な信頼を得て、旧領地を再封されたただ一人の武将立花宗茂の半生、生き様を描いた作品である。
「待たせたな、誾千代。ようやく戻って参ったぞ」
(中略)
「関ヶ原の戦で負けた時、かような日が来るとは思いも寄らなんだぞ。二十年前、
京に出ようと意を固めた折、必ず無双の花を咲かせて戻って参ると誓うたが、
いまにして思えば、わしにとって、無双の花とは、そなたのことであった・・・・」
(参考・参照)
👇️
福岡県観光WEBクロスロードふくおか
「立花宗茂、誾千代 ー 戦乱の世に生きたヒーロー&ヒロイン」
歴史にも疎く、無知無学な爺さん、正直なところ、「立花宗茂」、「誾千代」の名も、その史実も、これまで、ほとんど知らず分からずの類だったが、本書を読み、初めて詳しく知り、「へー!、そうだったのか」、目から鱗・・・・、である。
本書の舞台は、九州豊後、筑前、筑後、肥後、朝鮮半島、京、大阪、江戸、奥州南郷、と広いが、中心にしているのは、柳川。
福岡県筑後地方南西部に位置している「柳川市」は、若い頃から一度は訪ねてみたいと思っていた地のひとつだったが、結局、念願叶わず、一度も訪れたことは無く、今となっては、映像や画像で、その風情等を楽しんでいる風だが、本書により、一層、興味、関心が高まってきたような気がしている。