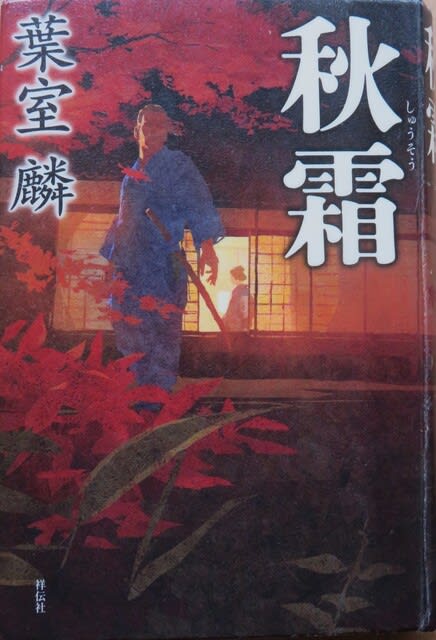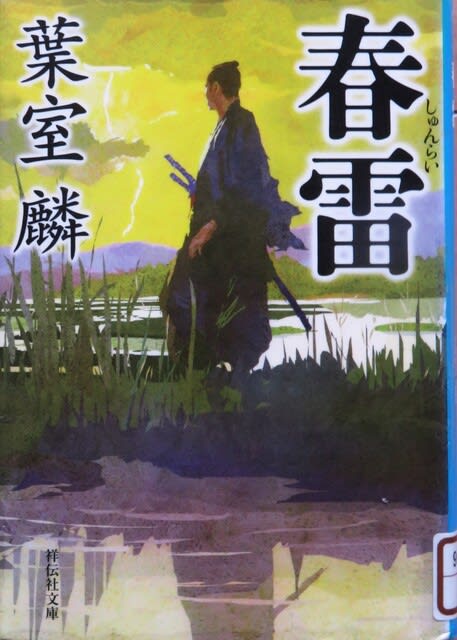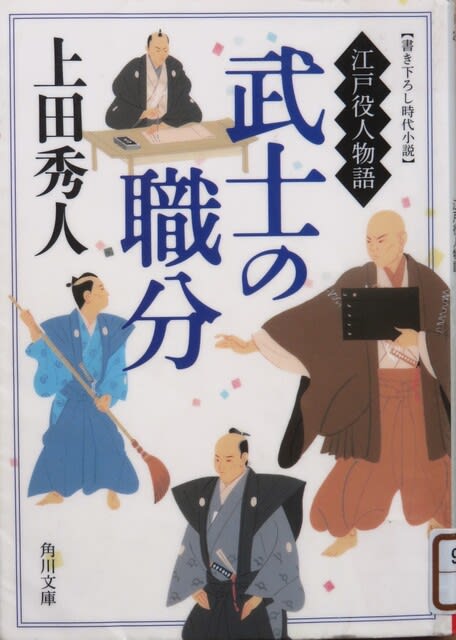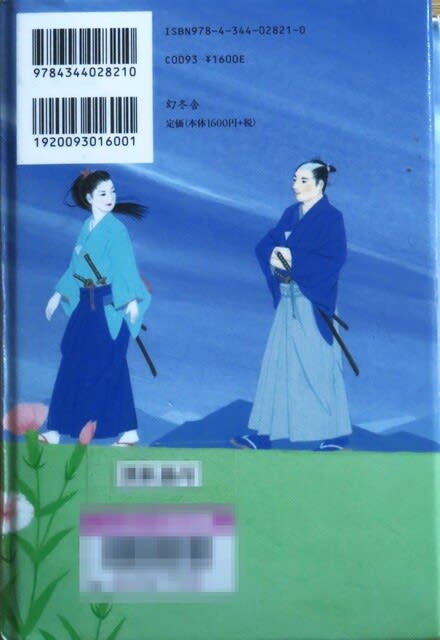図書館から借りていた、葉室麟著 「草笛物語」(祥伝社)を読み終えた。
本書は、著者創作の架空の小藩、九州豊後の「羽根藩(うねはん)」を題材にして描かれた長編時代小説「羽根藩シリーズ」の第5弾の作品である。
すでに、第1弾「蜩ノ記」、第2弾「潮鳴り」、第3弾「春雷」、第4弾「秋霜」は、読んでいるが、この第5弾「草笛物語」で、「羽根藩シリーズ」は、終わりのようだ。
毎度のこと、著者の筆致に引き込まれてしまい、あっと言う間に最後まで読んでしまったが、まだまだ続編が有ってもおかしくない内容で終っており、残念な感じすらしてしまう。
読んでも読んでも、そのそばから忘れてしまう老脳。
読んだことの有る本を、うっかりまた借りてくるような失態を繰り返さないためにも、
その都度、備忘録として、ブログ・カテゴリー「読書記」に、書き留め置くことにしている。

▢目次
(一)~(二十六)
▢主な登場人物
赤座颯太(主人公、あかざそうた、羽根藩藩士赤座兵庫・鶴の息子、鍋千代・藩主三浦吉通の小姓)、
水上岳堂(みずかみがくどう、赤座颯太の伯父)
戸田順右衛門(中老、鵙、戸田秋谷の息子、幼名郁太郎)・美雪(順右衛門の娘)、
佳代、
檀野庄三郎・薫・桃、
源吉・お春、
三浦吉通(羽根藩藩主、幼名鍋千代)、三浦吉房(前藩主)、三浦左近(三浦御一門、月の輪様)
吉田忠兵衛(羽根藩家老)、原市之進(羽根藩勘定奉行)、赤座九郎兵衛(羽根藩馬廻役)、
藤村平吾(鍋千代・藩主三浦吉通の小姓)、小林哲丸(鍋千代・藩主三浦吉通の小姓)、
寅吉、権助、三太、
▢あらまし等
読み進める内に、本書は、「羽根藩シリーズ」第1弾「蜩ノ記(ひぐらしのき)」ゆかりの人物が登場し、「蜩ノ記」の16年後の羽根藩を描いた作品であることに、気付かされる。
「蜩ノ記」は、羽根藩の要職にあった、主人公の戸田秋谷が、ある事件で蟄居の身となり、山深い村で家族と過ごし、三浦家家譜編纂を仕上げ、10年後、決められた通り切腹して果たした物語だったが、藩から見張り役として派遣され、秋谷を師と仰いだ若き檀野庄三郎がいた。
その庄三郎が、秋谷の娘薫(かおる)を娶り、娘桃と親子3人、すでに、藩の要職を離れ、相原村にある薬草園の番人をしている。さらに、秋谷の息子郁太郎(戸田順右衛門と名乗り)、中老となり、鵙殿(もずどの)等と呼ばれ、羽根藩藩政を動かす立場に上っているという時代背景、羽根藩の藩主家督相続騒動を縦軸にした物語になっている。
本書の主人公は・赤座颯太。颯太は、羽根藩江戸屋敷で生まれ育った13歳の少年で、羽根藩世子鍋千代の小姓だったが、両親が相次ぎ他界したため、伯父水上岳堂に身を寄せることになり、江戸から、豊後羽根藩へ。
そこに待ち受けていたものは・・・・。
国許では、家督相続を巡り、世子鍋千代を推す中老戸田順右衛門と、三浦家御一門の三浦左近を推す派が対立。鍋千代が新藩主三浦吉通となりお国入り、颯太は、再び藩主の小姓となり出仕することになるが、城内は陰謀策謀が渦巻き、月の輪様(三浦左近)が動き出し・・・・。
美雪が、お春が・・・、
どうする?、颯太、岳堂、壇野庄三郎、順右衛門、藩主吉通・・・、
「颯太はいずれ殿の側近として、うるさい重役であるおぬしを倒しにくるであろう」
庄三郎は順右衛門の横顔に目を遣りながら、何やら心楽しげにそう口にした。
「その日が楽しみです」
青く澄みわたった空を見上げるようにした順右衛門は、
ふっと笑みを浮かべてそう応えてから、庄三郎に呼びかけるように続けた。
「・・・・義兄上(あにうえ)」
蜩の鳴く声が空から降るように聞こえる。
で、終っている。
「ぴぃーーっ」・・・、表題「草笛物語」の「草笛」は、村の童たちがお互いの居場所を知らせるために吹く笛として、友を呼ぶ証しとして、随所で効果的に使われている。
本書は、「泣き虫颯太」と呼ばれていた少年赤座颯太が、次第に武士として成長してゆく姿が描かれており、若い藩主吉通と村の童達が連携して、月の輪様の暴挙を阻止しようとする場面等、陰湿陰謀の家督相続騒動が本筋ながらも、カラッと爽やか、「少年少女小説」のような要素も織り込まれた物語だった。