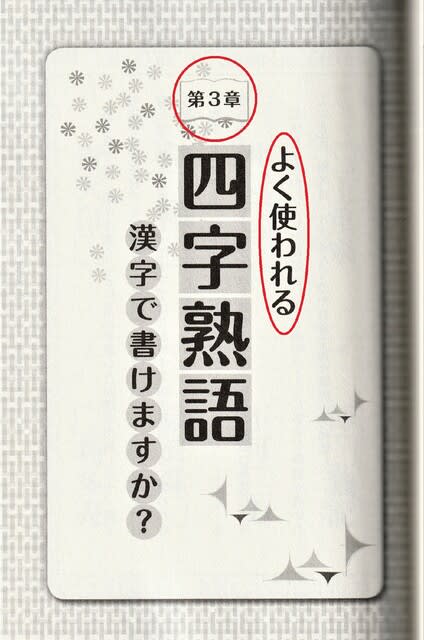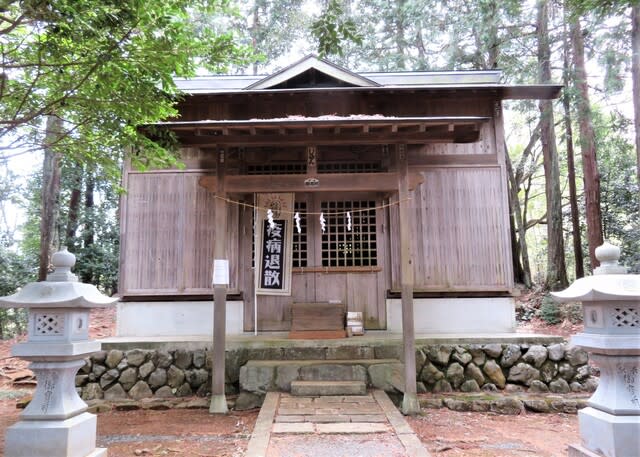鳥にも疎い爺さん、子供の頃から目の当たりにしていた スズメ、ツバメ、カラス、ハト位は、パッとみて直ぐに分かるが その他の野鳥については、実際に見ても 以前は、ことごとく「君の名は?」だった。
それが ブログをやるようになってからのこと、数多の方々の鳥の写真等を見て、次第に興味関心が湧き、散歩・ウオーキング途中、やたら写真を撮ってきたり、教えて貰ったり、自分で調べたりして、少しずつ分かる鳥が増えてきている。ただ、一度分かっても、そのそばから忘れてしまう老脳。ネット等から参照した情報を、記憶力減退老脳に代わる記憶補助として、ブログ カテゴリー 「爺さんの備忘録的鳥図鑑」に 書き留め置こう等と思っているところだ。(コピペ文)
3年前、2018年2月25日に、近くの川沿いを歩いていた時のこと、藪状の川岸になにやら見慣れない鳥が動いているのに気付き、少々撮りづらかったが なんとか2~3枚、コンデジでカシャ、カシャ、帰ってからネット等で調べてみると、自信は無かったが どうも クイナ(水鶏、秧鶏)だったことが分かった。最初で最後、あの時以後は、全く見かけることも無く、爺さんにとっては 貴重な写真が外付けHDに残っており、引っ張り出してみた。
「クイナ(水鶏、秧鶏)」
ツル目、クイナ科、クイナ属、
形態 全長 23cm~31cm、尾羽は短く、角張るか丸みを帯びる、
翼は短く、丸みを帯びる、嘴が長く、上が黒く、下が赤い。
分布 ユーラシア大陸、アフリカ大陸北部、北アメリカ大陸、インドネシア、
日本等 世界各地に 130種程が生息している。
沖縄の ヤンバルクイナもそのひとつ。
生態 湿原、湖沼、水辺、竹やぶ、水田等に生息、半夜行性、
食性は、昆虫、クモ、甲殻類、軟体動物、魚類、両生類、小型鳥類、
植物の茎や種等 雑食性