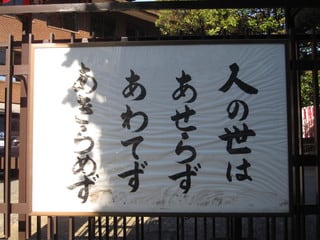連休初日、研究会出席のため京都へ。
午前6時台の東京発の新幹線のぞみのD席。
通路側の席です。
お隣は、恰幅のいいおじさん。
新幹線が動く前から、おもむろに駅弁を豪快に爆食。
朝一から、これだけ食べられるのは、ホントーにすごい!
完食されたあと、おもむろにリクライニングシートをフルに倒し、そして、睡眠の時間となりました。
車内の車掌さんの放送では、シートを倒すと後ろの方のテーブルのパソコン等が被害を受ける可能性があるので、ご注意を!というアナウンス・・・。
でも、隣のおじ様は、リクライニングシートを限界までフラット化・・・。
両手、両肘は、肘掛に思いっきりホールドさせてお休み。
隣の私は、お尻を思いっきり通路側にずらし、おじ様の肘があたらぬ様スライド。
D席のスペースが通常の8割方しかないんですけど・・・。
お休みの邪魔をすることもできないし・・・困った!
おじ様は、ビンボー席でも思いっきりグリーン車状態。
京都まで爆睡状態でした。
ホントーにすごい(笑)。
そもそも一列5席というJRさんの経営。
両方に人が座るB席は多少幅広に設定してあると、ものの本で読んだことがあります。
が、ユニバールデザインでいうと、かなり非人間的な状態です。
新幹線指定席、自由席にある肘掛・・・一体どっちの席のものなのでしょうか?
個人的な意見としては、どちらのものでもない・・・ということ。
肘掛の内側までは、双方の席の人が権利主張してもいいけれども、
肘掛の上には家族、親戚、恋人以外は乗せてはいけないのではないかということです。
日本人としてのおもてなしの心、ホスピタリティが必須の場面と言えると思います。
日本人としての気配りの肘掛・・・という基本的な考え方が大切なように思います。
隣のおじ様のおかげで、窮屈な思いをしながら京都に向った次第。
デッキに出て、小説を読んだり、スマホを見たり・・・。
徒然草の吉田兼好さんの言葉ではありませんが、これだから都人(みやこびと)でない方は???です。
いきなり京の都の逆コンセプトに遭遇・・・そのコントラストがいかにも面白き連休初日でした。
やれやれ。