秋と冬の稜線で

山歩雑談:霜月の雪山
昨日は今シーズン最初の雪山でした、笑
そんなワケで今日は昼ゴハン誘われて出た以外は@家だったんですけど、
昨日いた場所との落差アラタメテ思ったり、で、昨日ちょっと驚いたことアラタメテ。

登ったのは北奥千丈岳、標高2,601メートル・奥秩父山塊の最高峰です。
同じ登山口から花の百名山・国師ヶ岳→百名山・甲武信岳への縦走ルートに入ります。
この縦走ルートから逸れたポイントに北奥千丈岳があるんですけど、登山口の大弛峠から短時間で登れる山です。
標準タイムは大弛峠→北奥千丈岳まで片道1時間15分、大弛峠→国師ヶ岳もそれくらいなので日帰り充分できるルートになります。
↑
っていうふうに書くと、
「なーんだカンタンじゃん午後からでも楽勝だろw」
って思う人がいるんだろうなーと昨日あらためて思いました。
っていうのは・11月の山だっていうのにアイゼンも持たない不用意な人を多く見たからです。
11月の山でアイゼン持っていない人がどうなるか?
っていうと圧雪の氷に足もとが安定せず立往生→転倒滑落、遭難事故に陥ります。
そういう立往生サンを昨日は何人も見ました。

北奥千丈岳・国師ヶ岳までのルートは八割が木道です。
上の写真を見るとわかりますが、木道は板の下が空洞=橋と同じ状態になっています。
車を運転する人は経験アリだと思うんですけど、
橋=下が空洞=風が通る=低温下→凍結しやすいです。
また木道は通路=雪が踏まれる→圧雪→氷になる、いわゆるアイスバーン化しやすいワケです。
木道階段だと足を下ろす圧力が大きく=圧雪しやすく、新たな雪の下すぐ氷になっています。
ようするに「氷の階段」を歩くことになるわけです。
11月=秋=雪は降らない・と平地慣れしていると思いがち。
でも山の11月は降雪の季節です、雪が降らなくても霜が厚く積もるため凍結して薄氷が張ります。
天気予報を見て「けっこう温かいじゃん、零下じゃないし結氷とか嘘だろー」なんて大間違い、標高による気温低下を忘れずに。
また、山=県境な場合は地域またがる両方の天気から考える必要もあります。
標高による気温変化は季節によっても違いますが、
3,000メートル以下:1,000メートルで約5~6度
3,000メートル以上:1,000メートルで約10度
なぜ3,000メートルで気温変化が違うか?っていうと空気の湿度です。
標高3,000メートルを超えると湿度は低くなり乾燥します、乾燥空気のほうが気温低下ってことです。
北奥千丈岳や金峰山の登山口・大弛峠は標高2,365メートル。
大弛峠は山梨県甲府市にありますが、甲府地方気象台は標高273メートル。
↓
標高差2,092メートル=10~12度の温度差がある、ってことです。
甲府11月12日の気温は最高19.3度/最低8.7度→大弛峠は9度/零下3度くらいになります。
+
前日11月11日までに雨も降った。
↓
大弛峠では降雪、凍結が起きる。
最低気温が10度を下回る11月、山では零下がアタリマエってことです。
+
山は北斜面と南斜面で日照時間が違うため、気温もマッタク違います。
同じ斜面でも鬱蒼とした針葉樹林帯は暗い=日当たりが無い=気温が上がりません。

日向と日陰は気温差が大きい、
それが斜面の向きでずっと暗ければ気温差さらに大きくなります。
これは森の日当たりでも同じこと・10センチの距離でも日陰になれば氷が張ります、そのため、
↓
角を曲がったとたん足もとアイスバーン→転倒滑落、なんてことがフツーにあるワケです。
ここまで書くと解かると思うんですけど、
凍結は日照時間の影響も大きいため、標高が高くない山でもアタリマエに起きます。
北斜面・樹林帯で日照時間が少ない+谷から冷風が昇る、なんて条件下は冷蔵庫と同じだってことです。
こうした路面凍結は登山口に向かう林道でも同じこと、
カーブを曲がったとたんアイスバーン覆われている、なんてよくあります。
なので11月の山は車道もドライブ慎重に、スピードすこし落として路面凍結を予測しながらの運転が必要です。
11月の登山はアイゼンが欠かせません、軽アイゼンでも必ず持って行くこと。
もし忘れたなら登らない・ちょっとでも凍結があったら即回れ右、が安全を守ります。
林道の運転も同じこと、路面にアイスバーン発見したら危険信号です。
アイスバーンの走行は下り坂だとブレーキが利きにくく、難易度さらにUPします。
行きの登りは走れても帰りの下りはダメだ~~ってよくある話です。
↓
なのでイキナリ通行止め・イキナリ登山バス運休はよくあるコトです。
登山バスに乗ったけど途中で降ろされる、なんてコトも。
イキナリ降ろすなんてひどいなあ、って想う方もあると思います。
昨日も態度がナントカ話している登山客がいました、が、無理に運転走行して事故・死傷ナンテコトになるほうが不親切です。

アウトドアは楽しいです、その楽しさは自然に放りこまれる非日常感だろうなー思います。
その「非日常」っていうのは=「平地の感覚は通用しない」ってことです。
平地とは違う気温、天候変化、路面状況。
この違いが非日常感でもあるし、その違いから日常とマッタク違う事故も起こります。
たった一度のミス判断が大怪我・死亡事故になるなんてことは日常だと考えられないかもいれません、でもそれが山の日常です。
登山ブログもたくさんあって、テレビも登山番組たくさんあって、
登山やボルダリングやってますー宣言してくる芸能人イケメン俳優なんかも多くなって、
登山=「気軽にやれそうだなー」雰囲気ありますけど、気構え+知識技術がなくては即事故を起こします。
が、、、どれもイイとこしか採りあげない・注意喚起マッタクしないから、昨日みたいな立ち往生サンが多いんだろうと思います。
「あんまり大げさに危険言うのはカッコ悪いだろ?」
「こんな高い山でも簡単って言えちゃう俺カッコイイ、」
なんてカンジの登山ブログは、いつか事故る人です。
山の危険を解かっていない=登山をきちんと理解していないでも事故らず済んでいるのは、
周りが気をつけてくれている+運がイイ、
っていうだけで・その人の実力が優れているワケではありません。
自然に飛びこんで遊ぶことは、自然災害や天候変化の危険エリアに飛びこむこと。
その自覚があれば「備えあれば憂いなし」を実行するし、ブログにもそういう注意喚起は怠らないモンです。
無理山行はしない・注意喚起をしてくれる・観天望気する・ピークハントせず撤退も有りなのは信用おけます。
山の小屋主さんや警察・消防の山岳救助隊員さんは山の専門家、
そういう方たちは必ず注意喚起をしてくれます、で、ときには厳しいことも言ってくれます。
そういう厳しさはホントに相手の安全+楽しい登山を願ってくれるからです、山をホントに愛して守るために言ってくれます。
山は自分を自由にする~とか、
山おしゃれです~カッコいいでしょ~、
みたいなソウイウ精神論第一ブログ・雑誌書籍・テレビ情報はアウトで、笑
それくらい今現在・気軽に入山できるポイント=装備不足・レベル違いが原因になる遭難事故が増加中です。
そこらへん山ブロガーさん達みんな責任もってやってくれたら、山の遭難事故は減るんじゃないかなー思います。
登山も山ドライブも安全に楽しめたらイイなあ、
ナンテことを天気のいい休日に想ったので、なんとなく書いてみました、笑

第158回 過去記事で参加ブログトーナメント
 にほんブログ村
にほんブログ村
blogramランキング参加中!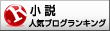


山歩雑談:霜月の雪山
昨日は今シーズン最初の雪山でした、笑
そんなワケで今日は昼ゴハン誘われて出た以外は@家だったんですけど、
昨日いた場所との落差アラタメテ思ったり、で、昨日ちょっと驚いたことアラタメテ。

登ったのは北奥千丈岳、標高2,601メートル・奥秩父山塊の最高峰です。
同じ登山口から花の百名山・国師ヶ岳→百名山・甲武信岳への縦走ルートに入ります。
この縦走ルートから逸れたポイントに北奥千丈岳があるんですけど、登山口の大弛峠から短時間で登れる山です。
標準タイムは大弛峠→北奥千丈岳まで片道1時間15分、大弛峠→国師ヶ岳もそれくらいなので日帰り充分できるルートになります。
↑
っていうふうに書くと、
「なーんだカンタンじゃん午後からでも楽勝だろw」
って思う人がいるんだろうなーと昨日あらためて思いました。
っていうのは・11月の山だっていうのにアイゼンも持たない不用意な人を多く見たからです。
11月の山でアイゼン持っていない人がどうなるか?
っていうと圧雪の氷に足もとが安定せず立往生→転倒滑落、遭難事故に陥ります。
そういう立往生サンを昨日は何人も見ました。

北奥千丈岳・国師ヶ岳までのルートは八割が木道です。
上の写真を見るとわかりますが、木道は板の下が空洞=橋と同じ状態になっています。
車を運転する人は経験アリだと思うんですけど、
橋=下が空洞=風が通る=低温下→凍結しやすいです。
また木道は通路=雪が踏まれる→圧雪→氷になる、いわゆるアイスバーン化しやすいワケです。
木道階段だと足を下ろす圧力が大きく=圧雪しやすく、新たな雪の下すぐ氷になっています。
ようするに「氷の階段」を歩くことになるわけです。
11月=秋=雪は降らない・と平地慣れしていると思いがち。
でも山の11月は降雪の季節です、雪が降らなくても霜が厚く積もるため凍結して薄氷が張ります。
天気予報を見て「けっこう温かいじゃん、零下じゃないし結氷とか嘘だろー」なんて大間違い、標高による気温低下を忘れずに。
また、山=県境な場合は地域またがる両方の天気から考える必要もあります。
標高による気温変化は季節によっても違いますが、
3,000メートル以下:1,000メートルで約5~6度
3,000メートル以上:1,000メートルで約10度
なぜ3,000メートルで気温変化が違うか?っていうと空気の湿度です。
標高3,000メートルを超えると湿度は低くなり乾燥します、乾燥空気のほうが気温低下ってことです。
北奥千丈岳や金峰山の登山口・大弛峠は標高2,365メートル。
大弛峠は山梨県甲府市にありますが、甲府地方気象台は標高273メートル。
↓
標高差2,092メートル=10~12度の温度差がある、ってことです。
甲府11月12日の気温は最高19.3度/最低8.7度→大弛峠は9度/零下3度くらいになります。
+
前日11月11日までに雨も降った。
↓
大弛峠では降雪、凍結が起きる。
最低気温が10度を下回る11月、山では零下がアタリマエってことです。
+
山は北斜面と南斜面で日照時間が違うため、気温もマッタク違います。
同じ斜面でも鬱蒼とした針葉樹林帯は暗い=日当たりが無い=気温が上がりません。

日向と日陰は気温差が大きい、
それが斜面の向きでずっと暗ければ気温差さらに大きくなります。
これは森の日当たりでも同じこと・10センチの距離でも日陰になれば氷が張ります、そのため、
↓
角を曲がったとたん足もとアイスバーン→転倒滑落、なんてことがフツーにあるワケです。
ここまで書くと解かると思うんですけど、
凍結は日照時間の影響も大きいため、標高が高くない山でもアタリマエに起きます。
北斜面・樹林帯で日照時間が少ない+谷から冷風が昇る、なんて条件下は冷蔵庫と同じだってことです。
こうした路面凍結は登山口に向かう林道でも同じこと、
カーブを曲がったとたんアイスバーン覆われている、なんてよくあります。
なので11月の山は車道もドライブ慎重に、スピードすこし落として路面凍結を予測しながらの運転が必要です。
11月の登山はアイゼンが欠かせません、軽アイゼンでも必ず持って行くこと。
もし忘れたなら登らない・ちょっとでも凍結があったら即回れ右、が安全を守ります。
林道の運転も同じこと、路面にアイスバーン発見したら危険信号です。
アイスバーンの走行は下り坂だとブレーキが利きにくく、難易度さらにUPします。
行きの登りは走れても帰りの下りはダメだ~~ってよくある話です。
↓
なのでイキナリ通行止め・イキナリ登山バス運休はよくあるコトです。
登山バスに乗ったけど途中で降ろされる、なんてコトも。
イキナリ降ろすなんてひどいなあ、って想う方もあると思います。
昨日も態度がナントカ話している登山客がいました、が、無理に運転走行して事故・死傷ナンテコトになるほうが不親切です。

アウトドアは楽しいです、その楽しさは自然に放りこまれる非日常感だろうなー思います。
その「非日常」っていうのは=「平地の感覚は通用しない」ってことです。
平地とは違う気温、天候変化、路面状況。
この違いが非日常感でもあるし、その違いから日常とマッタク違う事故も起こります。
たった一度のミス判断が大怪我・死亡事故になるなんてことは日常だと考えられないかもいれません、でもそれが山の日常です。
登山ブログもたくさんあって、テレビも登山番組たくさんあって、
登山やボルダリングやってますー宣言してくる芸能人イケメン俳優なんかも多くなって、
登山=「気軽にやれそうだなー」雰囲気ありますけど、気構え+知識技術がなくては即事故を起こします。
が、、、どれもイイとこしか採りあげない・注意喚起マッタクしないから、昨日みたいな立ち往生サンが多いんだろうと思います。
「あんまり大げさに危険言うのはカッコ悪いだろ?」
「こんな高い山でも簡単って言えちゃう俺カッコイイ、」
なんてカンジの登山ブログは、いつか事故る人です。
山の危険を解かっていない=登山をきちんと理解していないでも事故らず済んでいるのは、
周りが気をつけてくれている+運がイイ、
っていうだけで・その人の実力が優れているワケではありません。
自然に飛びこんで遊ぶことは、自然災害や天候変化の危険エリアに飛びこむこと。
その自覚があれば「備えあれば憂いなし」を実行するし、ブログにもそういう注意喚起は怠らないモンです。
無理山行はしない・注意喚起をしてくれる・観天望気する・ピークハントせず撤退も有りなのは信用おけます。
山の小屋主さんや警察・消防の山岳救助隊員さんは山の専門家、
そういう方たちは必ず注意喚起をしてくれます、で、ときには厳しいことも言ってくれます。
そういう厳しさはホントに相手の安全+楽しい登山を願ってくれるからです、山をホントに愛して守るために言ってくれます。
山は自分を自由にする~とか、
山おしゃれです~カッコいいでしょ~、
みたいなソウイウ精神論第一ブログ・雑誌書籍・テレビ情報はアウトで、笑
それくらい今現在・気軽に入山できるポイント=装備不足・レベル違いが原因になる遭難事故が増加中です。
そこらへん山ブロガーさん達みんな責任もってやってくれたら、山の遭難事故は減るんじゃないかなー思います。
登山も山ドライブも安全に楽しめたらイイなあ、
ナンテことを天気のいい休日に想ったので、なんとなく書いてみました、笑

第158回 過去記事で参加ブログトーナメント
撮影地:北奥千丈岳@山梨県
 にほんブログ村
にほんブログ村 blogramランキング参加中!

著作権法より無断利用転載ほか禁じます




























