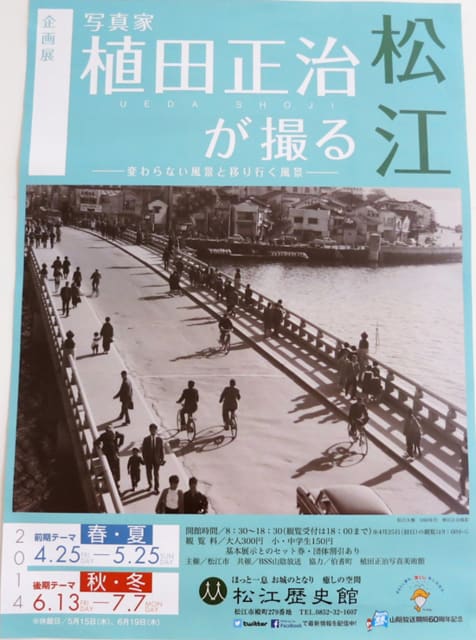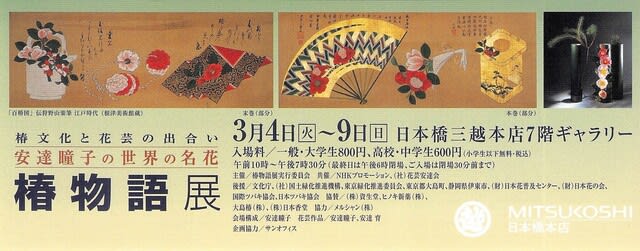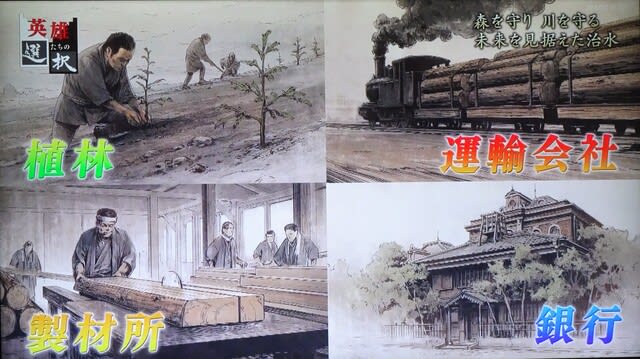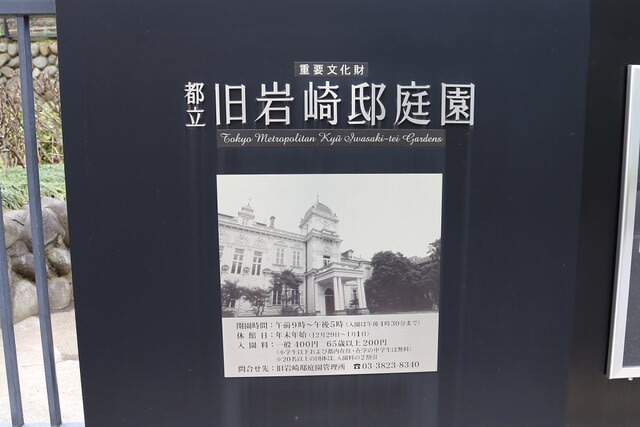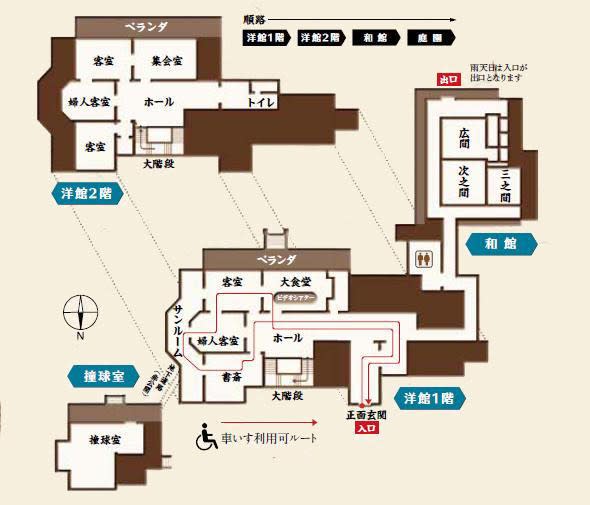名作のある風景・森鴎外「雁」 (日本経済新聞 2003/11/8)
7月9日は 小説家 翻訳家 陸軍軍医の
森 鴎外 が亡くなった鴎外忌
森鷗外(林太郎)は
1862(文久2)年1月19日
石見国津和野町田村(現・津和野町)にて
代々藩医の長男として生まれる。
1872(M5)年
父と共に上京し 政府高官の親族で
哲学者の西周(にし・あまね 1829-1897)
宅に下宿。
官立医学校へ入学するためにドイツ語を
学び始める。
1874(M7)年
第一大学区医学校
(現・東京大学医学部)予科に入学。
入学に必要な年齢が足りず
14歳と偽って試験を受ける。
1877(M10)年
本科へと進む。
ドイツ教官からの講義を受けるかたわら
佐藤元長(1818-1897)に師事し漢方医学
さらに漢詩や漢文といった文学にも
傾倒していく。
1881(M14)年
大学を卒業。しばらくは
父の橘井堂医院(北千住)を
手伝っていたが 陸軍軍医副となり
東京陸軍病院へ勤務する。
1882(M15)年
軍医本部に配属され プロイセン王国の
陸軍衛生制度の調査に従事。
同時に私立東亜医学校にて
衛生学の講義を受け持つ。
1884(M17)年
陸軍衛生制度のさらなる調査や
衛生学の習得のためドイツに留学
1884~87年
ラプツィヒ大学、ドレスデンの軍医学講習会
ミュンヘン大学、細菌学者ロベルト・コッホの
衛生試験所などを経て 勉学に励む。
カールスルーエで行われた
第4回赤十字国際会議では
通訳者を務め称賛された。
1888(M21)年
プロイセン近衛歩兵第二連隊の軍医に。
9月帰国し 陸軍軍医学舎と陸軍大学校の
教官を兼任。
1889(M22)年
読売新聞の付録として
「小説論」を発表し 文学活動を開始。
1890~91(M23-24)年
「舞姫」「うたかたの記」「文づかひ」など
ドイツを舞台にした小説を
相次いで発表し 注目を浴びる。
1894~1895(M27-28)年
日清戦争が勃発し
軍医部長として駆り出される。
終戦後は台湾にて勤務した後に帰国。
1896(M29)年
陸軍大学校教官に再度就任。
小池正道との共著「衛生新編」を発表。
文芸雑誌「めざまし草」を創刊。
1899(M32)年
陸軍軍医監に昇進。
北九州に徴兵区をもつ第十二師団の
軍医部長として小倉へと移る。
1902(M35)年
荒木志げ(1880-1936)と見合い結婚。
第一師団の軍医部長の辞令を受け
東京に赴任。
「めざまし草」を廃刊した後
上田敏(1874-1916)らと「芸文」
後に「万年艸」を創刊。
1904~1906年
日露戦争に軍医部長として出征。
1907(M40)年
陸軍軍医総監に昇進し
陸軍省医務局長となる。
1909(M42)年
文芸雑誌スバルにて
「半日」「ヰタ・セクスアリス」「鶏」
「青年」などを連載。
東京帝国大学から文学博士の学位を
授与される。
1911~18(M44-T7)年
「雁」「鼠坂」「阿部一族」
「山椒大夫」「高瀬舟」など執筆。
ゲーテなどの外国文学の翻訳も行う。
1916(T5)年
陸軍引退。
1919~21(T8-10)年
初代帝室美術院長(現・国立博物館長)を務める。
次第に病状が悪化。
1922(T11)年
腎委縮・肺結核により病死。享年60
(参考:ウィキペディア)