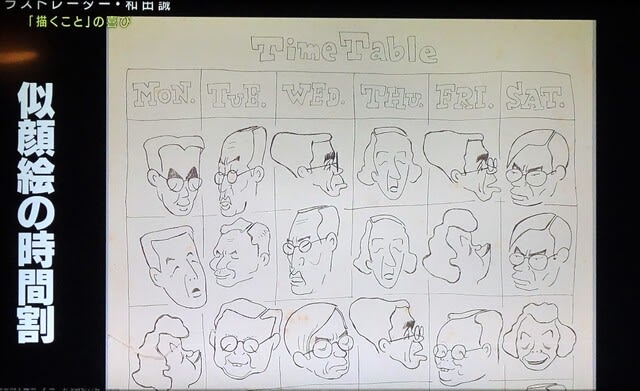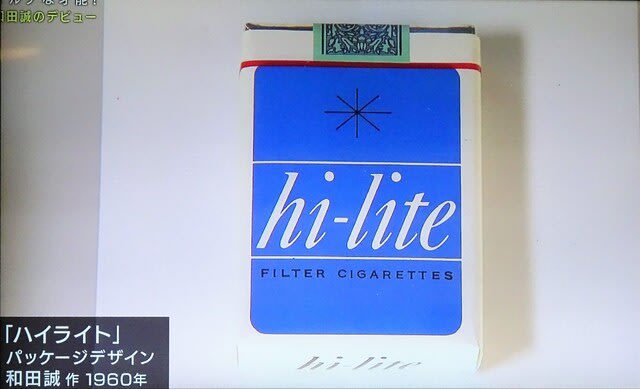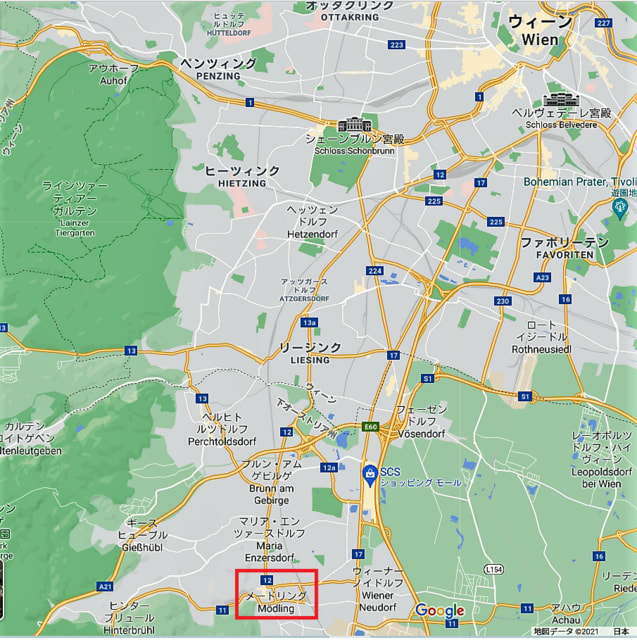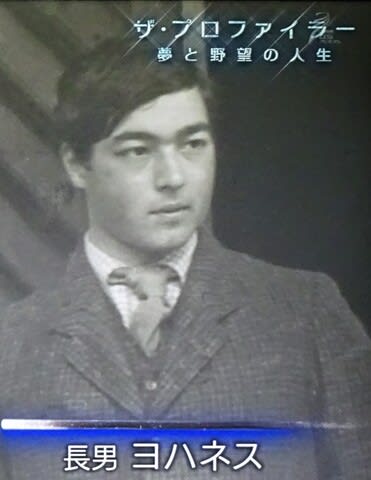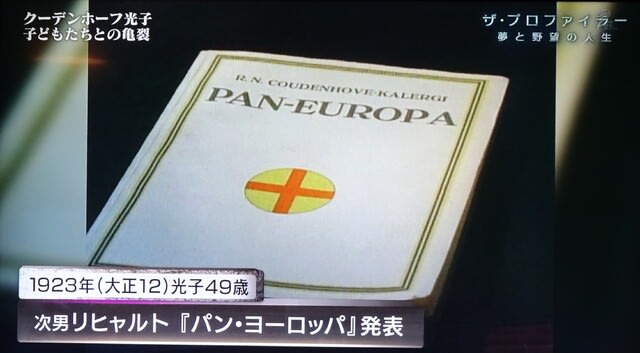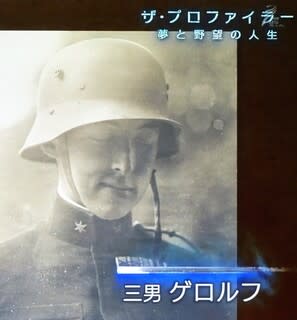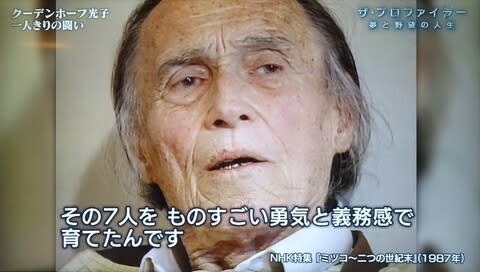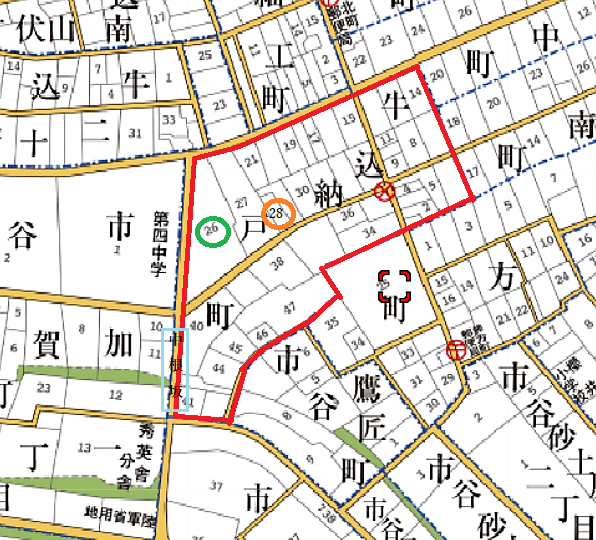続きクーデンホーフ光子について触れる。
光子は 日本で長男と次男を産み
総勢 7人の子をもうけるが
夫ハインリヒが亡くなったとき
光子31歳 子供たちは
上が12歳 下が2歳半だった。
その子供たちを取り上げて見る。
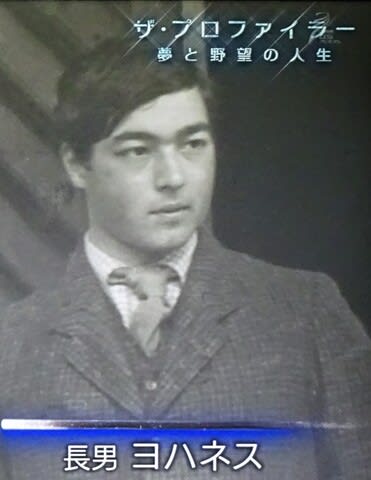
○長男:ヨハネス
(光太郎) 1893-1965
裕福なハンガリー系ユダヤ人の一族出身で
オーストリア=ハンガリー帝国
最初の女性パイロット
リリー・シュタインシュナイダー
(1891-1975)と最初の結婚する。
のちに
女優ウルスラ・グロースと再婚し
先妻の長女 ピクシーは後に
光子の心の支えになる。

○次男:リヒャルト
(栄次郎) 1894-1972
戦後の 1918(T7)年
リヒャルトが有名舞台女優
イダ・ローラント(1881-1951)と
結婚すると言い出すが
イダ・ローラントは
ユダヤ人で離婚歴が2度有り
加えて年齢が34歳で19歳のリヒャルトと
大きく離れていることから光子と対立し
リヒャルトは駆け落ちをしてしまう。
光子は死ぬまでリヒャルトを許さなかった。
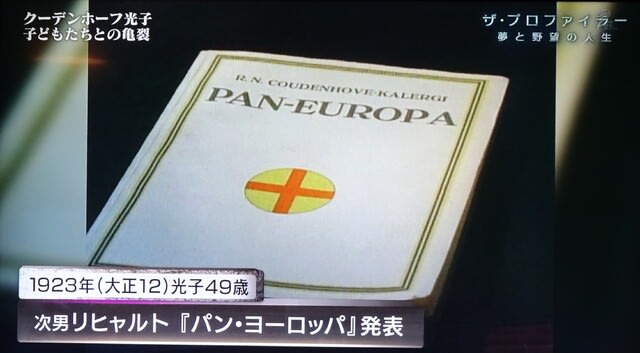
1923(T12)年
妻のイダの経済的支援で
「汎ヨーロッパ主義」を出版し
「ヨーロッパの28の民主主義国家が
アメリカのような一つの連邦国家として
まとまるべきだ」と唱えて
一躍ヨーロッパ論壇の寵児となる。
リヒャルトの母が東洋人光子光子の子であることがわかり
光子は“欧州連盟案の母”として知られる。
その後 リヒャルトはナチスに追われ
妻のイダ・ローランとアメリカに亡命した。
その逃避行が
不滅の人気のアカデミー賞映画
「カサブランカ」のモデルになっている。
*映画「カサブランカ」は
当ブログ(2011/4/10)で触れている。
*結婚歴は
1918(T')年 イダ・ローラント
(1881-1951)と結婚
1952年 アレクサンドラ・フォン・
ティーレ=ヴィンクラー伯爵夫人
(1896-1968)と再婚
1969年 メラニー・ベナツキー=ホフマン
(1909-1983)と再々婚
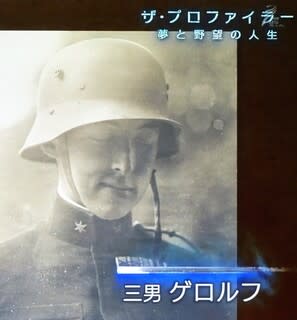
○三男:ゲロルフ
(ゲオルフ)1896-1978
1941年までプラハの日本大使館の
秘書兼報道官であり
プラハのカレル大学で
日本語と歴史の講師を務め
オリエンタルインスティテュートの
副学長を務めた。
なお 長女のバーバラ・クーデンホーフ
・カレルギー(1932-)は
オーストリアのジャーナリスト。
2001年 トマーシュ・ガリーグ・
マサリク クラスIVを受章している。
また三男のミャエル・クーデンホーフ
=カレルギー(1937-2018)は 画家で
2002年から日本で暮らしていた。

○長女:エリザベート 1898-1936
ウィーン大学で法律と
経済学の博士号をとり
最も優秀な頭脳を持っていたとも。
オーストリアの独裁者エンゲルベルト
・ドルフース首相(1892-1934)の
秘書を務めていたが その後
この首相はナチス党が政権を取った
ドイツに殺されため
パリへ亡命したが病気で若死にしている。

○次女:オルガ 1900-1976
母光子が脳溢血で半身不随になった時
25才であったが
光子の口述筆記を受け持ち
母の介護のため進学 婚期を逃し
生涯独身であった。
光子の死後 第二次世界大戦が終わると
チェコ兵によって収容所に入れられ
その後難民キャンプで暮らし、
ドイツで生活保護を受けながら、
貧しく孤独な生涯を終えている。

○三女:イダ・フリーデリケ・ゲレス
1901-1971
ウィーン大学卒業後
20世紀カソリック文学の
代表的作家になる。
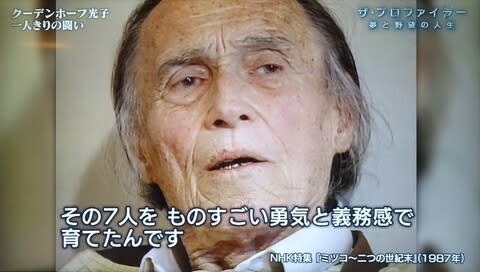
○四男:カール 1903-1987
ギリシャで大学教授をして
スイスで文筆業に。

光子の晩年
光子死去時(1941)見守ったには
三女・オルガだけ 葬儀に間に合ったのは
三男ゲロルフ(44歳)と
三女イダ(40歳)だけであった。
当時 長男ハンス(48歳)は
妻がユダヤ人のためローマに
次男 リヒャルト(47歳)はアメリカへ亡命中
四男 カール(38歳)はギリシャに
長女 エリザベートはすでに亡くなっていた。
( )内は当時の年齢
7人の子供は
長女を除いて光子より永い生涯を終えている。
・ハインリッヒ・クーデンホーフ・カレルギー
1859-1906・46歳
・クーデンホーフ光子
1874-1941・67歳
・長男 ハンス(光太郎)
1893-1965・72歳
・次男 リヒャルト(栄次郎)
1894-1972・77歳
・三男 ゲオルフ(ゲロルフ)
1896-1978・82歳
・長女 エリザベート
1898-1936・38歳
・次女 オルガ
1900-1976・76歳
・三女 イダ・フリーデリケ・ゲレス
1901-1971・70歳
・四男 カール
1903-1987・84歳
また 7人の内3人が博士号を取得
2人が作家になっている。
*写真はNHK「ザ・プロファイヤー」から