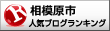2018.3.11訪問。湯河原駅を素通りして、駅前の通りを西へ。五所神社の向かい、道路を挟んで明神のクスはある。
説明板発見:史蹟「明神の楠」
樹種:クスノキ(くすのき科)
根回り:15、6メートル
樹齢:800年以上
五所神社は、古くは五所大明神社、又は五所大明神と称し、今を去る約1300余年天智天皇の御代、加賀の国の住人二見加賀之助重行らの手によってこの地方が開拓されたとき土肥郷の総鎮守として天照大神をはじめ五柱の神霊が鎮座されたと伝えられております。
治承4年(1180)8月源頼朝伊豆より挙兵の時、この地の豪族土肥次郎実平は一族と共にこれを助けて頼朝の軍を土肥の館に導き、石橋山合戦進発の前夜は、柱前において盛大な戦勝祈願の護摩をたいたといわれています。この時、実平によって佩刀一口が奉納され、今なお社宝として保存されております。
以来、領主庶民の崇敬特に厚く、長寿長命の神湯の産土神として今日に至っております。
昔の神社の境内は広大幽邃で参拝者は前方の千歳川の清流で禊をおこない、この「明神の楠」の下を経て神社に参拝しておりました。
正保3年(1646)この樹下の参道をもって当時入谷村といわれたこの地方が宮下、宮上の両村にわかれました。
その頃の参道には数多くの楠の巨木が生い茂っておりましたが、世の移り変わりと共に、今はこの一樹のみが歴史の跡を物語っております。」昭和54年4月1日 湯河原町指定文化財

でかいのはともかく、画像背後の高架って何だと思いますか?角度でわかりにくいかな?上の画像右下奥です。
実はこれ、新幹線なんです。こうね、800年の歴史に思いを馳せていると、新幹線が西へ東へ猛スピードで走り過ぎていくんです。あっちは瞬く間に時間がすぎてく。対して悠久の年月をここに立つ大楠との対比が凄いよね。

根回り15、6メートルの大楠の周囲をぐるりと巡ってると、根元あたりに小さな鳥居を見つけました。
上の画像では写ってないけれど、鳥居の奥に光が見えた。何だろう?と目を凝らしたら、向こう側が見えた。大楠の幹に穴が開いてたのです。もうびっくりしました。

穴を頭において大楠の周囲を巡ると、根元辺りは随分樹が痛んでます。仰ぎ見ると大楠の葉はそこそこ茂ってて元気そうだけれど、根元が頼りないです。大風が来たら倒伏しかねないんじゃ?と思ったけども、新幹線の高架が海からの風を防いでくれるんじゃないかな?と思い直しました。

さて、道路を渡ろうか?そもそもは道路向こうの五所神社の大楠を見にきたのです。時刻は15時56分です。時間が経つのは早いなあ〜。
説明板発見:史蹟「明神の楠」
樹種:クスノキ(くすのき科)
根回り:15、6メートル
樹齢:800年以上
五所神社は、古くは五所大明神社、又は五所大明神と称し、今を去る約1300余年天智天皇の御代、加賀の国の住人二見加賀之助重行らの手によってこの地方が開拓されたとき土肥郷の総鎮守として天照大神をはじめ五柱の神霊が鎮座されたと伝えられております。
治承4年(1180)8月源頼朝伊豆より挙兵の時、この地の豪族土肥次郎実平は一族と共にこれを助けて頼朝の軍を土肥の館に導き、石橋山合戦進発の前夜は、柱前において盛大な戦勝祈願の護摩をたいたといわれています。この時、実平によって佩刀一口が奉納され、今なお社宝として保存されております。
以来、領主庶民の崇敬特に厚く、長寿長命の神湯の産土神として今日に至っております。
昔の神社の境内は広大幽邃で参拝者は前方の千歳川の清流で禊をおこない、この「明神の楠」の下を経て神社に参拝しておりました。
正保3年(1646)この樹下の参道をもって当時入谷村といわれたこの地方が宮下、宮上の両村にわかれました。
その頃の参道には数多くの楠の巨木が生い茂っておりましたが、世の移り変わりと共に、今はこの一樹のみが歴史の跡を物語っております。」昭和54年4月1日 湯河原町指定文化財

でかいのはともかく、画像背後の高架って何だと思いますか?角度でわかりにくいかな?上の画像右下奥です。
実はこれ、新幹線なんです。こうね、800年の歴史に思いを馳せていると、新幹線が西へ東へ猛スピードで走り過ぎていくんです。あっちは瞬く間に時間がすぎてく。対して悠久の年月をここに立つ大楠との対比が凄いよね。

根回り15、6メートルの大楠の周囲をぐるりと巡ってると、根元あたりに小さな鳥居を見つけました。
上の画像では写ってないけれど、鳥居の奥に光が見えた。何だろう?と目を凝らしたら、向こう側が見えた。大楠の幹に穴が開いてたのです。もうびっくりしました。

穴を頭において大楠の周囲を巡ると、根元辺りは随分樹が痛んでます。仰ぎ見ると大楠の葉はそこそこ茂ってて元気そうだけれど、根元が頼りないです。大風が来たら倒伏しかねないんじゃ?と思ったけども、新幹線の高架が海からの風を防いでくれるんじゃないかな?と思い直しました。

さて、道路を渡ろうか?そもそもは道路向こうの五所神社の大楠を見にきたのです。時刻は15時56分です。時間が経つのは早いなあ〜。