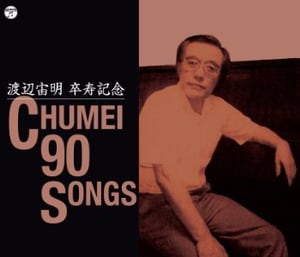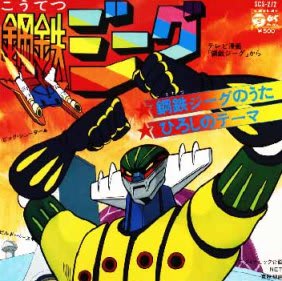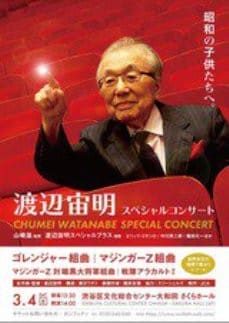ラテン音楽と関連して松岡直也さんの紹介は続きます。
「野球狂の詩」初期OPイントロのポロンポロンという
導入は、松岡さんのアドリブだそうで、宙明先生曰く
「あれは作曲家じゃ書けません。松岡さんらしく演って
もらった」とコメント。
その信頼度が押して知れるというモノです。

なお、その音色はクラヴィネットによる物だそうで。
楽器の特質にあった素晴らしい演奏だと感じ入りました。
クラヴィネットといえば、
スティーヴィー・ワンダーの「迷信」や
ELPの「ナットロッカー」、レッド・ツェッペリンの
「トランプルド・アンダーフット」などが浮かびます。

電子ハープシコード(?)とも言える、その楽器を使い
こなすには、かなりのセンスが必要と思うのですが、
渡辺さんは手癖っぽい演奏で見事に聴かせてくれてます。
そしてラテン楽器。
宙明先生はラテン楽器も相当に所有されているようで、
アニメや特撮曲で使われた物が紹介されていきました。
有名なギロは勿論、アクマイザー3のOP冒頭に鳴る金属音
「キラリラリーン」は、フレクサトーンという楽器の音だ
そうで、不破氏が実演されてビックリ。
※私ゃてっきりシンセによる物だと思っていた!
または気を付けなければハイハット音と同じに聴こえる
楽器とかをリズム楽器に使われていて、その細やかさも
特筆モノでした。

さらに宙明先生作曲のレア物紹介も行なわれ、非売品の
ソノシート「なにわや」のCMソングが流されました。
歌っているのが、なんとザ・ピーナッツ!
双子の歌姫は収録後に「イイ歌ね」と語り合っていたとか。
古い劇伴も「全力で作りました」と仰る宙明先生だけに、
CMソングも素晴らしいメロディです。
ソノシートが元だけに、未CD化の曲。「求む音源!」の
ノリでした。
いよいよ終盤、腹巻猫さんから「最近印象に残った事」を
尋ねられた宙明先生、そこで「君の名は。」「シン・ゴジラ」
「この世界の片隅に」を観た事を挙げてらっしゃいました!

しかも一番は「君の名は。」だとか、なんとお若い!!
なお、アニメ「けものフレンズ」もご覧になったそうだが、
これは「よくわからなかった」そうです。
※ていうか誰が勧めるんだ!?お孫さんか!?

今後のお仕事の紹介もありまして。
(しょこたんが出演している)NHKアニソンアカデミー校歌の
作曲や、まだ公表ができない仕事…などがあるそうです。
さらに発表されたばかりの「ギャバンVSデカレンジャー」の
主題歌を聴いて、「ああ、やっぱり安定の宙明節」とトロけ
そうになり、いよいよエンディング間際と思いきや。
宙明先生が再度ラテンのリズムに言及され始め、不破氏が
「さっき端折ってしまいましたが…」と改めて動画付きで
紹介するシーンも。
サルサなどで用いられるラテン音楽特有のリズムパターン、
クラーベ。
「2(ドス)、3(トレス)」や「3(トレス)、2(ドス)」を
基本に発展する多彩な物があるとの事。

これなんて発展させたら「ジャングル・ビート」になるなぁ
…なんて事を思っていたら
宙明先生が「ラテンアメリカ音楽もアフリカから来た黒人が
リズムを伝えた」ような話を始められ
「黒人がいなかったら、世界中の音楽は今のようにはなって
いません!」と断言なさったのです!
※確かにそうだけど、まずクラシック畑で勉強なさった渡辺
宙明先生から、ここまで高らかに黒人賛歌が飛び出すなんて
感激です!

私はパーカッションで「悪魔を憐れむ歌」、ジャングル・
ビートで「ノット・フェイドアウェイ」を思い出す、R・
ストーンズ・ファンでもあるんですから!
ブルースの事にも言及され、「次回のテーマはこれですか!」
みたいなムードのなか、イベントは終了。

いやぁ、今回も濃かった。
「また次回、開催あったらお会いしましょう」で閉幕の拍手。
先生は席を立つ時、そして袖にハケる時、それぞれ我々に
両手を上げて挨拶されました。
その度に大きな拍手。物販の「日活映画CD集」は売り切れに
なったそうで、先生人気は益々健在!
今後も期待で御座います。ありがとうございました!
「野球狂の詩」初期OPイントロのポロンポロンという
導入は、松岡さんのアドリブだそうで、宙明先生曰く
「あれは作曲家じゃ書けません。松岡さんらしく演って
もらった」とコメント。
その信頼度が押して知れるというモノです。

なお、その音色はクラヴィネットによる物だそうで。
楽器の特質にあった素晴らしい演奏だと感じ入りました。
クラヴィネットといえば、
スティーヴィー・ワンダーの「迷信」や
ELPの「ナットロッカー」、レッド・ツェッペリンの
「トランプルド・アンダーフット」などが浮かびます。

電子ハープシコード(?)とも言える、その楽器を使い
こなすには、かなりのセンスが必要と思うのですが、
渡辺さんは手癖っぽい演奏で見事に聴かせてくれてます。
そしてラテン楽器。
宙明先生はラテン楽器も相当に所有されているようで、
アニメや特撮曲で使われた物が紹介されていきました。
有名なギロは勿論、アクマイザー3のOP冒頭に鳴る金属音
「キラリラリーン」は、フレクサトーンという楽器の音だ
そうで、不破氏が実演されてビックリ。
※私ゃてっきりシンセによる物だと思っていた!
または気を付けなければハイハット音と同じに聴こえる
楽器とかをリズム楽器に使われていて、その細やかさも
特筆モノでした。

さらに宙明先生作曲のレア物紹介も行なわれ、非売品の
ソノシート「なにわや」のCMソングが流されました。
歌っているのが、なんとザ・ピーナッツ!
双子の歌姫は収録後に「イイ歌ね」と語り合っていたとか。
古い劇伴も「全力で作りました」と仰る宙明先生だけに、
CMソングも素晴らしいメロディです。
ソノシートが元だけに、未CD化の曲。「求む音源!」の
ノリでした。
いよいよ終盤、腹巻猫さんから「最近印象に残った事」を
尋ねられた宙明先生、そこで「君の名は。」「シン・ゴジラ」
「この世界の片隅に」を観た事を挙げてらっしゃいました!

しかも一番は「君の名は。」だとか、なんとお若い!!
なお、アニメ「けものフレンズ」もご覧になったそうだが、
これは「よくわからなかった」そうです。
※ていうか誰が勧めるんだ!?お孫さんか!?

今後のお仕事の紹介もありまして。
(しょこたんが出演している)NHKアニソンアカデミー校歌の
作曲や、まだ公表ができない仕事…などがあるそうです。
さらに発表されたばかりの「ギャバンVSデカレンジャー」の
主題歌を聴いて、「ああ、やっぱり安定の宙明節」とトロけ
そうになり、いよいよエンディング間際と思いきや。
宙明先生が再度ラテンのリズムに言及され始め、不破氏が
「さっき端折ってしまいましたが…」と改めて動画付きで
紹介するシーンも。
サルサなどで用いられるラテン音楽特有のリズムパターン、
クラーベ。
「2(ドス)、3(トレス)」や「3(トレス)、2(ドス)」を
基本に発展する多彩な物があるとの事。

これなんて発展させたら「ジャングル・ビート」になるなぁ
…なんて事を思っていたら
宙明先生が「ラテンアメリカ音楽もアフリカから来た黒人が
リズムを伝えた」ような話を始められ
「黒人がいなかったら、世界中の音楽は今のようにはなって
いません!」と断言なさったのです!
※確かにそうだけど、まずクラシック畑で勉強なさった渡辺
宙明先生から、ここまで高らかに黒人賛歌が飛び出すなんて
感激です!

私はパーカッションで「悪魔を憐れむ歌」、ジャングル・
ビートで「ノット・フェイドアウェイ」を思い出す、R・
ストーンズ・ファンでもあるんですから!
ブルースの事にも言及され、「次回のテーマはこれですか!」
みたいなムードのなか、イベントは終了。

いやぁ、今回も濃かった。
「また次回、開催あったらお会いしましょう」で閉幕の拍手。
先生は席を立つ時、そして袖にハケる時、それぞれ我々に
両手を上げて挨拶されました。
その度に大きな拍手。物販の「日活映画CD集」は売り切れに
なったそうで、先生人気は益々健在!
今後も期待で御座います。ありがとうございました!