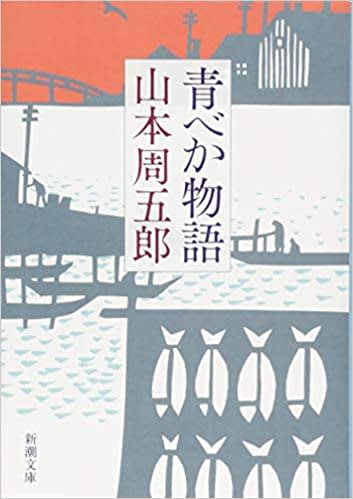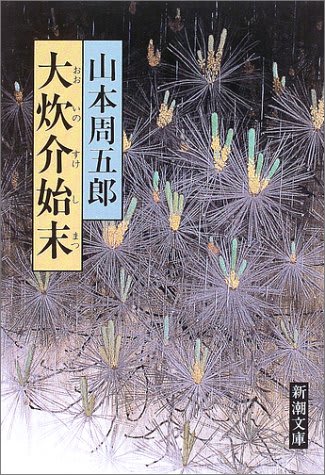山本周五郎
『栄花物語』★★★
題名から、平安時代の歴史物語が浮かぶけど、こちらは山本周五郎の栄花です。
華やかな平安世界絵巻ではなく、お江戸物語です。
13.栄花物語 - 歴史と物語:国立公文書館
勤労感謝の日 悪天候は前から分かっていた。
相方は出張準備でばたばたしているし、腰を据えて周五郎さんを読もう。
ってことで長編をチョイス★P701
読み応えがありそうな田沼意次の時代物
夜はワールドカップドイツ戦⚽
(勝てる気がしなかったのでテンション低め×××)
--------(抜粋)
収賄は事実か。近づく程、彼は高潔に見えるのだが。
徳川中期、時の先覚者として政治改革を理想に、非難と悪罵の怒号のなか、頑なまでに己れの意志を貫き通す老中田沼意次――従来、賄賂政治の代名詞のような存在であった田沼親子は、商業資本の擡頭を見通した進取の政治家であったという、新しい視点から、絶望の淵にあって、孤独に耐え、改革を押し進めんとする不屈の人間像を、時流に翻弄される男女の諸相を通して描く歴史長編
--------
田沼意次
即浮かぶのは、池波正太郎『剣客商売』でしょう。
(こちら途中挫折したまま(ー_ー)zzz)
I - ◆BookBookBook◆
I - ◆BookBookBook◆
池波正太郎『剣客商売』★★★★★借りたまま本箱で眠っていた(ある意味借りパク)いつか読もういつか読もうと日々は過ぎ・・渋めなハードカバー挿絵付読んで一言おもしろかった...
goo blog
まず主要登場人物一覧から、想像しつつ本編スタート
月の盃
汚名の人
登城時刻が四つ時(午前10時頃)とは、今で言うフレックスですな。
---
「政治は庶民のことなんか考えやしない」と信二郎が遮った、「政治というやつは、征服者が権力を執行するために設けた機関さ、いかなる時代が来、いかなる人がやっても、政治がその原則から出ることはないんだよ」
---
冬のちまた
夕顔の少将
甘美な毒
---
彼女には彼女の良心があり道徳があるのであった。
彼女は烈しい情熱の衝動に圧倒された。それはかつて経験したことのない、灼けるような、あらゆる筋肉の斂縮を伴う発作であった。
---
安藤対馬邸 陸奥の国、磐城平藩藩主の中屋敷が蛎殻町にあった。
遠州相良藩主田沼意次
香汗
狩の行事
---
「資本、利潤、経済」と定信は吐きだすように云った、「筆頭老中ともある人の口から、そのような言葉を聞こうとは思わなかった、まるで、——まるで商家の手代のようだ」
そして嘲笑の眼で相手を見、長袴をきれいにさばきながら、定信は去っていった。
---
「いっておくが、人間が善良であることは決して美徳じゃあないぜ、そいつは毀れ易い装飾品のようなもので、自分の良心を満足させることはできるが、現実にはなんの役にも立たない、そのうえ周囲の者にいつも負担を負わせるんだ」
「まわりの者に負担を負わせるって」
「しかも自分ではまったく知らずにさ、——もっともそれで終わることができれば幸福かもしれないがね」
---
——女に生れてくるというのは因果なものだ。
おはまはそう云った。身につまされたのであろうか、そのおはま自身が、求めて苦労をしようとして泣いている。苦労させたくないという男の気持を、逆に悲しがり怨んでいるのである。‥‥‥泣くことに楽しむほど、おはまはもう若くはない。云っていることは本気なのだ。決してみえや意地ではない、本気で泣いているのだということは信二郎にはよくわかった。
——人はこの絆のために、愛したり憎んだり、殺しあいさえするんだ。この絆のために、‥‥‥ばかなものだ。
---
「金というやつは、持っている人間によって汚れもすれば清くもなる、——おさださんの手に渡れば、それでこの金も清くなるよ」
「旦那、そう思って下さいますか」
「おれが思うんじゃない、金というやつはそういうものだというだけだ」
そして信二郎じゃそれをふところに入れた。
「どうかお願い申します」
すべてをそのひと言に託すように云って、新助は両手を膝につき、低く頭をさげた。
---
あだ化粧
---
―—病人は死期が迫るとよく自分の手を見る
という俗語がある。
---
かはたき
家老の服部半蔵
小金ヶ原
---
「外様から将軍世子の妻を迎えることはできない」
---
獲物
---
「やる以上は共犯者になる、共犯者になることを怖れるなら手を出さぬがいい、おれはどちらかの共犯者にならなければならなかった、そしてその一方を選んだのだ、もう引返すことはできないし、手を出した以上は裏切るとか裏切らぬとか、名分にこだわる必要はない、この事実の上に立って、ここから歩きだすよりほかに途はないんだ」
保之助はそのことを頭に刻みつけるかのように、暫くじっと眼をつむっていた。
---
花のうわさ
足音
風の彼方
「倹約な箱入り息子」
---
廊下の外は裏庭になっていた。榎らしい、まだ枝の裸な太い樹が、横に五六本並んでいて、それを境に向こうの暗い宵闇のなかに、低い平屋の小さな家があり、煤けた障子にぼうと、いかにも侘しく灯の映っているのが見えた。
―—あの灯の下にも生活があるんだ。
保之助はぼんやりとそう思った。その灯の色はほの暗く乏しげで、貧しい生活をそのままあらわしているようであった。
―—この茶屋の華やかな騒ぎを、あの灯の下の人たちはどう聞いているだろうか。
---
白書院評定
どうしても意次目線になってしまい、
白河候が軽んじて懐古趣味な武家社会にしがみついているようにしか思えない。
---
―—この人たちは自分の家が焼けていることにも気がつかないのだ。
詰所へ戻りながら、意次はそう思った。
―—自分の肌に火がついて熱さを感ずるまでは、火の恐ろしさを知ろうともしない人たちだ。
---
埃立つ街
傷心
---
―—倹約な箱入り息子だって三年経てば三つになるさ。
「青山は悪いやつだ、おまえは悪人だぞ」
「それをいまごろ知ったのか」
「きさまは悪人だ」保之助は唇をふるわせて云った、「おれはおはまさんに会った、あの人は笑っていた、泣いてくれたら、おれはもっと楽だった、しかしあの人は笑っていたぞ、わかるか信二郎」
「おはまが笑い、保之助が泣くか」
---
「主従とか夫婦、友達という関係は、生きるための方便か単純な習慣にすぎない。それは眼に見えない絆となって人間を縛る、そして多くの人間がその絆を重大であると考えるあまり、自分が縛られていることにも気づかず、本当は好ましくない生活にも、いやいやひきずられてゆくんだ」
「おれはいつもおれ自身でいたい、だからどんな絆に縛られることもがまんしないんだ」
---
その子の気性が理解出来るような気がする。
どちらかと言うと相方と重なる。
官覚の歪み
月代(さかやき)・・未だに読めないわたし
慥かな足音
---
武士の魂といわれた刀が、意次には凶器としか考えられなかったのである。
---
「われわれのやって来たことは、汀で砂の堤防を築くようなものだった」
―—隠退するがいい、肩の荷をおろして、もうお互いに休息しようではないか。
---
愛の明暗
---
「そうだ、善とか真実などというものは、実際には意味がないのかもしれない」
---
吉原の火事
定信登場
---
大樹は風雪の中でこそ培うべきものだ。こう云って、自分の言葉のりきんでいるのが可笑しいかのように唇でそっと笑った。
確実に自分を追いつめてくる、眼には見えないある力の存在。
「その覚悟をしていた筈ではないか」
駕籠の中で意次は自分に云った。
「いまになってなにを狼狽するんだ」
「なに、不利な戦いには馴れている」
「——まったく、いつも不利な戦ばかりやって来たものです」意知はこう云って苦しそうに顔をそむけた、
意知の死んだ翌日、佐野善左衛門の罪科がきまり、即日切腹になった。
---
「侍どもは権威に腰をかけて飢え、商人どもは恐れいり奉って暖衣飽食する。まことに天下泰平というわけですな」
---
しぐれの中
ぬかった道
---
―—この世に生きている以上、あらゆる者が無償ではいられない。
---
全体を通して青山信二郎、藤代(河井)保之助を中心とした市井の生活を描く。
自由気ままな信二郎に惹かれしまうけど、安之助の方に真の武士を思う。
いつの時代にも上手く立ち回る人もいるし、一心を貫く人もいる。
つながりのある田沼意次に関しては、どう感情移入してよいものやら?
(『剣客商売』の印象が強)
何だかトーンダウンしてしんみり終了
心中して幸せに? 死してお互い煩わしい現実から見えぬ世へ。