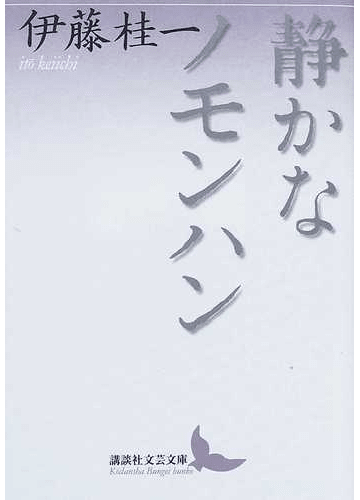W・G・ゼーバルト
訳 鈴木仁子
『[改訳]アルステルリッツ』★★★
ゼーバルド・コレクション
第6巻(2003年初の邦訳→2012年改訳)
アウステルリッツ[新装版] - 白水社
アウステルリッツ[新装版] - 白水社
全米批評家協会賞ほか、多数受賞の最高傑作 建築史家の主人公が語る暴力と権力の歴史 建築史家のアウステルリッツは、帝国主義の遺物の駅舎、要塞、...
W・G・ゼーバルト
初作家さんです(ドイツ生まれのイギリス定住)
読書会メンバからのおすすめ!?本
パラパラ捲ってみて思ったのは「段落がない!」
どこまでも続く文字の羅列・・
写真が盛り込まれているのが救い。
--------(抜粋)
建築史家アウステルリッツは、帝国主義の遺物である駅舎、裁判所、要塞、病院、監獄の建物に興味をひかれ、ヨーロッパ諸都市を巡っている。そして、彼の話の聞き手であり、本書の語り手である〈私〉にむかって、博識を開陳する。それは近代における暴力と権力の歴史とも重なり合っていく。
歴史との対峙は、まぎれもなくアウステルリッツ自身の身にも起こっていた。彼は自分でもしかとわからない理由から、どこにいても、だれといても心の安らぎを得られなかった。彼も実は、戦禍により幼くして名前と故郷と言語を喪失した存在なのだ。自らの過去を探す旅を続けるアウステルリッツ。建物や風景を目にした瞬間に、フラッシュバックのようによみがえる、封印され、忘却された記憶……それは個人と歴史の深みへと降りていく旅だった……
多くの写真を挿み、小説とも、エッセイとも、旅行記とも、回想録ともつかない、独自の世界が創造される。
欧米で最高の賛辞を受けた、新世紀の傑作長編
--------
---
闇はいっこうに散じていかない。いやむしろ、われわれが記憶おけるものがいかに僅かであることか、ひとつの生命が消え去るたびにいかに多くのものが忘れ去られていくことか、それ自体は思い起こす力をもたない無数の場所と事物に付着していた種々の歴史が、誰の耳にも入らず、どんな記憶にも残されず、語り継がれれもいかないがゆえに、世界がいわば自動的に空になってしまうかを思えば、闇はいっそう濃くなるばかりなのだ。
---
カフェ・デ・ゼスペランス(「カフェ絶望」とも読める)
---
<駅狂い>
---
夜、寒い部屋で眠りに引きこまれる前には、自分も暗い水底に沈んでいるような気のすることがよくありました。ヴァルヌーイ湖の哀れな魂と同じく、眼をおおきく瞑って、頭上はるか、幽かに射しこむ薄日を仰ぎ見ているような、鬱蒼と木の茂る岸辺に恐ろしげな様相でぽつんと立っている石塔の、さざ波に見え隠れする水影に眼を凝らしているかのような気がしたものです。
---
あのふたりは、自分たちの心の冷たさによってゆっくり死んでいったのかもしれないという気がします。
---
私は何時間も窓辺にたたずんで、窓ガラスをしたたり落ちる水が横桟の上にこしらえた二インチから三インチの氷の山の、模様の妙に見入っていたものです。
---
言っておかなくてはならないことがある。試験用紙にはダヴィーズ・イライアスではなく、ジャック・アウステルリッツと書いてもらわなくてはなりません。
「どうやらそれが」
「きみの本名らしいのですね」
「すみません、先生、この名前はどういう意味なのでしょうか」
「じきわかると思いますがね、モラヴィア地方の小さな町がこの名前ですよ、有名な戦争があった場所です」
---
アウステルリッツの会戦
---
つまるところ、われわれは自分たちの知り得ないことを、<戦局は二転三転した>といった笑止千万な一行なり、似たり寄ったりの毒にも薬にもならぬ表現なりにひと括りにしてしまうしか、なすすべをもっていない。
われわれの歴史への関心というのは、つまるところ出来あいの、頭の中に先に刷りこまれたイメージへの関心にほかならず、われわれはそれをためつすがめつしているだけである、じつは真実はまったく別のところ、誰も気づかないどこか別の片隅にあるというのに、
---
問いただすと、大火事になってほしかったんですと、学校の建物がなくなって瓦礫と灰の山になってほしかったんですと答えました。
---
エンサイン
記憶もまた夜の闇からぽっかりと心に浮かび上がってくるのです、けれど摑もうとするとまたすうっと暗くなってしまう、それもまた、現像液に浸しすぎた印画紙によく似ています。
遠い道のりをひとり戻ってきた鳩の話を、私はのちにくり返し思い起こさずにはいられませんでした。
今にして思います。とアウステルリッツは語った。あのころ、あの場所に変わることなく漂っていた平安のなかであとかたもなく消えてしまえていたなら、どんなによかっただろうと。
---
ひょっとしたら人類の不幸は、いつのころか体温がこの基準値からはずれてしまって、しじゅう少し熱っぽい状態にあることと関係があるのではないだろうか、
現実世界の中に一瞬起こった非現実的なもののきらめき、
---
ターナーの水彩スケッチ
---
アルバムにでもするように、旅人として歩んだ、忘却の彼方にほとんど沈んでいた風景をいまひとたび眼の前に立ち現せてみたかったのです。
---

闇に沈んだわが家で机に向かい、鉛筆の先がライトの明かりにまるで生き物のようにその影像をどこまでも忠実に辿っていくのを、そしてその影が左から右、行からつぎの行へ罫線を引いた紙の上を規則正しく滑っていくのをひたと眺めていることに、いかばかりの安らぎを得ていたことだったでしょうか。
---
迷妄
---
アウステル語ります。とにかく語りまくります(笑)
一旦休憩
こちらの本は速読は不可能
---
夕闇が降りると家を出て、ひたすら遠くへ遠くへ歩くのです、
---
リヴァプール・ストリート駅

---
人生の決定的な一歩は、漠たる内面の衝動から踏み出されることがほとんどなのです。
---
見捨てられた状態こそが、過去の長い歳月のうちに私の心を破壊してしまったのだ、と気づいたことであり、そして自分は一度としてまことに生きていたためしがなかった、あるいは死の前日になってようやく生まれたようなものだ、との思いに、途方もない疲労感に襲われたことばかりです。
---
「安く上がって涙なしに暮らせる方法って?」
「<家賃無料=悲しみ無用>」
--
色鮮やかなマヨルカ焼き
---
手袋店
---
――食べ物が少し入ったリュックをひとつ
‥‥‥あれから思い返すに、自分ののちの人生はヴェラのこの短い言葉に尽きていた、
---
わたしたち制圧された側の人間は、なんというか、海抜以下に生きているみたいで、国じゅうの経済がナチの親衛隊に牛耳られ、企業がばたばたとドイツ管理下に置かれていくのを黙って見ているしかなかった。
---
写真の中でなにかが動いているような気がするの、ひそかな絶望のため息が、聞こえてくるような気がするの。まるで写真そのものに記憶があって、わたしたちのことを思い出しているかのように、わたしたち生き残りと、もうこの世のひとでない彼らの、ありし日の姿を思い出しているかのように。

---
過去のいずれかの時にか自分は過ちをおかしたのだ、との想いが沸き起こりました。だから今、自分はまやかしの、間違った人生を送っているのだ。
---
ユダヤ人虐殺のあった町バッハラッハの近辺で、折り畳み椅子に腰を掛けてさらさらと水彩画を描いているジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナーが浮かんできます。
---
追放され消し去られたという、私自身が長きにわたって抑圧し、いまむりやり扉をこじ開けられて出てきた感情に対して、理性は無力だったのです。
---
H・G・アードラーという私には未知だった人が、テレージエンシュタット・ゲットーの成立、展開、内部組織について記したもので、1945年から1947年にかけてのとみに困難な状況下にあって、一部をプラハ、一部をロンドンで執筆され、1955年にドイツの出版社から世に出るまで何度も改訂を得た書物でした。
テレージエンシュタットは、一平方キロたらずの面積に一時期六万人が詰めこまれていました。
偽りの楽園
---
≪世界のすべての記憶≫
---
幽閉された動物たちと私たち人間の観客が、おたがいに見つめ合っているので、理解のかなわぬ溝に、へだてられたままに、
---
プラハでヴィラに出逢い生前の母について話を聞く場面に心が動かされた。
「~とアウステルリッツは語った」が目に付いた(あえて不自然さをのんで、原文通り入れたそう)