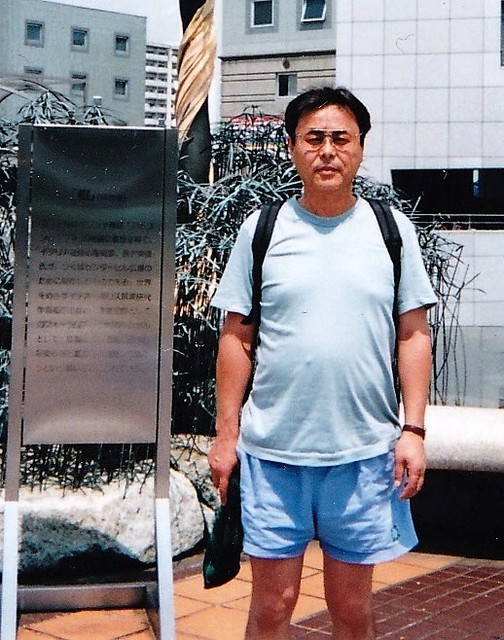昨日の続きです。
磐梯吾妻スカイライン中間点(後で判ったのですけど)、浄土平で絶景に感動し、“ツキ”が尽きていない事も確認し、次なる絶景ポイントを求めて車を走らせました。
このまま走って何があるのか? 兎に角、何だか判らないで走っていました。高度は少しずつ下がっているようです。
ガスの切れ間から顔を出す紅葉が綺麗です。でも、ホントのところ、そろそろ「ただの紅葉」には飽きてきました。

先ほどの浄土平で、今日の“メインビュースポット”はお終いかも?との気持ちになり、昼飯は何を食べるか?何て考え始めていると、深い谷を越えるアーチ橋に差し掛かりました。

歩道にはゾロゾロと人が歩き、谷底を覗いています。橋を渡って左折した先に駐車場が見えました。
係員が一人居て、誘導しているのですが、道路の片側を駐車スペースにした狭くて、長い、収容台数が十数台の狭い駐車場です。

これはダメかと思いつつ、空きを待つ車の後ろに並んだら、直ぐに列は動き出しすんなりと駐車。やっぱり“ついて”いるのです。
これまた、絶景です! 紅葉の谷にかかるアーチ橋。 傍らの石柱に“つばくろ谷”と刻まれていました。

スゴイです。プロ仕様?の大判のカメラが三脚を立てて何台も並んでいます。こうして、陽射しの変化を見ながらシャッターチャンスを待っているのでしょう。

ここは、「ただの紅葉」ではありません。深い谷にアーチ橋が架かっているのです。景色に高さがあり、奥行きがあります。
深い谷が、アーチ橋が、色とりどりの紅葉が、互いを引き立て合っているのです。

私も、ここは一つ、イイ写真を狙いました。如何でしょうか?

それで、「つばくろ谷」の“つばくろ”なのですが、この言葉を聞くと、想い出すのが、
♪旅の‘つばくろ’ 淋しかないか
♪おれもさみしい サーカス暮らし
♪とんぼがえりで 今年もくれて
♪知らぬ他国の 花を見た
「サーカスの唄」です。作詞が西條八十、作曲が古賀政男です。いまから74年も前の歌です。
そんな古い歌をこの私が知っているのですから、当時、大ヒットした曲なのでしょう。戦前の歌なのですよ。
歌い出しの「旅のつばくろ」がイイです。哀愁がいっぱいです。兎に角「サーカス」の唄ですから、哀愁がいっぱい、哀愁だらけです。
この谷にも、春になると「つばくろ」が沢山飛んで来るのでしょうね。
念の為に一応説明しておきますが、「つばくろ」は「燕」で、「ツバメ」のことです。
つばくろ【燕】(ツバクラの転) ツバメの異称。
ツバクラ【燕】「つばくらめ」の略。
つばくら‐め【燕】ツバメの古称。〈和名抄18〉
[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]
それと、橋は不動沢橋と云い、今見ているのが「新不動沢橋」で、駐車場は「旧不動沢橋」への道路だったのです。展望台は橋の一部を利用したものでした。

この銘板は「橋業界」では、正式名称を「橋歴板」と云うようです。

橋歴板に「二等橋」とありますが、この等級は何をもって分けるのでしょうか?
調べてみたら「荷重」でした。
1939年(昭和14年)の基準では、
一等橋 - 13t (国道橋)
二等橋 - 9t (府県道橋)
1956年(昭和31年)の基準改正で、
一等橋 - 20t (TL-20)
二等橋 - 14t (TL-14)
と、いうような事でした。
「つばくろ谷」も絶景!でした。感動!しました。
これで、磐梯吾妻スカイラインは終わりのようです。
さぁ。次は、いよいよ、今回の「メインイベント」初めての「鍾乳洞」です。
それでは、また明日。
磐梯吾妻スカイライン中間点(後で判ったのですけど)、浄土平で絶景に感動し、“ツキ”が尽きていない事も確認し、次なる絶景ポイントを求めて車を走らせました。
このまま走って何があるのか? 兎に角、何だか判らないで走っていました。高度は少しずつ下がっているようです。
ガスの切れ間から顔を出す紅葉が綺麗です。でも、ホントのところ、そろそろ「ただの紅葉」には飽きてきました。

先ほどの浄土平で、今日の“メインビュースポット”はお終いかも?との気持ちになり、昼飯は何を食べるか?何て考え始めていると、深い谷を越えるアーチ橋に差し掛かりました。

歩道にはゾロゾロと人が歩き、谷底を覗いています。橋を渡って左折した先に駐車場が見えました。
係員が一人居て、誘導しているのですが、道路の片側を駐車スペースにした狭くて、長い、収容台数が十数台の狭い駐車場です。

これはダメかと思いつつ、空きを待つ車の後ろに並んだら、直ぐに列は動き出しすんなりと駐車。やっぱり“ついて”いるのです。
これまた、絶景です! 紅葉の谷にかかるアーチ橋。 傍らの石柱に“つばくろ谷”と刻まれていました。

スゴイです。プロ仕様?の大判のカメラが三脚を立てて何台も並んでいます。こうして、陽射しの変化を見ながらシャッターチャンスを待っているのでしょう。

ここは、「ただの紅葉」ではありません。深い谷にアーチ橋が架かっているのです。景色に高さがあり、奥行きがあります。
深い谷が、アーチ橋が、色とりどりの紅葉が、互いを引き立て合っているのです。

私も、ここは一つ、イイ写真を狙いました。如何でしょうか?

それで、「つばくろ谷」の“つばくろ”なのですが、この言葉を聞くと、想い出すのが、
♪旅の‘つばくろ’ 淋しかないか
♪おれもさみしい サーカス暮らし
♪とんぼがえりで 今年もくれて
♪知らぬ他国の 花を見た
「サーカスの唄」です。作詞が西條八十、作曲が古賀政男です。いまから74年も前の歌です。
そんな古い歌をこの私が知っているのですから、当時、大ヒットした曲なのでしょう。戦前の歌なのですよ。
歌い出しの「旅のつばくろ」がイイです。哀愁がいっぱいです。兎に角「サーカス」の唄ですから、哀愁がいっぱい、哀愁だらけです。
この谷にも、春になると「つばくろ」が沢山飛んで来るのでしょうね。
念の為に一応説明しておきますが、「つばくろ」は「燕」で、「ツバメ」のことです。
つばくろ【燕】(ツバクラの転) ツバメの異称。
ツバクラ【燕】「つばくらめ」の略。
つばくら‐め【燕】ツバメの古称。〈和名抄18〉
[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]
それと、橋は不動沢橋と云い、今見ているのが「新不動沢橋」で、駐車場は「旧不動沢橋」への道路だったのです。展望台は橋の一部を利用したものでした。

この銘板は「橋業界」では、正式名称を「橋歴板」と云うようです。

橋歴板に「二等橋」とありますが、この等級は何をもって分けるのでしょうか?
調べてみたら「荷重」でした。
1939年(昭和14年)の基準では、
一等橋 - 13t (国道橋)
二等橋 - 9t (府県道橋)
1956年(昭和31年)の基準改正で、
一等橋 - 20t (TL-20)
二等橋 - 14t (TL-14)
と、いうような事でした。
「つばくろ谷」も絶景!でした。感動!しました。
これで、磐梯吾妻スカイラインは終わりのようです。
さぁ。次は、いよいよ、今回の「メインイベント」初めての「鍾乳洞」です。
それでは、また明日。