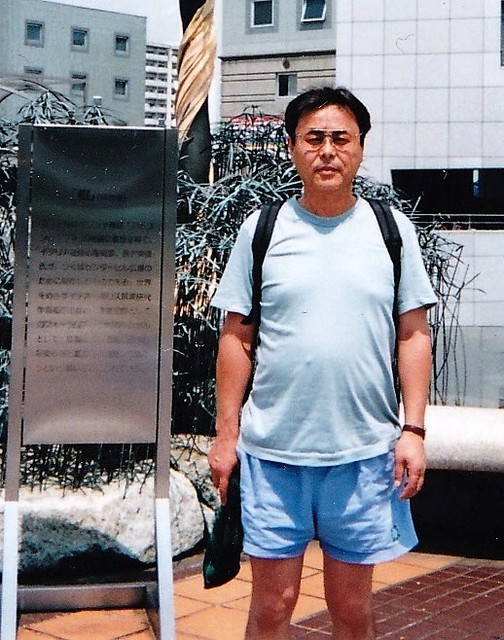道潅と云ってもねェ・・・・・・・・今は知らないんだろうなァ。
江戸城を造った人ですね。落語の「道潅」の話しでも知られています。
「道潅」のあらすじです。
猟の途中で雨が降ってきたので、近くのみすぼらしい民家で 雨具を借りようとしたら、出てきた女性が、黙って山吹のひと枝を差し出したのです。
道潅も、その場で何のことやら判らず怒って帰りました。山吹を差し出したのは『お貸しする雨具がありません』との、断りの意味でした。
山吹の一枝を差し出すことで、山吹を詠んだ有名な
『七重八重 花は咲けども山吹の 実の一つだに なきぞ悲しき』
という和歌を思い出しなさいと言うサインでした。
雨具を借りにきたのだから、詠われている『実の』と、雨具の『簑』を掛詞にして、『実の一つだに なきぞ悲しき』なのだから『お貸しする簑はありません』と云っていたのです。山吹には実がならないそうなんです。
『七重八重 花は咲けども 山吹の 実のひとつだに なきぞ悲しき』
道潅と云えば、この歌ですね。本歌では「なきぞあやしき」だそうです。この歌は平安時代、今から千年ぐらい前の、兼明親王(かねあきらしんのう)という人の歌だそうです。

【都電の面影橋のそばにある「山吹の里」の碑です。この辺で娘と出会ったとか】

このみすぼらしい「民家の娘」が「紅皿欠け皿」民話で知られる「紅皿」であったとした説があり、その「紅皿の墓」と云われているのが新宿区の大聖院にあります。上の写真です。それが、寺の境内というよりも、「元境内」であった「駐車場」の片隅にあるので判りにくく探し回ってしまった。

「悲劇のヒロイン?」の話しと、「悲劇のヒーロー?」がいつの間にか結びついたのです。
「紅皿欠け皿」は、世界中に伝わる「シンデレラ伝説」の日本版で、所謂、「継母もの」です。「紅皿」がいじめられる姉の名前で、「欠け皿」妹の名前です。姉の紅皿が歌を詠んだことから、二つの話しが合体したようです。それにしても変な名前です。
それでですね。「七重八重・・・・・・」の歌の話しですが、民家の娘が、山吹のひと枝を差し出して、雨具の断りとして使ったのは、娘の解釈であり、歌の本来の意味は別にあると思っていたのです。
それに、落語ではそのように解釈できる演じ方をしています。
ところが、驚いたことに(そんなに驚かない?)最初から雨具を断る為に詠んだ歌だったのです。それが、12時間に及ぶ「今回の大調査?」で判明しました。
そのことは、兼明さん自身が歌の説明をした『詞書(ことばがき)』に書いていたのです。
雨の降った日、兼明さんの家に来客があり、帰りに蓑を貸してほしいと言われて、黙って山吹の枝を折って渡したのです。
受け取った人は何のことか分からずに帰り、後日、あれはどういうことだったのかと使いの者を寄越したので、あの歌を詠んで渡したそうです。
今ならば、『実の』と『簑』を掛けた『おやじギャグ』だと思います。
兼明さんは、醍醐天皇の皇子という偉い方だそうです。
そんな偉い方なのに、貸してあげる簑のが無いというのは、なんか不自然ですけどね。歌本来の隠された謎がある筈です。絶対に、そんな気がするのです。
そこで、私が「大胆」に推理してみました。
七重八重・・・とくれば、七、八、ですから、次は九で「九重」ですよね、九重は音読みで「きゅうちゅう」になり「宮中」に繋がるのです。
「花は咲けども 山吹の」、この「山吹」は「山吹色」すなわち「黄金」意味しているのです。
「花は咲けども」は、それなりに「処遇」されたが、
「実のひとつだに なきぞ悲しき」結果として、たいした財産も残せなかった。
結論。
宮中に上がり、それなりに処遇はされたが、結果として、たいした財産も残せず、雨具のひとつも客に貸せない、貧しい状況に今はある。
「何とかしてくれよ!」
こんな愚痴を歌ったのではないでしょうか?もの凄い画期的な解釈です。

それで、話しを戻します。
兼明さんは914年生まれで、987年に、73歳で亡くなっています。
山吹の歌が載った、「後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)」は、兼明さんが亡くなってから、99年後の1086年に編纂さられています。
太田道潅は、後拾遺和歌集が出来てから、346年後の室町時代の1432年に生まれ、1486年に54歳で亡くなりました。
亡くなった理由は、主君の上杉定正が、道潅を自らの城に招き、風呂をすすめ、その入浴中に殺してしまったのです。
優秀な部下である道潅に、自分の地位を奪われると思ったようです。悲劇のヒーローですね。
落語のネタ本になったのは、湯浅常山の書いた『常山紀談』です。この本は、有名な武将のエピソードを集めたものです。道潅が亡くなった後、253年後の江戸時代の1739年に書かれました。
最初に演じた落語家が、いつ頃の誰であるかは判りません。多分、江戸の後期か明治時代の初期でしょう。歌舞伎の演目にもあったそうです。
歌が詠まれてから、平安、室町、江戸、明治、大正、昭和、平成の現在まで約千百年の時が流れています。
歩きまわり、いろいろ調べて、少し考える。いいよねェ~こういうのって。
お・や・す・み・・・・・・・































 を発見し、スルドイ推理により、小津監督の深層心理に迫り、驚くべき製作意図を完璧?
を発見し、スルドイ推理により、小津監督の深層心理に迫り、驚くべき製作意図を完璧?  に解明した大長編 (それほど長くないです
に解明した大長編 (それほど長くないです ) の力作です。
) の力作です。
 小説仕立てで、書いてみました。
小説仕立てで、書いてみました。 それでは、はじまり、はじまり・・・・・・・・・・・。
それでは、はじまり、はじまり・・・・・・・・・・・。








 食事
食事 
 をしたときに、十文字の付け人が「支度部屋」から、わざわざ私たちの為に「サイン」を持ってきてくれたのです。
をしたときに、十文字の付け人が「支度部屋」から、わざわざ私たちの為に「サイン」を持ってきてくれたのです。



 どういうことなんだ
どういうことなんだ  』 突っ込み禁止
』 突っ込み禁止