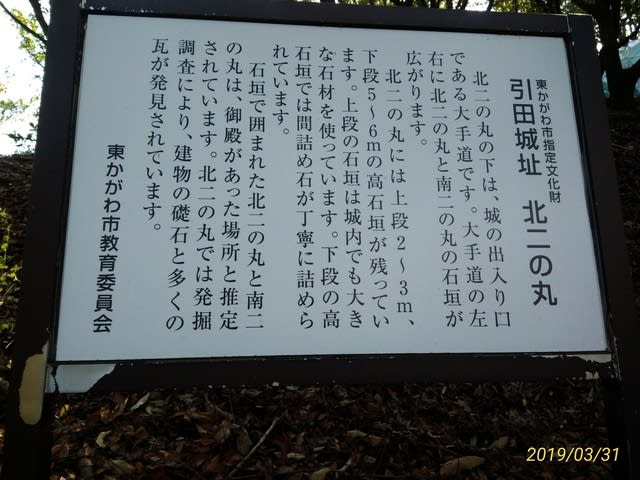2019年3月31日(日)
二日目、
"眼下の町並みを見る
下山する前に北上し、
『南二の丸』
を確認した。
夏なら藪になってるかも?
北二の丸、東二の丸への分岐
すぐに引き返し、
再び、西の郭に戻った。
これより下山する。
10時40分、
港側登山口に降りました。
約2時間40分、山のなかを歩き回った。
そして、
10時54分
讃州井筒屋敷で、
続百名城スタンプget!
次の汽車まで約一時間待ちなので、
屋敷を見学することにした。
入場料は300円也。
ボランティアガイドのおじさんが屋敷内を案内してくれました。
この屋敷は、
江戸時代より醤油と酒造りを行っていた商家。
建物は江戸後期から明治期に建築されたもの。
当主はその後、高松だったかな?
移られたので、現在は観光施設になりました。
話を聞いてたら、写真撮るのを忘れて、全く画像がありません。
屋敷のパンフレットももらい忘れたのか、手元にないので、
ここでは再現できません。
庭にいくつもある灯籠が、それぞれ違う形で、傘灯籠というの変わったものもあった。
欄間の飾りも凝ってました。↑香川県のネット画像を拝借。
蔵には鼠返しとして取り付ける斜め板をはめる仕掛けがあった。
屋根裏部屋は杜氏が住み込む部屋で、寒さ対策として階段部分を板で閉められる仕組みになってた。
お風呂は五右衛門風呂ではなくて、
桶風呂でした。
小さい頃、五右衛門風呂だった我が輩としては羨ましい限りであった。
このほか、色々聞いたが忘れた。
約40分、丁寧な解説でした。
そして、
11時42分、引田駅。
結局、午前中四時間、
引田で過ごしました…

弟夫婦が、長い連休をとって
本日、フランスの隣の国へ出かけました。
娘夫婦と孫に会うためです。
羨ましいですな。
我が輩も例年なら、今の時期は遠征の準備をしてるのですが、
今年は出かけない。
大型連休に、楽しみが無い。
トホホや…
馬《●▲●》助ヒヒーン"