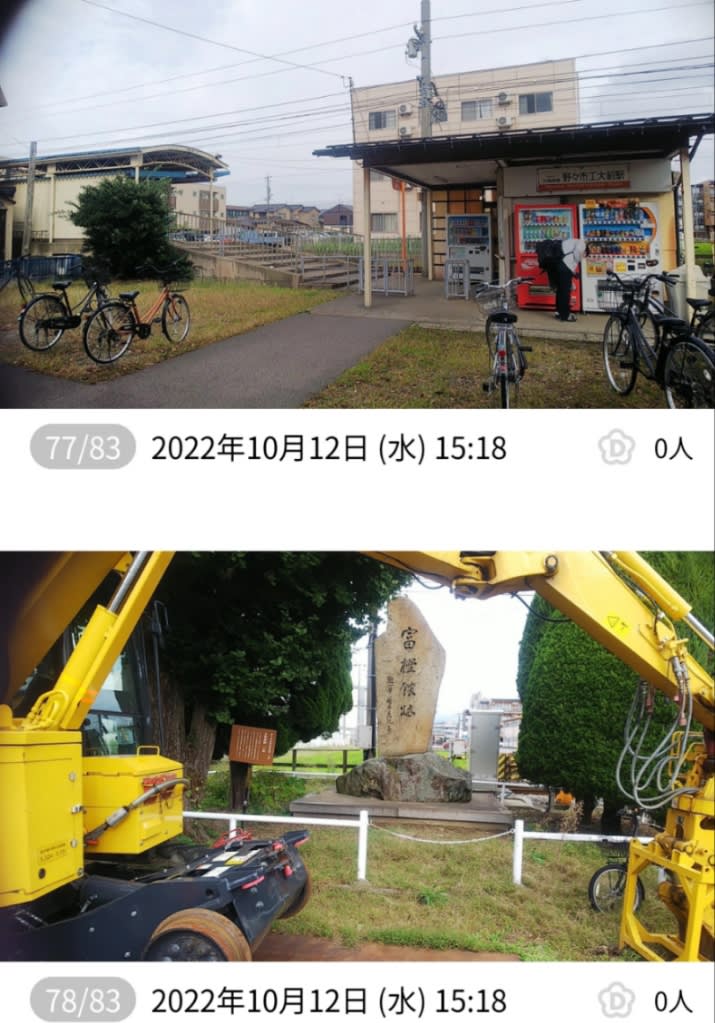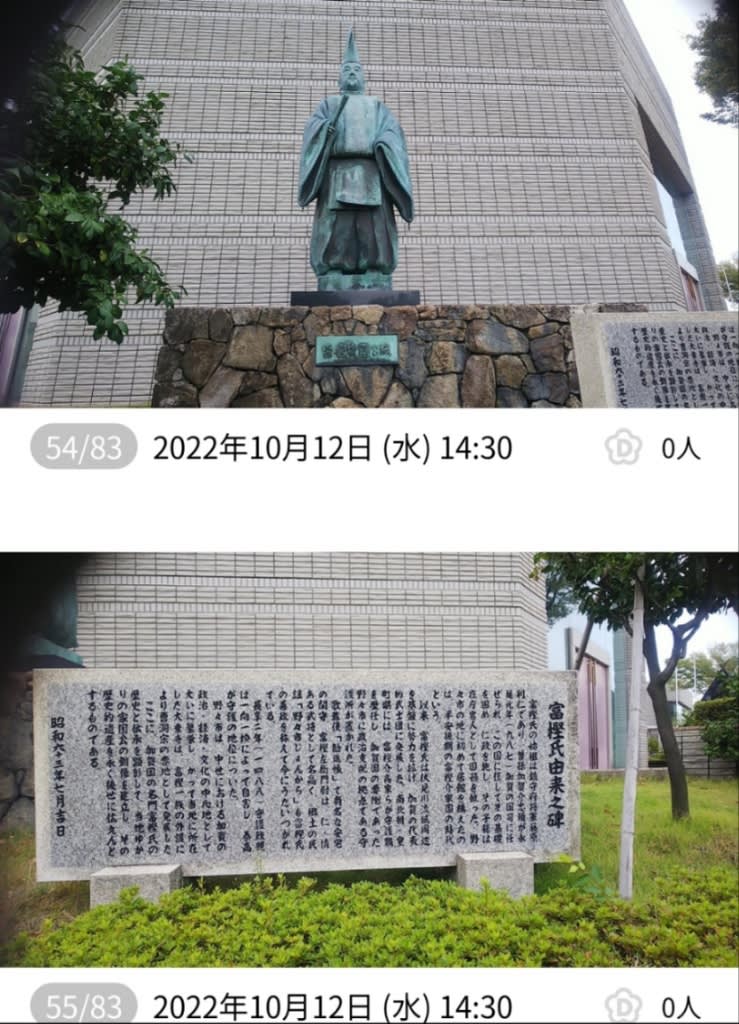地名ちょこっと紹介
【朝倉館跡】福井市
あさくらやかたあと。
福井市郊外の一乗谷地区に残る城館跡。
越前守護の朝倉氏の居館だった所で城下町を含めて全域が土の下に良好な状態で埋もれてました。
1967年から発掘調査がおこなわれて復元され、国の特別史跡に指定されてます。
国の特別史跡というのは、いわゆる国宝に値する史跡ということ。
我が県の安土城跡及び彦根城も同様に国の特別史跡です。
40数年前学生時代に見学に行きました。
資料館が発掘調査の拠点となっていてお粗末な造作でした。
しかし、いつの間にか一大観光施設となり百名城にも指定されました。
この建物も老朽化したため、昨年反対側の敷地に新しく資料館が建てられました。
新資料館、いつか見に行かねば!
以前にも述べたと思うが、昨年一乗谷の山城に登った。
昔は誰も登る人が無かったが、近年ハイキングコースが整備され、山城人気もありたくさんの人が登るようになりました。
巨大な山城で隅から隅まで探索したら帰りの汽車の時間に間に合わなくなり、路線バスも終了して困った。
しかし、復元建物の売店で働いてる女性が車で駅まで送ってくれて、無事に帰ることができた。
いやぁもう感謝感激飴おかき。
地獄に仏とはまさにこのこと。
実は北国街道歩きでも福井県の人に何度も助けられたことがある。
福井県の人はほんとに良い人ばかり、足向けて寝られませんわ。
それに引き換え、我が県民は…
朝倉氏の由来は、福井県ではなくて
但馬国養父郡朝倉。
平安時代に日下部氏が朝倉に居住し、朝倉氏と称した。
その後、別家が越前に移り守護の斯波氏を滅ぼして戦国大名となるのです。
なお、現在養父市八鹿町朝倉地区には朝倉城跡が残されてます。
いつか訪ねてみたい。
ちなに養父は「やぶ」、八鹿は「ようか」と読む。
難読ですよね。
この八鹿町の特産が山椒で、「朝倉山椒」と呼ばれてます。
この朝倉山椒の名付け親が、
驚くなかれ
牧野富太郎博士なのです。
新品種として登録されたそうです。
朝倉氏は我が近江の浅井氏と強い結びつきがあり、浅井氏の城や砦は朝倉氏の影響を受けたものがいくつもある。
浅井氏の本拠は伊吹山系。
牧野博士は伊吹山に何度も訪れて薬草などの研究をされました。
浅井氏、朝倉氏と牧野博士、
アサからぬ縁にバンザイサンショウ!
ちなみに牧野博士の2番目の奥さんは彦根藩士の娘さんでした。
その縁で彦根城にも訪れて
「オオトックリイチゴ」という新品種を発見されました。
トックリは徳利の形に似てるから。
彦根城でしか見られない固有種なので是非ともお越しいただき、とっくりと見てほしいものです。
明後日に続く
Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ
前回、美濃松山駅の読み方について述べたが、美濃紙は「みのうがみ」ではなくて「みのがみ」と読みますよね。
基本的に美濃は「う」を略して「みの」と呼ぶのが正解のようです。
ところで、京都市には
阪急「西院駅」がある。
当然ながら「さいいん」と読む。
しかし、嵐電の西院駅は「さい」と読む。
江戸時代「西院」を「さい」と呼んでたのを採用したもの。
だから、どちらも正しい。
でもどちらも「さいいん」と読んでしまうよね。
ちなみに嵐山の有名か酒の神様「松尾大社」は「まつおたいしゃ」と読むが、本来の読みは「まつお」ではなくて
「まつのお」。
のが入るのですの…
Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ
5月、皐月になりました。
我が家のサツキの花は今年も咲かなかったが、ツツジは綺麗に咲きました


今満開!
とはいえ、ツツジはツバキと同じく散ると汚い
ウ~ン…
明日から大型連休の後半戦に突入。
名神高速道路の大津インターチェンジ付近では30キロ以上の渋滞が予想されてます。
我が輩は山の上からその渋滞を見に行こうと思ってます
て、どんな趣味や?
馬《●▲●》助ヒヒーン♪